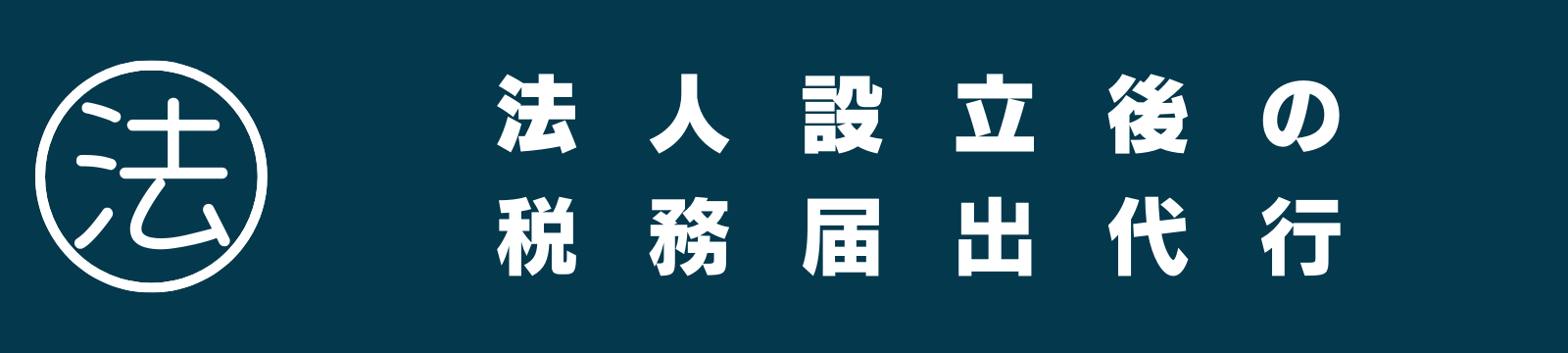はじめに

新たに会社を設立された皆様は、登記手続きを終えられた後も、税務署、年金事務所、労働基準監督署など、様々な機関への届出・手続きを行う必要があります。これらの手続きは、法令を遵守し、適正な事業運営を行うために欠かせません。本記事では、会社設立後に必要となる税務・労務手続きについて、具体的に解説します。対象読者は、会社設立者、経営幹部、および関連業務の担当者です。

税務関係の届出・手続
税務署
会社設立後、最初に行うべき重要な手続きとして、管轄税務署への各種届出が挙げられます。事業開始にあたり、税務署に提出が必要となる主な届出・手続きは以下の通りです。
法人設立届出書
法人設立届出書は、会社設立を税務署に通知するための最も基本的な書類です。会社名、所在地、代表者氏名、事業目的、設立年月日など、会社概要を記載します。提出期限は会社設立の日(設立登記の日)から2ヶ月以内です。期限を過ぎても罰則はありませんが、税務署からの法人税申告書等の重要書類が届かなくなる可能性があるため、速やかな提出をお勧めします。
通常、添付書類は定款の写し1部です。以前は登記事項証明書も必要でしたが、現在は原則不要です。ただし、税務署の管轄によっては添付を求められる場合や、都道府県・市区町村への届出には必要となる場合があるため、事前に確認しましょう。法人設立届出書には法人番号記載欄がありますが、設立登記後に国税庁から郵送される法人番号通知書で確認できます。未到着の場合は空欄でも問題ありません。事業目的欄は、定款記載の事業目的を全て詳細に記入する必要はなく、主要な事業内容を簡潔に記載するのが一般的です。
青色申告の承認申請書
青色申告の承認申請書は、法人税の申告を青色申告で行うために、会社が税務署に提出する書類です。青色申告には、欠損金の10年間繰越控除や、資本金1億円以下の企業における欠損金繰戻しによる前年度法人税額還付など、多くの税務上のメリットがあります。これらのメリットを享受するため、多くの企業が青色申告を選択しています。
提出期限は、会社設立の日から3ヶ月以内、または最初の事業年度終了日のいずれか早い日までです。この期限を過ぎると、設立第1期目からの青色申告適用はできませんので、注意が必要です。青色申告の承認申請書には、使用帳簿の種類や記帳方法などを記載しますが、添付書類は不要です。会計ソフトを使用している場合は、その旨を記載すれば問題ありません。青色申告は税制上の優遇措置が大きいため、特に設立初期の赤字が見込まれる場合や、事業拡大を計画している場合は、積極的に活用しましょう。
給与支払事務所等の開設届出書
給与支払事務所等の開設届出書は、従業員や役員に給与を支払う事業所を開設したことを税務署に届け出るための書類です。ここでいう給与には、従業員への給料だけでなく、経営者自身への役員報酬も含まれます。したがって、従業員を雇用していない一人社長の会社であっても、役員報酬を支払う場合は、この届出書の提出が必要です。この届出により、税務署から源泉徴収に関する納付書や年末調整関係書類が送付されます。
提出期限は、給与支払事務所等の開設日から1ヶ月以内であり、法人設立届出書よりも短い点に注意が必要です。添付書類は原則不要です。届出書には給与支払開始年月日を記載する欄があり、設立後すぐに給与支払いが開始されない場合は、その予定日を記載します。この手続きは源泉徴収義務を履行する上で非常に重要です。会社は給与支払いの際、所得税を源泉徴収し国に納付する義務があります。この届出により税務署はその情報を把握し、適切な納税手続きを案内します。一人社長の場合でも、役員報酬は給与所得となるため、この届出は必須です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、従業員への給与から源泉徴収した所得税の納付を、原則毎月行うところを年2回にまとめて行う場合に提出する申請書です。この特例は、給与支給人員が常時10人未満の小規模事業所が対象となります。承認されると、1月から6月までに支払った給与等から源泉徴収した所得税は7月10日まで、7月から12月までに支払った給与等から源泉徴収した所得税は翌年1月20日までに納付すればよくなります。
この申請書に提出期限はなく、随時提出可能です。原則として、提出した月の翌月に支払う給与等から特例が適用されます。添付書類は通常必要ありません。この特例により、毎月の納付事務負担を軽減できます。特に、従業員数が少ない会社にとっては、事務作業の効率化に繋がるため、検討をお勧めします。ただし、納期限徒過によるペナルティには注意し、年2回の納期限を確実に管理しましょう。
棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産の評価方法の届出書は、会社が保有する商品、製品、仕掛品などの棚卸資産について、法定評価方法以外の方法で評価したい場合に提出する書類です。法人税法では棚卸資産の法定評価方法が定められており、この届出書を提出しない場合は、法定評価方法(通常は最終仕入原価法)で申告する必要があります。
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。添付書類は特に必要ありません。届出書には、採用したい評価方法(例えば、個別法、先入先出法、総平均法など)を記載します。適切な評価方法を選択することで、会社の会計処理や税務申告において、より実態に合った資産評価が可能です。評価方法の選択は、会社の業種や事業内容によって最適なものが異なるため、慎重に検討しましょう。
減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却資産の償却方法の届出書は、会社が保有する建物、機械、車両などの減価償却資産について、法定償却方法以外の方法で償却したい場合に提出する書類です。法人税法では減価償却資産の法定償却方法が規定されており、この届出書を提出しない場合は、法定の償却方法で償却しなければなりません。
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。添付書類は特に必要ありません。届出書には、資産の種類ごとに採用したい償却方法(例えば、定額法、定率法など)を記載します。償却方法の選択は、会社の財務状況や将来計画に影響を与える可能性があります。適切な償却方法を選択することで、会社の利益状況をより適切に反映させることができます。
事前確定届出給与に関する届出書
事前確定届出給与に関する届出書は、会社が役員に対し、特定時期に確定額の給与を支給することを事前に税務署に届け出ることにより、その給与を損金算入するための手続きです。
提出期限は、原則として株主総会等の決議日から1ヶ月以内です。ただし、設立の日以後2ヶ月を経過する日までの期限もあるため、いずれか早い日が適用されます。添付書類として、届出書の他に、株主総会議事録の写しなど、役員給与の決定内容を証明する書類が必要です。
この制度を利用することで、役員報酬額を適切に設定し、会社の利益調整が可能です。ただし、事前届出と異なる支給を行った場合、その給与は損金として認められない可能性があるため注意が必要です。
定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書
定款の定め等により決算が確定しないなどの理由で、法人税、地方法人税、消費税、法人住民税、法人事業税などの申告期限延長を申請するための書類が、「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」です。
提出期限は、原則として最初に特例の適用を受けようとする事業年度終了の日までです。連結納税制度を採用している場合は、最初に適用を受けようとする事業年度終了の日の翌日から45日以内となります。添付書類として、定款、寄附行為、規則、規約の写しが必要です(調査部所管法人が書面で申請する場合は2部)。
市町村の法人住民税については、異動届提出時に、法人税で認められた延長月や対象事業年度、税務署への申請日などを記載し、税務署に提出した申請書の写しなどを添付します。
消費税の新設法人に該当する旨の届出書
消費税の新設法人に該当する旨の届出書は、設立時の資本金が1,000万円以上の場合に提出が必要となる書類です。ただし、法人設立届出書の該当欄に必要事項を記載することで、この届出書の提出を省略できる場合があります。
適格請求書発行事業者の登録申請書
適格請求書発行事業者の登録申請書は、インボイス制度に基づき、適格請求書(インボイス)を発行できる事業者として登録を受けるための申請書です。免税事業者でも申請可能(※)ですが、免税事業者が申請した場合は、後述する「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなくても、自動的に課税事業者になってしまうため注意が必要です。
(※)原則として免税事業者はインボイス登録できず、別途「消費税課税事業者選択届出書(後述)」を提出しなければなりませんが、2029年9月30日までの経過措置期間中に登録申請を行う場合は、登録申請書を提出するだけで課税事業者になることができます。
提出期限は特に定められていませんが、適格請求書の発行が必要な場合は速やかに申請することが推奨されます。免税事業者が特定の規定に基づき登録を受ける場合は、提出日から15日以降の希望日を登録希望日として記載できます。
添付書類として、納税地の異動に関する届出書の写し(該当する場合)や、その他参考資料があれば添付します。e-Taxで申請する場合は、マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要となることがあります。
消費税課税事業者選択届出書
消費税課税事業者選択届出書は、免税事業者が課税事業者となることを選択する場合に提出する書類です。例えば、多額の設備投資を行い、消費税の還付を受けられる可能性がある場合などに検討されます。提出期限は、課税事業者になろうとする課税期間の初日の前日までです。
消費税簡易課税制度選択届出書
消費税簡易課税制度選択届出書は、消費税の計算を簡易課税で行いたい場合に提出する書類です。業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて消費税額を計算するため、事務負担を軽減できます。提出期限は、適用を受けようとする課税期間の前日までです。
都道府県税事務所・市町村役場
法人設立届出書(都道府県税事務所・市町村役場)
法人設立届出書(都道府県税事務所・市町村役場)は、税務署への届出とは別に、都道府県税事務所や市町村役場にも提出が必要です。これは法人住民税や法人事業税など、地方税に関する手続きのためです。
提出期限や必要添付書類は各自治体で異なりますが、多くの場合、設立日から2週間~2ヶ月以内に設定されています。例えば、東京都税事務所の場合は事業開始日から15日以内です。添付書類としては、定款の写しと登記事項証明書が必要となることが多いです。提出先自治体のウェブサイト等で事前に確認しましょう。
労務関係の届出・手続
会社設立後、従業員を雇用する場合や、法人として社会保険加入義務が発生する場合は、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所への届出・手続きが必要です。
労働基準監督署
労働基準監督署は、労働基準法や労働安全衛生法など、労働条件や労働者の安全衛生に関する法令を管轄する機関です。会社設立後、従業員を雇用する際は、以下の届出・手続きが必要となる場合があります。
労働保険保険関係成立届
労働保険保険関係成立届は、従業員(パート・アルバイトを含む)を一人でも雇用した場合に、労災保険・雇用保険の保険関係成立のために提出が必要です。提出期限は、保険関係が成立した日(最初の従業員雇用日)の翌日から10日以内です。
添付書類として、法人の場合は登記簿謄本、個人事業主の場合は住民票が必要です。また、原則として労働保険概算保険料申告書も添付します。事業所所在地が登記上のものと異なる場合は、賃貸契約書の写しが必要となることがあります。
労働保険概算保険料申告書
労働保険概算保険料申告書は、労働保険の保険関係成立後、その年度の労働保険料(労災保険料と雇用保険料の概算額)を申告・納付するための書類です。提出期限は、保険関係が成立した日の翌日から50日以内です。通常、「労働保険保険関係成立届」の事業主控えを添付します。
適用事業報告書
適用事業報告は、会社が労働基準法の適用を受ける事業所となったことを報告するための書類です。従業員を一人でも雇用した場合に提出が必要であり、提出期限は、適用事業となった後、遅滞なくとされています。添付書類は特にありません。
就業規則届
常時10人以上の従業員を使用する事業所は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。就業規則を作成または変更した場合は、遅滞なく提出する必要があります。提出の際は、就業規則と、労働者代表の意見書を添付します。
ハローワーク
ハローワーク(公共職業安定所)は、主に雇用保険に関する業務を取り扱っています。従業員を雇用し、雇用保険の加入要件を満たす場合は、以下の届出・手続きが必要です。
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険の適用事業所となった場合に、その事実を届け出るための書類です 。提出期限は、適用事業所となった日の翌日から10日以内です 。添付書類として、登記簿謄本、雇用契約書、労働基準監督署受理済みの労働保険保険関係成立届の事業主控えなどが必要です 。労働者の雇用実態や賃金支払い状況を証明する書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)も求められることがあります 。
雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険適用事業所設置届は、雇用保険の適用事業所となった事実を届け出るための書類です。提出期限は、適用事業所となった日の翌日から10日以内です。添付書類として、登記簿謄本、雇用契約書、労働基準監督署受理済みの労働保険保険関係成立届の事業主控えなどが必要です。労働者の雇用実態や賃金支払状況を証明する書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)も求められることがあります。
年金事務所
年金事務所は、主に健康保険、厚生年金保険に関する業務を取り扱っています。法人として会社を設立した場合、原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられています。
健康保険・厚生年金保険新規適用届
健康保険・厚生年金保険新規適用届は、法人が新たに社会保険の適用事業所となるための届出です。提出期限は会社設立日から5日以内と非常に短いので注意が必要です。添付書類として、法人(商業)登記簿謄本(発行から90日以内の原本)、法人番号指定通知書のコピーが必要です。事業所所在地が登記簿謄本と異なる場合は、賃貸借契約書のコピーや公共料金の領収書などが別途必要になることがあります。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届は、役員や従業員が社会保険に加入する際に、その資格取得を届け出るための書類です。提出期限は、資格取得の事実があった日(設立日または入社日)から5日以内です。原則として添付書類は不要です。ただし、60歳以上の方が退職後1日も空けずに再雇用された場合など、特定のケースでは添付書類が必要になることがあります。
健康保険被扶養者(異動)届
健康保険被扶養者(異動)届は、被保険者に扶養家族がいる場合や、扶養家族に異動があった場合に提出する書類です。提出期限は、事実発生から5日以内です。添付書類として、戸籍謄本や住民票、収入を証明する書類などが必要になります。
主要な届出・手続の期限と必要書類一覧
提出が必須または強く推奨される税務上の届出をハイライトしています。その他の届出の提出は、税理士にご相談いただいたうえで提出されることを推奨します。また、労務関係の届出については、適用要件に該当した際に、遅滞なく届出をするようにしてください。
| 提出先 | 届出・手続名 | 期限 | 主な添付書類 |
|---|---|---|---|
| 税務署 | 法人設立届出書 | 設立日から2ヶ月以内 | 定款の写し |
| 青色申告の承認申請書 | 設立日から3ヶ月以内または最初の事業年度終了日の前日まで | なし | |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設日から1ヶ月以内 | なし | |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 随時 | なし | |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立第1期の確定申告書提出期限まで | なし | |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 設立第1期の確定申告書提出期限まで | なし | |
| 事前確定届出給与に関する届出書 | 株主総会決議日から1ヶ月以内など | 届出書、株主総会議事録の写し | |
| 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書 | 最初に適用を受けようとする事業年度終了の日までなど | 定款の写し | |
| 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 該当する場合速やかに | なし | |
| 適格請求書発行事業者の登録申請書 | 特になし | 納税地の異動に関する届出書の写し(該当する場合) | |
| 消費税課税事業者選択届出書 | 選択しようとする課税期間の初日の前日まで | なし | |
| 消費税簡易課税制度選択届出書 | 選択しようとする課税期間の前日まで | なし | |
| 都道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 各自治体による | 定款の写し、登記事項証明書(自治体による) |
| 市町村役場 | 法人設立届出書 | 同上 | 同上 |
| 労働基準監督署 | 労働保険保険関係成立届 | 雇用日の翌日から10日以内 | 登記簿謄本、労働保険概算保険料申告書、賃貸契約書の写し(場合による) |
| 労働保険概算保険料申告書 | 雇用日の翌日から50日以内 | 労働保険保険関係成立届の事業主控え | |
| 適用事業報告書 | 雇用後遅滞なく | なし | |
| 就業規則届 | 常時10人以上雇用後遅滞なく | 就業規則、労働者の意見書 | |
| ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 適用事業所となった日の翌日から10日以内 | 登記簿謄本、雇用契約書、労働保険保険関係成立届の事業主控え、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用日の翌月10日まで | 原則なし(場合により雇用保険被保険者証など) | |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 設立日から5日以内 | 登記簿謄本、法人番号指定通知書のコピー、賃貸借契約書のコピー(場合による) |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 設立日または雇用日から5日以内 | 原則なし(特定のケースでは添付書類あり) | |
| 健康保険被扶養者(異動)届 | 事実発生から5日以内 | 戸籍謄本、住民票、収入証明書など |
まとめ

会社設立後の税務・労務関係の届出・手続きは多岐にわたり、それぞれ提出期限や必要書類が定められています。本記事で解説した通り、正確な情報を把握し、適切に手続きを行うことが、法令遵守と円滑な事業運営の鍵となります。特に社会保険関係の届出など、提出期限が非常に短いものもあるため、設立直後から計画的に準備を進めましょう。
本記事の情報は最新のものに基づいていますが、法改正等により変更される可能性もあります。常に最新情報を確認するため、国税庁、厚生労働省、日本年金機構のウェブサイトを参照したり、税理士、社会保険労務士などの専門家へ相談したりすることを推奨します。