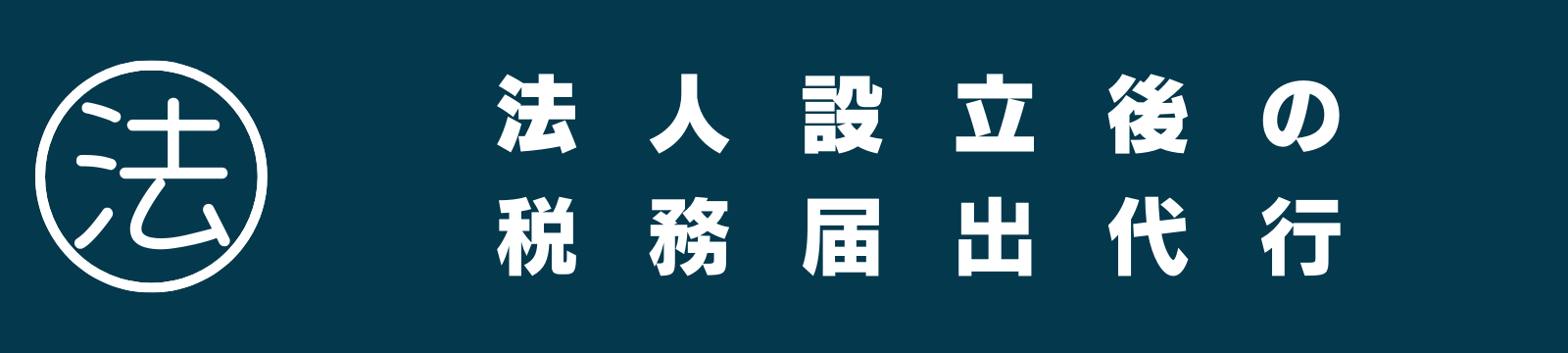「ついに自分の会社を設立したぞ!」
大きな夢と希望を胸に、法務局での登記手続きを終えたばかりのあなた。その達成感と興奮は、何物にも代えがたいものでしょう。会社設立、誠におめでとうございます。
しかし、安堵のため息をつくのは、まだ少し早いかもしれません。実は、会社の登記完了は、長い航海の「出港準備」が整ったに過ぎません。これからあなたの会社が事業という大海原へ漕ぎ出すためには、税務署や年金事務所など、さまざまな官公庁へ「航海の届出」を行う必要があるのです。
- 「登記が終わったら、あとは事業を始めるだけだと思っていた…」
- 「具体的に、いつまでに、どこへ、何を提出すればいいの?」
- 「本業の準備で忙しくて、手続きのために平日に役所へ行く時間なんてない…」
- 「もし手続きを忘れたら、何か罰則でもあるの?」
もしあなたが今、このような不安や疑問を抱えているなら、ご安心ください。本記事は、まさにそんなあなたのために書かれました。
この記事では、公認会計士・税理士である筆者が、会社設立後に必要な手続きの全体像から、専門家への代行依頼のメリット・デメリット、費用相場まで、プロの視点で網羅的に解説します。
この記事を最後まで読めば、設立後の手続きに関する不安は完全に解消され、自信を持って事業のスタートダッシュを切ることができるでしょう。
【この記事の結論】面倒な設立後の手続きは、オンライン完結のスポット代行が最適解
先にこの記事の結論からお伝えします。
会社設立後の煩雑な手続き、特に税務関連の届出は、専門家(税理士)に代行を依頼するのが最も効率的で確実です。中でも、まだ顧問税理士を探す段階ではない起業家にとっては、必要な手続きだけを低価格で依頼できる「スポット代行サービス」が最適解と言えます。
中でも、本記事でご紹介する「法人設立後の税務届出代行」サービスは、
- LINEで申し込みから完了まで全てが完結する手軽さ
- 顧問契約不要で、税務届出のみを5,500円(税込)で依頼できる明朗会計
- 国家資格者である税理士が直接対応する安心感
を兼ね備えており、多忙な起業家にとってまさに「救世主」とも言えるサービスです。
なぜそう言えるのか、これから詳しく解説していきます。まずは、なぜこれらの手続きがそれほど重要なのか、その理由から見ていきましょう。
第1章:なぜ会社設立後の手続きが重要なのか?放置する3つの深刻なリスク
「少しぐらい手続きが遅れても、大丈夫だろう」そう考えるのは非常に危険です。会社設立後の手続きは、単なる事務作業ではありません。これらは法律で定められた法人の「義務」であり、怠った場合には事業の根幹を揺るがしかねない深刻なリスクが伴います。
リスク1:【最大のリスク】青色申告の承認が受けられず、納税額が大幅に増加する
会社設立後の手続きで、最も致命的なミスが「青色申告の承認申請書」の提出忘れです。
青色申告とは、正規の簿記の原則に従って帳簿を作成することを条件に、税制上の様々な優遇措置を受けられる制度です。この申請書を期限内に提出しない場合、自動的に「白色申告」となり、以下のような特典をすべて受けられなくなります。
青色申告の主なメリット
- 欠損金(赤字)の繰越控除:
- 設立初年度が赤字だった場合、その赤字を最大10年間繰り越し、翌年度以降に発生した黒字と相殺できます。これにより、将来の法人税を大幅に節約できます。
- 例: 1年目に300万円の赤字、2年目に500万円の黒字が出た場合
- 青色申告: 500万円(黒字) – 300万円(繰越赤字) = 200万円が課税対象
- 白色申告: 500万円(黒字)がそのまま課税対象
- 少額減価償却資産の特例:
- パソコンやデスクなど、1個あたり30万円未満の資産を購入した場合、年間合計300万円まで、購入した年度に一括で経費(損金)にできます。これにより、設備投資を行った年度の税負担を軽減できます。
- 白色申告の場合、原則として10万円以上の資産は、定められた耐用年数に応じて数年間に分けて減価償却(経費化)しなければなりません。
- その他:
- 特別償却や税額控除など、様々な優遇措置が用意されています。
提出期限は「設立の日以後3ヶ月を経過した日」と「第1期の事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日までです。この期限をたった1日でも過ぎてしまうと、設立1期目は青色申告が適用できず、本来払う必要のなかった多額の税金を納めることになりかねません。これはスタートアップ期のキャッシュフローにとって、計り知れない打撃となります。
リスク2:無申告加算税や延滞税など、余分なペナルティが発生する
法人設立届出書を提出しない、あるいは法人税の申告・納税を期限内に行わない場合、以下のようなペナルティが課せられます。
- 無申告加算税: 納付すべき税額に対して、最大20%の割合で課される附帯税。
- 延滞税: 法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される、利息に相当する附帯税。
- 青色申告の承認取消: 2期連続で期限内に申告しなかった場合、青色申告の承認が取り消されることがあります。
これらのペナルティは、本来であれば支払う必要のないコストです。無駄な支出を避けるためにも、期限内の手続きは絶対です。
リスク3:社会的信用を失い、融資や取引に悪影響が出る
税務や社会保険の手続きを適切に行っていない会社は、金融機関や取引先から「コンプライアンス意識の低い、信頼できない会社」と見なされます。
- 融資審査への影響: 日本政策金融公庫や銀行から創業融資を受けようとする際、税務署の受付印がある各種届出書の控えの提出を求められることがほとんどです。手続きを怠っていると、融資の審査で不利になる、あるいは融資自体を受けられない可能性があります。
- 取引上の不利益: 大企業との取引では、コンプライアンス体制が厳しくチェックされます。社会保険に未加入であることなどが発覚すれば、取引を断られるケースも考えられます。
このように、設立後の手続きを軽視すると、税金面だけでなく、資金調達や事業拡大の面でも大きな足かせとなってしまうのです。
第2章:【完全網羅】会社設立後に必要な手続きチェックリスト&カレンダー
設立後の手続きの重要性をご理解いただけたところで、次に「具体的に何をすべきか」を明確にしていきましょう。手続きは大きく分けて「①税務関連」「②社会保険・労働保険関連」「③その他」の3つに分類されます。
ここでは、提出先、提出期限、そして手続きの概要を一覧にまとめました。ご自身の会社の状況と照らし合わせながら、抜け漏れがないかチェックしてください。
最優先で対応すべき手続きカレンダー(モデルケース)
多くの手続きには期限があります。ここでは、4月1日に会社を設立した場合のモデルスケジュールをご紹介します。
| 時期 | 手続き | 提出先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 設立後すぐ | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 年金事務所 | 従業員がいなくても社長1人でも加入義務あり |
| 〜4月中旬 | 法人設立届出書 | 都道府県税事務所・市町村役場 | 期限が短い場合が多いので最優先で |
| 従業員雇用後すぐ | 労働保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 雇用から10日以内 |
| 従業員雇用後すぐ | 雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク | 雇用から10日以内 |
| 〜5月末日 | 法人設立届出書 | 税務署 | 設立から2ヶ月以内 |
| 〜5月末日 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 給与支払開始から1ヶ月以内 |
| 〜6月30日 | 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 【最重要】 設立から3ヶ月以内 |
| 随時 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 適用を受けたい月の前月末まで |
① 税務関連の手続き(事業を行うすべての法人が対象)
税務関連の手続きは、会社の利益や節税に直結する最も重要な手続きです。
1. 法人設立届出書
- 目的: 会社を設立したことを国や地方自治体に知らせ、納税義務者として登録するための届出。
- 提出先と期限:
- 税務署: 設立の日から2ヶ月以内
- 都道府県税事務所: 設立の日から1ヶ月以内(自治体により異なる)
- 市町村役場: 設立の日から1ヶ月以内(自治体により異なる)
- ※東京23区内に本店を置く場合は、都税事務所への提出のみでOK。
- 添付書類: 定款の写し、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)など。
ポイント: 提出先が3ヶ所に分かれているのが面倒な点です。また、都道府県と市町村は税務署よりも期限が短く設定されていることが多いため、登記が完了したら真っ先に準備に取り掛かりましょう。
2. 青色申告の承認申請書
- 目的: 青色申告の様々な税制優遇(欠損金の繰越控除など)を受けるための申請。
- 提出先: 税務署
- 提出期限: 設立の日から3ヶ月以内(正確には、設立日以後3ヶ月を経過した日と第1期事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで)
- 添付書類: なし
ポイント: 前章で解説した通り、これを出し忘れることのデメリットは計り知れません。法人設立届出書と同時に、必ず提出しましょう。
3. 給与支払事務所等の開設届出書
- 目的: 役員報酬や従業員給与を支払い、源泉徴収(給与から所得税を天引き)を始めることを税務署に知らせるための届出。
- 提出先: 税務署
- 提出期限: 給与支払事務所を開設してから1ヶ月以内
- 添付書類: なし
ポイント: 社長1人の会社でも、役員報酬を支払う場合は提出が必要です。法人設立届出書と同時に提出するのが一般的です。
4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 目的: 毎月10日に行う源泉所得税の納付を、年2回(7月10日と翌年1月20日)にまとめるための申請。
- 適用要件: 給与の支給人員が常時10人未満であること。
- 提出先: 税務署
- 提出期限: 適用を受けたい月の前月末日まで
ポイント: 毎月の納付手続きは意外と手間がかかるため、小規模な会社にとっては事務負担を大幅に軽減できる便利な制度です。
② 社会保険・労働保険関連の手続き(役員報酬や従業員給与を支払う法人が対象)
法人は、たとえ社長1人であっても社会保険への加入が法律で義務付けられています。
1. 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 目的: 健康保険・厚生年金保険に加入するための手続き。
- 提出先: 年金事務所
- 提出期限: 事業所を設立してから5日以内
- 添付書類: 登記事項証明書の写しなど。
ポイント: 提出期限が「5日以内」と非常に短いため注意が必要です。社長自身の「被保険者資格取得届」も併せて提出します。
2. 労働保険 関係成立届
- 目的: 従業員(パート・アルバイト含む)を1人でも雇用した場合に、労災保険と雇用保険の保険関係を成立させるための手続き。
- 提出先: 労働基準監督署
- 提出期限: 従業員を雇用した日の翌日から10日以内
3. 雇用保険 適用事業所設置届
- 目的: 雇用保険に加入する事業所であることを届け出る手続き。
- 提出先: ハローワーク
- 提出期限: 事業所を設置した日の翌日から10日以内
③ その他の手続き
- 許認可の申請: 建設業、飲食業、古物商、人材派遣業など、事業内容によっては行政の許認可が必要です。許認可なしで営業すると罰則の対象となるため、事前に必ず確認しましょう。
- 法人口座の開設: 事業用の資金管理や取引の信用度向上のために、法人口座は必須です。開設には登記事項証明書や定款などが必要となり、審査にも時間がかかるため、早めに申し込みましょう。
- 役員報酬の決定: 役員報酬の金額は、設立から3ヶ月以内に決定する必要があります。一度決定すると、原則として事業年度の途中では変更できないため、慎重に検討しましょう。
第3章:手続きは誰に頼む?専門家ごとの役割と選び方
これだけ多くの手続きがあると、「自分一人で全部やるのは無理かもしれない…」と感じるのも無理はありません。ここで選択肢となるのが、専門家への代行依頼です。
しかし、「会社設立後の手続き」と一言で言っても、その内容によって相談すべき専門家は異なります。ここでは、各専門家の役割と、どのようなケースで誰に依頼すべきかを解説します。
税理士 (Tax Accountant) – 税金と会計のプロフェッショナル
- 主な役割:
- 税務関連の届出代行(法人設立届出書、青色申告など)
- 日々の記帳代行、決算申告
- 節税対策のアドバイス
- 資金調達(融資)のサポート、経営コンサルティング
- 依頼すべきケース:
- 今回のテーマである「設立後の税務届出」を依頼したい場合、第一の相談先となります。
- 経理や会計の知識に不安がある。
- 効果的な節税を行いたい。
- 将来的に顧問契約を結び、経営全般の相談相手が欲しい。
司法書士 (Judicial Scrivener) – 登記のプロフェッショナル
- 主な役割:
- 会社設立の登記申請
- 役員変更や本店移転などの登記変更
- 不動産登記
- 依頼すべきケース:
- 会社設立の登記手続きそのものを依頼する場合。設立後の税務届出などは業務範囲外です。
社会保険労務士 (Social Insurance and Labor Consultant) – 人事と労務のプロフェッショナル
- 主な役割:
- 社会保険・労働保険の手続き代行
- 就業規則の作成、給与計算
- 助成金の申請代行
- 労務トラブルに関する相談
- 依頼すべきケース:
- 従業員を雇用し、社会保険や労働保険の手続きを任せたい場合。
- 助成金の活用を検討している場合。
行政書士 (Administrative Scrivener) – 許認可申請のプロフェッショナル
- 主な役割:
- 事業に必要な許認可の申請代行(建設業許可、飲食店営業許可など)
- 会社設立時の定款作成
- 官公庁に提出する書類の作成全般
- 依頼すべきケース:
- 自分の事業に許認可が必要な場合。
【まとめ】設立後の手続き、誰に何を頼むべきか?
| 手続き内容 | 主な相談先 |
|---|---|
| 税務届出(法人設立届出書、青色申告など) | 税理士 |
| 社会保険・労働保険の手続き | 社会保険労務士 |
| 許認可の申請 | 行政書士 |
| 会社設立の登記 | 司法書士 |
このように、手続きごとに専門家が分かれているのが実情です。そのため、複数の手続きを代行してほしい場合は、それぞれの専門家を探すか、あるいは税理士や司法書士が他の専門家と連携している「ワンストップサービス」を提供している事務所に依頼するのが効率的です。
第4章:手続き代行のメリット・デメリットと気になる費用相場
専門家に依頼すべきなのは分かったけれど、やはり気になるのは「費用」と「本当にそれだけの価値があるのか」という点でしょう。ここでは、代行を依頼するメリットとデメリット、そして具体的な費用相場を詳しく見ていきます。
代行を依頼する5つの絶大なメリット
メリット1:圧倒的な時間の節約【本業に集中できる】
もしこれらの手続きをすべて自分で行う場合、どれくらいの時間がかかるでしょうか?
- 情報収集: どの書類が必要で、どこで入手し、どう書くのかを調べる時間(推定:3〜5時間)
- 書類作成: 慣れない書類の記入に費やす時間(推定:3〜4時間)
- 役所回り: 税務署、都道府県税事務所、市町村役場、年金事務所などを平日の日中に回る時間(移動・待ち時間含め、推定:丸1日〜2日)
合計すると、最低でも2〜3日は本業の時間を削られることになります。あなたの1日の稼働価値が3万円だとすれば、それだけで6〜9万円分の機会損失が発生しているのと同じです。代行を依頼すれば、この貴重な時間をすべて本業の準備や営業活動に充てることができます。
メリット2:ミスの防止と確実性【ペナルティを回避】
専門家は、日々これらの業務を行っているプロです。書類の記載ミスや添付書類の漏れ、そして何より「提出期限」を確実に守ってくれます。特に青色申告の申請忘れのような、取り返しのつかないミスを防げることは、代行費用以上の価値があると言えるでしょう。
メリット3:精神的な負担からの解放
「あの手続き、期限はいつまでだっけ…」「この書き方で合っているのかな…」
事業の立ち上げで頭がいっぱいの中、常に手続きのことが頭の片隅にある状態は、大きな精神的ストレスになります。この見えない負担から解放され、事業のことだけを考えられる環境を手に入れられるのは、大きなメリットです。
メリット4:節税メリットの最大化
税理士に依頼すれば、青色申告の適用を確実に受けられるだけでなく、設立時の資本金の設定や役員報酬の金額など、将来の節税を見据えたアドバイスをもらえる可能性があります。
メリット5:専門家との繋がりができる
今回依頼した専門家と良好な関係を築ければ、将来的に何か困ったことがあった際に、気軽に相談できる心強いパートナーとなります。
デメリットと注意点
もちろん、デメリットも存在します。
- 費用がかかる: 当然ながら、専門家への報酬が発生します。
- 専門家との相性: レスポンスが遅かったり、説明が分かりにくかったりと、コミュニケーションがうまくいかないケースも稀にあります。
- 丸投げによる知識不足: 全てを任せきりにしてしまうと、経営者として最低限知っておくべき税務や労務の知識が身につきにくいという側面もあります。
【費用相場】会社設立後の手続き代行はいくらかかる?
依頼する範囲や事務所によって料金は様々ですが、一般的な相場は以下の通りです。
- 税務関連の届出のみ(法人設立届出書、青色申告など)
- 相場: 1万円 〜 3万円程度
- 税務+社会保険の手続きセット
- 相場: 5万円 〜 10万円程度
- 税理士との顧問契約とセットの場合
- 「設立後の届出代行費用:0円」
- これは、月々数万円の顧問料に、届出代行の実質的な費用が含まれているモデルです。設立当初から継続的なサポートを求める場合には良い選択肢ですが、「まずは届出だけお願いしたい」という方には不向きです。
第5章:【結論】時間がない・面倒なら「スポット代行」が今のあなたに最適
ここまでの内容を整理しましょう。
- 会社設立後の手続きは複雑で期限もあり、放置するとリスクが大きい。
- 自分でやるには多くの時間が奪われ、ミスをする可能性もある。
- 専門家に依頼すれば確実だが、顧問契約を結ぶと月々の費用が発生する。
この状況を踏まえた上で、設立間もない起業家にとって最も合理的で賢い選択肢は何か?
それが、顧問契約を結ばずに、設立後の届出という「必要な作業」だけを単発で依頼する『スポット代行』という選択です。
なぜ今「スポット代行」が選ばれるのか?
- コストを最小限に抑えられる
- 設立当初は、まだ売上も安定せず、毎月数万円の顧問料は大きな負担です。「スポット代行」なら、1〜3万円程度の支払いで、当面の煩雑な手続きをすべて完了させることができます。
- 顧問契約は、事業が軌道に乗ってからでOK
- 本当に税理士のサポートが必要になるのは、日々の取引が増え、売上が立ち、決算が近づいてくるタイミングです。まずはスポットで手続きを済ませ、事業の成長に合わせて顧問契約を検討するのが賢明です。
- 専門家との「お試し」にもなる
- スポットで依頼してみて、その税理士の対応の速さや人柄、説明の分かりやすさなどを確認できます。もし相性が良いと感じれば、将来の顧問契約の有力な候補となるでしょう。
そして、この「スポット代行」の利便性を極限まで高めたのが、『オンライン完結型』のサービスです。
税理士事務所に足を運ぶ必要も、電話で何度もやり取りする必要もありません。スマートフォン一つで、いつでもどこでも依頼が完結する。これこそ、時間と場所に縛られずに働く現代の起業家に最適なスタイルではないでしょうか。
第6章:【サービス紹介】LINEで完結!税理士による『法人設立後の税務届出代行』
お待たせいたしました。
これまでの解説で浮き彫りになった、「低コストで、確実に、手間なく、設立後の税務届出を完了させたい」というあなたのニーズを、完璧に満たすサービスをご紹介します。
それが、のどか会計事務所が提供する「法人設立後の税務届出代行」です。
このサービスが、他の代行サービスと一線を画す「4つの特徴」
特徴1:圧倒的な手軽さ!『LINEで完結』
このサービスの最大の特徴は、申し込みから必要書類の提出、そして完了報告まで、すべてのやり取りがLINEで完結する点です。
- 面倒な会員登録は不要
- 電話やメールでの煩わしいやり取りも一切なし
- 税理士事務所へ出向く必要もありません
あなたは、LINEのトーク画面でいくつかの質問に答えて、定款の写しと本人確認書類の写真を送るだけ。あとは専門家である税理士が、責任を持ってすべての手続きを電子申請で完了させてくれます。
特徴2:驚きの低価格!『顧問契約不要で5,500円』
「専門家に頼むと高いのでは…」という心配は無用です。
このサービスは、設立後の税務届出に特化したスポット契約のため、顧問契約を結ぶ必要は一切ありません。
料金は、以下の手続きがすべて含まれた基本パッケージで、わずか5,500円(税込)。
【基本パッケージに含まれる内容】
- 法人設立届出書(税務署・都道府県・市町村の3ヶ所分)の作成・提出
- 青色申告の承認申請書の作成・提出
- 給与支払事務所等の開設届出書の作成・提出
- e-Tax(国税電子申告システム)のID・パスワード発行
- eLTAX(地方税電子申告システム)のID・パスワード発行
一般的な相場(1万円〜3万円)と比較しても、非常にリーズナブルな価格設定です。さらに、クレジットカード決済にも対応しているため、支払いもスムーズです。
特徴3:絶対的な安心感!『公認会計士・税理士が直接対応』
安さや手軽さだけではありません。このサービスを運営するのは、公認会計士・税理士・行政書士の国家資格を持つ、小野好聡氏が代表を務める「のどか会計事務所」です。
無資格のスタッフではなく、税務と会計のプロフェッショナルである税理士本人が、あなたの会社の届出を直接、そして責任を持って代行します。専門家ならではの視点で、あなたの会社の状況に合わせた最適な届出を確実に行います。
特徴4:全国どこでもOK!『日本全国対応』
手続きはすべてオンライン(電子申請)で行うため、あなたが日本のどこで会社を設立したとしても、サービスを利用することが可能です。北は北海道から南は沖縄まで、地域を問わず、すべての起業家をサポートします。
ご利用の流れは、驚くほど簡単な4ステップ
- 公式LINEを友だち追加
- まずは、「法人設立後の税務届出代行」サービスサイトのボタンから公式LINEを友だち追加します。
- 必要事項の入力&書類提出
- LINEで送られてくる質問フォームに、会社の基本情報を入力します。
- 定款の写しと、代表者の本人確認書類(運転免許証など)をスマホで撮影し、LINEで送信します。
- 料金のお支払い
- LINEで案内される決済ページから、クレジットカードで料金(5,500円)を支払います。
- 手続き完了&データ納品
- 税理士が各種届出書の作成と電子申請を行います。申請が完了したら、提出した書類の控えと、e-Tax/eLTAXのID・パスワードがデータで納品されます。
これだけです。あなたは役所に一度も足を運ぶことなく、設立後の最も重要で面倒な税務手続きを、すべて完了させることができます。
こんな方にこそ、このサービスをおすすめします!
✅ 本業の立ち上げが忙しく、役所に行く時間がない方
✅ 手続きが複雑で、自分でやるのが面倒だと感じている方
✅ 書類の書き方や提出期限に不安があり、ミスなく確実に終わらせたい方
✅ コストは最小限に抑えたいが、専門家にお願いしたい方
✅ まずはスポットで依頼して、信頼できる税理士か見極めたい方
✅ 電話や対面でのやり取りが苦手で、チャットで気軽に済ませたい方
もし一つでも当てはまるなら、このサービスはあなたのためのものだと言っても過言ではありません。
よくある質問(Q\&A)
- Q. 本当に顧問契約は不要ですか?後から勧誘されたりしませんか?
- A. はい、完全にスポットでのご依頼ですので、顧問契約は一切不要です。手続き完了後に、しつこい営業を行うこともございませんのでご安心ください。
- Q. 介護事業以外の業種でも依頼できますか?
- A. はい、もちろんです。運営母体の「のどか会計事務所」は介護・障がい福祉分野に強みを持っておりますが、本サービスはIT、飲食、小売、建設など、あらゆる業種の法人様にご利用いただけます。
- Q. 依頼してから完了まで、どれくらいの日数がかかりますか?
- A. お客様からの情報とご入金が確認できてから、通常3〜5営業日ほどで申請を完了いたします。お急ぎの場合は、その旨をLINEでお知らせください。
- Q. 社会保険の手続きもお願いできますか?
- A. 本サービスは「税務届出」に特化しております。社会保険の手続きは、提携している社会保険労務士をご紹介することが可能ですので、お気軽にご相談ください。
まとめ:面倒な手続きはプロに任せ、あなたは事業の成長に全集中を!
本記事では、会社設立後に必要となる手続きの重要性から、具体的な内容、そして専門家への代行依頼という選択肢について、詳しく解説してきました。
改めて、重要なポイントを振り返ります。
- 会社設立後の手続き、特に「青色申告の承認申請」は期限厳守が絶対。
- 手続きを怠ると、余計な税金を払う、融資が受けられないなど、深刻なリスクがある。
- 自分で全て行うには、多くの時間と手間がかかり、ミスの可能性も伴う。
- 多忙な起業家にとって、顧問契約不要の「スポット代行」が最も賢い選択。
あなたの時間は有限であり、何よりも貴重な経営資源です。その貴重な時間を、慣れない書類作成や役所回りに費やすべきでしょうか?それとも、商品開発、顧客開拓、資金調達といった、会社の未来を創る本質的な業務に投下すべきでしょうか?
答えは、明白です。
今回ご紹介した「法人設立後の税務届出代行」サービスは、あなたの貴重な時間を守り、設立後の不安を解消するための強力なツールです。たった5,500円という投資で、「時間」「安心」「確実性」の3つを手に入れることができるのです。
面倒な手続きは、信頼できるプロフェッショナルに任せる。そして、あなたは社長として、あなたの事業を成長させることだけに、全ての情熱と時間を注ぎ込んでください。
さあ、今すぐ下のボタンから公式LINEを友だち追加して、スムーズな事業のスタートを切りましょう!