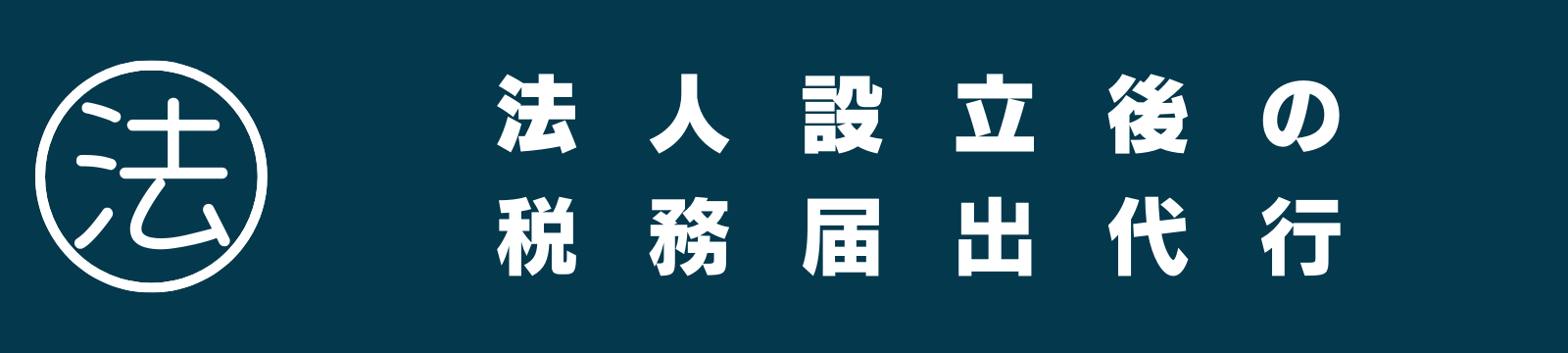はじめに

日本における会社設立には、主に株式会社と合同会社の2つの形態があります。株式会社は、株式発行による資金調達を前提とした法人形態であり、比較的規模の大きな企業や、将来的な株式公開を目指す企業に多く選択されます。一方、合同会社は、出資者(社員)が直接経営に関与する持分会社であり、設立手続きが比較的簡便で、柔軟な組織運営が可能です。近年、合同会社は中小企業やスタートアップを中心に、設立件数を増やしています。
本記事では、日本全国で共通する株式会社と合同会社の設立手続きについて、設立準備段階から設立後の手続きまでを時系列で網羅的に解説します。それぞれの会社形態の特徴を踏まえつつ、具体的な手続きの流れ、必要な準備、留意点を詳細に説明します。本記事が、日本での会社設立を検討されている皆様にとって、有益な情報源となれば幸いです。

会社設立の方法
まず結論として、会社設立手続は、非常に煩雑かつ、注意すべきポイントも多いです。このため、自分一人で進めるのではなく、専門家や会社設立サービスに頼ることをおすすめします。
この時に依頼する専門家として、会社設立などの商業登記を独占業務としている「司法書士」に依頼するのが一般的です。なお、複雑な許認可が絡む場合には、定款の作成に行政書士が関与する場合もあります。この場合、通常、会社設立のために必要な印紙代等の法定費用のほかに、登記書類の作成と申請手数料が発生します。
また、「マネーフォワードクラウド会社設立」のように、フォームに必要事項を入力するだけで、会社設立登記に必要な書類が作成できるサービスもあります。専門家に定款のチェックもして貰えるので安心です。また、電子定款による登記となるため、印紙代の負担が4万円軽減されるといったメリットもあります。手間と費用を抑えつつ自身で会社設立手続を進めたいなら、こういったサービスを利用することをおすすめします。
株式会社と合同会社に共通する設立準備
株式会社と合同会社の設立手続きには、共通して行うべき準備段階が存在します。この段階で適切な準備を行うことが、その後の手続きを円滑に進める上で非常に重要となります。
会社名(商号)の決定
株式会社と合同会社のいずれにおいても、会社名(商号)の決定は最初の重要なステップです。会社名は、法務省が定めたルールに従って決定する必要があります。商号は、今後の事業展開に大きく影響する重要な要素であり、後から変更するには費用と手間がかかるため、慎重に検討しましょう。
株式会社、合同会社のいずれを設立する場合でも、会社名(商号)の決定は最初の重要なステップです。会社名は、法務省が定めるルールに従って決定する必要があります。商号は、今後の事業展開に大きく影響する要素であり、後から変更するには費用と手間がかかるため、慎重な検討が必要です。
会社名の制限①
会社名を決定する際には、いくつかのルールと制限があります。まず、株式会社の場合は「株式会社」、合同会社の場合は「合同会社」の文字を、会社名の前または後に必ず含めなければなりません。例えば、「〇〇株式会社」や「株式会社〇〇」といった形式です。略称である「K.K.」や「LLC」を登記に使用することはできません。ただし、「LLC」については、「合同会社」と併記する形であれば商号に含めることが可能です。
会社名の制限②
使用できる文字にも制限があります。漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字が使用可能です。符号については、「&」「’」「,」「-」「.」「・」などが、原則として字句を区切る場合に限り使用できます。ただし、これらの符号を先頭や末尾に用いることはできません。ローマ字を使用する場合に限り、単語と単語の間に空白(スペース)を入れることができます。疑問符(?)、感嘆符(!)、音符(♪)、星印(★)、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳなど)は使用できません。
会社名の制限③
同一の所在場所に、同一の商号(同じ名前の会社)を登記することはできません。これは、バーチャルオフィスやシェアオフィスのように、一つの住所に複数の会社が存在する場合に特に注意が必要です。事前に、法務局のオンライン登記情報提供サービスや管轄の法務局で調査することをおすすめします。
会社名の制限④
会社の一部門を示す文字(例:支店、支社、部門など)は、商号に使用できません。ただし、「代理店」や「特約店」といった文字は使用できる場合があります。また、銀行業、保険業、信託業、学校法人など、特定の事業を行う会社のみが使用できると法律で定められている文字は、該当する事業を行わない会社は使用できません。
会社名の制限⑤
実績のある有名企業や大手企業と誤認されるような名前は避けるべきです。著名な会社と同一または類似する商号の使用は、不正競争防止法に抵触する可能性があります。さらに、商標登録されている名称を使用すると、商標権侵害となるリスクもあります。公序良俗に反するような単語も使用できません。
会社名決定の際の留意事項①
会社名を検討する際には、ルールや制限だけでなく、いくつかの重要な検討事項があります。まず、覚えやすく、発音しやすい会社名を選ぶことが重要です。短い名前(3~4文字)は特に覚えやすい傾向があります。日本語の場合、母音から始まる言葉は発音しやすく耳に残りやすいとされています。事業内容が連想しやすい社名にすることもおすすめです。顧客に対して提供するサービスや製品のイメージを伝えやすくなります。
会社名決定の際の留意事項②
会社名と同一または類似するドメイン名が取得可能かどうかを確認することも重要です。これは、インターネットでの展開やSEO対策において非常に重要な要素となります。会社名には、創業の想いや理念を込めることもできます。由来を説明しやすい名前にすることで、会社のPRにも繋がります。海外展開を視野に入れている場合は、外国語での意味や発音も考慮しましょう。進出予定の国でネガティブな意味を持つ言葉や発音にならないか事前に確認することが望ましいです。
会社名決定の際の留意事項③
類似商号の調査は、法務局のオンライン登記情報提供サービスや窓口で行うことができます。以前は類似商号の規制がありましたが、現在は同一住所に同一商号がないかどうかが主な確認事項となっています。ただし、近隣に類似する商号で同一の事業を行っている会社がある場合などは、不正競争防止法による差止請求や損害賠償請求を受ける可能性もあるため、念のため調査しておくことを推奨します。商標調査は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用して無料で行うことができます。
会社名決定の際の留意事項④
会社名のアイデアが出ない場合は、事業内容や理念、創業者の名前、所在地、商品やサービス名、造語、縁起の良い言葉などを参考に検討したり、専門家に依頼したり、一般公募したりする方法もあります。造語にする場合は、読み間違いを防ぐためにカタカナ表記にするのが無難です。
事業目的の設定
事業目的とは、会社がどのような事業活動によって利益を上げるのかを明確にするものです。会社設立時に作成する定款に必ず記載しなければならない項目であり、会社は原則として、定款に記載されていない事業を行うことはできません。後から事業を追加する場合には、株主総会(株式会社の場合)または総社員の同意(合同会社の場合)での決議後、法務局への届出が必要です。
事業目的設定のポイント①
事業目的を設定する際には、いくつかの重要なポイントがあります。まず、事業目的は、適法性、営利性、明確性の3つの要件を満たす必要があります。違法な内容や公序良俗に反する目的、営利を目的としない活動(ボランティア活動など)、誰が見ても内容が理解できない不明瞭な記載は認められません。
事業目的設定のポイント②
現在すぐに行う事業だけでなく、将来的に行う可能性のある事業も記載しておくことをお勧めします。事業目的の数に制限はありませんが、多すぎると何をやっている会社かわかりにくくなるため、設立直後は絞った方が良いという意見もあります。一般的には、5~10個程度に抑えることが推奨されています。
事業目的設定のポイント③
許認可が必要な事業を行う場合は、許認可の要件を満たす文言を事業目的に含める必要があります。事前に、関係省庁に確認することが重要です。例えば、古物商許可を得るためには、「古物営業法に基づく古物商」という文言が必要です。
事業目的設定のポイント④
事業目的の最後には、「前各号に付帯関連する一切の事業」という文言を入れるのが一般的です。これにより、記載した事業に付随する関連事業も行うことができるようになります。
事業目的設定のポイント⑤
事業目的は、誰が見ても事業内容が明確にわかるように、具体的に記載しましょう。曖昧な表現や専門用語の多用は避けるべきです。同業他社の事業目的を参考にすることも有効です。会社のホームページや法人登記簿謄本で確認できます。
事業目的設定のポイント⑥
事業目的の記載が不明確であったり、違法な内容が含まれていたりすると、公証人の認証(株式会社の場合)を受けられず、定款そのものが無効となる可能性があります。また、税務、融資、許認可の取得にも影響を与える場合があるため、慎重に検討し、正確に記載することが重要です。
本店所在地の決定
本店所在地とは、会社の本店の住所を指します。会社設立の際に不可欠な情報であり、定款に必ず記載する必要があります。
本店所在地として指定できる場所
本店所在地として指定できる場所に特別な制限はありません。一般的には、店舗や事務所の住所を指定しますが、創業者の自宅や賃貸物件、レンタルオフィス、バーチャルオフィスなどを本店所在地にすることも可能です。
ただし、賃貸物件を本店所在地とする場合は、事前に大家さんや管理会社に事務所としての利用が認められているか確認をとっておきましょう。賃貸契約で法人登記が禁止されている場合もあります。公営住宅など、公的な賃貸物件の場合は特に注意が必要です。
自宅を本店所在地とする場合、登記情報として自宅の住所が公開されるため、プライバシーの面で問題が生じる可能性があります。また、取引先や金融機関からの信用を得にくい場合もあります。
バーチャルオフィスやコワーキングスペースも本店所在地として登録できますが、業種によっては事務所の要件が規定されている場合や、レンタル会社自体が法人登記を禁止している場合があるので、事前に確認が必要です。また、金融機関によっては、バーチャルオフィスを本店所在地とする企業に対して、追加書類の提出を求めたり、口座開設を断ったりするケースもあります。
本店所在地は、融資や助成金の申請にも影響を与える可能性があります。対象エリア内で本店所在地を検討する必要があります。
本店所在地の定款への記載方法
定款に本店所在地を記載する方法は、最小行政区画(市区町村、東京都の特別区)までとする方法と、具体的な番地まで記載する方法の2種類があります。最小行政区画までの記載例:「当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。」この場合、渋谷区内で本店を移転しても定款変更の手続きは不要です。具体的な番地までの記載例:「当会社は、本店を東京都渋谷区○○町1丁目2番3号に置く。」この場合、同じ市区町村内での本店移転であっても定款変更の手続きが必要になり、費用がかかります。
登記申請書には、定款の記載方法に関わらず、番地まで正確に記載する必要があります。ビル名や部屋番号は任意ですが、郵便物の確実な受取のためには記載することが推奨されます。定款に番地まで記載しない場合は、登記申請前に「本店所在地決定書」を作成し、本店所在地を確定させる必要があります。
事業年度の設定
事業年度とは、会社の決算を行う対象となる一定期間のことです。一般的には1年間と定められます。
事業年度の開始日と決算日は自由に設定することができます。例えば、事業年度の始期を4月1日に設定した場合、決算日は翌年3月31日になります。多くの日本企業は4月始まりの3月決算を採用していますが、これに縛られる必要はありません。
会社の繁忙期を避けたり、資金繰りが良い時期に決算日を設定するなど、ご自身の事業の都合に合った決算日にすることをおすすめします。事業年度は、定款に記載する必要があります。
法人用の印鑑の準備
会社設立の申請と、設立後の会社運営のためには、会社名義の印鑑が必要です。
一般的に準備される印鑑の種類は以下の通りです。
- 会社実印: 法務局への登記申請の際に必要となる、最も重要な印鑑です。
- 会社銀行印: 銀行の法人口座開設や、手形・小切手の振出などに必要です。
- 角印: 領収書や請求書など、代表者印を押すほど重要ではない書類への押印に用います。
- ゴム印: 契約書や署名欄を自筆サインではなく押印で済ませる際に便利です。
会社設立の手続きに必須となるのは会社実印のみですが、その他の印鑑もあらかじめ準備しておくことで、会社設立後の運営開始までの期間を短縮できます。
株式会社の設立手続
前項で解説した共通の準備に加え、株式会社の設立には特有の手続きが必要となります。
基本事項の決定
上記で解説した会社名、事業目的、本店所在地、事業年度、法人用印鑑の準備に加え、株式会社の設立には以下の基本事項を決定する必要があります。
資本金
まず、資本金についてです。株式会社設立に必要な資本金は、会社法上1円以上と定められています。しかし、資本金の額は会社の信用力や資金調達能力に影響を与えるため、事業計画や将来の展望を踏まえ、適切な金額を設定することが重要です。一般的には、初期費用と3~6ヶ月分の運転資金を目安に決定することが推奨されています。また、許認可が必要な事業では、最低資本金額が定められている場合があります。さらに、資本金の額は、消費税や法人住民税などの税金にも影響を与えるため、注意が必要です。
発起人
次に、発起人を決定します。発起人とは、会社を設立する手続きを進める人のことです。発起人は1人でも複数でも構いません。発起人になるためには、必ず1株以上の出資が必要です。
役員構成
役員構成も決定します。株式会社には、原則として最低1名以上の取締役が必要です。取締役の中から代表取締役を選定します。取締役会を設置する場合は、取締役3名以上と監査役1名以上の設置が必要です。役員の人数や構成は、会社の規模や事業内容によって決定します。
株式に関する事項
株式に関する事項として、発行可能株式総数を決定する必要があります。公開会社では発行済株式総数の4倍までと上限が決まっていますが、非公開会社においては上限は定められていません。設立後の資金調達を視野に入れて、高い上限を設定することも可能です。
設立日
最後に、設立日を決定します。登記申請を行った日が会社の設立日となります。土日祝日は設立日にできません。
定款の作成
決定した基本事項に基づき、会社の基本規則を定めた定款を作成します。定款には、必ず記載しなければならない絶対的記載事項、記載しないと効力が生じない相対的記載事項、任意で記載できる任意的記載事項があります。絶対的記載事項は、事業の目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名と住所、発行可能株式総数です。
定款は、書面または電子データ(電子定款)で作成することができます。電子定款は、印紙代4万円が不要になるというメリットがありますが、作成には専用のソフトウェアやICカードリーダーなどの準備が必要です。
定款の認証
作成した定款は、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。これは、株式会社の設立に必須の手続きです。認証には、公証人手数料(資本金の額によって3~5万円程度)と、紙の定款の場合は収入印紙代4万円、定款の謄本作成手数料などがかかります。電子定款の場合は収入印紙代は不要です。
認証を受ける際には、定款3通、発起人全員の印鑑証明書、実印、収入印紙(紙の場合)、公証人への手数料、定款の謄本交付手数料が必要です。代理人が行く場合は委任状なども必要になります。
資本金の払込み
定款の認証後、発起人は各自が引き受けた株式の払込金額を、発起人代表者の銀行口座に払い込みます。払込があったことを証明するため、払込証明書と、銀行口座の通帳のコピーなどを用意します。
設立登記の申請
資本金の払込が完了したら、本店所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行います。申請期間は、原則として、会社設立の基準となる日から2週間以内です(株式会社の場合、通常は発起設立における手続きの最終日、または募集設立における創立総会終結の日)。
設立登記の申請には、いくつかの書類を添付する必要があります。主な添付書類は、設立登記申請書、認証済みの定款、払込証明書、発起人の同意書(必要な場合)、設立時取締役の就任承諾書、設立時代表取締役の就任承諾書、設立時取締役の印鑑登録証明書、印鑑届出書などです。
登記の際には、登録免許税(資本金の額の1000分の7、最低15万円)を納付する必要があります。
設立後の手続き
登記完了後には、税務署、都道府県税事務所、市町村役場に法人設立の届出を行います。また、年金事務所やハローワークでの社会保険・雇用保険の加入手続きも必要です。さらに、事業活動を円滑に進めるため、法人口座を開設することも推奨されます。

合同会社の設立手続
合同会社は、株式会社と比較して設立手続きが簡便であるという特徴があります。
基本事項の決定
上記で解説した会社名、事業目的、本店所在地、事業年度、法人用印鑑の準備に加え、合同会社の設立には以下の基本事項を決定する必要があります。
まず、資本金(出資財産額)についてです。株式会社と同様に、資本金は1円以上で設立可能です。ただし、事業の信用や初期の資金繰りを考慮し、適切な金額を設定しましょう。一般的に、初期費用に加え3~6ヶ月分の運転資金を用意しておくことが推奨されます。
次に、社員構成を決定します。合同会社では、出資者である社員全員が原則として業務執行権を持ちます。社員の中から、実際に業務を行う「業務執行社員」、会社を代表する「代表社員」を定めることができます。代表社員は株式会社における代表取締役、業務執行社員は株式会社における取締役に相当する役割です。
そして、合同会社を設立する上で必要となる発起人全員の氏名と住所を決定します。発起人とは、会社設立の手続きを行う人のことです。
定款の作成
決定した基本事項に基づき、定款を作成します。合同会社の定款には、株式会社のような公証人による認証手続きは不要です。定款の絶対的記載事項は、目的、商号、本店所在地、社員の氏名または名称および住所、社員の出資の目的、社員の責任(社員の全部が有限責任である旨)です。
定款は、書面または電子データ(電子定款)で作成することができます。電子定款の場合も、株式会社と同様に印紙代4万円が不要になります。
会社の印章を注文する
登記で使用する会社印鑑(代表者印、銀行印、角印など)を準備します(株式会社と同様)。
出資
定款で定めた出資を履行します。金銭出資の場合は、金融機関の口座を利用し、出資金の払込みを行います。具体的な方法としては、発起人または代表社員の個人口座に、各社員が出資額を振込む、または預け入れを行う形が一般的です。
払込後、払い込まれた預金通帳のコピーと、「払込証明書」を作成します。定款に資本金に関する記載がない場合は、「資本金決定書」を作成する必要があります。
登記申請
本店所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行います。主な添付書類は、合同会社設立登記申請書、定款、代表社員の印鑑証明書、払込証明書、印鑑届出書、社員の同意書(必要な場合)、本店所在地決定書(必要な場合)、代表社員及び資本金決定書(必要な場合)などです。
登記の際には、登録免許税(資本金の額の1000分の7、最低6万円)を納付する必要があります。
設立後の手続き
株式会社と同様に、税務署、都道府県税事務所、市町村役場に法人設立の届出を行います。また、年金事務所やハローワークでの社会保険・雇用保険の加入手続きも必要です。さらに、事業活動を円滑に進めるため、法人口座を開設することも推奨されます。

株式会社と合同会社の主な相違点と考慮事項
| 特徴 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款の認証 | 必須 | 不要 |
| 設立時の最低資本金 | 1円以上 | 1円以上 |
| 所有者と経営の分離 | 可能 | 原則として所有者(社員)が経営 |
| 機関設計の柔軟性 | 比較的制約が多い | 比較的柔軟 |
| 社会的信用度 | 一般的に高い | 向上傾向にある |
| 設立費用(資本金を除く) | 比較的高い(定款認証費用、登録免許税の最低額が高い) | 比較的低い(定款認証費用不要、登録免許税の最低額が低い) |
| 設立手続きの複雑さ | 比較的複雑 | 比較的簡便 |
| 意思決定のスピード | 株主総会の決議が必要な場合があり、合同会社に比べて遅くなる場合がある | 社員の同意に基づき比較的迅速 |
| 利益分配の柔軟性 | 株主の持ち株比率に応じて分配 | 定款の定めにより柔軟に決定可能 |
| 役員の任期 | 原則としてあり(最長10年まで伸長可能) | 原則としてなし |
| 決算公告の義務 | あり | なし |
| 株式譲渡 | 原則として自由(譲渡制限を設けることも可能) | 社員の同意が必要 |
| 向いている企業 | 大規模な事業展開、株式公開を目指す企業 | 中小企業、スタートアップ、個人事業に近い形態での事業展開を目指す企業 |
まとめ

本記事では、日本における株式会社と合同会社の設立手続きについて、設立準備から設立後の手続きまでを網羅的に解説しました。両社には共通する準備段階がある一方で、定款認証の有無、機関設計、出資者の責任など、多くの点で違いが見られます。
株式会社は、その組織構造や株式発行の仕組みから、大規模な事業展開や将来的な株式公開を目指す企業に適しています。一方、合同会社は、設立手続きが簡便であり、出資者が直接経営に関与できる柔軟な組織運営が可能なため、中小企業やスタートアップ、個人事業に近い形態での事業展開を目指す企業にとって魅力的な選択肢です。
社設立を検討する際には、それぞれの会社形態のメリットとデメリットを十分に理解し、自社の事業計画や将来の展望、経営方針に最も適した形態を選択することが重要です。また、本記事で解説した手続きは一般的なものであり、個々のケースによっては追加の手続きや書類が必要となる場合があります。そのため、会社設立の際には、専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に相談し、適切なアドバイスを受けることを強く推奨します。設立後の税務や労務に関する手続きも忘れずに行い、円滑な会社運営を目指しましょう。