
のどか会計事務所
- 公認会計士・税理士・行政書士事務所
- サービス提供地域:全国
- 営業時間:火~金 10:00~16:00
- 代表者:小野 好聡
- 〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13−20 - インボイス登録番号:T7810142329217

のどか会計事務所


















![【開業前必見】地域別訪問看護ステーション数人口比調査[2024年8月版]のアイキャッチ画像](https://nodokaya.jp/nodoka_kaikei/wp-content/uploads/2024/09/【開業前必見】-地域別訪問看護ステーション数-人口比調査-1024x576.png)
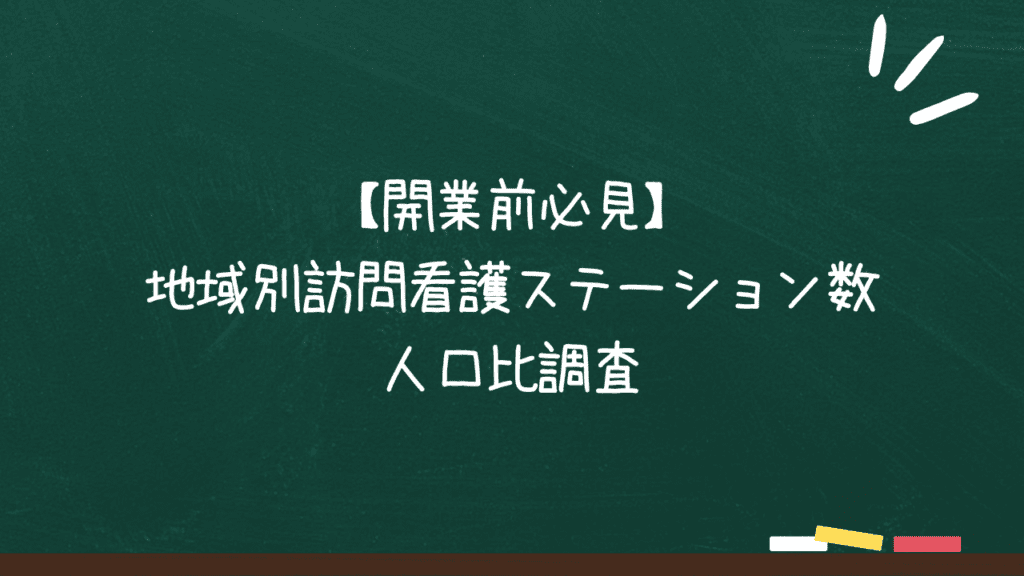
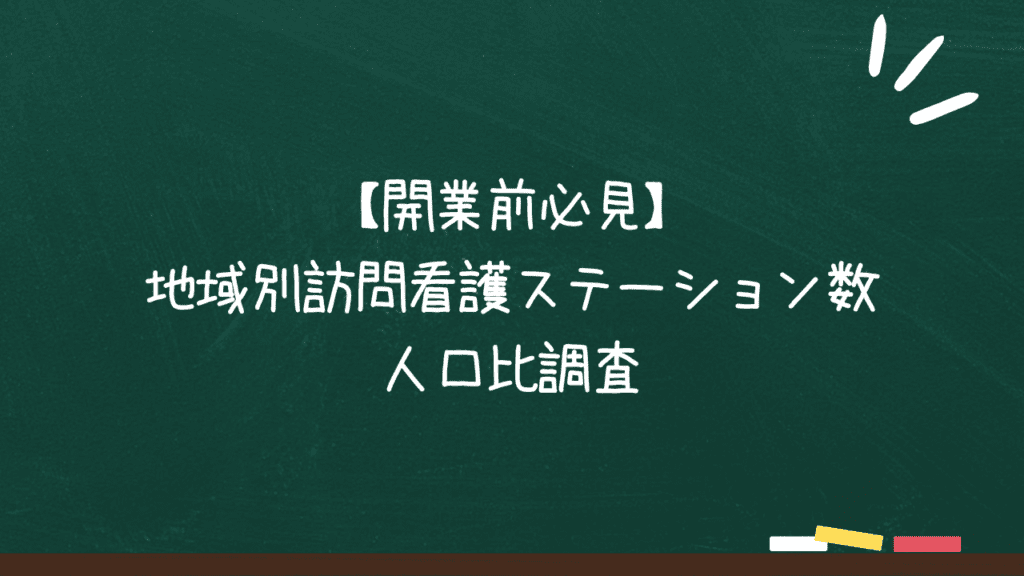
























とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)








訪問看護に携わる中で、「特別管理加算」について「算定要件が複雑でよくわからない」「医療保険と介護保険でどう違うの?」「どんな記録が必要?」といった疑問をお持ちではありませんか?
特別管理加算は、医療依存度の高い利用者さんの在宅療養を支え、訪問看護ステーションの運営においても重要な加算です。特に2024年度(令和6年度)の報酬改定では、対象者の拡大や理学療法士等による訪問の減算ルールとの関連など、知っておくべき変更点がありました。
この記事では、訪問看護の特別管理加算について、皆さまが抱える疑問にQ&A形式でわかりやすくお答えします。加算I・IIの対象となる具体的な状態から、医療保険・介護保険それぞれの算定要件、必要な届出や記録、複数事業所が関わる場合のルール、そして最新の改定情報まで、網羅的に解説します。
この記事を読めば、特別管理加算に関する知識が整理され、日々の業務やステーション運営に自信を持って臨めるようになるはずです。


【訪問看護】
特別管理加算
基本的な考え方
訪問看護の「特別管理加算」とは、特別な医療的管理(例えば、気管カニューレの管理、留置カテーテルの管理、重度の褥瘡処置、頻回な点滴など)が必要な利用者に対して、訪問看護ステーションが計画的に管理を行った場合に、月1回算定できる加算のことです。
この加算の目的は、医療依存度の高い利用者が住み慣れた自宅や地域で安心して質の高い療養生活を送れるように支援すること、そして、そのような高度な管理を行う訪問看護ステーションの労力や専門性を経済的に支えることにあります。
はい、特別管理加算は利用者の状態や管理の重症度に応じて「特別管理加算Ⅰ」と「特別管理加算Ⅱ」に分かれています。
もし、一人の利用者がⅠとⅡの両方の条件を満たす場合は、重症度の高い「加算Ⅰ」が優先して算定されます。同じ月にⅠとⅡの両方を算定することはできません。


【訪問看護】
特別管理加算
対象となる方・状態
対象となるのは、厚生労働大臣が定める特別な管理が必要な状態にある利用者です。主な状態は以下の通りです。
【加算Ⅰ(重症度が高い方)】
【加算Ⅱ(上記以外で特別な管理が必要な方)】
いいえ、単にカテーテルが留置されているだけでは算定できません。訪問看護において、排液の性状・量の観察、薬剤の注入、水分バランスの計測・管理など、計画的な管理が行われていることが必要です。例えば、中心静脈ポートが留置されていても、訪問看護で薬剤注入などが行われていない場合は算定できません。記録で計画的な管理内容を示す必要があります。
褥瘡が特別管理加算Ⅱの対象となるのは、深さが真皮を超えている状態(NPUAP分類Ⅲ度またはⅣ度、DESIGN-R分類D3、D4またはD5に相当)です。算定には、週1回以上の定期的な状態観察・アセスメント・評価(部位、サイズ、深さ、ポケット、滲出液、肉芽・壊死組織の状態、炎症・感染兆候など)を行い、発生部位や実施したケア内容について訪問看護記録書に詳細に記録することが必要です。
点滴注射の扱いは、医療保険と介護保険で異なります。
どちらの場合も、実施内容や医師への報告状況などを記録する必要があります。
在宅酸素療法指導管理を受けている状態は特別管理加算Ⅱの対象となり得ますが、注意点があります。算定対象となる月において、実際に酸素吸入を行っている必要があります。もし、その月に一度も酸素吸入の実績がなければ、たとえ機器が設置されていても算定できません。日々の訪問看護記録に使用状況を記録しておくことが重要です。
在宅自己疼痛管理(PCA)が特別管理加算Ⅱの対象となるのは、持続的な痛みに対して、PCAポンプなどを用いて注射薬(医療用麻薬など)を患者自身が管理している状態を指します。内服薬(飲み薬)のみで痛みをコントロールしている場合は、この加算の対象とはなりません。
いいえ、単に吸引処置が必要であるだけでは、特別管理加算の算定対象とはなりません。ただし、気管カニューレを使用している、あるいは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態で、それに伴い吸引が必要な場合は、特別管理加算Ⅰの対象となります。


【訪問看護】
特別管理加算
算定の条件・手続き
算定には、計画的な管理の実施と記録が共通で必要ですが、体制要件と届出は医療保険と介護保険で異なります。
どちらの保険の場合も、利用者の状態に応じた訪問看護計画を作成し、計画に基づいて管理を行い、その内容を詳細に記録することが共通の要件となります。
医療保険の訪問看護の対象となる利用者には、急性期病院退院直後の方、難病の方、末期がんの方など、病状が不安定で急変リスクが高い場合が多いと考えられます。このような医療ニーズが高く緊急性の高い利用者への特別な管理には、日中だけでなく夜間・休日を含めた緊急時の対応能力が不可欠であるとの判断から、24時間対応体制の整備が前提条件とされていると考えられます。
いいえ、「緊急時訪問看護加算」の算定自体は、医療保険の特別管理加算の必須要件ではありません。ただし、特別管理加算の必須要件である「24時間対応体制加算の届出」を行うためには、実質的に緊急時訪問看護加算(介護保険)と同様の、24時間連絡・対応できる体制が求められます。根底にある体制整備の考え方は共通・類似しています。
加算の根拠を示すために、詳細な記録が不可欠です。主に以下の記録が必要です。
記録は「計画に基づき、どのようなアセスメントと評価を経て、そのケアを実施したか」がわかるように具体的に記載することが重要です。記録が不十分な場合、加算の算定が認められない、あるいは監査等で返還を求められるリスクがあります。


【訪問看護】
特別管理加算
医療保険と介護保険の違い
A15: 共通点も多いですが、運用上の重要な違いがあります。主な違いは以下の表の通りです。
| 項目 | 医療保険 | 介護保険 |
|---|---|---|
| 算定額/単位数 | Ⅰ相当:5,000円/月 Ⅱ相当:2,500円/月 | Ⅰ:500単位/月 Ⅱ:250単位/月 |
| 必須となる体制 | 24時間対応体制加算の届出が必須 | 特になし (緊急時連絡体制の整備は望ましい) |
| 複数事業所による算定 | 可能 (各事業所が要件を満たせば) | 不可 (1利用者につき1事業所のみ、事業所間で合議が必要) |
| 区分支給限度基準額 | 制度上なし | 対象外 (限度額に含まれない) |
| 届出先 | 地方厚生(支)局 | 都道府県・市町村 |
医療保険と介護保険で扱いが異なります。
いいえ、介護保険の特別管理加算は、区分支給限度基準額の算定対象外です。つまり、この加算を算定しても、利用者の月々の介護保険サービス利用可能枠(限度額)を圧迫することはありません。これは、医療依存度が高い方が費用を心配せずに必要なサービスを受けられるようにするための配慮です。


【訪問看護】
特別管理加算
算定・請求について
介護保険の特別管理加算は、原則として、その月の最初の介護保険給付対象となる訪問看護を行った日に、その日の訪問看護費(所定単位数)に加算して請求します。月1回の定額(単位数)算定となります。医療保険の場合は、訪問看護療養費明細書に記載して請求します。


【訪問看護】
特別管理加算
関連サービス・加算
はい、訪問看護サービス以外にも、「看護小規模多機能型居宅介護(看多機)」や「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」においても、同様の趣旨で特別管理加算(またはそれに準ずる加算)が設定されている場合があります。
ただし、注意点として、同一月内に、例えば介護保険の訪問看護で特別管理加算を算定した場合、同月に定期巡回・随時対応型訪問介護看護や看護小規模多機能型居宅介護で同様の加算を算定することはできません(逆も同様です)。医療保険の訪問看護とも重複して算定できません。これは、同じ管理状態に対して複数のサービスから二重に評価されることを防ぐためです。
「専門管理加算」(250単位/月)は、令和6年度改定で新設された加算です。これは、緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・膀胱ケアに関する専門的な研修を修了した看護師などが、その専門知識を活かして計画的な管理を行った場合に算定できます。
特別管理加算とは別の加算であり、算定要件を満たせば、特別管理加算と併せて算定することが可能です。専門性の高い看護をさらに評価する目的で導入されました。
改定の影響-1024x576.jpg)
改定の影響-1024x576.jpg)
【訪問看護】
特別管理加算
令和6年度(2024年度)改定の影響
はい、主に以下の変更点がありました。
この減算は、訪問看護ステーションが看護中心の役割を果たすことを促すルールです。以下のいずれかに該当する場合、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(PT・OT・ST)による訪問1回あたり8単位が減算されます(令和6年6月1日施行)。
特別管理加算との関係: この減算ルールにより、PT・OT・STの訪問が多いステーションは、看護職員の訪問を増やすか、あるいは緊急時対応や重度者対応の体制・実績を示す必要があります。特別管理加算を算定することは、減算を回避する手段の一つとなり、ステーションにとってその戦略的重要性は格段に高まりました。


【訪問看護】
特別管理加算
その他
原則として、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるリハビリテーション目的の訪問が中心で、看護職員による計画的な管理が行われていないと判断される場合は、特別管理加算は算定できません。特別管理加算はあくまで「看護職員による特別な医学的管理」を評価するものであるためです。
契約に関するご相談は無料です。こちらからご予約ください。
面談方法は、Zoomによるオンライン面談となります。
はじめての方でも簡単にご利用いただけますのでご安心ください。
まずは以下のボタンからお申し込みください。
ご記入いただいたメールアドレス宛に事前ヒアリングシートのURLをお送りいたします。
面談に先立って事前ヒアリングシートへのご記入をお願いいたします。
ご記入いただいた事前ヒアリングシートに基づいて、面談時にヒアリングを実施致します。
ヒアリング内容に基づいて、お見積りをいたします。
お見積り内容に合意いただけた場合は、ご契約の手続を進めさせていただきます。
その他のお問い合わせはこちらから
【全国対応】
運営基準で要求される
\就労支援会計・区分会計に対応!/

介護・障がい福祉に強い! コスパ抜群の定額制! 創業期・小規模を応援! 記帳代行で負担軽減! 全国対応! 税理士が直接対応! 融資に強い! MFクラウド専門!
