
のどか会計事務所
- 公認会計士・税理士・行政書士事務所
- サービス提供地域:全国
- 営業時間:火~金 10:00~16:00
- 代表者:小野 好聡
- 〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13−20 - インボイス登録番号:T7810142329217

のどか会計事務所


















![【開業前必見】地域別訪問看護ステーション数人口比調査[2024年8月版]のアイキャッチ画像](https://nodokaya.jp/nodoka_kaikei/wp-content/uploads/2024/09/【開業前必見】-地域別訪問看護ステーション数-人口比調査-1024x576.png)
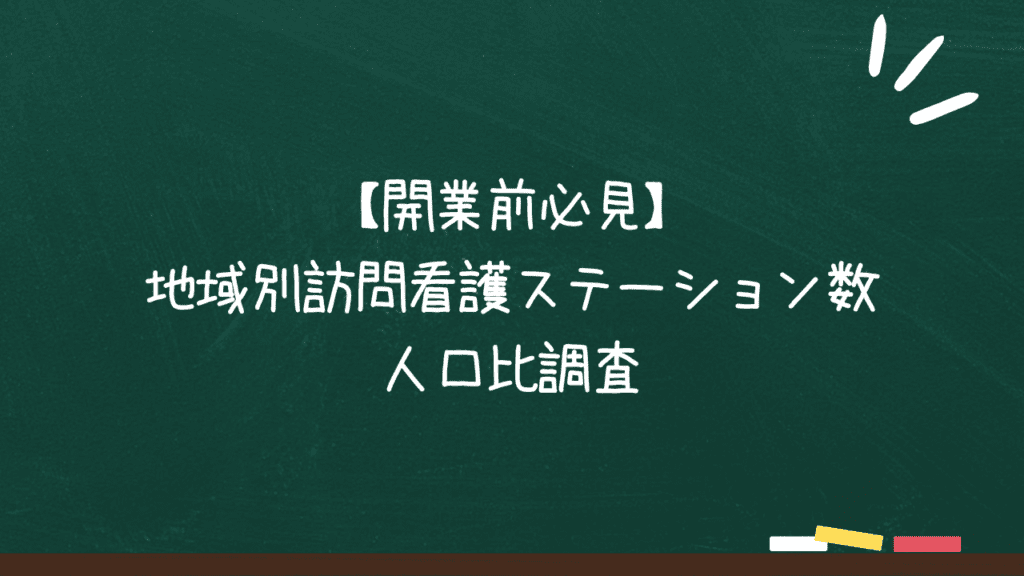
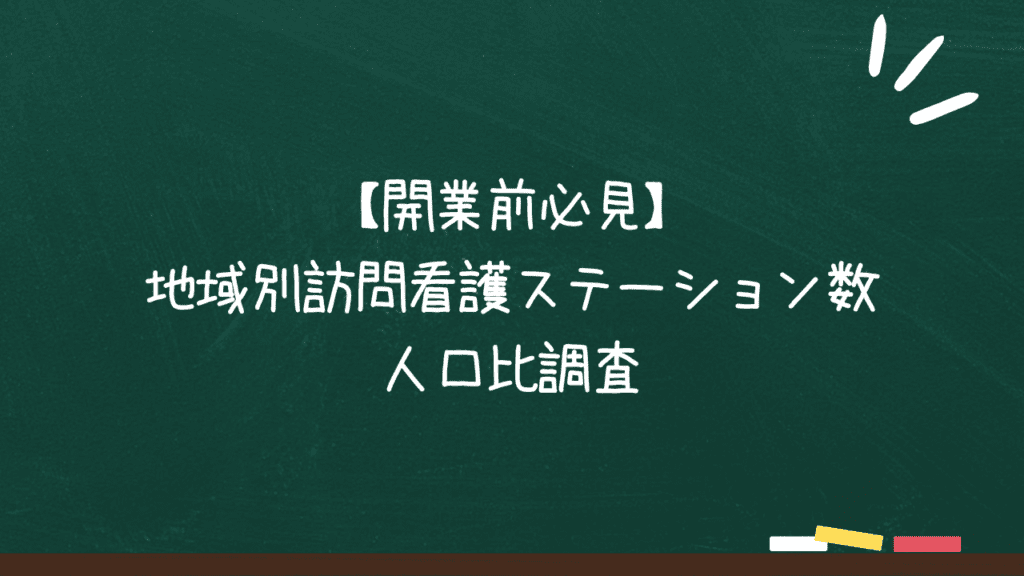
























とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)








「就労継続支援B型ってどんなサービス?」「自分は利用できるのかな?」「A型とは何が違うの?」「工賃(お給料)はもらえる?」 就労継続支援B型の利用を検討されている方や、そのご家族、支援者の方は、様々な疑問をお持ちではないでしょうか。
この記事では、就労継続支援B型に関する皆さまの疑問に、Q&A形式でわかりやすくお答えします。 「どんな人が対象になるの?」「具体的な仕事内容は?」「A型との違いは?」「工賃はどのくらいもらえる?」「どうやって利用を始めればいいの?」「メリットやデメリットは?」といった基本的な疑問から、利用する上で知っておきたい詳細情報まで、最新の情報に基づいて網羅的に解説しています。
この記事を読めば、就労継続支援B型についての理解が深まり、ご自身やご家族にとって最適な選択をするための一歩を踏み出せるはずです。ぜひ最後までご覧いただき、疑問や不安の解消にお役立てください。


就労継続支援B型とは?
就労継続支援B型の概要と特徴
就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。一般の企業などで雇用契約を結んで働くことが現時点で難しい、障害や指定難病のある方々に対して、雇用契約を結ばずに(非雇用型)、就労や生産活動の機会を提供し、関連する訓練を行うサービスです。利用者は比較的柔軟なペースで活動に参加できます。
「非雇用型」とは、利用者と事業所の間で雇用契約を結ばないということを意味します。そのため、利用者は労働基準法上の「労働者」とはみなされません。具体的には以下の点が特徴です。
主な目的は、一般就労が困難な方に対し、生産活動などの機会提供を通じて、就労に必要な知識や能力の向上を図り、自立した生活を支援することです。また、利用者が希望する就労の実現に向けた支援や、生産活動への対価(工賃)の支払い、心身の健康維持、社会参加の促進なども目的とされています。単なる作業場所ではなく、日中の居場所や社会との繋がりを維持する役割も担っています。


就労継続支援B型とは?
利用できる人・条件
原則として18歳以上で、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)、または国が指定する難病(令和6年4月時点で369疾病)のある方が対象です。その上で、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
利用開始は原則18歳以上ですが、利用に関して年齢の上限はありません。一度利用を開始すれば、年齢を理由に利用できなくなることはありません。
必ずしも障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)を持っている必要はありません。手帳は障害の状態を証明するものですが、B型サービスの利用可否は、利用対象となる条件を満たし、市区町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」を取得できるかどうかで決まります。手帳がなくても、医師の診断書や他の条件を満たすことで受給者証が交付され、サービスを利用できる場合があります。逆に、手帳を持っていても、サービス利用のためには別途、受給者証の申請・交付が必要です。


就労継続支援B型とは?
サービス内容・活動
事業所によって多岐にわたりますが、主に以下のような生産活動や、それに伴う訓練が行われます。
これらの作業を通じて、規則正しい生活習慣、集中力・持続力、作業遂行能力、コミュニケーション能力などの維持・向上を目指す訓練も行われます。
いいえ、事業所によって大きく異なります。提供される作業の種類や難易度、1日のスケジュール、工賃の水準、事業所の設備、スタッフや他の利用者の雰囲気、支援方針などは様々です。そのため、利用を検討する際は、複数の事業所を見学したり、体験利用したりして、ご自身の興味、能力、希望する働き方や環境に合った場所を慎重に選ぶことが非常に重要です。
「施設外就労」とは、B型事業所のスタッフが同行・支援する形で、事業所の外(例えば一般企業や官公庁など)へ出向いて作業を行うことです。事業所内での活動に慣れてきた方が、より実際の職場に近い環境での就労を経験し、社会性や就労意欲を高めるためのステップとして活用されることがあります。
事業所によっては、利用者の自宅や最寄り駅などへの送迎サービスを提供している場合があります。ただし、これは必須のサービスではないため、全ての事業所で実施しているわけではありません。送迎の有無や範囲、利用条件などは事業所ごとに異なるため、希望する場合は事前に確認が必要です。


就労継続支援B型とは?
A型との違い
就労継続支援にはA型とB型があり、主な違いは以下の通りです(報酬額は最新の公表データに基づいています)。
| 特徴 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
|---|---|---|
| 雇用契約 | あり | なし |
| 報酬の種類 | 賃金(給与) | 工賃(生産活動対価) |
| 最低賃金保障 | あり | なし |
| 平均月額報酬(目安) | 約 86,752円 (令和5年度) | 約 23,053円 (令和5年度、※計算方法変更後) |
| 平均時間額報酬(目安) | 約 947円 (令和4年度) | 約 243円 (令和4年度) |
| 主な対象者 | 契約に基づき就労可能だが一般就労困難な方 | 契約に基づく就労が困難な方 |
| 勤務時間の柔軟性 | 比較的低い (雇用契約に基づく) | 比較的高い (体調等に合わせやすい) |
| 労働保険(雇用・労災) | 適用あり | 適用なし |
| 年次有給休暇 | あり | なし |
| 利用開始プロセス | 面接等の採用選考がある場合が多い | 主に受給資格と空き状況による |
| 年齢制限(原則) | 65歳未満 | なし |
※B型の令和5年度平均工賃月額は、令和6年度報酬改定に伴う計算方法の変更(従来の「工賃支払対象者数」から「1日あたり平均利用者数」を基準とする方法へ)により、前年度までと比較して見かけ上、数値が大きく増加しています。個々の利用者の工賃が必ずしも同程度増加したわけではない点に注意が必要です。
簡単に言うと、A型は「雇用契約を結び、最低賃金以上の給料をもらって働く」のに対し、B型は「雇用契約を結ばず、作業の対価として工賃をもらい、比較的柔軟に活動する」という違いがあります。
について-1024x576.jpg)
について-1024x576.jpg)
就労継続支援B型とは?
工賃(報酬)について
はい、B型事業所での生産活動に対して「工賃」が支払われます。ただし、これは雇用契約に基づく「賃金」ではなく、最低賃金の適用はありません。
全国の平均工賃は、月額で約 23,053円(令和5年度)、時間額で約 243円(令和4年度) です。
(注意点)
令和5年度の月額平均工賃(23,053円)は、令和6年度報酬改定に伴う計算方法の変更により、前年度(令和4年度:17,031円)から見かけ上、大きく増加しています。これは、従来の「工賃支払対象者数」ではなく「1日あたり平均利用者数」を計算の基準とするようになったためで、個々の利用者が受け取る工賃が必ずしもこの平均額まで増加したとは限りません。
工賃額は、事業所の収益状況、行っている作業内容(例:クリーニング作業は比較的高く、軽作業は低い傾向)、利用者の作業時間や日数、成果などによって、事業所ごとに定められたルールに基づき決定されます。
低い工賃水準はB型事業の長年の課題であり、いくつかの要因が複合的に関わっています。
B型の平均的な工賃額だけでは生活費を賄うことが難しいため、多くの利用者は障害年金や生活保護といった他の公的な経済支援制度を併用しています。利用を検討する際には、ご自身の状況に合わせて、工賃収入とこれらの制度を組み合わせた生活設計を考えることが重要です。具体的な制度については、市区町村の担当窓口や相談支援事業者に相談できます。


就労継続支援B型とは?
利用開始までの流れ・手続き
就労継続支援B型を利用するための一般的な手続きの流れは以下の通りです。自治体によって細部が異なる場合があるので、まずはお住まいの地域の窓口に相談しましょう。
B型事業所を探す主な方法は以下の通りです。
「障害福祉サービス受給者証」は、就労継続支援B型を含む、障害者総合支援法に基づく特定の福祉サービスを利用する資格があることを市区町村が証明する公的な書類です。この受給者証がないと、原則としてサービスを利用することはできません。
受給者証には、利用者情報、支給決定されたサービスの種類(例:就労継続支援B型)、1ヶ月あたりに利用できる日数(支給量)、サービスの有効期間、利用者負担上限月額、利用する事業所名(決定している場合)などが記載されています。
はい、受給者証には有効期間が定められているため、サービス利用を継続するには更新手続きが必要です。有効期間はサービスの種類や個人の状況によって異なる場合があるため、記載されている有効期間を確認し、期限が近づいたら市区町村の窓口や相談支援事業者に相談して更新手続きを行ってください。
サービス利用にかかる費用の原則1割が利用者負担となりますが、所得に応じた月ごとの負担上限額が定められています。世帯(本人と配偶者、18歳未満の場合は保護者)の所得状況(主に市町村民税の課税状況)によって負担上限月額が決まり(例:生活保護・住民税非課税世帯は0円、課税世帯は9,300円または37,200円)、それを超える費用負担は生じません。利用者の多く(9割以上)は負担上限月額0円の区分に該当し、実質的に無料でサービスを利用しているケースが多いです。
ただし、事業所での食費(昼食代など)や、生産活動で使う材料費の一部などについては、別途実費負担となる場合があります。
はい、希望通りに利用できない可能性はあります。主な理由は以下の通りです。


就労継続支援B型とは?
メリットとデメリット
就労継続支援B型の利用には、以下のようなメリットとデメリット(課題点)があります。
【メリット(利点)】
【デメリット(課題点)】


就労継続支援B型とは?
利用中のこと
就労継続支援B型の利用期間には、原則として制限はありません。利用者は自分のペースで、必要に応じて長期間にわたりサービスを利用し続けることが可能です。
はい、必要に応じて他の障害福祉サービスと組み合わせて利用することが可能です。例えば、日中はB型事業所で活動し、朝夕の身支度や家事援助として居宅介護(ホームヘルプ)を利用したり、休日に移動支援を利用したり、家族の休息のために短期入所(ショートステイ)を利用したりするケースなどが考えられます。
ただし、サービスの種類によっては併用が難しい場合もあります(例:常時介護が必要で生活介護を利用している場合など)。どのような組み合わせが可能か、またそれが本人にとって最適かは、個々の状況によって異なるため、担当の相談支援専門員や市区町村の窓口とよく相談してサービス等利用計画を作成することが重要です。
はい、可能です。利用者の状況や意向の変化によって、サービスの利用を中止したり、他のB型事業所や、A型事業所、就労移行支援事業所などに移ったりすることはできます。
利用の中止や変更を希望する場合は、まずは現在利用している事業所のスタッフや、担当の相談支援専門員に相談しましょう。他の事業所に移る場合は、移りたい先の事業所を探し、空き状況を確認した上で、改めて利用申請やサービス等利用計画の変更、契約などの手続きが必要になる場合があります。
はい、ステップアップは可能です。B型事業所での活動を通じて、働くことへの自信がついたり、体力や作業能力が向上したり、症状が安定したりした場合、より高い工賃(賃金)や一般就労を目指して、就労継続支援A型事業所への移行や、ハローワークなどを通じた一般企業への就職(一般就労)に挑戦することができます。実際に、B型からA型や一般就労へ移行する人は一定数います(ただし、移行率は事業所によって差があります)。事業所によっては、こうしたステップアップに向けた相談や支援(例:就職活動の練習、履歴書の書き方指導、面接同行など)を行っている場合もあります。移行を考え始めたら、事業所のスタッフや相談支援専門員に相談してみましょう。
(補足)
ただし、B型は必ずしも移行を前提としたサービスではなく、利用期間に制限がないことからもわかるように、多くの利用者にとっては安定した日中活動の場として長期的に機能しています。ステップアップはあくまで「可能性」の一つであり、利用継続も重要な選択肢です。


就労継続支援B型とは?
相談窓口
就労継続支援B型の利用に関する相談は、主に以下の窓口で行うことができます。
契約に関するご相談は無料です。こちらからご予約ください。
面談方法は、Zoomによるオンライン面談となります。
はじめての方でも簡単にご利用いただけますのでご安心ください。
まずは以下のボタンからお申し込みください。
ご記入いただいたメールアドレス宛に事前ヒアリングシートのURLをお送りいたします。
面談に先立って事前ヒアリングシートへのご記入をお願いいたします。
ご記入いただいた事前ヒアリングシートに基づいて、面談時にヒアリングを実施致します。
ヒアリング内容に基づいて、お見積りをいたします。
お見積り内容に合意いただけた場合は、ご契約の手続を進めさせていただきます。
その他のお問い合わせはこちらから
【全国対応】
運営基準で要求される
\就労支援会計・区分会計に対応!/

介護・障がい福祉に強い! コスパ抜群の定額制! 創業期・小規模を応援! 記帳代行で負担軽減! 全国対応! 税理士が直接対応! 融資に強い! MFクラウド専門!
