
のどか会計事務所
- 公認会計士・税理士・行政書士事務所
- サービス提供地域:全国
- 営業時間:火~金 10:00~16:00
- 代表者:小野 好聡
- 〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13−20 - インボイス登録番号:T7810142329217

のどか会計事務所


















![【開業前必見】地域別訪問看護ステーション数人口比調査[2024年8月版]のアイキャッチ画像](https://nodokaya.jp/nodoka_kaikei/wp-content/uploads/2024/09/【開業前必見】-地域別訪問看護ステーション数-人口比調査-1024x576.png)
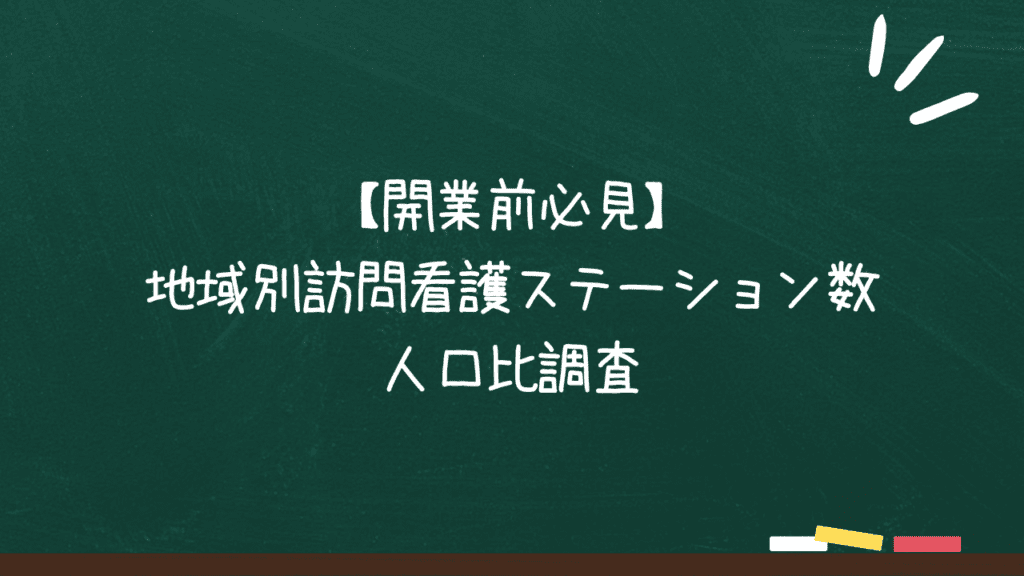
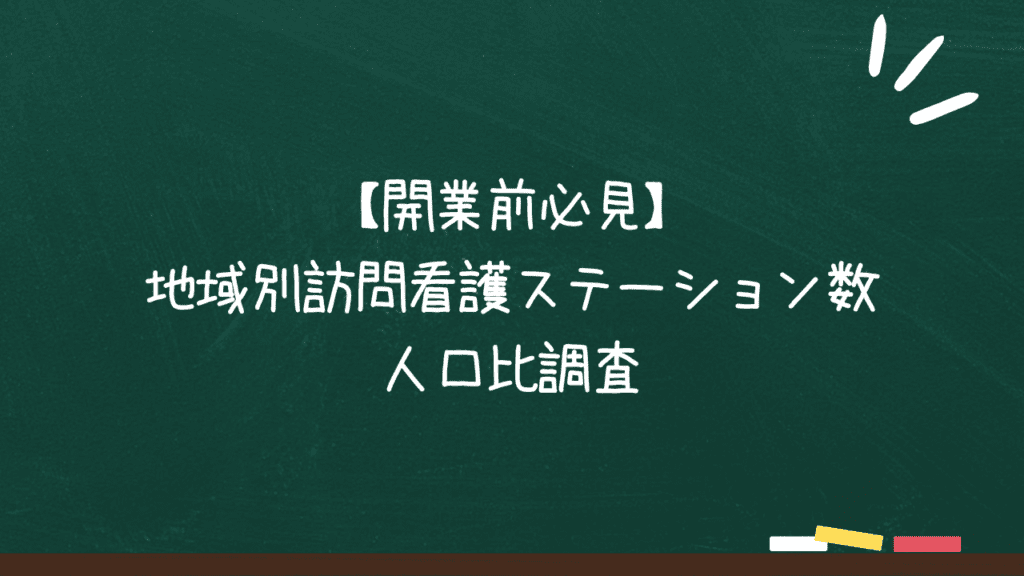
























とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)








令和7年度(2025年度)の「処遇改善加算」について、「どんな制度なの?」「前の加算と何が変わった?」「職員の給料はどうやって上げればいい?」「キャリアパス要件や職場環境等要件って、具体的に何をすればいいの?」「もし期限までに要件整備が間に合わなかったらどうなる?」など、様々な疑問をお持ちではないでしょうか?
令和6年度に一本化され、令和7年度も引き続き職員の処遇改善に欠かせないこの加算制度。しかし、要件や手続きが複雑で、正確な理解が難しいと感じている方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、厚生労働省やこども家庭庁から発出された最新の通知とQ&Aに基づき、介護保険サービスと障害福祉サービスに共通する処遇改善加算に関するよくある疑問とその答えを、Q&A形式で分かりやすくまとめました。
制度の基本的な仕組みから、具体的な賃金改善の方法、キャリアパス要件・職場環境等要件の詳細、申請手続きの流れ、そして注意すべき点(要件未達の場合のペナルティなど)まで、事業者や職員の皆様が知りたい情報を網羅しています。
この記事を読むことで、令和7年度の処遇改善加算に関する疑問を解消し、適切な制度活用を進めるための一助となれば幸いです。


令和7年度 処遇改善加算
制度の基本について
介護・福祉の現場で働く職員さんの給料を上げる(処遇を改善する)ために、事業所に支給されるお金(加算)のことです。以前は「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」と3種類ありましたが、令和6年6月から手続きを分かりやすくするなどの目的で一つにまとめられました。
はい、原則として上がります。この加算を受け取った事業所は、受け取った加算額の合計額以上に、職員さんの賃金(基本給、手当、賞与など)を改善することが義務付けられています。
令和6年度の報酬改定で加算の一本化や加算率の引き上げが行われました。令和7年度も引き続き、職員の処遇改善を進めることが求められています。また、令和7年度中は、キャリアパス要件や職場環境等要件について、年度内に整備することを約束すれば、年度当初から要件を満たしたものとして扱われる経過措置があります。


令和7年度 処遇改善加算
賃金改善の方法について
はい、その通りです。加算の総額を上回る賃金改善が必要です。ただし、賃金改善に伴って増える社会保険料などの事業主負担分(法定福利費等)を含めることはできます。
基本給、手当、賞与(ボーナス)など、どの項目で賃金を改善するかは事業所が決めることができます。ただし、安定的な処遇改善のためには、基本給を上げることが望ましいとされています。また、加算Ⅰ~Ⅳを算定する場合、加算Ⅳの加算額の半分以上は、基本給または毎月決まって支払われる手当(基本給等)の改善に充てる必要があります。
ベースアップとは、賃金表などを改定して、基本給や毎月決まって支払われる手当の水準を一律に引き上げることです。
旧3加算(処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算)のうち、旧ベースアップ等加算を算定していなかった事業所が、令和7年度に新たに処遇改善加算Ⅰ~Ⅳを算定する場合などは、旧ベースアップ等加算に相当する額の3分の2以上を、ベースアップ等により新規に引き上げる必要があります(月額賃金改善要件Ⅱ)。
仕事の内容に直接関係があり、個人の事情(通勤距離や家族構成など)とは関係なく、毎月決まって支払われる手当のことです。例えば、職能手当、資格手当、役職手当などが該当します。月によって金額が変わる手当も含まれます。
通勤手当や扶養手当など、個人の事情によって支給される手当や、月によって支払われるかどうかが変わる手当は「決まって毎月支払われる手当」には含まれません。
時給制の職員の時給を上げることや、日給制の職員の日給を上げることは、基本給の引き上げとして扱って問題ありません。また、時給や日給に上乗せされる手当も、「決まって毎月支払われる手当」と同じように扱ってよいとされています。
原則として、加算による賃金改善を行う部分以外で、賃金水準を下げてはいけません。ただし、経営状況の悪化などやむを得ない理由がある場合は、労使でよく話し合い、合意した上で、都道府県等に「特別事情届出書」を提出すれば認められる場合があります。
また、職員の入れ替わり(勤続年数が長い職員が退職し、新卒者を採用したなど)によって事業所全体の平均賃金が下がった場合でも、個々の職員の賃金表などを引き下げていなければ、実績報告の際に調整が認められる場合があります。
加算が算定される月と、実際に賃金を支払う月が同じでなくても構いません。例えば、6月分の加算を原資とする賃金改善を、6月中に見込みで支払う、7月中に支払う、報酬が振り込まれる8月中に支払う、といったパターンが考えられます。どの方法にするかは事業所が選択できますが、事前に職員と話し合っておくことが望ましいです。
ただし、事業所が廃止になる場合は、最終の給与支払いまでに、受け取った加算額以上の賃金改善をすべて行う必要があります。
加算の要件を満たさないため、差額ではなく、受け取った加算額全額の返還が必要になる可能性があります。ただし、不足分を一時金などで追加支給することで、返還を求められない場合もあります。
はい、可能です。令和6年度に受け取った加算額の一部を、令和7年度の賃金改善の原資として繰り越すことができます。その場合、繰り越した額は全額、令和7年度の賃金改善に充てる必要があります。


令和7年度 処遇改善加算
賃金改善の対象となる職員について
加算の配分は、利用者に直接サービスを提供する職員(ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員など)への配分が基本です。特に、経験や技能のある職員(勤続10年以上の介護福祉士など)に重点的に配分することとされています。
ただし、事業所の判断で、事務職員や調理員、運転手など、その他の職種の職員に配分することも可能です。
はい、可能です。以前の旧特定加算とは異なり、処遇改善加算では、賃金改善前の年収が440万円以上の職員も賃金改善の対象に含めることができます。
はい、雇用形態に関わらず対象とすることができます。派遣職員の場合は、派遣元の会社と相談し、加算分が派遣職員の給与に反映されるように協議する必要があります。


令和7年度 処遇改善加算
加算の要件について
職員が将来の目標を持って働き続けられるように、キャリアアップの道筋や、それに応じた給料の仕組み、研修制度などを整備するための要件です。具体的には、以下のような内容が含まれます。
令和7年度中は、要件Ⅰ~Ⅲについて、年度内に整備することを約束すれば、年度当初から満たしたものとみなされる経過措置があります。
職員が働きやすい環境を作るための取り組みに関する要件です。例えば、「入職促進」「資質の向上」「両立支援」「健康管理」「生産性向上」「やりがい・働きがいの醸成」といった区分があり、それぞれの区分について、定められた数の取り組みを行う必要があります。
全ての項目を実施する必要はなく、区分ごとに決められた数以上の取り組みを選択して実施します。例えば、加算Ⅰ・Ⅱの場合は、「生産性向上」区分で3つ以上(うちICT活用などは必須)、その他の区分で各2つ以上の取り組みが必要です。
こちらも令和7年度中は、年度内に整備することを約束すれば、年度当初から満たしたものとみなされる経過措置があります。また、「障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業」を申請する場合は、令和7年度の適用が猶予されます。
これは加算ⅠまたはⅡを算定する場合の「キャリアパス要件Ⅳ」のことです。経験・技能のある職員(勤続10年以上の介護福祉士などが基本ですが、事業所の裁量で設定可能)の中から、賃金改善後の年収が440万円以上となる人を1人以上設定する必要があります。
ただし、小規模な事業所で職員間の賃金バランスへの配慮が必要な場合や、地域や職員全体の賃金水準が低く、すぐに440万円まで引き上げるのが難しい場合など、合理的な理由があれば、この要件を満たさなくてもよいとされています。その場合は、計画書に理由を記載する必要があります。


令和7年度 処遇改善加算
手続きについて
主に以下の手続きが必要です。
はい、法人単位で処遇改善計画書や実績報告書を一括して作成し、それぞれの事業所の指定権者に提出することができます。
算定する加算区分が変わる場合や、対象事業所に増減があった場合、キャリアパス要件の適合状況が変わった場合などは、変更届を提出する必要があります。


令和7年度 処遇改善加算
その他
賃金改善が行われていない、虚偽の申請をしたなどの場合は、不正受給とみなされ、受け取った加算金の返還や、加算の取り消しとなる場合があります。
まずは、事業所の指定を受けている都道府県や市町村の担当部署にお問い合わせください。厚生労働省のウェブサイトにも情報が掲載されています。
令和7年度の計画書で「令和8年3月末までに要件を整備し、実績報告書で報告する」と誓約した場合、年度末の実績報告の時点で整備が完了している必要があります。
もし期限までに整備が完了しなかった場合、加算の算定要件を満たさないため、令和7年度に受け取った処遇改善加算は返還対象となる可能性があります。
契約に関するご相談は無料です。こちらからご予約ください。
面談方法は、Zoomによるオンライン面談となります。
はじめての方でも簡単にご利用いただけますのでご安心ください。
まずは以下のボタンからお申し込みください。
ご記入いただいたメールアドレス宛に事前ヒアリングシートのURLをお送りいたします。
面談に先立って事前ヒアリングシートへのご記入をお願いいたします。
ご記入いただいた事前ヒアリングシートに基づいて、面談時にヒアリングを実施致します。
ヒアリング内容に基づいて、お見積りをいたします。
お見積り内容に合意いただけた場合は、ご契約の手続を進めさせていただきます。
その他のお問い合わせはこちらから
【全国対応】
運営基準で要求される
\就労支援会計・区分会計に対応!/

介護・障がい福祉に強い! コスパ抜群の定額制! 創業期・小規模を応援! 記帳代行で負担軽減! 全国対応! 税理士が直接対応! 融資に強い! MFクラウド専門!
