
のどか会計事務所
- 公認会計士・税理士・行政書士事務所
- サービス提供地域:全国
- 営業時間:火~金 10:00~16:00
- 代表者:小野 好聡
- 〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13−20 - インボイス登録番号:T7810142329217

のどか会計事務所


















![【開業前必見】地域別訪問看護ステーション数人口比調査[2024年8月版]のアイキャッチ画像](https://nodokaya.jp/nodoka_kaikei/wp-content/uploads/2024/09/【開業前必見】-地域別訪問看護ステーション数-人口比調査-1024x576.png)
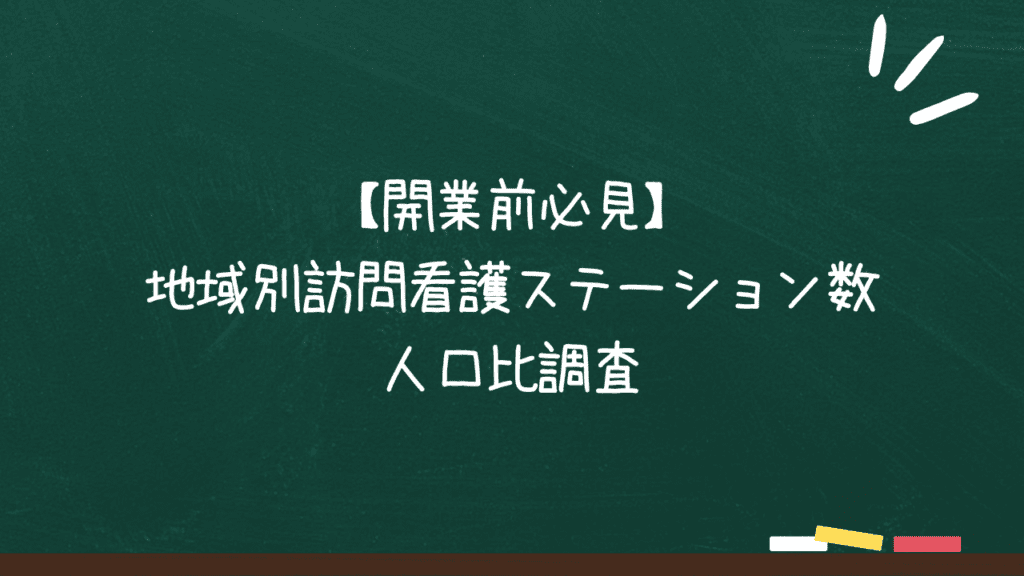
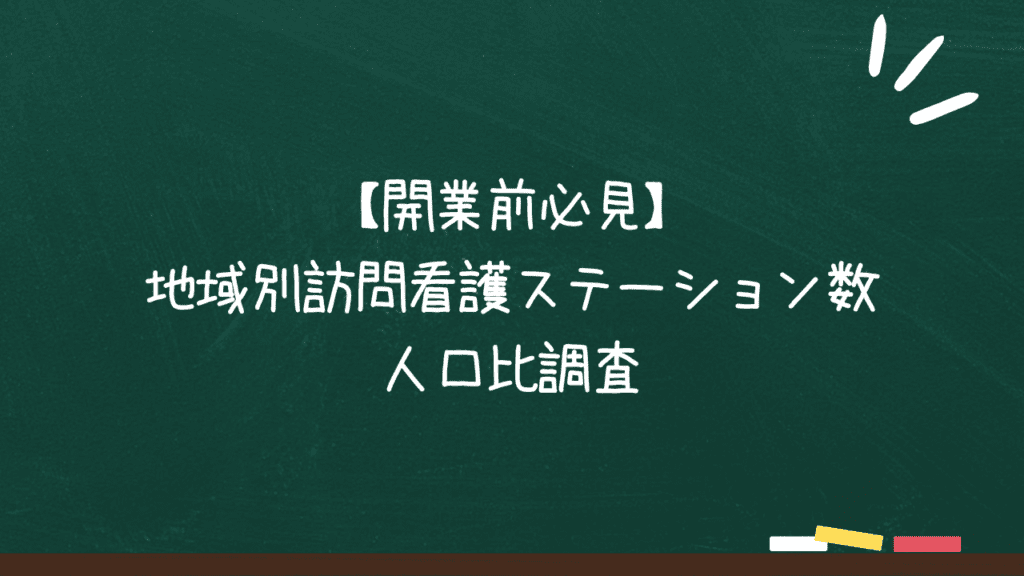
























とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)








役員社宅制度は、企業が役員に住居を提供する福利厚生制度の一種です。この制度を適切に活用すれば、法人税や役員個人の所得税・住民税、さらに社会保険料の負担を合法的に軽減できる可能性があります。しかし、単に節税のためだけでなく、福利厚生の充実や優秀な人材の確保・維持といった、事業運営上のしっかりとした目的を持って導入することが重要です。税務調査では、特に同族会社の場合、形式的な要件を満たしているかだけでなく、なぜこの制度を導入したのかという実質的な理由(事業上の合理性)も合わせて確認される傾向にあるため、注意が必要です。
役員社宅の税務上の取り扱いは複雑で、所得税法、法人税法、国税庁の通達によって厳格なルールが定められています。本記事では、役員社宅制度の全体像を明らかにし、税務上のメリットを享受するためのポイント、社会保険料への影響に関する注意点、潜むリスク、具体的な導入・運用方法まで、詳しく解説していきます。
役員社宅として税務上のメリットを受けるには、以下の3つの形式的な要件をすべて満たす必要があります。これらの要件は、税務当局が制度の適正性を判断する上で非常に重要視します。
社宅として利用する物件の賃貸借契約は、必ず法人名義で家主(大家)と締結しなければなりません。役員個人の名義で契約している場合、会社が家賃を負担したとしても、それは社宅の貸与とは認められず、全額が役員への給与(住宅手当)として課税対象となります。
役員は、会社に対して「賃貸料相当額」以上の家賃を支払う必要があります。この金額は国税庁が定める計算方法(後述)によって算出され、これを下回る場合や無償で貸与されている場合は、差額(または全額)が役員への現物給与とみなされ、所得税・住民税の課税対象となります。
物件の家賃全額は、契約者である法人が家主へ直接支払う必要があります。役員が自己負担分を含めて家主に直接支払う形式は認められません。役員が負担すべき賃貸料相当額は、会社が役員から別途徴収します。実務上は、役員報酬からの天引き(給与天引き)によって徴収するのが一般的かつ確実です。
原則として、役員の居住用住宅が対象です。会社が第三者から借り上げる「借り上げ社宅」と、会社が所有する「社有社宅」のどちらも対象となりますが、実務上は固定資産税や維持管理の負担がない借り上げ社宅が多く選ばれる傾向にあります。
役員がすでに個人で契約している、または所有している住宅を後から法人契約に切り替えて社宅とすることは、税負担の回避(租税回避)とみなされるリスクが非常に高く、原則として認められません。
法人税法上の「役員」(取締役、監査役など)が対象です。同族会社の場合は、特定の状況下で役員とみなされる親族等も含まれる可能性がありますが、会社から個人への利益供与とみなされやすいため、より慎重な運用が求められます。なお、一般の従業員(使用人)向けの社宅制度もありますが、役員とはルールが異なります。
役員社宅制度は、法人と役員双方にメリットをもたらす可能性があります。
法人が支払う社宅家賃は、原則として「地代家賃」として法人の損金に算入できます。役員から徴収する賃貸料相当額は「雑収入」や「受取家賃」として益金(収益)に計上されますが、通常、支払家賃の方が徴収額より大幅に高いため、その差額が実質的な損金となり、法人の課税所得を圧縮します。これにより、法人税等の負担が軽減されます。賃貸契約に伴う仲介手数料や、一部の礼金なども損金または繰延資産として処理できる場合があります。
役員社宅の提供に伴い役員報酬(現金給与)を減額調整する場合、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の算定基礎となる標準報酬月額が下がる可能性があります。これにより、法人負担分の社会保険料も軽減されることが期待されます。
ただし、注意が必要です。社宅という「現物給与」自体にも、税務上の賃貸料相当額とは別に、社会保険料算定のための評価額が存在します。これは厚生労働大臣が告示する基準(都道府県ごと、住宅の状況に応じて定められる)で評価され、その評価額から役員負担家賃を控除した額が報酬月額に加算されて標準報酬月額が決まります。そのため、現金給与を減額しても、この現物給与の評価額によっては、期待したほどの社会保険料軽減効果が得られない、あるいは全く軽減されない可能性もあります。社会保険料の削減効果だけを安易に期待するのは避け、専門家による正確な影響試算が必要です。
特に家賃相場の高い都市部において、有利な条件での住居提供は、優秀な経営人材の獲得や維持に繋がる魅力的な福利厚生となり得ます。
最大のメリットは、役員が適正な賃貸料相当額(通常、市場家賃より低い)を負担していれば、市場家賃とその負担額との差額(会社が実質的に負担している部分)は、役員の給与所得として課税されない点です。これは、同額を現金で住宅手当として受け取った場合、その全額が給与所得として課税されるのとは対照的です。結果として、所得税および住民税の負担が軽減されます。
法人側と同様に、役員報酬(現金給与)が減額調整されれば、役員個人が負担する社会保険料も軽減される可能性があります。ただし、ここでも厚生労働省基準に基づく現物給与評価額が標準報酬月額の算定に影響するため、必ずしも現金給与の減額分がそのまま社会保険料の軽減につながるとは限りません。
家賃負担の軽減、所得税・住民税の軽減、そして(上記の注意点を踏まえた上での)社会保険料の潜在的な軽減効果により、役員の実質的な可処分所得(手取り収入)は、同等の価値を現金給与で受け取る場合と比較して増加する可能性があります。
理論上、役員社宅の導入と役員報酬の適切な調整を組み合わせることで、単純に報酬を増額する場合と比較して、法人・個人の税負担や社会保険料負担(ただし前述の注意点あり)を合わせたトータルコストを抑えつつ、役員の手取り額を増やす効果が期待できる場合があります。 これは、社宅による経済的利益が非課税となる効果や、役員報酬(現金給与)の変動に伴う税・社会保険料への影響によるものです。ただし、これはあくまで理論上の可能性であり、個別の状況や社会保険料の現物給与評価額の影響を考慮した慎重な検討が必要です。
賃貸料相当額の計算は制度の根幹であり、誤ると税務リスクに直結します。計算方法は住宅の区分によって異なります。
まず、貸与する住宅が以下のいずれに該当するかを判定します。
以下のいずれかに該当する住宅です。
上記の基準を超える住宅で、後述の豪華社宅に該当しないもの。
税務上の「豪華社宅」に該当すると判断された場合、後述する特別な計算方法は適用されず、節税メリットは基本的に享受できません。判定は、形式的な基準と実質的な判断基準の両面から行われます。
豪華社宅の判定は、床面積という客観的基準に加え、「社会通念」といった要素が含まれるため、税務当局との解釈の違いが生じやすい点に注意が必要です。特に高額な物件や特殊な設備を持つ物件を社宅とする場合は、税務リスクが高まるため、専門家への相談が不可欠です。
住宅の区分に応じて、以下の計算式により月額の賃貸料相当額を算出します。
以下の3つの要素の合計額が、月額の賃貸料相当額となります。
賃貸料相当額 = (A) + (B) + (C)
(A) = (その年度の建物の固定資産税の課税標準額) × 0.2%
(B) = 12円 × (その建物の総床面積(㎡) / 3.3㎡)
(C) = (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額) × 0.22%
多くの場合、市場家賃の10%~30%程度になることが一般的です。
所有形態(自社所有か借り上げか)によって計算方法が異なります。
上記①②の計算式は適用されません。賃貸料相当額は「通常支払うべき使用料に相当する額」、すなわち市場家賃全額とみなされます。したがって、豪華社宅と判定されると、役員社宅としての節税メリットは失われます。
賃貸料相当額の計算には、「建物の固定資産税の課税標準額」と「敷地の固定資産税の課税標準額」の情報が不可欠です。この情報は、毎年4月~6月頃に物件の所有者(家主)に送付される「固定資産税・都市計画税 納税通知書」に同封されている「課税明細書」に記載されています。
借り上げ社宅の場合、法人(賃借人)はこの通知書を受け取らないため、家主(または管理会社)に情報提供を依頼するか、物件所在地の市区町村役場で「固定資産評価証明書」を取得する(または「固定資産課税台帳」を閲覧する)必要があります。ただし、借り上げ社宅の場合、この情報入手には実務上のハードルが存在することがあります。 家主が情報提供に協力的でなかったり、手続きが煩雑であったり、役所での証明書取得に賃貸借契約書等の提示や家主の委任状が必要となるなど、スムーズに進まないケースも想定されます。この情報入手の難しさが、正確な計算を行う上での課題となる可能性があります。
固定資産税の課税標準額は、原則として3年ごとに評価替えが行われます。評価替えにより課税標準額が変更された場合、賃貸料相当額も再計算し、役員からの徴収額を見直す必要があります。直近の評価替えは2024年度であり、次回の全国一斉の評価替えは2027年度の予定です。このタイミングでの見直しを怠ると、徴収不足となり税務リスクが生じる可能性があります。
実務上、「役員負担は家賃の50%」という話を聞くことがありますが、これは必ずしも正確ではありません。
小規模住宅の場合に、計算に基づかずに一律で家賃の50%を徴収すると、役員負担額が必要以上に高くなり、その分、法人が損金算入できる額(支払家賃 – 役員負担額)が減少してしまいます。つまり、節税メリットが大きく損なわれることになります。固定資産税課税標準額の確認には手間がかかる場合もありますが、正確な計算を行い、最低限必要な賃貸料相当額を徴収することが、制度のメリットを最大限に引き出すための鍵となります。
したがって、「家賃の50%を徴収しておけば安全」という考え方は、特に小規模住宅においては誤りであり、機会損失につながる可能性があります。手間を惜しまず正確な計算を行うことが、最適な節税戦略となります。
メリットの裏には、デメリットや注意すべき点も存在します。
物件の選定、賃貸借契約の締結・更新・解約手続き、家賃の支払い、役員からの賃料徴収、社宅規程の策定・維持管理など、相応の事務負担が発生します。社有社宅の場合は、さらに物件の維持管理、修繕対応、固定資産税の支払いなども必要となります。初期費用(敷金、礼金、仲介手数料など)や、借り上げ社宅の場合は役員の入退去による空室期間の家賃負担リスクも考慮が必要です。
会社が物件を指定する場合や、立地・家賃上限などの条件を設ける場合、役員は自身の希望通りの住居を選べない可能性があります。また、会社が住居に関与することに対して、プライバシーの観点から抵抗を感じる役員もいるかもしれません。さらに、役員社宅は法人名義の物件であるため、役員個人が住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に受けられる住宅ローン控除(減税)の適用対象外となります。将来的にマイホーム購入を考えている役員にとってはデメリットとなり得ます。そして、役員の地位を失った場合(退職など)、原則として社宅から退去する必要があります。
役員社宅制度において、会社が負担して非課税となるのは、基本的に「住宅の貸与」そのものに係る費用(家賃、管理費・共益費など)です。それ以外の費用を会社が負担すると、原則として役員への給与として課税されるため、注意が必要です。
これらの対象外費用を会社が負担してしまうと、せっかくの節税効果が損なわれるだけでなく、予期せぬ追徴課税を受けるリスクがあります。社宅規程などで、これらの費用の負担区分を明確にしておくことが重要です。
円滑かつ適法に運用するには、以下の準備と管理が不可欠です。
税務調査等で制度の正当性を主張するためには、以下の書類を整備し、適切に保管しておく必要があります。
役員社宅は、役員給与や福利厚生費と並び、税務調査でチェックされやすい項目の一つです。特に同族会社の場合は、より詳細な確認が行われる傾向があります。
税務調査において最も重要なのは、役員社宅制度が、個人的な利益供与や租税回避を主たる目的としたものではなく、会社の福利厚生や業務上の必要性に基づき、客観的かつ合理的なルールに従って適正に運用されていることを示すことです。
役員社宅制度はメリットが大きい反面、税務当局にその適正性を否認されるリスクも内包しています。否認された場合の影響は甚大であるため、リスク要因を理解し、適切な対策を講じることが極めて重要です。
税務調査において、役員社宅の取り扱いが否認される主な要因としては、以下のような点が挙げられます。
役員社宅の税務上の取り扱いが否認された場合、法人・役員双方に以下のようなペナルティ(追徴課税等)が発生します。
このように、役員社宅の否認は、単に節税メリットが失われるだけでなく、過去数年分に遡って法人・個人の双方に多額の追徴課税とペナルティをもたらす可能性があります。
上記の否認リスクを最小限に抑えるためには、以下の対策を講じることが重要です。
役員社宅制度の運用にあたっては、過去の判例や裁決事例、そして最新の税制改正の動向を把握しておくことが、リスク管理と適正な運用維持のために役立ちます。
過去の判例や裁決事例を見ていくと、役員社宅に関する税法の解釈や具体的な適用基準を理解する上で役立ちます。特に注意したいのが、豪華社宅の判定(形式だけでなく実質的な判断が重要となる点)、経済的利益をどう評価するか、家具付き社宅で家具の費用負担をどう考えるか、同族会社特有の税務リスク(行為計算否認)といった論点です。これらの実際のケースを知ることで、税務当局がどのような点を問題視し、どのような場合に否認する可能性があるのか、その傾向が見えてきます。
役員社宅に関する税務上の取り扱いの根幹(特に賃貸料相当額の計算方法)は、比較的長期間、大きな変更なく運用されています。 しかし、以下の点には注意が必要です。
したがって、基本的なルールが安定しているからといって安心するのではなく、常に最新の税務動向や判例・裁決事例に関心を持ち、自社の運用が現在の税務当局の解釈や社会通念から逸脱していないか、定期的に見直す姿勢が重要です。
役員社宅制度を導入するか否かを判断する際には、他の役員報酬・福利厚生制度と比較し、それぞれの特徴、メリット・デメリット、費用対効果を総合的に評価することが重要です。
どちらが有利かは個別の状況によりますが、役員社宅の導入にあたっては、管理コストや社会保険料への影響を慎重に考慮する必要があります。
役員社宅は、継続的な住居費負担に対する税負担軽減に有効な場合がありますが、導入・維持管理の手間とコスト、税務リスクを伴い、社会保険料のメリットは限定的または無い可能性もあります。「守りのコスト最適化」の手段と言えるでしょう。一方、ストックオプションは「攻めの報酬」、退職金は長期的な視点、住宅手当はシンプルさが特徴です。
役員社宅は、企業の財務状況、経営戦略、役員のニーズ、そしてコンプライアンス体制の整備状況などを総合的に勘案し、他の報酬・福利厚生制度とのバランスの中で、福利厚生としての側面も重視しつつ、その導入を検討すべき制度です。包括的な役員報酬戦略の一部として位置づけることが、その効果を最大限に引き出し、リスクを管理する上で重要となります。
役員社宅制度は、厳格な要件を満たせば大きな税務メリット(法人税、所得税・住民税の軽減)を享受できる有効な手段です。しかし、運用は複雑であり、賃貸料相当額の正確な計算、書類整備、税務否認リスクへの対策が不可欠です。社会保険料の軽減効果は限定的または無い可能性がある点に十分留意が必要です。
導入を検討する際は、費用対効果の試算(社会保険料の影響含む)、管理体制の評価、リスク許容度の確認、役員の意向確認を行い、必ず事前に税理士等の専門家に相談してください。安易な導入は避け、福利厚生としての合理性も確保しつつ、コンプライアンスを最優先する運用体制の構築が成功の鍵となります。特に個人物件の社宅化や豪華社宅は原則として避ける方が賢明です。
役員社宅制度は、メリットとコスト・リスク(特に社会保険料への影響と税務リスク)を十分に理解し、自社にとって真に価値ある戦略であるかを見極めた上で、慎重に導入を決定することが求められます。
契約に関するご相談は無料です。こちらからご予約ください。
面談方法は、Zoomによるオンライン面談となります。
はじめての方でも簡単にご利用いただけますのでご安心ください。
まずは以下のボタンからお申し込みください。
ご記入いただいたメールアドレス宛に事前ヒアリングシートのURLをお送りいたします。
面談に先立って事前ヒアリングシートへのご記入をお願いいたします。
ご記入いただいた事前ヒアリングシートに基づいて、面談時にヒアリングを実施致します。
ヒアリング内容に基づいて、お見積りをいたします。
お見積り内容に合意いただけた場合は、ご契約の手続を進めさせていただきます。
その他のお問い合わせはこちらから
【全国対応】
運営基準で要求される
\就労支援会計・区分会計に対応!/

介護・障がい福祉に強い! コスパ抜群の定額制! 創業期・小規模を応援! 記帳代行で負担軽減! 全国対応! 税理士が直接対応! 融資に強い! MFクラウド専門!
