
のどか会計事務所
- 公認会計士・税理士・行政書士事務所
- サービス提供地域:全国
- 営業時間:火~金 10:00~16:00
- 代表者:小野 好聡
- 〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13−20 - インボイス登録番号:T7810142329217

のどか会計事務所


















![【開業前必見】地域別訪問看護ステーション数人口比調査[2024年8月版]のアイキャッチ画像](https://nodokaya.jp/nodoka_kaikei/wp-content/uploads/2024/09/【開業前必見】-地域別訪問看護ステーション数-人口比調査-1024x576.png)
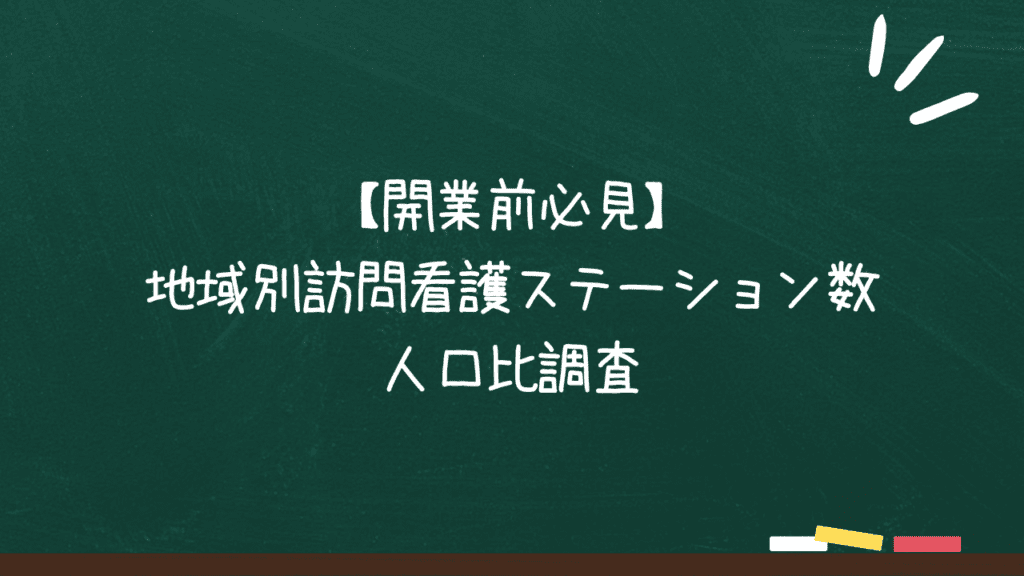
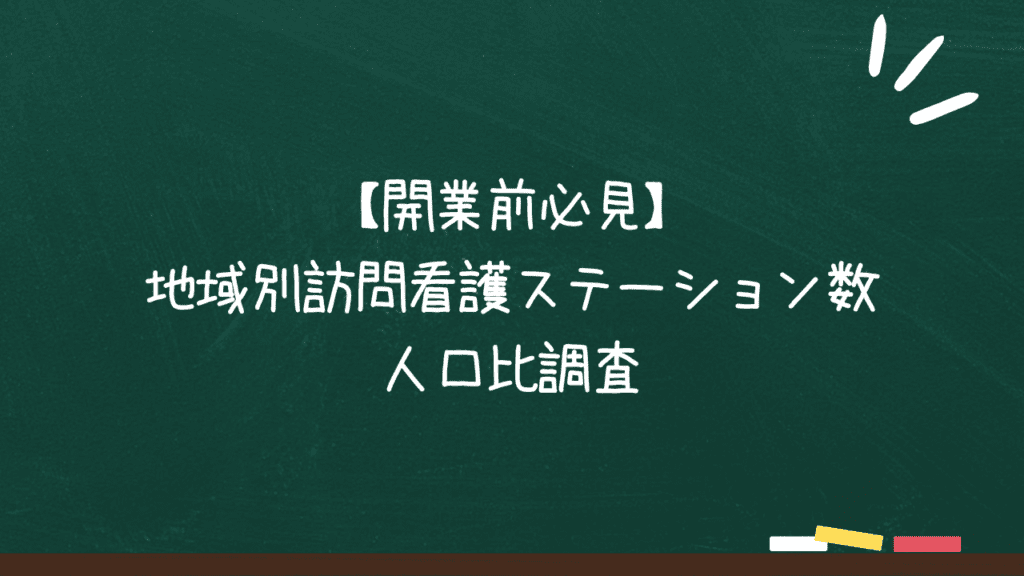
























とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)






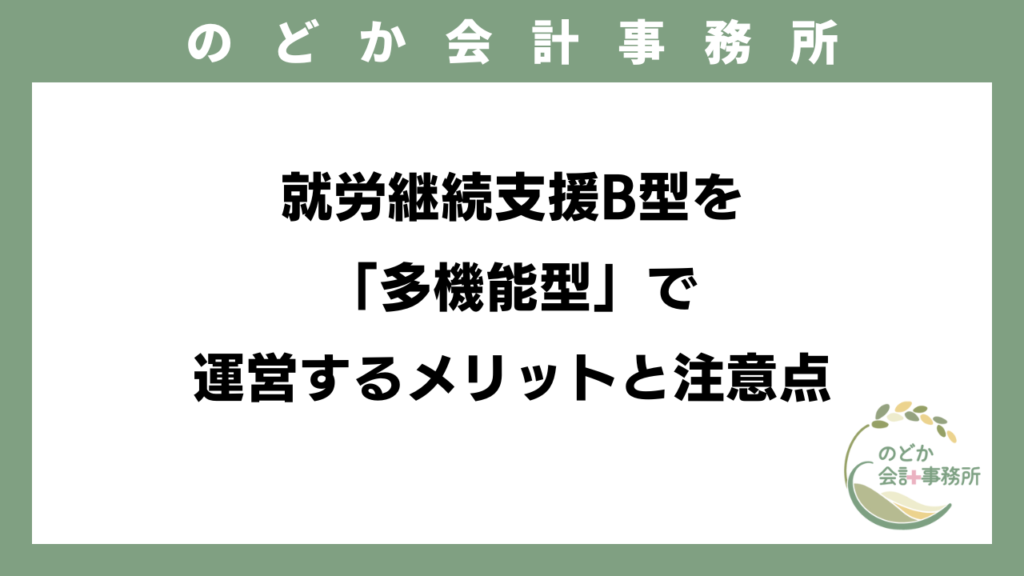
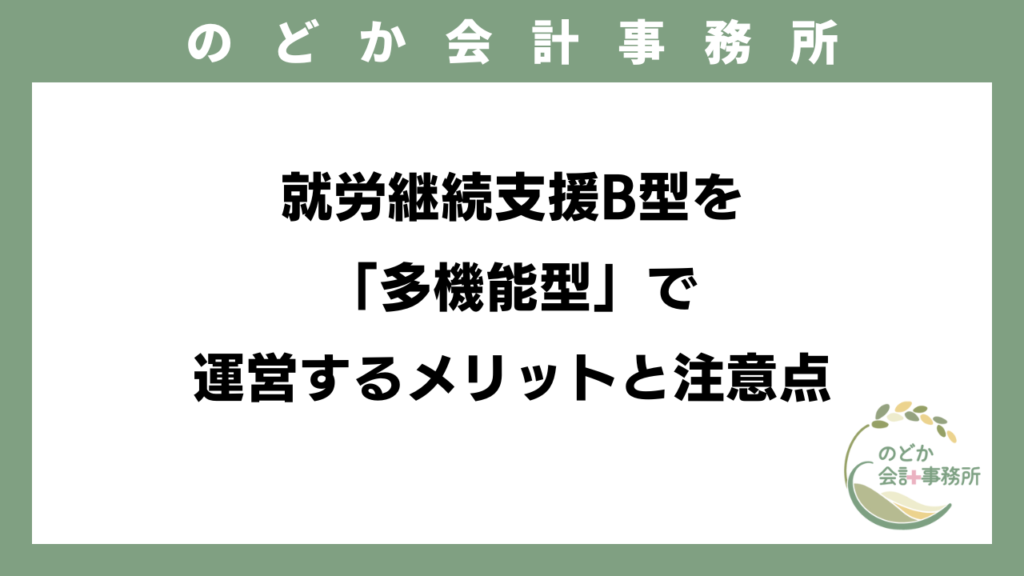
就労継続支援B型事業所の運営形態の一つに「多機能型事業所」があります。これは、一つの事業所内で、B型サービスに加えて、就労継続支援A型、就労移行支援、生活介護、放課後等デイサービスなど、複数の障害福祉サービス(または児童福祉サービス)を一体的に提供する形態を指します。多機能型として運営する場合でも、提供するサービス種類ごとに指定を受ける必要があります。
多機能型事業所にはいくつかのメリットが期待できます。まず、管理者やサービス管理責任者、事務職員、相談室や休憩室といった一部の人員や設備・スペースを複数のサービスで共用できるため、運営コストの削減につながる可能性があります。また、事業所の設立・運営に関する基準が一部緩和される点もメリットです。例えば、就労継続支援B型単独の場合、利用定員は原則20人以上必要ですが、多機能型であればB型の定員を10人以上とすることが可能になります。さらに、利用者の状態やニーズが変化した際に、同じ事業所内でスムーズにサービスを移行しやすくなり、切れ目のない支援を提供しやすくなる点や、異なるサービスの職員が連携しやすくなることで、より包括的な支援計画の立案・実行にもつながる可能性も利点です。
運営面での効率化や基準緩和が期待できる一方、多機能型は運営管理、特に会計処理が格段に複雑化するという大きな注意点があります。人員配置については、管理者やサービス管理責任者は、それぞれ一定の要件を満たせば複数のサービスを兼務することが可能です。 一方、直接支援を行う職員(職業指導員や生活支援員など)は、原則として各サービスの人員基準を個別に満たす必要があります。設備も、共用できるスペースはありますが、各サービスに必要な専用スペースは確保しなければなりません。そして最も大きな影響は会計処理です。B型サービス内部での「福祉事業活動」と「生産活動」の区分に加え、提供する複数のサービス間(例:B型と生活介護)でも共通経費を按分する必要が生じます。これにより、コスト管理や按分計算がより詳細かつ精緻になり、事務負担が増大します。多機能型を選択する場合は、これらのメリットと管理・会計の複雑化というトレードオフを慎重に検討する必要があります。
契約に関するご相談は無料です。こちらからご予約ください。
面談方法は、Zoomによるオンライン面談となります。
はじめての方でも簡単にご利用いただけますのでご安心ください。
まずは以下のボタンからお申し込みください。
ご記入いただいたメールアドレス宛に事前ヒアリングシートのURLをお送りいたします。
面談に先立って事前ヒアリングシートへのご記入をお願いいたします。
ご記入いただいた事前ヒアリングシートに基づいて、面談時にヒアリングを実施致します。
ヒアリング内容に基づいて、お見積りをいたします。
お見積り内容に合意いただけた場合は、ご契約の手続を進めさせていただきます。
その他のお問い合わせはこちらから
【全国対応】
運営基準で要求される
\就労支援会計・区分会計に対応!/

介護・障がい福祉に強い! コスパ抜群の定額制! 創業期・小規模を応援! 記帳代行で負担軽減! 全国対応! 税理士が直接対応! 融資に強い! MFクラウド専門!
