
のどか会計事務所
- 公認会計士・税理士・行政書士事務所
- サービス提供地域:全国
- 営業時間:火~金 10:00~16:00
- 代表者:小野 好聡
- 〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13−20 - インボイス登録番号:T7810142329217

のどか会計事務所


















![【開業前必見】地域別訪問看護ステーション数人口比調査[2024年8月版]のアイキャッチ画像](https://nodokaya.jp/nodoka_kaikei/wp-content/uploads/2024/09/【開業前必見】-地域別訪問看護ステーション数-人口比調査-1024x576.png)
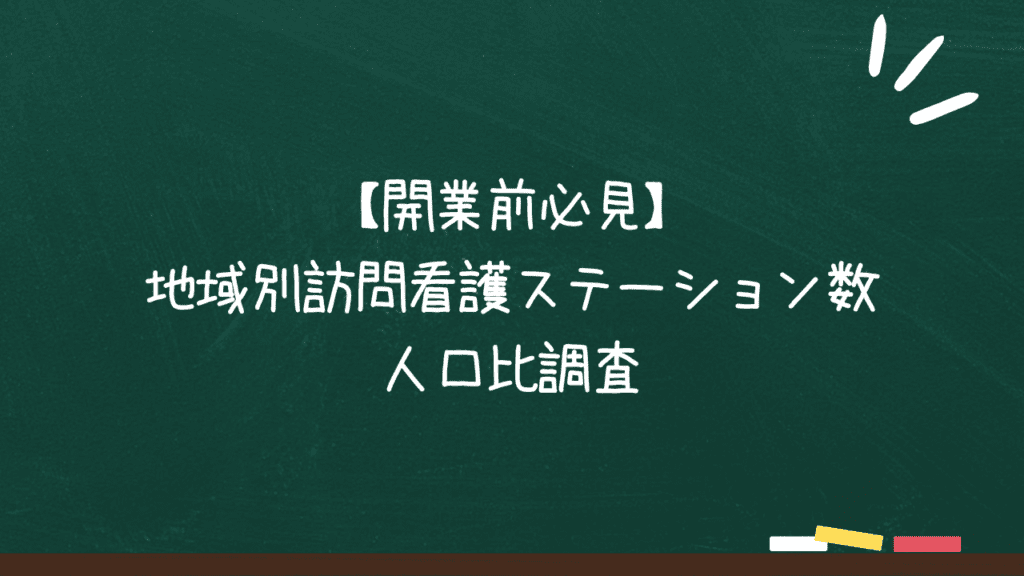
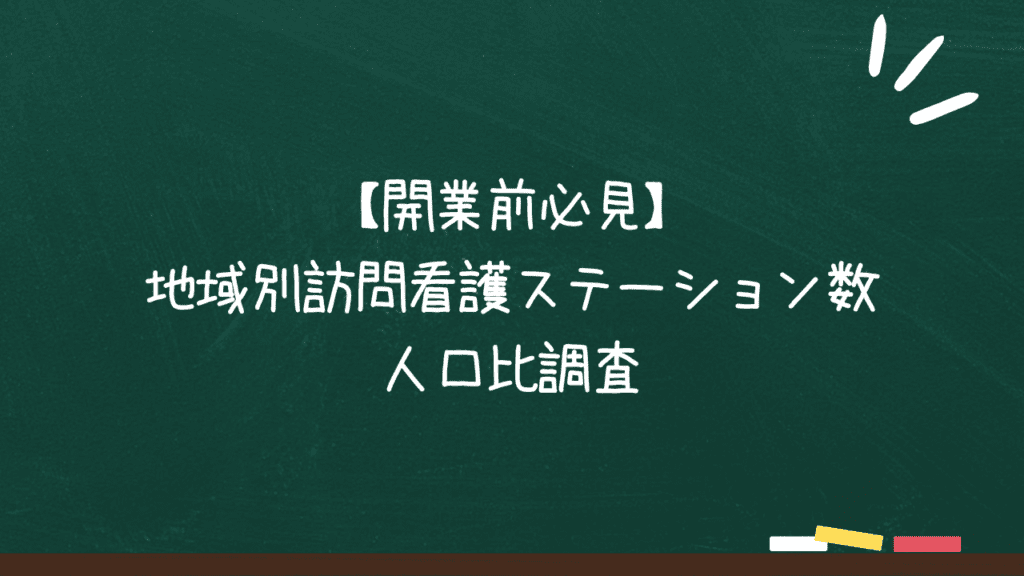
























とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)








小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模企業の役員などが、事業をやめたり役員を退いたりした後の生活安定や事業再建のための資金を事前に準備するための国の制度です。1965年に制定された小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。国の機関が運営するため、信頼性と安定性が高く、多くの経営者に利用されています。「経営者のための退職金制度」とも呼ばれ、2023年3月末時点で約162万人が加入しています。
加入資格は、主に事業の種類と「常時使用する従業員」の数で決まります。
小規模企業共済が節税対策として注目されるのは、掛金を支払う時と共済金を受け取る時の両方で税制上の優遇があるためです。
年間に支払った掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、その年の課税所得から差し引かれます。これにより、所得税と住民税が軽減されます。1年以内の前納掛金もその年の控除対象となるため、年末に前納することで戦略的な節税も可能です。
これは所得から控除される「所得控除」であり、節税額は個人の所得税・住民税の合計税率(限界税率)によって変わります。所得が高い人ほど節税効果は大きくなります。確定申告や年末調整で控除を受けるには、中小機構発行の「掛金払込証明書」が必要です。
年間掛金84万円(月額7万円)の場合の年間節税額の目安は以下の通りです。
(注:所得税率は簡便的に算定、住民税は10%と仮定して計算しています。実際の税額は個々の状況で異なります。)
高所得者ほど節税メリットが大きいことがわかります。ただし、これは「税金の繰り延べ」であり、将来共済金を受け取る際には課税されます。しかし、受取時の税制優遇があるため、多くの場合、拠出時より低い税負担で済むことが期待されます。
将来、共済金を受け取る際にも税負担が軽くなる措置があります。
税法上「退職所得」となり、他の所得と分けて税金計算(分離課税)されるため、税負担が大幅に軽減されます。
税法上「公的年金等の雑所得」となり、他の公的年金と合算して「公的年金等控除」が適用されます。他の所得と合わせて総合課税され、原則として確定申告が必要です。
一括部分は退職所得、分割部分は公的年金等の雑所得として計算されます。
多くの場合、一時金で受け取る(退職所得扱い)方が税負担は軽くなる傾向があります。退職所得控除が大きく、課税対象が1/2になるためです。
分割受取(10年または15年)は、共済金額300万円以上かつ満60歳以上などの条件を満たす場合に選択でき、運用利息相当分が加算され受取総額は増えます。しかし、総合課税による税負担増を考慮する必要があります。
例として、掛金納付25年で共済金1,700万円を受け取る場合(概算)
この例では一時金が有利ですが、個人の退職後の収入状況や生活設計によって最適な選択は異なります。事前のシミュレーションが重要です。
メリットが多い一方で、知っておくべきデメリットやリスクもあります。
最も注意すべき点の一つが「元本割れ」です。主に以下のケースで発生します。
自己都合で解約する場合、解約手当金を受け取るには最低12ヶ月の掛金納付が必要です。解約手当金の額は、掛金納付月数に応じて掛金合計額の80%~120%の範囲で定められており(小規模企業共済法施行令 別表第二)、掛金納付月数が20年(240ヶ月)に満たない場合の任意解約では、支給率が100%を下回る(80%~99.25%の範囲)ため、元本割れとなります。
納付月数が12ヶ月未満の場合は解約手当金は支給されません(全額掛け捨てとなります)。正規の共済事由(廃業など)でも、納付6ヶ月未満では共済金は支払われません。
掛金納付が12ヶ月以上滞ると強制解約され、解約手当金は任意解約と同様、20年未満なら元本割れする可能性があります。
廃業(共済金A)や老齢給付(共済金B)など、正規の共済事由で受け取る場合は、加入期間が短くても(6ヶ月以上)、通常は掛金総額の100%以上が支払われます。元本割れリスクは「脱退理由」に大きく左右されます。
掛金は、原則として退職や廃業などの正規事由発生か任意解約まで引き出せません。20年未満の任意解約は元本割れリスクがあり、税制面でも不利(一時所得扱い、後述)なため、実質的に資金は長期間固定されます。
この流動性の低さを補うのが「契約者貸付制度」(後述)ですが、貸付で対応できない不測の事態には対応しにくいという制約があります。
掛金を減額した場合、その減額された部分の掛金は将来の利息計算の対象から外れ、運用されなくなります。それに加えて、単に掛金の払込額が少なくなることにより、将来受け取る共済金等の額も減少し、契約者貸付の限度額の伸びも緩やかになります。また、その年の所得控除額も当然減少します。安易な減額はこうした複合的な影響があるため、慎重に検討しましょう。
加入、掛金変更、共済金請求にはそれぞれ手続きが必要です。
「掛金月額変更申込書」を使用します。用紙は中小機構から取り寄せるか、オンライン手続きが必要です。掛金の増額・減額は、原則として申込書が中小機構に受理された月(またはオンライン手続き完了月)から適用されます。ただし、口座振替への反映タイミングは申込時期(締切日)によって異なり、特に減額の場合は希望月の締切日までの手続き完了が必要です。 詳細は中小機構にご確認ください。減額を検討する際は、前述の影響を理解し、慎重に判断しましょう。
共済事由が発生したら請求手続きを行います。
個人事業廃止の場合、廃業届提出後に手続きとなるため、共済金受取までにタイムラグがあります。廃業資金としてすぐ必要な場合は注意が必要です。
長期の積立制度であるため、以下のリスクも考慮しましょう。
長期間の物価上昇により、将来受け取る共済金の実質的な価値が目減りするリスクがあります。制度の予定利率は1.0%と低めで、インフレ率がこれを上回ると実質価値は低下します。
このリスクへの対策としては、拠出時の節税効果を実質リターンと捉えること(特に高所得者)、iDeCoやNISAなど他の投資手段と組み合わせることが考えられます。
再掲になりますが、20年(240ヶ月)未満での任意解約は、解約手当金が掛金合計額を下回り、元本割れとなります。
さらに、65歳未満で任意解約した場合、解約手当金は税法上「一時所得」として扱われます。(注:65歳未満の共済契約者が任意解約により受け取る解約手当金は、税法上、一時所得として扱われます。)一時所得は、過去に払った掛金を経費にできず(既に所得控除済みのため)、他の所得と合算して課税されるため、退職所得扱いに比べて税負担が重くなる可能性があります。
掛金の全額所得控除や受取時の退職所得控除などの税制優遇は、将来の税法改正で見直される可能性があります。控除額の縮小や税率変更などが考えられます。
制度自体は国が運営しており安定していますが、税制面のメリットが将来変わる可能性は否定できません。対策としては、iDeCoやNISAなど他の制度と組み合わせる(分散投資)、税制改正の動向に注意を払うことが挙げられます。
退職金準備・節税の選択肢としてiDeCo(個人型確定拠出年金)もあります。
| 特徴 | 小規模企業共済 | iDeCo |
|---|---|---|
| 加入資格 | 小規模企業の経営者・役員等(従業員数要件あり) | 広く国民(自営業者、会社員等) |
| 掛金上限(月) | 70,000円 | 加入者区分による(例:自営業者68,000円、会社員23,000円等) |
| 掛金の所得控除 | 全額 | 全額 |
| 受取時の税制優遇 | 退職所得控除、公的年金等控除 | 退職所得控除、公的年金等控除 |
| 運用方法 | 加入者選択不可(機構が一括運用) | 加入者が運用商品(投信等)を選択 |
| 元本保証・運用リスク | 計算式に基づく。任意解約時等に元本割れリスクあり | 商品による(投信等は元本保証なし、市場リスクあり) |
| 契約者貸付制度 | あり | なし |
| 途中引出し | 任意解約可(20年未満ペナルティあり) | 原則60歳まで不可 |
どちらが良いかは個人の状況や考え方によります。
両方の資格があれば併用も可能です。小規模企業共済で安定性と高い控除枠を確保し、iDeCoで運用による資産成長を目指す、という戦略が取れます。両方の掛金が所得控除の対象となるため、最大限の節税と資産形成を両立したい場合に有効です。
共済契約を解約せずに、払い込んだ掛金の範囲内(掛金の7~9割が目安)で事業資金等を借りられる制度です。
運転資金、設備投資、納税資金などに活用できます。早期解約を避けるセーフティネットになります。ただし、あくまで借入れであり、計画的な返済が必要です。返済が滞ると延滞利子(年14.6%)が発生し、共済契約に影響が出る可能性もあります。
小規模企業共済は、節税と退職金準備を両立できる強力なツールですが、その特性を理解し、計画的に利用することが重要です。
これらの点を踏まえ、ご自身の状況に合わせて小規模企業共済を戦略的に活用してください。
契約に関するご相談は無料です。こちらからご予約ください。
面談方法は、Zoomによるオンライン面談となります。
はじめての方でも簡単にご利用いただけますのでご安心ください。
まずは以下のボタンからお申し込みください。
ご記入いただいたメールアドレス宛に事前ヒアリングシートのURLをお送りいたします。
面談に先立って事前ヒアリングシートへのご記入をお願いいたします。
ご記入いただいた事前ヒアリングシートに基づいて、面談時にヒアリングを実施致します。
ヒアリング内容に基づいて、お見積りをいたします。
お見積り内容に合意いただけた場合は、ご契約の手続を進めさせていただきます。
その他のお問い合わせはこちらから
【全国対応】
運営基準で要求される
\就労支援会計・区分会計に対応!/

介護・障がい福祉に強い! コスパ抜群の定額制! 創業期・小規模を応援! 記帳代行で負担軽減! 全国対応! 税理士が直接対応! 融資に強い! MFクラウド専門!
