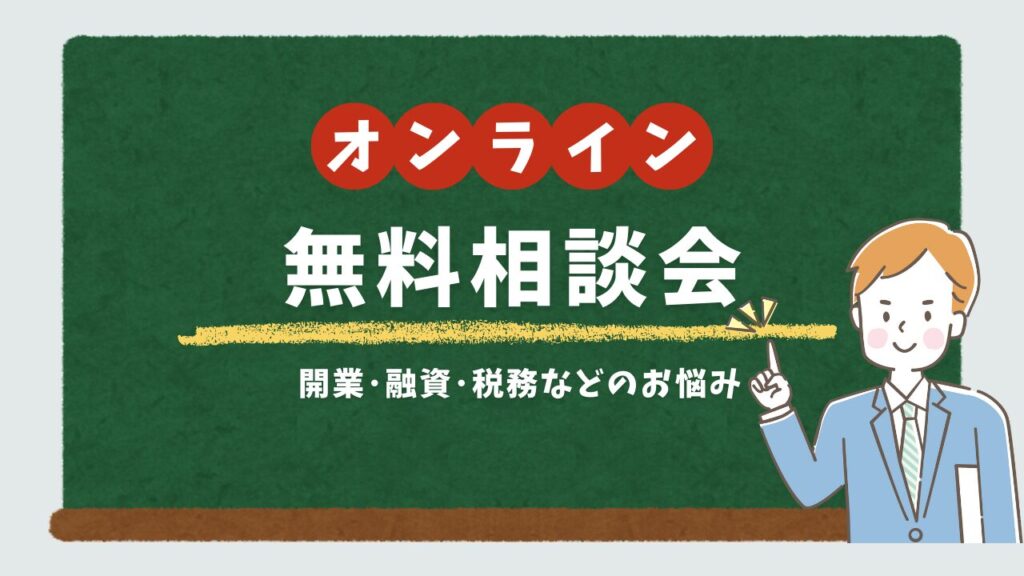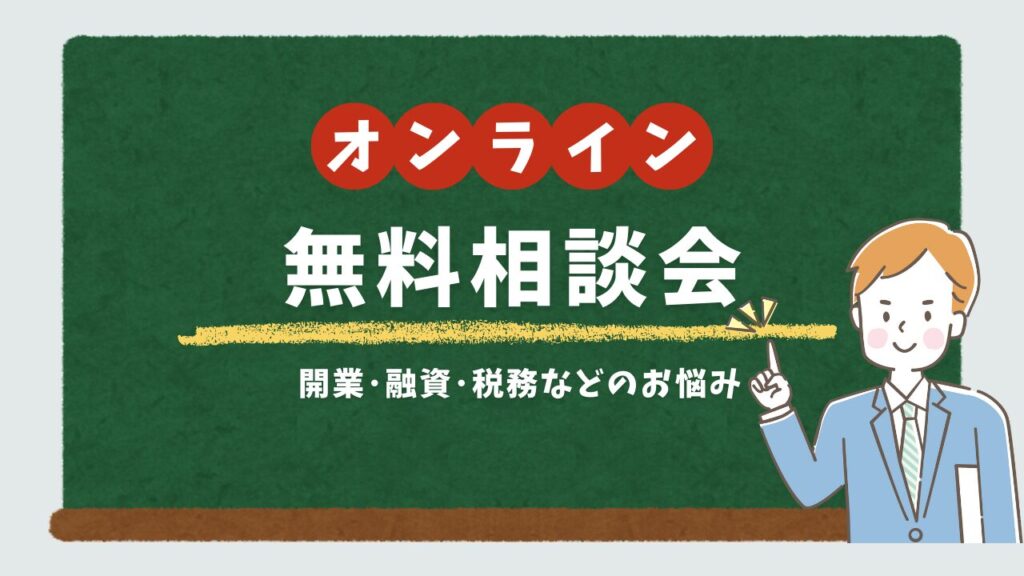【大阪 税理士】年間11万円~!
決算料と記帳代行込みで安心の税理士事務所
古くから「商人の街」として栄え、今も数多くの中小企業が地域経済を力強く支える大阪。この活気ある街では、コストへの意識も高く、シビアな目で合理的かつ質の高いサービスが求められます。日々の経営に奮闘されたり、これから事業を軌道に乗せようと考えたりする中で、避けては通れないのが税金の問題です。専門家である税理士のサポートを検討し始めた時、まずこんな疑問が浮かびませんか?
「大阪で税理士を探しているけれど、どこに頼めばいいかわからない…」
「税理士費用って、結局いくらかかるの?」
「創業したばかり。コストは抑えたいけど、税金のことは不安…」
大阪で事業を立ち上げたばかりの方や、日々の経営に奮闘されている事業者様にとって、税理士選びは重要な課題です。特に創業期は、限られた資金の中で最適なサポートを見つけたいと考えるのは当然のことでしょう。
そんな悩みを抱える大阪の事業者様へ。「のどか会計事務所」なら、創業1期目は決算料・記帳代行料込みで年間総額110,000円からという、驚きの低価格で充実した税務サポートを提供しています。
(※原則として介護・障がい福祉事業者様限定のプランです)
この記事では、税理士選びで後悔しないための基礎知識から、コストパフォーマンスに優れた税理士を見つけるヒントまで、詳しく解説していきます。税理士の役割や費用相場、確定申告や税務調査の基本、そして「のどか会計事務所」がなぜ創業期の介護・障がい福祉事業者様におすすめなのか、その理由を具体的にご紹介します。税務に関する不安を解消し、事業成長に集中できる環境を手に入れるための一助となれば幸いです。
目次
なぜ税理士が必要なのか?税理士の役割とメリットを知ろう

なぜ税理士が必要なのか?
税理士の役割とメリットを知ろう
まず、「税理士」とは具体的にどのような専門家で、どんなことを依頼できるのか、基本的なところから見ていきましょう。
税理士とは?その役割と独占業務
税理士は、税理士法という法律に基づいて認定された税務に関する国家資格を持つ専門家です。その主な使命は、日本の「申告納税制度」(納税者自身が所得や税額を計算して申告・納税する制度)が正しく機能するように、納税者を専門的な知識でサポートすることにあります。
税理士には、法律によって税理士資格を持つ者だけが行える「独占業務」が定められています。これは、たとえ報酬を受け取らなくても(無償でも)、資格のない人が行うことは原則として禁止されている業務です。税法の複雑さや税金が国や社会にとって重要であることを考えると、これらの業務は専門家である税理士に任せるべき、という考えに基づいています。
税理士の主な独占業務は以下の3つです。
- 税務代理納税者の代理人として、税務署などの税務官公署とのやり取りを行うことです。具体的には、以下のような業務が含まれます。
- 確定申告書、法人税申告書、消費税申告書、相続税申告書などの作成と提出代行
- 青色申告の承認申請などの各種申請・届出
- 税務調査への立会いと対応
- 税務署の決定(更正・決定)に対する不服申立て(審査請求など)の手続き 税務に関する手続きや税務調査は専門知識が必要なため、税理士の代理は非常に心強いサポートとなります。
- 税務書類の作成納税者に代わって、税務署などに提出する申告書や申請書などの書類を作成することです。
- 確定申告書、法人税申告書、消費税申告書、相続税申告書
- 青色申告承認申請書
- 年末調整に関する書類、法定調書
- その他、税務署などに提出する各種書類 税理士が作成することで、法律の要件を満たした正確な書類を作成することができます。
- 税務相談納税者からの具体的な税金に関する相談に応じることです。
- 所得金額や税額の計算方法に関する相談
- 取引が税務上どのように扱われるか(節税に関するアドバイスを含む)
- 税務調査への対応方法に関する相談
- 相続や事業承継に関する税務上の相談など 専門的なアドバイスを受けることで、納税者は正しい判断を下し、事前に税法を守ることができます。
これらの独占業務に加えて、税理士は会計業務(記帳代行、決算書の作成支援など)や経営コンサルティングといった関連業務も幅広く行っています。税金の計算は正確な会計処理が前提となるため、税理士が会計業務も併せてサポートすることは、特に中小企業や個人事業主にとって非常に合理的です。
税理士に依頼するメリット
税理士に業務を依頼することには、多くのメリットがあります。
- 正確な申告と納税
複雑な税法に基づいて正確な申告書を作成し、適切な納税額を算出してくれるため、申告漏れや計算ミスを防ぐことができます。税務署からの信頼にも繋がります。
- 節税対策
税法の範囲内で認められる様々な控除や特例制度を最大限に活用し、合法的な節税対策を提案・実行してくれます。税理士は最新の税制改正にも精通しているため、有利な制度を見逃すリスクを減らせます。
- 時間と手間の削減
煩雑な記帳作業、書類作成、申告手続きなどを専門家に任せることで、経営者や事業主は貴重な時間を節約し、コア業務に集中できます。
- 経営判断のサポート
月次試算表などを通じて会社の財務状況をタイムリーに把握し、経営に関する客観的で的確なアドバイス(資金繰り改善、コスト削減、収益向上策など)を受けることができます。経営の羅針盤としての役割も期待できます。
- 税務調査への的確な対応
万が一、税務調査が入った場合でも、専門家として冷静に立会い、納税者の代理として調査官と対峙してくれます。不用意な発言による不利な状況を避け、適切な主張や交渉を行うことで、精神的な負担も大幅に軽減されます。
- 融資・資金調達の円滑化
金融機関からの融資を受ける際に必要となる信頼性の高い事業計画書や決算書の作成支援、金融機関との交渉サポートなど、資金調達を有利に進めるための支援も期待できます。税理士が関与することで、金融機関からの信用度が高まることもあります。
- 最新情報の入手
税制改正はもちろん、補助金・助成金、関連法規の変更など、事業運営に影響を与える可能性のある最新情報をタイムリーに提供してくれます。
税理士と他の専門家(士業)との違い
世の中には「士業」と呼ばれる様々な専門家がいます。税理士と混同されやすい他の主な士業との違いを理解し、どのような場合にどの専門家に相談すべきかを知っておきましょう。
- 公認会計士
- 主な役割
企業の財務諸表(決算書)が正しく作成されているかを第三者の立場からチェックする「監査」の専門家。特に上場企業などに対し、財務情報の信頼性を保証する役割を担います。
- 独占業務
財務諸表監査。
- 税理士との違い
税理士は「税務」、公認会計士は「監査・会計」が中心。公認会計士は税理士登録すれば税理士業務も可能ですが、税理士は監査業務はできません。大企業の監査だけでなく、中小企業の会計指導やコンサルティングも行います。
- 弁護士
- 主な役割
法律全般のエキスパート。契約トラブル、債権回収、労務問題、損害賠償請求など、あらゆる法的紛争の解決をサポートします。契約書の作成・チェックなども主要業務です。
- 独占業務
訴訟代理、法律相談、示談交渉など、法律事務全般。報酬目的で弁護士以外が行うと「非弁行為」となります。
- 税理士との違い
税理士は税法、弁護士は法律全般。税務に関する争いでは、弁護士が訴訟代理人、税理士は補佐人として連携することがあります。弁護士資格があれば税理士業務もできますが、主に税務訴訟や複雑な法解釈が絡む案件に関与します。
- 司法書士
- 主な役割
不動産(土地・建物)の売買や相続、会社の設立や役員変更などに関わる「登記」手続きの専門家。法務局への申請代理が中心です。
- 独占業務
不動産登記、商業・法人登記の申請代理。裁判所提出書類(相続放棄申述書など)の作成も行います。
- 税理士との違い
税理士は税務署、司法書士は法務局が主な窓口。会社設立(税理士:税務届出、司法書士:設立登記)や相続(税理士:相続税申告、司法書士:不動産登記)では連携が不可欠です。
- 行政書士
- 主な役割
役所などの官公署に提出する書類作成や、事業に必要な許認可申請の代行を行う専門家。建設業、飲食店、古物商、運送業など、多種多様な許認可申請を扱います。
- 独占業務
官公署への提出書類作成・代理提出、権利義務(契約書等)・事実証明(議事録等)に関する書類作成。ただし、税務書類作成や登記申請、紛争解決など、他の法律で制限された業務はできません。
- 税理士との違い
税理士は税務、行政書士は行政手続きが専門。許認可が必要な事業を開始する際には行政書士のサポートが重要です。
- 社会保険労務士(社労士)
- 主な役割
従業員の入退社に伴う労働保険・社会保険の手続きや、就業規則の作成、給与計算、助成金申請、労務管理に関する相談など、人事・労務分野の専門家です。
- 独占業務
労働・社会保険に関する申請書等の作成・提出代行、労働者名簿・賃金台帳などの法定帳簿作成。
- 税理士との違い
税理士は税務・会計、社労士は労務・社会保険の専門家。給与計算は両者に関連しますが、年末調整などの税務判断は税理士の領域です。従業員を雇用する上で、社労士は頼れる存在です。
大阪で税理士を選ぶ際のポイント
大阪には多くの税理士事務所があります。数ある選択肢の中から、自社に最適なパートナーを見つけるためには、いくつかの比較検討ポイントがあります。
費用体系をしっかり確認する:総額と内訳の重要性
税理士報酬は事務所によって様々です。契約後に「思ったより高かった」とならないよう、料金体系を詳細に確認することが不可欠です。
- 顧問料
税務相談や月次チェックなど、継続的なサポートに対する基本料金。通常は月額または年額で設定されます。事務所によっては、記帳代行が含まれていない場合があるので注意が必要です。
- 記帳代行料
日々の取引入力(記帳)を依頼する場合の料金。顧問料とは別に、仕訳数などに応じて請求されることがあります。創業期や人手が足りない場合に依頼することが多い業務です。
- 決算料(申告料)
法人税や消費税などの確定申告書作成・提出に対する年1回の料金。顧問料に含まれず、別途請求されるのが一般的です。
- 年末調整費用
従業員の年末調整を依頼する場合、従業員数に応じて別途費用がかかることが多いです。
- その他オプション費用
税務調査立会い、融資支援、補助金申請サポートなどは、基本料金に含まれず、別途料金が発生する可能性があります。
【ここがポイント!】
「月額顧問料が安い」というだけで選ぶのは危険です。決算料や記帳代行料が別途高額に設定されている可能性も。必ず年間の総額でいくらになるのか、見積もりを取得し、どのサービスが料金に含まれているのか内訳を明確にしてもらいましょう。決算料や記帳代行料が顧問料に含まれている「コミコミ料金」や月額定額制(サブスクリプション)の事務所を選ぶと、費用の見通しが立ちやすく安心です。
専門分野や得意業種:見極め方と注意点
税理士の中には、特定の分野(相続税、国際税務など)や業種(医療、IT、建設など)に特化している事務所もあります。自社の業種や相談したい内容に精通した税理士であれば、より深いレベルでのアドバイスや業界特有の課題への対応が期待できます。
【注意点】
ただし、「専門」を謳っていても、マーケティング目的で専門を謳っているだけで、必ずしも専門であるとは限りません。また、専門性を理由に料金が高めに設定されていることもあります。ホームページの情報だけでなく、無料相談などの機会を利用して、具体的な業務内容や業種への理解度などを直接確認することが重要です。「専門」という言葉に惑わされず、総合的な対応力を見極めましょう。
コミュニケーションの取りやすさ・相性:長期的な関係のために
税理士とは、会社の財務状況という機密情報を共有し、長期的に付き合っていく可能性が高いパートナーです。そのため、気軽に相談できるか、説明が分かりやすいか、信頼できる人柄かといった、コミュニケーション面や相性は非常に重要です。
- 説明の分かりやすさ
専門用語を多用せず、こちらのレベルに合わせて丁寧に説明してくれるか。
- 質問のしやすさ
初歩的な質問でも快く答えてくれるか、威圧感なく相談できる雰囲気か。
- レスポンスの速さ
メールや電話での問い合わせに対する返答は迅速か。緊急時の対応はどうか。
- 担当者との相性
契約後の主な担当者が誰になるのか(資格を持った税理士本人か、経験の浅いスタッフか)。可能であれば、契約前に担当者と話してみるのが理想です。資格を持つ税理士が直接対応してくれる事務所なら、質の高いコミュニケーションと安心感が得られます。
いくつかの事務所の無料相談を受けてみて、コミュニケーションの質や相性を比較検討することをおすすめします。
対応スピードとICT活用度:現代ビジネスに不可欠な要素
変化の速い現代において、税理士の対応スピードや情報共有の方法も重要な選択基準です。ICT(情報通信技術)をどの程度活用しているかも、業務の効率性や利便性に直結します。
- クラウド会計ソフトへの対応
マネーフォワードクラウドやfreee会計など、主要なクラウド会計ソフトに対応しているか、導入支援は可能か。クラウド会計は、リアルタイムでの業績把握、銀行口座やクレジットカードとの連携による自動仕訳、場所を選ばないアクセスなど、多くのメリットがあります。
- オンラインコミュニケーション
Zoomなどを使ったオンラインでの面談や相談が可能か。大阪府内でも移動時間を節約できますし、府外の事業者でも大阪の税理士に依頼しやすくなります。
- チャットツールの活用
Stock、Chatwork、Slack、LINEなどのビジネスチャットツールでの連絡に対応しているか。電話やメールよりも迅速で手軽なコミュニケーションが可能です。
- 資料共有の方法
紙媒体だけでなく、クラウドストレージ(OneDrive,Google Drive, Dropboxなど)を利用したデータ共有に対応しているか。郵送の手間やコストを削減できます。
ICT活用に積極的な事務所は、業務効率が高く、結果として費用対効果の高いサービスを提供できる傾向があります。また、ペーパーレス化やリモートワークといった現代的な働き方にも柔軟に対応できる可能性が高いでしょう。
創業期こそ税理士選びが重要!大阪でコストを抑えるポイント

創業期こそ税理士選びが重要!
大阪でコストを抑えるポイント
事業をスタートさせたばかりの創業期は、やるべきことが山積みです。資金も人材も限られ、経営者は本業に集中したい時期です。税務や経理は後回しにしたくなるかもしれませんが、実は創業期こそ税理士のサポートが事業の成否を左右すると言っても過言ではありません。
なぜ創業期に税理士が必要なのか?
- 設立・開業時の複雑な手続きをミスなくクリア
会社設立登記後の税務署・都道府県・市町村への各種届出(法人設立届出書、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書など)は種類が多く、提出期限も定められています。これらの手続きを漏れなく行うことで、後々のトラブルや税務上の不利益を防ぎます。
- 創業融資を有利に進める
創業融資の申請には、説得力のある事業計画書が不可欠です。税理士は、金融機関が見るポイントを押さえた事業計画書の作成を支援し、面談対策などのアドバイスも行います。税理士のサポートがあることで、融資の成功確率が高まることが期待できます。
- 節税効果の高い役員報酬の設定
法人の場合、役員報酬の決め方一つで、法人と個人のトータルでの税負担が大きく変わります。創業初期に、会社の利益計画や税金・社会保険料を考慮した最適な役員報酬額を決定しておくことが重要です。税理士はこの判断を専門的にサポートします。
(※事業年度開始から3ヶ月以内など、決定時期に制限あり)
- 将来を見据えた経理体制の基礎固め
最初から適切な会計ソフトを選び、効率的な経理ルールを構築しておくことで、事業規模が拡大しても混乱なく対応できる基盤を作れます。
- 税務上の有利な制度を最大限活用
青色申告の承認申請は、設立・開業から一定期間内に提出しないと、初年度からそのメリット(最大65万円の特別控除、赤字の繰越など)を受けられません。税理士がいれば、こうした有利な制度を確実に活用できます。
- 早期からのコンプライアンス意識の醸成
創業当初から税理士と関わることで、日々の取引における経費計上の注意点などを学び、税務コンプライアンス意識を高めることができます。
「税理士費用がもったいないから、もう少し売上が安定してから…」と考えるのは、実はリスクが高い選択です。創業期のわずかな手続きミスや判断の誤りが、後々、追徴課税や融資の失敗といった形で、何倍ものコストになって返ってくる可能性があるのです。創業期の税理士費用は、事業を軌道に乗せるための重要な「投資」と捉えるべきでしょう。
創業期の税理士選び!大阪でコストを抑える賢い選択
創業期の貴重な資金を有効に使うために、コストパフォーマンスを重視した税理士選びが求められます。以下の点をチェックしましょう。
- 創業者向けの特別プラン
創業期限定の割引料金や、負担の少ないパッケージプランが用意されているか。
- 料金の透明性
月額顧問料に何が含まれ、何が別途費用となるのかが明確か。決算料や記帳代行料が込みになっていると、総額が分かりやすく安心です。
- 月額定額制(サブスク)
年間の費用が予測しやすく、キャッシュフロー管理がしやすい月額定額制は、創業期に適しています。
- 記帳代行込み
経理に時間を割けない創業期には、記帳代行が含まれているプランが負担軽減につながります。
- ICT活用による効率化
クラウド会計などを活用し、効率化によって低価格を実現している事務所は狙い目です。
【大阪の創業者(介護・福祉分野)必見!】
年間11万円~!のどか会計事務所の圧倒的コスパ
「創業費用を少しでも抑えたい!」
「でも、税金のことは専門家にしっかり見てほしい…」
そんな切実な願いを持つ大阪の創業者・起業家の方々(特に介護・障がい福祉分野)に、自信を持っておすすめするのが「のどか会計事務所」です。
\ のどか会計事務所が創業期(介護・福祉)に選ばれる理由 /
- 衝撃の創業期価格!年間11万円から
最大の魅力は、創業1期目限定の特別価格。決算料・記帳代行料が全て込みで、年間総額110,000円からという、業界最安値水準の特別プランをご用意しています。月額にすると約9,167円から。この価格で税理士のフルサポートが受けられるのは、創業期の大きなアドバンテージです。
- 明瞭会計!決算料・記帳代行料0円のサブスクモデル
「結局いくらかかるの?」という不安を解消する、月額定額制(サブスクリプション)を採用。さらに、多くの事務所で別途請求される決算料や記帳代行料が、月額顧問料に含まれています。年間の税理士費用が明確で、資金計画が立てやすいのがメリットです。
- クラウド会計専門で効率化を追求
マネーフォワードクラウド公認メンバーとして、クラウド会計の活用を前提としたサービスを提供。業務効率化を徹底することで、低価格ながら質の高いサービスを実現しています。これから経理を始める方にも、スムーズな導入をサポートします。
- 大阪から全国へ!オンラインで完結
事務所は大阪市にありますが、Zoom、チャット、クラウドストレージなどを駆使し、全国どこでも対応可能です。大阪にいながら、全国の事業者様をサポートしています。もちろん、大阪近隣の方もオンラインでスムーズに対応します。
- 資格を持つ税理士が直接対応!安心の品質
経験豊富な税理士が、お客様からの相談に直接対応します。専門家と直接話せるため、的確でスピーディーな課題解決が期待できます。
- カイポケ利用特典も!
介護・福祉事業者向け経営支援サービス「カイポケ」のアンバサダーも務めており、事務所経由での申し込みで月額利用料の無料期間延長特典があります(介護保険サービス全般と障がい福祉の訪問系サービス・障害児通所支援サービスに対応)。
のどか会計事務所の低価格は、徹底したICT活用による業務効率化と、「創業期の介護・福祉事業者を応援したい」という強い想いによって成り立っています。安さだけでなく、質の高いサポートを求める大阪の創業者(介護・福祉分野)にとって、最適な選択肢の一つと言えるでしょう。
(※原則として顧問契約は介護・障がい福祉事業者様限定となります)
これだけは知っておきたい!税理士関連業務の基礎知識

これだけは知っておきたい!
税理士関連業務の基礎知識
税理士に業務を依頼する際、関連する税務や会計の基本的な知識があると、よりスムーズにコミュニケーションが取れ、提供されるサービスの価値を最大限に引き出すことができます。ここでは、特に知っておきたい基礎知識を分かりやすく解説します。
確定申告の基礎(個人・法人)
確定申告とは?
個人や法人が、一定期間(通常1年間)の所得(儲け)と、それに対して納めるべき税金の額を計算し、税務署に申告・納税する一連の手続きです。日本の多くの税金は、この「申告納税方式」が採用されています。
【個人の確定申告】
- 対象となる期間
毎年1月1日から12月31日までの1年間。
- 申告と納税の期限
原則として、翌年の2月16日から3月15日まで。
- 確定申告が必要となる主なケース
- 個人事業主やフリーランスとして事業所得や不動産所得があり、計算した結果、納める税金がある場合。
- 会社員など給与所得者でも、年収が2,000万円を超える場合、副業での所得(収入から経費を引いた額)が年間20万円を超える場合、2ヶ所以上から給与をもらっていて年末調整されない収入がある場合など。
- 公的年金等の収入が400万円を超える場合、または年金以外の所得が20万円を超える場合。
- 土地・建物や株式などを売却して利益が出た場合(一定の条件を除く)。
- 生命保険の一時金などを受け取った場合。
- 医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税など)、住宅ローン控除(1年目)など、年末調整では適用できない控除を受けて税金の還付を受けたい場合(これを「還付申告」といい、翌年1月1日から5年間申告可能)。
- 年末調整との関係
多くの会社員は年末調整で所得税の計算が終わりますが、上記のケースに該当する場合や、年末調整で適用できない控除を使いたい場合は、自身で確定申告が必要です。
- 副業所得20万円の注意点
所得税の確定申告が不要な副業所得(年間20万円以下)でも、住民税の申告は別途必要になるケースがあります。確定申告をすれば住民税の申告は不要ですが、しない場合は市区町村への確認が必要です。
【法人の確定申告】
- 対象となる期間
法人が定款で定めた事業年度(通常は1年間)。
- 申告と納税の期限
原則として、事業年度終了の日の翌日から2か月以内。(例: 3月31日決算の法人は5月31日が期限)
- 申告義務
株式会社、合同会社など、原則として全ての法人が対象です。
- 赤字でも申告は必要!
たとえ事業が赤字であっても、確定申告を行う義務があります。赤字を申告することで、その赤字(欠損金)を将来(最大10年間)の黒字と相殺し、将来の税負担を軽減できる「欠損金の繰越控除」という重要なメリット(青色申告の場合)を受けられます。無申告は、このメリットを失うだけでなく、税務調査のリスクを高めたり、融資審査で不利になったりする可能性があります。
- 提出書類
法人税申告書(非常に多くの「別表」と呼ばれる添付書類が必要)、決算報告書(貸借対照表、損益計算書など)、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書など、個人の申告に比べて格段に複雑で、専門的な知識が要求されます。消費税の課税事業者であれば、消費税申告書も必要です。
- 納税する税金
法人税・地方法人税(国税)に加え、法人事業税・法人住民税(地方税)の申告・納税も必要です。法人住民税には、赤字でも資本金や従業員数に応じて課税される「均等割」という区分があります。
確定申告をしない・遅れた場合のペナルティ
期限を守らない場合、厳しいペナルティが待っています。
- 無申告加算税
申告しなかったことに対する罰金(最大30%)。
- 延滞税
納税が遅れた日数に応じてかかる利息(最大14.6%)。
- 重加算税
所得隠しなど悪質な場合に課される、さらに重い罰金(最大40%)。
- 青色申告の取消し
(法人・個人事業主)期限後申告が続くと、様々な税務メリットがある青色申告の承認が取り消されるリスクがあります。
- 信用の失墜
金融機関からの評価が下がり、融資が受けにくくなる可能性があります。
記帳代行とは?
事業活動における日々の取引(売上、仕入、経費の支払い、入出金など)を、領収書、請求書、銀行通帳などの資料をもとに、会計ルールに従って帳簿(現代では主に会計ソフト)に記録していく作業を「記帳」と言います。この記帳は、正確な決算書を作成し、正しい税額を計算するための基礎となります。
「記帳代行」とは、この時間と専門知識を要する記帳作業を、税理士事務所などが事業者に代わって行うサービスのことです。記帳代行を利用することで、事業者は記帳業務の負担から解放され、コア業務に専念できるというメリットがあります。
のどか会計事務所の税務顧問サービスでは、この記帳代行が基本料金に含まれているため、安心して経理業務を任せることができます。
年末調整とは?確定申告との違い
年末調整は、主に会社などに勤務する給与所得者を対象とした手続きです。勤務先の会社が、毎月の給与から天引き(源泉徴収)している所得税の年間合計額と、その従業員の年間の給与総額に基づいて計算される正しい所得税額とを比較し、その過不足を年末(通常は12月)に精算する仕組みです。
これにより、多くの給与所得者は、自分で確定申告をしなくても、所得税の納税が完了します。
ただし、年末調整で計算・控除できる項目は限られています。例えば、給与所得以外の所得(副業など)や、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を除く)、雑損控除、住宅ローン控除の初年度適用などは、年末調整では対応できません。
したがって、これらの所得や控除がある場合は、年末調整を受けていたとしても、別途確定申告が必要になります。逆に言えば、確定申告をすることで、年末調整では受けられなかった控除を適用し、払いすぎた税金の還付を受けられる可能性があるということです。
「節税」と「脱税」は全く違う!正しい税知識を
税金の負担を少しでも軽くしたい、と考えるのは経営者として当然のことです。しかし、その方法を間違えると、取り返しのつかない事態を招きかねません。「節税」と「脱税」は、似ているようで全く異なる概念です。
- 節税
税法で認められているルールや制度(控除、特例など)を合法的に活用して、税負担を軽減する行為です。例えば、必要経費を漏れなく計上すること、iDeCoやNISAといった税制優遇制度を利用すること、青色申告を選択して特別控除を受けることなどが挙げられます。節税は、法律が納税者に認めた正当な権利であり、積極的に検討すべきものです。
- 脱税
売上の一部を隠したり、存在しないまたは事業に関連しない経費を計上(架空経費)したり、帳簿や領収書を改ざん・偽造したりするなど、意図的に不正な手段を用いて納税義務を免れようとする違法行為(犯罪)です。
- 租税回避
税法の条文では直接禁止されていないものの、通常の経済活動では考えられないような取引形態をとるなどして、結果的に税負担を軽減しようとする行為。合法と違法の境界線上にあり、税務当局から「法の趣旨に反する」として否認されるリスクを伴います。
脱税のリスクは計り知れません。 発覚した場合、本来納めるべき税金(本税)だけでなく、高額な延滞税、そして悪質性に応じた加算税(特に意図的な隠蔽・仮装があった場合は重加算税)が課され、納税額が当初の何倍にも膨れ上がる可能性があります。さらに、悪質なケースでは刑事告発され、懲役刑や罰金刑といった刑事罰を受けることになり、社会的信用は完全に失墜します。税務調査では、「知らなかった」という言い訳は通用しないことがほとんどです。疑わしい節税策には手を出さず、必ず税理士に相談し、合法的な範囲での対策を検討しましょう。
税務調査とは?いつ、何をされるのか?
税務調査とは、税務署などが、納税者(法人・個人)が行った申告内容が税法に照らして正しいかどうかを確認するために実施する調査活動のことです。日本の税制は自己申告が原則(申告納税制度)であるため、その内容の適正性を担保するために行われます。
- 誰が対象?
法人、個人事業主、相続税を申告した人など、申告納税を行っている全ての人が対象となる可能性があります。統計的には、毎年調査を受ける確率は法人で約3%、個人で約1%程度と低いですが、業種や申告内容、過去の状況などによっては選定されやすくなる傾向があります(例:売上の急変動、長期間調査がない、現金商売など)。
- 調査の種類
- 任意調査
一般的な税務調査で、事前に調査日時等の通知があります。納税者には調査に協力する義務(受忍義務)があり、正当な理由なく拒否はできませんが、日程調整の交渉は可能です。
- 強制調査(査察調査)
「マルサ」と呼ばれる国税局査察部が悪質・大口の脱税事件に対して行う調査。裁判所の令状に基づき、予告なく強制的に行われます。
- 調査期間
通常、直近3年分の申告内容が対象となりますが、申告漏れの内容によっては5年、意図的な不正(脱税)が疑われる場合は最大7年まで遡って調査されることがあります。
- 調査の流れ(任意調査の場合)
- 事前通知
税務署から納税者本人または顧問税理士へ、電話で調査日時・場所・対象税目・対象期間などが通知されます。
- 調査当日
調査官(通常1~2名)が事務所や店舗などを訪問。まず事業概要などをヒアリングし、その後、総勘定元帳、請求書、領収書、契約書、預金通帳などの帳簿書類を確認します。疑問点があれば質問されます。
- 結果の通知
調査の結果、問題がなければ「申告是認」の通知があります。もし申告内容に誤りが見つかれば、税務署から修正申告を行うよう勧められ(修正申告勧奨)、納税者が応じれば修正申告書を提出して追加納税します。指摘に納得できない場合は、税務署が職権で税額を決定・変更する「更正・決定」という処分が行われることもあります。
- ペナルティ
申告漏れ等が指摘されれば、追加の本税に加え、過少申告加算税や延滞税が課されます。意図的な隠蔽・仮装と判断されれば、最も重い重加算税(35%または40%)が適用されます。
- 税理士の役割
税理士は、事前準備のアドバイス、調査当日の立会い、調査官との専門的な質疑応答、納税者の権利保護、調査後の対応(修正申告など)まで、一貫して納税者をサポートします。税務調査の連絡があったら、すぐに税理士に相談することが重要です。
税務調査は不安に感じるかもしれませんが、日頃から正確な経理処理を行い、帳簿書類を整理・保存しておくことが最善の対策です。そして、専門家である税理士を味方につけることで、安心して対応することができます。
消費税とインボイス制度の基礎:事業者必見のポイント
消費税の基本
消費税は、商品やサービスの販売・提供といった「消費」に対して課される税金です。事業者は、売上時に顧客から消費税を預かり、仕入れや経費の支払時に自身が支払った消費税を差し引いた差額(これを仕入税額控除といいます)を国に納めます。税率は標準10%と軽減税率8%(飲食料品[酒類・外食除く]、定期購読の新聞)の複数税率です。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
2023年10月1日からスタートした新しい消費税のルールです。この制度の導入により、仕入税額控除を受けるための要件が大きく変わりました。
- インボイス(適格請求書)とは?
売手(事業者)が買手(事業者)に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための請求書や領収書のこと。「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」などの記載が必要です。
- 誰が発行できる?
税務署に申請して登録を受けた「適格請求書発行事業者」だけがインボイスを発行できます。
- 誰が登録できる?
誰でも登録可能です。ただし、登録することによって、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者であっても、自動的に消費税の課税事業者となります。
- 仕入税額控除への影響
買手(課税事業者)が仕入税額控除を受けるためには、原則として、取引相手から交付されたインボイスを保存することが必要になりました。つまり、免税事業者からの仕入れについては、原則として仕入税額控除ができなくなった(=買手の納税負担が増える)ということです。
- 免税事業者はどうする?
取引先(買手)が課税事業者で仕入税額控除を重視する場合、免税事業者のままでは取引を継続してもらえなかったり、消費税分の値引きを要求されたりする可能性があります。そのため、取引を維持するために、あえて課税事業者となってインボイス登録をするという選択をする免税事業者もいます。もちろん、取引先が一般消費者や他の免税事業者、簡易課税制度選択者などであれば、影響は比較的小さいです。
- 経過措置・負担軽減策
- 仕入税額控除の経過措置
免税事業者からの仕入れでも、2026年9月までは80%、2029年9月までは50%の仕入税額控除が可能です。
- 2割特例
インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった場合、2026年9月までの期間限定で、納税額を売上税額の2割に軽減できます。
- 少額特例
基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者等は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスがなくても帳簿保存のみで仕入税額控除が可能です(2029年9月まで)。
インボイス制度は、すべての事業者に関係する重要な制度変更です。自社がインボイスを発行する必要があるのか、取引先からインボイスをもらう必要があるのか、免税事業者との取引はどうするのかなど、税理士に相談しながら適切な対応を確認することが重要です。
補助金・助成金の基礎知識:返済不要の資金を活用
補助金・助成金は、国や地方自治体などが、事業者の設備投資、IT導入、販路開拓、雇用、研究開発といった様々な取り組みを支援するために支給する、原則として返済が不要な資金です。事業の成長や経営改善のための大きなチャンスとなり得ます。
- 補助金と助成金の違い(主な傾向)
- 補助金
経済産業省などが管轄することが多く、新しい事業や設備投資など、国の政策目標に沿った取り組みを支援。公募期間が限られ、申請内容を審査して採択・不採択が決まる(競争がある)。比較的高額なものも多い。
- 助成金
厚生労働省が管轄することが多く、雇用の維持・促進、人材育成、職場環境改善など「ヒト」に関する取り組みを支援。財源は雇用保険料の場合が多い。定められた要件を満たせば原則支給される。通年募集のものも多い。
- 共通のポイント
- 後払い
事業を実施し、経費を支払った後に、報告・検査を経てから支給されるのが基本。そのため、一時的に自己資金や融資で立て替える必要がある。
- 一部補助
かかった経費の全額ではなく、一部(例: 1/2、2/3など)が補助される。補助率や上限額が決まっている。
- 目的・経費の限定
申請した計画以外の目的には使えず、対象となる経費も細かく定められている。
- 申請プロセス(概要)
- 自社に合う制度を探し、公募要領を熟読する。
- 事業計画書を作成し、必要書類を揃える。
- 申請期間内に提出する。
- 審査を受ける(補助金は採択・不採択あり)。
- 採択後、交付申請・決定を経て事業を開始する。
- 事業完了後、実績報告書と証拠書類を提出する。
- 検査を受け、補助・助成金額が確定したら請求し、受給する。
- 受給後も報告義務がある場合も。
- 税理士の役割
補助金・助成金の申請には、事業計画(特に財務面)の策定や、採択後の経理処理、税務上の取り扱いなど、税理士がサポートできる部分が多くあります。資金調達の一環として、税理士に相談してみるのも良いでしょう。ただし、申請手続きの代行自体は、制度によって行政書士や社会保険労務士(特に助成金)が専門となる場合もあります。
補助金・助成金は種類が多く、手続きも複雑なため、情報収集と計画的な準備が成功の鍵です。公的なポータルサイト(J-Net21、ミラサポplusなど)や、商工会議所、専門家などを活用しましょう。
のどか会計事務所の詳細紹介:安心と納得のサービス
ここからは、この記事でご紹介している「のどか会計事務所」について、もう少し詳しく見ていきましょう。
(※顧問契約は原則として介護・障がい福祉事業者様限定となります)
事務所概要と代表者プロフィール
- 事務所名
のどか会計事務所(公認会計士・税理士・行政書士事務所)
- 所在地
〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13-20
- 代表者
小野 好聡
- 代表者保有資格
公認会計士、税理士、行政書士、宅地建物取引士、介護事務管理士
- サービス提供地域
ICT活用により全国対応
- 特徴
介護・障がい福祉分野に特化。創業期の支援にも力を入れています。
代表である小野好聡は、監査法人での上場企業監査から中小企業の会計・税務実務まで、10年以上にわたる多様な現場経験を持ち、机上の空論ではない、実務に根差したアドバイスが期待できます。データ分析や業務効率化も得意としており、現代的なアプローチで経営をサポートします。
提供サービスと料金体系:驚きのコスパを実現
のどか会計事務所の主力サービスは「サブスク税務顧問サービス」です。
(※原則として介護・障がい福祉事業者様限定)
- 内容
税務相談、記帳代行、月次試算表作成、各種税務届出、決算・申告(法人税・消費税・地方税等)など、基本的な税務・会計業務を月額定額で提供。
- 驚きの料金設定(税抜)
- 【創業1期目 特別価格】年間 110,000円~
- 月額換算 約9,167円~
- 追加の決算料0円!記帳代行料も0円!
- 【年商1,500万円未満】月額 18,000円~
- 【年商3,500万円未満】月額 28,000円~
- (※上記は営利法人・消費税免税事業者の場合。詳細はお問い合わせください)
- (※会計ソフトはマネーフォワードクラウド専門。別途ご契約が必要です)
一般的な税理士事務所では年間40万円程度~が相場と言われる中、決算料・記帳代行料込みでこの価格設定は、特に創業期やコストを抑えたい事業者にとって大きな魅力です。
その他のサービス
- 開業支援
会社設立(マネーフォワードクラウド会社設立利用推奨)、指定申請代行(介護・福祉等、個別見積)、創業融資支援(成功報酬制、顧問契約で半額)など。
- スポット(単発)依頼
顧問契約がない方向けに、キャッシュフロー計算書作成、就労支援事業会計対応、融資支援、補助金申請支援、運営指導対策書類点検(介護・福祉等)、その他個別コンサルティングなども対応可能です。
介護・障がい福祉分野への深い知見
のどか会計事務所は、介護・障がい福祉事業に特化した専門性を持っています。複雑な介護保険制度や障害者総合支援法に関連する会計処理(「会計の区分」、「就労支援事業会計」など)、処遇改善加算の管理、運営指導対策など、業界特有の課題に精通しています。
介護・福祉分野の事業者であれば、業界特有の悩みを理解し、的確なアドバイスを提供できる専門家として、これ以上ないパートナーとなるでしょう。
まずは無料相談から!
「自分の場合はいくらになるんだろう?」
「どんなサポートが受けられるか具体的に聞きたい」
そう思われた介護・障がい福祉事業者様は、ぜひ無料相談をご活用ください。
契約を無理強いすることは一切ありません。まずは気軽に、あなたの悩みや疑問をぶつけてみてください。
まとめ:大阪での税理士選び、後悔しないために
大阪で事業を運営していく上で、信頼できる税理士の存在は不可欠です。税務申告の代行だけでなく、節税対策、経営アドバイス、資金調達支援など、その役割は多岐にわたります。
この記事では、税理士の基本的な役割や他の専門家との違い、大阪で税理士を選ぶ際の重要なポイント、そして確定申告や税務調査といった基礎知識について解説してきました。
税理士選びで失敗しないためのチェックポイント
- 年間総額費用はいくらか?(決算料・記帳代行料は込みか?)
- 自社の業種や課題への理解度はどうか?(介護・福祉なら専門知識は必須)
- コミュニケーションは円滑か?相性は良さそうか?
- クラウド会計やオンライン対応など、ICT活用度はどうか?
- 創業期であれば、特別なサポートや料金プランはあるか?
これらの点を踏まえ、複数の事務所を比較検討し、ご自身に最適な税理士を見つけることが重要です。
そして、もしあなたが大阪で介護・障がい福祉事業を創業された方、あるいはコストパフォーマンスを重視して税理士を探しているなら、決算料・記帳代行料込みで年間11万円からという、圧倒的なコストパフォーマンスを誇る「のどか会計事務所」は、ぜひ検討していただきたい選択肢です。
(※顧問契約は原則として介護・障がい福祉事業者様限定となります)
全国対応のオンラインサービスと、資格を持つ税理士による直接対応で、価格以上の価値を提供しています。まずは無料相談で、その価値を体験してみてはいかがでしょうか。
この記事が、大阪で活躍されるあなたの税理士選び、そして事業の成功の一助となれば幸いです。
コラム:大阪府の税務署
私たちの生活や事業活動に深く関わる税金。その申告や納税、さまざまな疑問に対応する国の機関が「税務署」です。日本有数の経済規模を誇る大阪府内には、府民や企業の税務をサポートするため多くの税務署が設置されています。今回は、大阪府内の税務署の主な役割と利用方法についてご紹介します。
税務署の主な役割と大阪府内の設置状況
税務署の最も重要な役割は、所得税、法人税、消費税といった国税を適切に賦課(税額を決定)し、徴収することです。これに伴い、確定申告書の受付や審査、税に関する一般的な相談への対応、納税証明書の発行など、幅広い業務を行っています。大阪府内には、大阪市内だけでも複数の税務署が区ごとに設置されているほか、堺市、東大阪市、豊中市、吹田市など、主要な都市や地域にも税務署があり、それぞれが担当するエリア(管轄区域)が決まっています。
確定申告・税相談での利用と注意点
確定申告の時期は税務署が最も混雑しますが、年間を通じて税金に関する手続きや相談が可能です。「住宅ローン控除について知りたい」「個人事業の経理について」など、困ったときには身近な相談窓口となります。最近では、国税庁のウェブサイトにある「タックスアンサー」で調べる方法や、e-Taxを利用した電子申告・納税も便利です。税務署で相談や手続きを行う際は、ご自身の住所地や事業所の所在地を管轄する税務署を確認することが重要です。管轄違いの場合、対応してもらえない業務もあるため注意しましょう。
コラム:大阪府税事務所とは
自動車税種別割や不動産取得税など、私たちの生活や事業に身近な「府税」(都道府県税)。これらの大阪府が課税する税金に関する手続きや相談の窓口となるのが「大阪府税事務所」です。国の税金(国税)を扱う税務署とは異なる役割を持っています。今回は、大阪府税事務所の主な業務内容や利用についてご紹介します。
府税事務所の主な役割と大阪府内の体制
大阪府税事務所の主な役割は、大阪府が条例で定める地方税、いわゆる「府税」の賦課(税額の決定)と徴収です。具体的には、個人事業税、法人府民税・法人事業税、不動産取得税、自動車税(種別割・環境性能割)、軽油引取税などが対象となります。これらの府税に関する納税証明書の発行や、納税に関する相談も受け付けています。大阪府内には、担当エリアごとに複数の府税事務所(例:なにわ北府税事務所、なにわ南府税事務所、三島府税事務所、泉北府税事務所など)が設置されており、それぞれの管轄区域が決まっています。
府税に関する手続きや相談での利用
府税事務所は、自動車の購入・登録時に関わる税金の手続きや、土地・家屋などを取得した際の不動産取得税の申告、個人事業主の方の事業税申告などで利用する機会があります。また、「納税通知書の内容について聞きたい」「納税が難しい場合の相談をしたい」といった、府税に関する様々な疑問や相談に対応しています。近年では、一部の手続きについてオンライン申請や電子納税も可能になっています。府税事務所を利用する際は、ご自身の住所地や事業所の所在地、手続きの内容によって管轄が異なるため、事前に確認することが重要です。


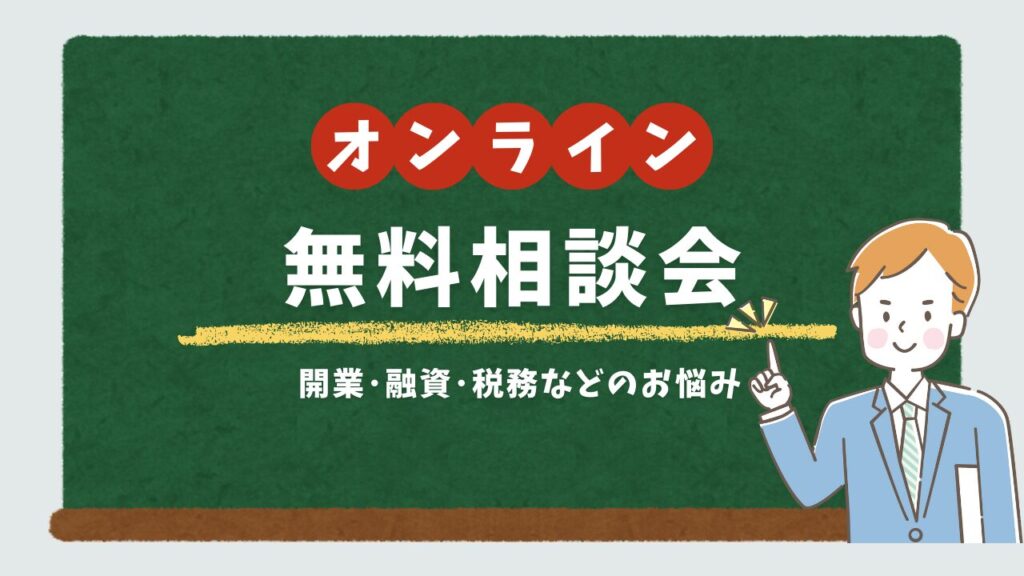
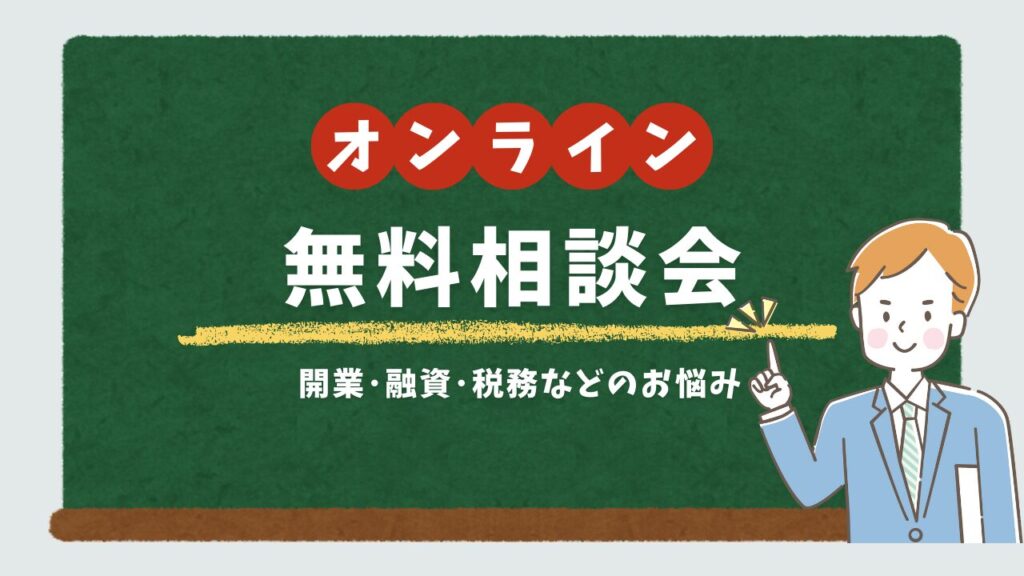
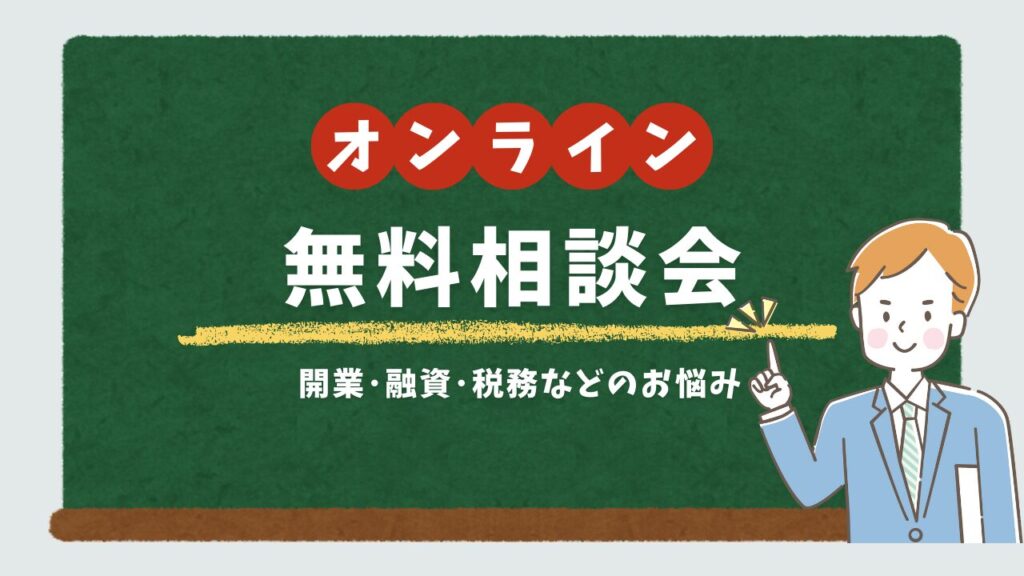


















![【開業前必見】地域別訪問看護ステーション数人口比調査[2024年8月版]のアイキャッチ画像](https://nodokaya.jp/nodoka_kaikei/wp-content/uploads/2024/09/【開業前必見】-地域別訪問看護ステーション数-人口比調査-1024x576.png)
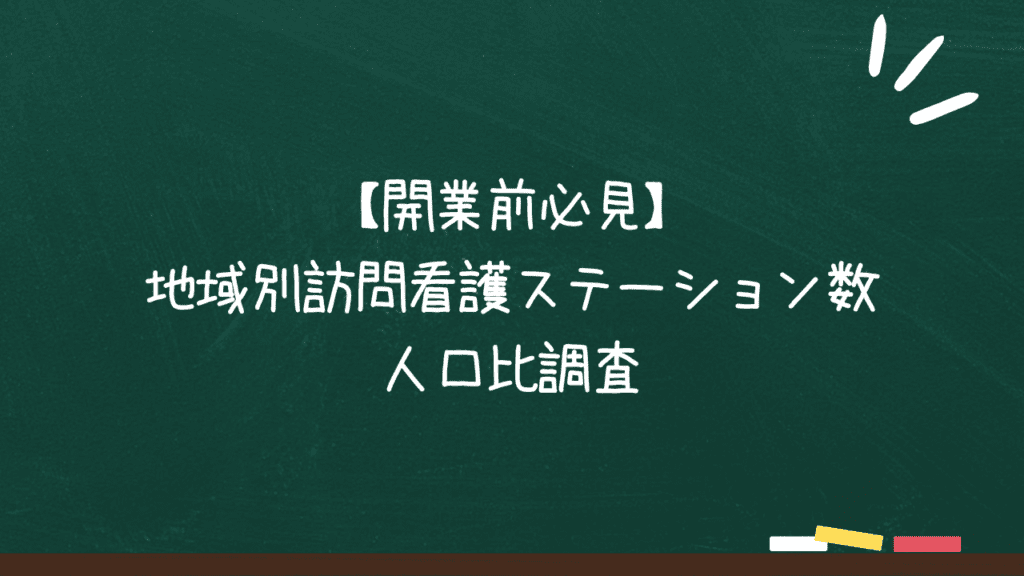
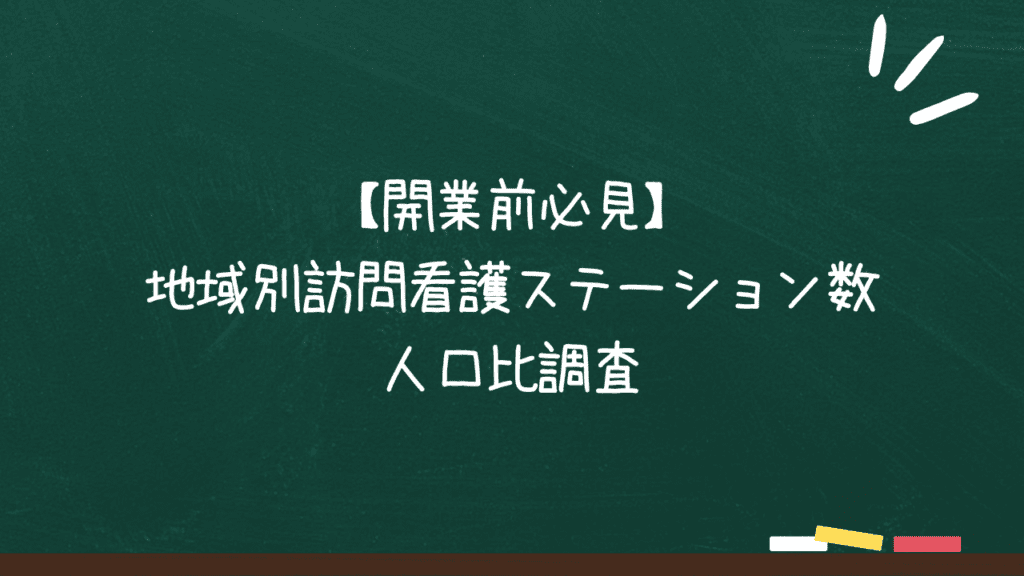
























とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)