Q&Aで解説!訪問看護ステーションの開業/立ち上げガイド 指定基準・費用・資金調達(融資・補助金)・人材確保・経営戦略
PR
ℹ️【介護・障害福祉】✕【合同会社】限定の開業支援特別価格!
手数料3万5千円で会社設立!
\のどか屋のスポットサービス/

\今すぐチェック!/
目次

訪問看護ステーションの開業・立ち上げという、地域医療への貢献に繋がる大きな一歩。しかし、その道のりは決して平坦ではありません。「指定基準の複雑さ」「多額の開業資金と運転資金の確保」「深刻な人材不足と定着の難しさ」「激化する競争環境での経営戦略」…など、クリアすべき課題は山積みです。
「具体的に何から始めれば?」「失敗しないためのポイントは?」「頼れる相談先は?」
そんな疑問や不安を抱えるあなたのために、この記事では訪問看護ステーションの開業・立ち上げに関するあらゆる情報をQ&A形式で徹底解説します。法人設立から指定申請の注意点、必要な費用と賢い資金調達(融資・補助金)、人材確保・定着の具体的な施策、業務効率化と質向上を実現するICT活用法、そして成功に不可欠な経営戦略と差別化のポイントまで、専門的な知見に基づき網羅的にまとめました。この記事を読めば、開業プロセス全体像と各ステップで押さえるべき要点が明確になり、自信を持って次の一歩を踏み出せるはずです。
【開業準備と指定申請】

訪問看護ステーションの開業/立ち上げガイド
開業準備と指定申請
訪問看護ステーションを開業するには、まず何をすれば良いですか? 全体的な流れは?
まず、訪問看護ステーションを開業するためには、法人を設立し、事業計画を策定する必要があります。その後、開業に必要な資金調達(自己資金、融資、補助金など)を行い、事務所の確保、人員(管理者、看護職員など)の採用、必要な設備や備品(事務用品、医療機器、車両など)の準備を進めます。最後に、事業所所在地の都道府県(または政令指定都市・中核市)へ介護保険サービスの指定申請を行い、認可を受けることで開業できます。多くの場合、介護保険の指定を受けると医療保険の指定も受けたものとみなされる「みなし指定」となりますが、医療保険独自の指定申請が必要な場合もあるため、地方厚生(支)局への確認も必要です。
開業に必要な「指定基準」とは何ですか?
指定基準には大きく「人員基準」「設備基準」「運営基準」があります。これらは厚生労働省令などで定められています。
- 人員基準: 看護職員(保健師、看護師、准看護師。助産師も含む場合あり)を常勤換算で2.5人以上(うち1名は常勤)配置する必要があります。また、管理者は原則として常勤の保健師または看護師(助産師も含む場合あり)である必要があります。
- 設備基準: 事業運営に必要な広さの専用事務室(または明確に区画された共有スペース)、プライバシーに配慮した相談室、感染予防のための独立した手洗い設備、個人情報や記録を保管するための鍵付き書庫が必要です。事務所は他の事業と明確に区画されている必要があります。
- 運営基準: 事業目的、運営方針、職員体制、営業時間、サービス内容・料金、通常の事業実施地域、緊急時対応、虐待防止措置、苦情処理体制、業務継続計画(BCP)などを定めた「運営規程」を作成・整備する必要があります。記録の整備や衛生管理も求められます。
指定申請の手続きで、特に注意すべき点やスムーズに進めるコツはありますか?
指定申請は、単なる手続きではなく事業開始準備の総点検であり、慎重な準備が必要です。
- 注意点: よくある不備として、人員・設備基準の解釈違い、書類間の記載内容不整合、書類の有効期限切れ、署名・押印漏れなどが挙げられます。
- 準備と確認: 開設予定から逆算し、余裕をもって準備を開始します。必ず事業所所在地の自治体の最新の申請手引きを確認してください。申請期限は自治体により異なり、例えば一般的に「指定希望月の前々月末」などとされていますが、具体的な日付は必ず確認が必要です。
- 事前相談: 不明点、特に設備(事務所の区画分け等)や人員(管理者の兼務等)の基準解釈に迷う場合は、必ず事前に管轄の行政窓口に相談しましょう。
- 申請時点での体制: 申請書類提出時点で、事務所の内装、必要な備品(机、椅子、鍵付き書庫、洗面設備等)の設置、人員(管理者、基準を満たす看護職員等)の確保と雇用契約の締結を完了させておく必要があります。その状態を示す写真の提出や、場合によっては現地確認(実地調査)も求められます。これは指定前に相応の投資が必要となることを意味し、財務リスクとなります。
- 書類作成: 全ての申請書類・添付書類について、記載漏れ、誤記、不整合がないか、提出前に何度も確認します。運営規程や収支予算書は、雛形を参考にしつつも自社の実情に合わせて具体的に作成します。チェックリストを活用し、提出書類を網羅的に確認します。
- 専門家の活用: 不安な場合は社会保険労務士やコンサルタントに相談することも有効です。
- その他: 指定を受ける前に指定済みであるかのような広告や勧誘活動はできません。申請後の行政からの問い合わせには迅速に対応し、申請内容に変更が生じた場合は速やかに報告します。
【資金調達】

訪問看護ステーションの開業/立ち上げガイド
資金調達
訪問看護ステーションの開業には、どれくらいの費用がかかりますか?
開業にかかる費用は、事業所の規模、立地、選択する設備等によって大きく変動しますが、一般的な目安として初期費用が300万円〜600万円程度、さらに事業が軌道に乗るまでの運転資金(最低でも6ヶ月分)として500万円〜900万円程度、合計で800万円〜1,500万円程度が必要とされています。これはあくまで一般的な目安であり、個別の事業計画においては詳細な見積もりとシミュレーションが不可欠です。特に、介護・医療保険の報酬はサービス提供から入金まで通常2ヶ月以上かかるため、この間の人件費や家賃などの運転資金を十分に確保することが極めて重要です。キャッシュフロー管理の失敗は、たとえ収益性があっても事業失敗に繋がる可能性があります。
初期費用や運営費用の具体的な内訳を教えてください。
- 初期費用: 法人設立費用(約10万~30万円)、指定申請手数料(約3万円)、事務所の賃貸契約初期費用(敷金、礼金、仲介手数料、前家賃など数十万~百万円規模)、内装・改修費(必要に応じて)、事務用備品・IT機器(PC、複合機、電話、タブレット等で数十万~百数十万円)、電子カルテ導入費用(システムによる)、医療機器・物品(体温計、血圧計、訪問バッグ等 数十万円)、車両購入費またはリース初期費用、広告宣伝費(求人、パンフレット、ウェブサイト制作等 数十万円)、各種保険料(損害賠償責任保険等)などが含まれます。
- 運営費用(月額): 最も大きな割合を占める人件費(給与、賞与、社会保険料など。総支出の70~80%に達することも)、家賃(数万~十数万円)、水道光熱費(数万円)、通信費(数万円)、車両関連費(リース料/燃料費/駐車場代等 数万~十数万円)、消耗品費(医療・衛生材料、事務用品等 数万円)、ICT関連費(電子カルテ月額利用料等 数万円)、広告宣伝費、その他諸経費などが継続的に発生します。これらの費用も、個別の事業計画に基づき詳細に見積もる必要があります。
開業資金はどのように調達すれば良いですか?
自己資金だけで全てを賄うのは難しい場合が多いため、外部からの資金調達を組み合わせるのが一般的です。主な方法として、日本政策金融公庫(JFC)などの公的金融機関や民間金融機関からの融資、国や地方自治体が提供する補助金・助成金の活用が挙げられます。
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」について詳しく教えてください。
この制度は、新たに事業を始める方や事業開始後7年以内の方を対象とした融資制度です。
- 融資限度額: 7,200万円(うち運転資金4,800万円)。
- 利率: 原則「基準利率」(借入期間や担保有無で変動。概ね1%台後半~3%台前半が多い)ですが、女性や35歳未満、55歳以上の方、特定の創業支援を受けた方などは低い「特別利率」が適用される場合があります。
- 担保・保証人: 原則として無担保・無保証人となります。
- 自己資金要件: 以前は創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要でしたが、この要件は撤廃されました(2024年改定)。ただし、融資条件の変更であり、融資審査の条件が大きく変わった訳ではないので、最低でも必要資金の20~30%程度の自己資金を準備されることを推奨します。
- 返済期間: 設備資金は最長20年、運転資金は最長10年(それぞれ据置期間最長5年)。
- 申請プロセス: JFCへの相談後、申込書・事業計画書を提出し、面談・審査を経て融資が実行されます。通常、申込から融資実行まで約1ヶ月程度かかると言われています。
- ※訪問看護ステーションの場合、通常「新規開業・スタートアップ支援資金」とは別途設けられている「ソーシャルビジネス支援資金」が適用されます。融資条件は「新規開業・スタートアップ支援資金」と概ね同じです。なお、融資希望者が融資制度を選択するのではなく、融資希望者の状況に応じた融資制度が日本政策金融公庫によって選択・適用されます。
日本政策金融公庫の融資を受けるための事業計画書では、どのような点が重視されますか?
JFCの融資審査では、提出された事業計画書が非常に重要視されます。特に以下の点がポイントとなります。
- 事業の実現可能性: 提供するサービス内容、ターゲット顧客、市場・競合分析、自社の強み・弱みなどが具体的かつ現実的に書かれているか。差別化された明確な商品・サービス内容も重要です。
- 収支計画・資金計画: 売上予測、費用(初期費用・運転資金)の見積もり、資金調達計画、返済計画などが具体的で、根拠があり、無理のない計画になっているか。特に、報酬入金までのタイムラグを考慮した運転資金計画が重要です。
- 経営者の資質: 経営者の創業動機、これまでの経験(特に訪問看護やヘルスケア分野との関連性)、人脈なども重視されます。
- 計画の具体性: 「何を」「いつまでに」「どのように」行うのかが明確に示されているか。 単なる数字だけでなく、事業のストーリー、経営者の信頼性、計画の現実性が総合的に評価されます。
開業や運営に使える補助金・助成金にはどのようなものがありますか? 申請時の注意点は?
返済不要の補助金・助成金も積極的に活用しましょう。代表的なものとして以下があります。
- 国(厚生労働省): キャリアアップ助成金(非正規→正規転換等)、特定求職者雇用開発助成金(就職困難者雇用)、両立支援等助成金(育児・介護両立支援)、業務改善助成金(賃上げ+生産性向上投資)など。
- 国(経済産業省): IT導入補助金(電子カルテ、業務効率化ツール等)など。
- 都道府県・市町村: 自治体独自の創業支援制度(低利融資、家賃補助等)や、都道府県が実施する介護ICT導入補助金(介護ソフト、タブレット等)など。補助金情報は多岐にわたり複雑なため、中小企業庁の「ミラサポplus」や中小機構の「J-Net21」といったポータルサイトを活用して探すことも有効です。
申請時の注意点
- 要件確認: 各制度の細かい要件(対象者、対象経費、期間等)を公募要領で熟読し、完全に対象となるか確認。
- 申請期間: 公募期間が短い、予算上限で早期終了する場合あり。常に最新情報をチェックし早めに準備。
- 書類の正確性: 様式を守り、記載漏れや不備なく正確・丁寧に作成。
- 計画の具体性・整合性: 補助金を使った計画が具体的で、他の提出書類と整合性が取れていることが重要。
- 実績報告: 採択後は計画通りの実施報告と証拠書類の提出が必須(怠ると返還の場合も)。
- 重複受給: 同一経費について複数の補助金・助成金を重複して受給できない場合が多い。
【運営体制の構築】

訪問看護ステーションの開業/立ち上げガイド
運営体制の構築
事務所の立地選びや設備で気をつけることはありますか?
事務所の立地は家賃(運営費)に大きく影響します。都市部中心地は高額ですが、地方や郊外では抑えられます。訪問エリアへのアクセス、スタッフの通勤しやすさ、駐車場の確保なども、訪問効率や人材確保の観点から重要な考慮事項です。設備面では、指定基準を満たす広さ、相談室、手洗い場、鍵付き書庫は必須です。また、効率的な運営のため、PC、複合機、電話、スマートフォンやタブレットなどのIT機器、体温計、血圧計などの基本的な医療機器も必要です。
訪問用の車両は、購入とリースのどちらが良いですか?
購入とリースにはそれぞれメリット・デメリットがあり、ステーションの資金状況(特に初期のキャッシュフロー)、管理能力、長期的なコスト意識によって選択が異なります。
- 購入: 初期費用は大きいが総支払額は抑えられる可能性あり。資産となり走行距離制限なし。税金・保険・整備は自己負担・管理。
- リース: 初期費用を抑えられ月々の支払いが一定で経費管理しやすい。メンテナンスリースなら車検・整備費用も含まれ管理が楽。総支払額は高くなる傾向。契約期間や走行距離に制限がある場合が多い。 開業初期で資金を抑えたい場合や、車両管理の手間を省きたい場合はリースが有利な場合があります。長期的に見てコストを抑えたい、自由に車両を使いたい場合は購入も選択肢となります。必要な台数、利用頻度、駐車場代なども考慮して総合的に判断しましょう。車両コスト管理は経営上重要です。
管理者の兼務要件はどのように緩和されましたか?
令和6年度改定で、管理者の責務(従業員や業務の一元的な管理、法令遵守の担保など)が改めて明確化された上で、兼務可能な範囲について「同一敷地内」という地理的な制限が撤廃されました。管理業務に支障がないと判断されれば、離れた場所にある他の事業所の管理者や職務との兼務も可能となり、人材活用の柔軟性が高まりました。ただし、「管理業務に支障がないこと」「質の高いサービス提供」が条件であり、適切な管理体制の維持が引き続き求められる点に留意が必要です。
24時間連絡体制の要件緩和について教えてください。
利用者からの電話連絡について、従来は原則として看護師等が直接対応する必要がありましたが、看護師等に速やかに連絡できる体制等が確保されている場合は、看護師等以外の職員(事務員など)でも一次対応が可能になりました。これにより、特に夜間や休日の看護師の負担軽減が期待されます。ただし、緩和の適用には、詳細な要件(マニュアル整備、迅速な連絡体制、管理者による状況把握、記録、利用者同意、届出など)が付随すると考えられ、その遵守が不可欠です。
【人材確保・定着】

訪問看護ステーションの開業/立ち上げガイド
人材確保・定着
訪問看護師の採用や定着は難しいと聞きますが、現状はどうなっていますか?
訪問看護業界は慢性的な人材不足と、病院看護師よりも高い離職率が課題です。調査年や対象によって数値は変動しますが、複数の調査で訪問看護師の離職率は一貫して15%を超え、病院看護師(概ね11%前後)より高い傾向が示されています。特に経験3年未満や小規模な事業所ではさらに高い傾向も見られます。高齢化等で需要は増大しており、採用・定着はこの業界における経営上の最重要課題の一つです。
どうすれば良い人材を確保し、定着させられますか?
効果的な採用と定着のためには、多角的な取り組みが必要です。
- 採用戦略
- 多様なチャネル(求人サイト、SNS、リファラル採用、学校連携など)を活用。
- 求人情報では業務内容、給与、福利厚生、ステーションの理念や魅力、そして訪問看護への不安(一人での判断、オンコール等)に対するサポート体制を具体的に、透明性をもって伝える。
- 面談や見学を複数回行い、相互理解を深めミスマッチを防ぐ。
- 定着率向上の取り組み(離職理由を踏まえて)
- 教育・研修: 新人への丁寧なOJT、継続的な学習支援(内部研修、外部研修・資格取得補助など)。
- キャリアパス: 成長の道筋や専門性を評価する仕組みを示す。
- 働きがいのある環境: 良好なコミュニケーション、支援的なマネジメント、意見の尊重、公正な評価、安全・健康への配慮。
- 処遇改善: 地域の相場を踏まえた競争力のある給与体系。令和6年度新設の「訪問看護ベースアップ評価料」の活用も重要。充実した福利厚生。
- ワークライフバランス: ICT活用による業務効率化。柔軟な勤務形態(時短、週4日、直行直帰など)。休暇取得促進。オンコール体制の負担軽減策(当番回数制限、手当、代替要員など)も重要です。
給与だけでなく、「働きがい」「働きやすさ」「成長実感」といった多面的なアプローチが重要です。人件費比率の高さと離職率の高さを考慮すると、定着促進策は重要な経営戦略と言えます。
訪問看護未経験者を採用する場合、どのような教育体制が必要ですか?
未経験者は訪問看護特有の業務(一人での判断・対応、利用者宅でのマナー等)に不安を感じやすいため、丁寧な教育体制が不可欠です。
- 導入研修(座学): 訪問看護の基礎知識を学びます。
- 同行訪問(OJT): 経験豊富な先輩看護師に同行し、実際のケアを見学・実践。十分な期間を設け、個人の習熟度に合わせて段階的に独り立ちできるようサポートします。
- メンター制度: 先輩看護師が教育担当となり、技術指導だけでなく、精神的なサポートや相談役を担います。
- 定期的な面談・フィードバック: 管理者やメンターが定期的に面談を行い、不安や疑問を解消し、成長を評価・フィードバックします。
- マニュアル整備: 業務手順や緊急時対応などをまとめたマニュアルを整備し、いつでも確認できるようにします。
- 研修機会の提供: スキルアップのための内部勉強会や事例検討会、外部研修への参加を支援します。 未経験者が安心して業務に慣れ、自信を持って働けるような、焦らず段階的に学べる環境を作ることが定着の鍵となります。
【ICT活用】

訪問看護ステーションの開業/立ち上げガイド
ICT活用
訪問看護でICT(情報通信技術)を活用するメリットは何ですか?
ICT活用は、業務効率化、情報共有円滑化、ケアの質向上、スタッフ負担軽減に不可欠です。特に、記録・請求業務の時間短縮、スタッフ間・多職種間のスムーズな情報連携(リアルタイム共有)、移動効率の改善、利用者状態の遠隔把握、データに基づいた運営改善などに大きなメリットがあります。人材定着(残業削減、負担軽減)や経営改善にも繋がります。医療DXは国の推進方針でもあります。
訪問看護では、具体的にどのようなICTツールが活用されていますか?
様々なツールが活用されています。
- 電子カルテ(EHR): 訪問看護記録、情報共有、請求(レセプト)連携などの基盤システム。クラウド型とオンプレミス型があります。
- 遠隔モニタリングツール: バイタルサイン(血圧、脈拍、SpO2等)や活動量を利用者宅から遠隔で把握するセンサーやデバイス。状態変化の早期発見や医師との連携に活用。
- オンライン診療・服薬指導連携ツール: ビデオ通話システム等を用いて、訪問看護師が医師のオンライン診療や薬剤師のオンライン服薬指導をサポート。
- スケジュール・訪問ルート最適化ツール: AI等が利用者情報、スタッフスキル、移動手段等を考慮し、最適な訪問計画・ルートを自動作成・調整。管理業務削減、移動時間短縮、訪問件数増を実現。
- コミュニケーション・情報共有ツール: EHR内のチャット機能や、医療介護専用の多職種連携システム、ビジネスチャットツール(セキュリティ配慮要)などで、迅速・確実な連絡・情報共有を促進。
電子カルテの「クラウド型」と「オンプレミス型」の違いと選び方のポイントは?
電子カルテには主に2つのタイプがあります。
- クラウド型: インターネット経由でサービスを利用。
- メリット: 初期費用が比較的安い(無料~数十万円)、サーバー管理不要、場所を選ばずアクセス可能、アップデート自動。
- デメリット: 月額利用料が継続的に発生、ネット環境必須、カスタマイズ性低い場合あり。訪問看護では導入しやすいとされます。
- オンプレミス型: 自社内にサーバーを設置。
- メリット: カスタマイズ性が高い、院内LANで利用可(機能による)、長期的なランニングコストは抑えられる可能性。
- デメリット: 初期費用が高額(数百万円~)、サーバー管理・保守が必要、アップデート手動または別途費用、災害時データ保護対策が自社で必要。
- 選び方のポイント: ステーションの規模、予算、IT管理体制(専任者有無)、必要な機能、他システム連携、セキュリティポリシー、外部アクセス頻度などを考慮します。機能、費用、操作性、サポート体制、そしてIT導入補助金等の対象となるかを比較検討しましょう。
【経営戦略と差別化】

訪問看護ステーションの開業/立ち上げガイド
経営戦略と差別化
訪問看護ステーションの経営を成功させるためのポイントは何ですか?
ステーション数の増加による競争激化の中、成功には戦略的な視点が不可欠です。ポイントは以下の通りです。
- 明確な戦略と差別化: 他社との違いを打ち出す。SWOT分析などを活用。
- 質の高いサービス提供: 専門性を高め、利用者や紹介元から信頼されるケアを提供する。運営基準でも質の評価・改善が求められます。
- 適切な経営管理: 的確な事業・資金計画(特に運転資金確保[Q4参照])と、データに基づいた判断。
- 強力な地域連携: 地域の医師、病院、ケアマネジャー、介護事業者などとの良好な関係を構築・維持し、紹介獲得やスムーズな連携体制を築く。
- 人材マネジメントの成功: 優秀なスタッフを採用し、働きがいのある環境で定着を図る。
- 変化への柔軟な適応: 報酬改定などの制度変更や地域のニーズの変化に柔軟に対応する。 これらの要素は相互に関連しており、総合的な取り組みが求められます。
他の訪問看護ステーションと差別化するには、どのような方法がありますか?
差別化は持続的成長に不可欠です。他社と明確に異なる「特長」を持つことが重要です。以下のような戦略が考えられます。
- 専門特化(特定の分野に特化し専門性を高める)
- 緩和ケア特化: 終末期がん患者等への高度なケア。
- 精神科特化: 精神疾患を持つ利用者に特化。独自の報酬体系があり、戦略的な意味合いを持つ可能性も。
- 小児特化: 医療的ケア児や発達障害児等への専門的ケアと家族支援。
- 難病特化: ALSやパーキンソン病など特定の難病に特化。
- 独自の運営モデル
- 多職種連携強化: ICT活用や物理的な連携拠点構築でチームケアの質を高める。
- 先進的なICT活用: 電子カルテに加え、AIスケジュール最適化ツールや遠隔モニタリングなどを導入し、効率と質を向上。
- 地域活動との連携・拠点化: 「暮らしの保健室」や認知症カフェ運営、地域の看護人材育成拠点(「教育ステーション」)となるなど、地域貢献を通じて信頼と支持を得る。
- 大規模化・広域展開: 事業所統合やサテライト設置で提供エリアを拡大し、経営基盤を強化する。規模が大きいことで「機能強化型訪問看護ステーション」として評価され、報酬面・機能面で有利になる可能性も。
【支援サービス】

訪問看護ステーションの開業/立ち上げガイド
支援サービス
訪問看護ステーションの開業や運営について、どこに相談できますか?
専門的な知識が必要なため、様々な支援機関を活用すると良いでしょう。課題に応じて適切な相談先を選択し、組み合わせて活用することが有効です。
- 公的機関
- 厚生労働省: 制度情報、報酬改定情報、ガイドライン等。
- 都道府県・指定都市等: 指定申請の窓口、基準に関する相談、地域独自の補助金情報など。
- よろず支援拠点: 国が設置した無料の経営相談所。
- 日本政策金融公庫(JFC): 創業融資の相談・提供。
- 独立行政法人 福祉医療機構(WAM): 医療・福祉施設向け融資、経営情報提供。
- ハローワーク: 求人、人材紹介、雇用関連助成金の申請窓口。
- 業界団体
- 公益財団法人 日本訪問看護財団: 開設・運営相談窓口、研修・セミナー開催、情報提供、書籍・マニュアル発行など。
- 一般社団法人 全国訪問看護事業協会: 会員向け実務相談、政策提言、情報提供、研修会開催、書籍・報告書発行など。
- 公益社団法人 日本看護協会: 看護全般に関する政策提言、調査研究・情報提供、研修など。
- 民間サービス
- 司法書士: 法人設立登記に関する専門的サポート。
- 社労士: 指定申請書類作成・提出代行。労務管理に関する専門的サポート。
- 税理士: 税務、会計に関する専門的サポート。
- ICTベンダー・システム会社: 電子カルテ等のシステム導入支援、IT導入補助金申請サポートなど。
これらの機関は、情報提供、研修、融資相談、申請支援、経営アドバイスなど、様々な形でサポートを提供しています。
お問い合わせ
ご契約までの流れ
STEP
オンライン面談のご予約
契約に関するご相談は無料です。こちらからご予約ください。
面談方法は、Zoomによるオンライン面談となります。
はじめての方でも簡単にご利用いただけますのでご安心ください。
まずは以下のボタンからお申し込みください。
STEP
事前ヒアリングシートの入力
ご記入いただいたメールアドレス宛に事前ヒアリングシートのURLをお送りいたします。
面談に先立って事前ヒアリングシートへのご記入をお願いいたします。
STEP
オンライン面談&お見積り
ご記入いただいた事前ヒアリングシートに基づいて、面談時にヒアリングを実施致します。
ヒアリング内容に基づいて、お見積りをいたします。
STEP
ご契約
お見積り内容に合意いただけた場合は、ご契約の手続を進めさせていただきます。
その他のお問い合わせ
その他のお問い合わせはこちらから
SHARE!




















![【開業前必見】地域別訪問看護ステーション数人口比調査[2024年8月版]のアイキャッチ画像](https://nodokaya.jp/nodoka_kaikei/wp-content/uploads/2024/09/【開業前必見】-地域別訪問看護ステーション数-人口比調査-1024x576.png)
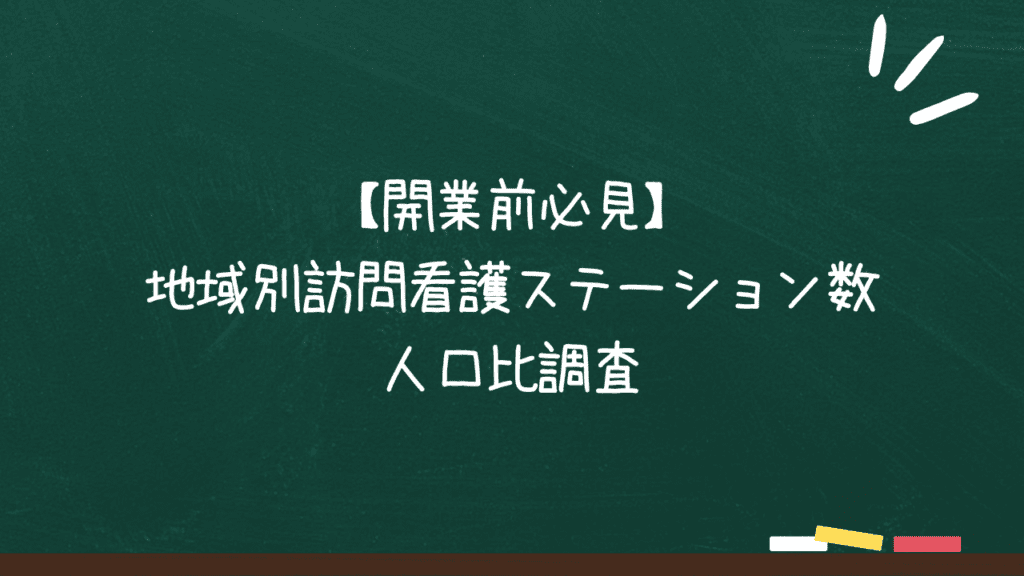
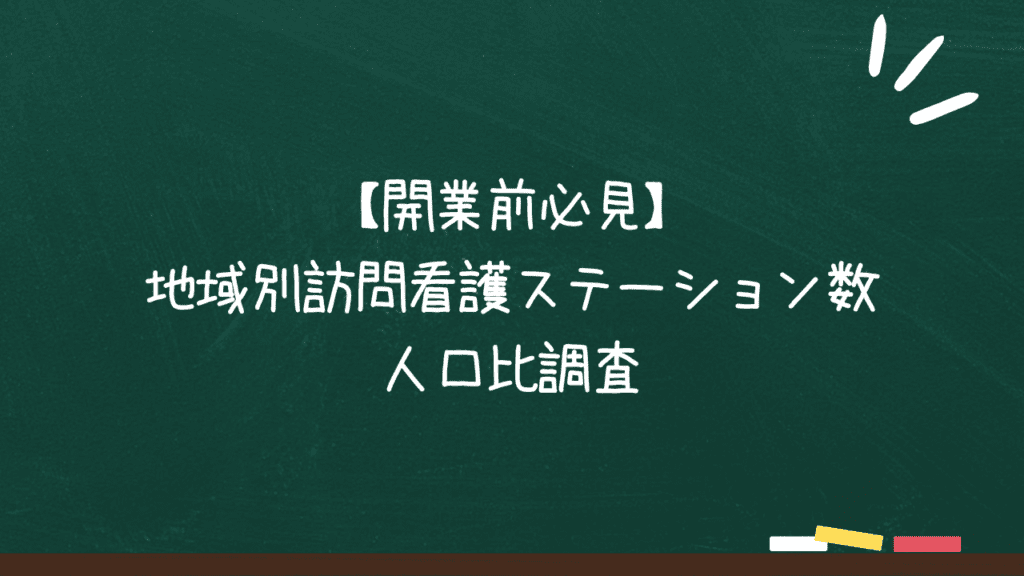
























とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)






・人材確保・経営戦略-1024x576.png)
・人材確保・経営戦略-1024x576.png)
・人材確保・経営戦略_開業準備と指定申請-1024x576.jpg)
・人材確保・経営戦略_開業準備と指定申請-1024x576.jpg)
・人材確保・経営戦略_資金調達-1024x576.jpg)
・人材確保・経営戦略_資金調達-1024x576.jpg)
・人材確保・経営戦略_運営体制の構築-1024x576.jpg)
・人材確保・経営戦略_運営体制の構築-1024x576.jpg)
・人材確保・経営戦略_人材確保・定着-1024x576.jpg)
・人材確保・経営戦略_人材確保・定着-1024x576.jpg)
・人材確保・経営戦略_ICT活用-1024x576.jpg)
・人材確保・経営戦略_ICT活用-1024x576.jpg)
・人材確保・経営戦略_経営戦略と差別化-1024x576.jpg)
・人材確保・経営戦略_経営戦略と差別化-1024x576.jpg)
・人材確保・経営戦略_支援サービス-1024x576.jpg)
・人材確保・経営戦略_支援サービス-1024x576.jpg)

