
のどか会計事務所
- 公認会計士・税理士・行政書士事務所
- サービス提供地域:全国
- 営業時間:火~金 10:00~16:00
- 代表者:小野 好聡
- 〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13−20 - インボイス登録番号:T7810142329217

のどか会計事務所


















![【開業前必見】地域別訪問看護ステーション数人口比調査[2024年8月版]のアイキャッチ画像](https://nodokaya.jp/nodoka_kaikei/wp-content/uploads/2024/09/【開業前必見】-地域別訪問看護ステーション数-人口比調査-1024x576.png)
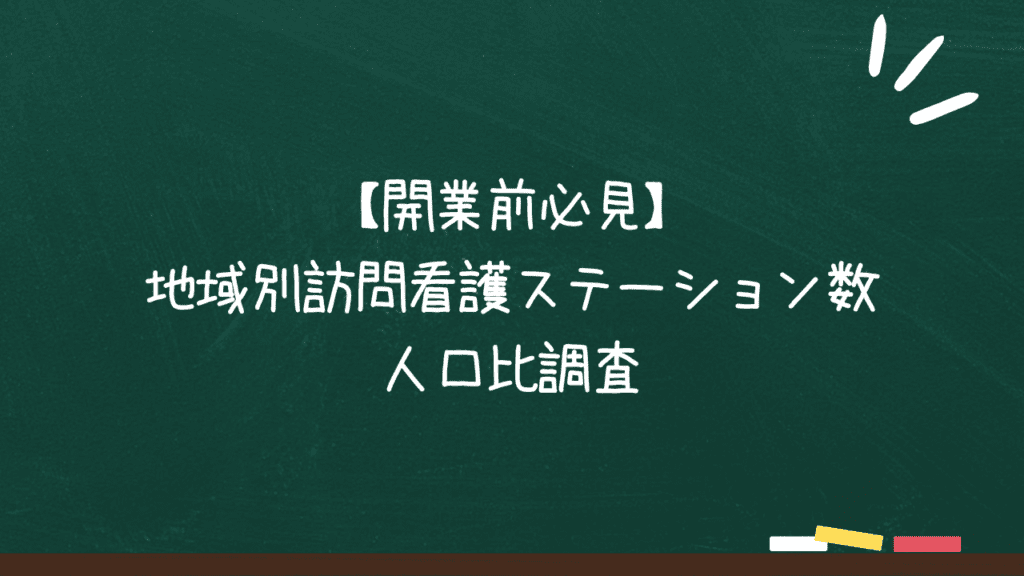
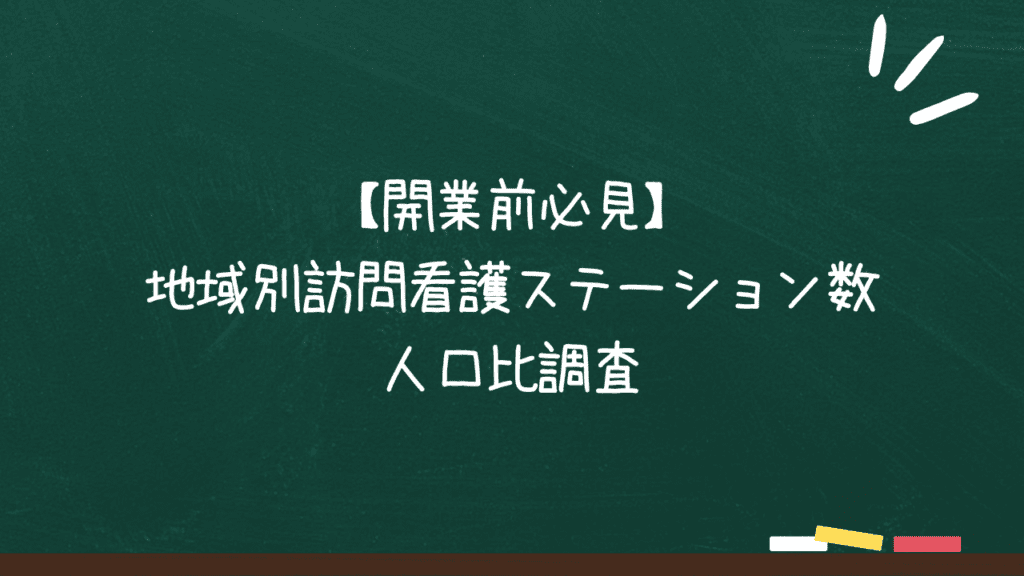
























とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)








「放課後等デイサービスってどんなサービス?」「うちの子は利用できるの?」「手続きや料金はどうなっているの?」
放課後等デイサービスの利用を検討されている保護者の方や、制度について詳しく知りたいと考えている関係者の皆様へ。
この記事では、放課後等デイサービスに関する様々な疑問に、Q&A形式で分かりやすくお答えします。サービスの基本的な定義や目的、利用対象となるお子さんの条件、具体的な申請手続きや費用負担、そして「5領域」に基づいた支援内容まで、全30問のQ&Aで網羅的に解説。
学童保育との違いや、2024年度に行われた最新の制度改正(報酬改定やガイドライン改訂)の内容もしっかり反映していますので、「今」知りたい情報がここにあります。
この記事を読むことで、放課後等デイサービスへの理解が深まり、お子さんにとって最適なサービス選択や利用に向けた準備を進めるための一助となれば幸いです。


放課後等デイサービスとは?
基本情報
放課後等デイサービスは、小学校、中学校、高等学校(特別支援学校を含む)に通う、障害のあるまたは発達に特性のあるお子さんを対象とした、児童福祉法に基づく福祉サービスです。学校の授業終了後や夏休みなどの長期休暇中に、指定された事業所で、日常生活能力の向上や社会との交流を促進するための支援を提供する通所型のサービスです。
主な目的は、お子さんが日常生活や社会生活を円滑に送るためのスキル獲得を支援し、社会とのつながりを深めることです。具体的には、基本的な生活習慣の習得、コミュニケーション能力の育成、集団生活への適応などを支援します。学校や家庭とは異なる環境での多様な経験を通じて、一人ひとりの状況に応じた発達支援を行い、子どもの最善の利益を守り、健全な育成を図ることを目指します。最終的には、将来の自立と地域社会への参加を支援することが目標です。近年のガイドラインでは、これらに加えてお子さん自身の幸福感(ウェルビーイング)や主体性(エンパワメント)、意見表明権の尊重といった視点も重視されています。
主な根拠法は児童福祉法です。2012年の児童福祉法改正により、障害のある子どもたちが地域で支援を受けられる「障害児通所支援」の一つとして明確に位置づけられました。この改正で、それまでの「児童デイサービス」が、未就学児向けの「児童発達支援」と学齢児向けの「放課後等デイサービス」に分けられました。
はい、関連はあります。障害者総合支援法は主に18歳以上の大人の障害者を対象としていますが、放課後等デイサービスから大人のサービスへ移行する時期の支援や、相談支援など一部のサービスでは、児童福祉法と障害者総合支援法の両方が関わってきます。ただし、例えば「日中一時支援」のように、似たようなサービスでも障害者総合支援法に基づくものもあり、根拠法が異なる場合があります。
はい、2023年4月1日にこども家庭庁が発足したことに伴い、放課後等デイサービスを含む多くの障害児支援サービスは、こども家庭庁の所管に移管されました。ガイドラインの作成や制度改正などは、主にこども家庭庁が担当します。


放課後等デイサービスとは?
利用対象・条件
以下の条件を満たすお子さんが対象となります。
いいえ、必ずしも手帳や医師の確定診断が必須というわけではありません。最も重要なのは、お子さんに「療育の必要性がある」と認められることです。これは、児童相談所、市区町村の保健センター、医師などの専門機関の意見を参考に、お住まいの市区町村が総合的に判断し、支給決定を行います。ただし、お住まいの自治体によって実際の運用や「必要性」の判断基準に多少の違いがある可能性もあります。
はい、学校に在籍さえしていれば、不登校の状態であっても利用は可能です。2024年度からは不登校児への支援を評価する加算も新設されています。ただし、高校中退などで学校に籍がない場合は、原則として対象外となります。
原則として対象は18歳(高校卒業)までですが、高校卒業後などに大学等へ進学せず、引き続き放課後等デイサービスの利用が必要であると認められる場合には、満20歳に達するまで利用期間を延長することが可能です。


放課後等デイサービスとは?
利用手続き・費用
一般的な利用開始までの流れは以下の通りです。詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。
保護者が自分で作成する「セルフプラン」も可能ですが、多くの場合、市区町村から指定を受けた「相談支援事業所」に依頼して、専門の相談支援専門員に作成してもらことが推奨されています。相談支援事業所は、お子さんの状況や希望を聞き取り、適切なサービス利用に向けた計画案を作成してくれます。利用料はかかりません。
申請から受給者証が交付されるまでには、通常1~2ヶ月程度かかることが多いようです。混雑状況や書類の準備状況によっても変動するため、早めに相談を開始することをおすすめします。
サービスにかかった費用の原則1割が自己負担となります。ただし、家計への負担が重くなりすぎないよう、世帯の所得に応じて1ヶ月あたりの負担上限月額が決められています。負担上限月額は以下の通りです(最新情報は自治体にご確認ください)。
はい、基本的なサービス利用料(1割負担及び上限額の対象)とは別に、おやつ代、教材費、イベント参加費、外出時の交通費などが「実費負担」として請求される場合があります。これらの費用は負担上限月額の計算には含まれませんので、契約前に事業所に確認することが大切です。


放課後等デイサービスとは?
支援内容
A15: 一人ひとりのお子さんの状況に合わせて作成される「個別支援計画」に基づき、様々な支援や活動が行われます。2024年7月改訂の最新ガイドラインでは、支援内容を「5領域」と呼ばれる以下の5つの発達側面から捉え、これらを網羅的に含んだ総合的な支援を行うことが求められています。
事業所によっては、学校の宿題のサポートや基礎学力の向上を目指した学習支援を行っている場合もあります。ただし、放課後等デイサービスは学習塾ではなく、あくまで発達支援を主目的とする福祉サービスです。学習支援は、総合的な発達支援の一環として位置づけられています。2024年度の制度改正では、単なる預かりや学習塾的な支援に偏る事業所は、公費(報酬)が減算されたり、場合によっては対象外となったりする可能性が示唆されています。
個別支援計画(放課後等デイサービス計画とも呼ばれます)は、一人ひとりのお子さんの発達段階や特性、ニーズに合わせて、具体的な支援目標や内容を定めた計画書のことです。この計画に基づいて日々の支援が行われます。計画の作成は、主に事業所に配置されている児童発達支援管理責任者(児発管)が中心となり、保護者や子ども本人の意向を確認しながら作成・見直しを行います。
(補足:2024年度からは、作成した個別支援計画を指定障害児相談支援事業所にも交付することや、国が示す標準様式を活用することが求められています。)
「5領域」とは、子どもの発達を「①健康・生活」「②運動・感覚」「③認知・行動」「④言語・コミュニケーション」「⑤人間関係・社会性」の5つの側面から捉え、バランスの取れた総合的な支援を提供するための枠組みです。2024年度からは、放課後等デイサービス事業所はこの5領域を網羅的に考慮して個別支援計画を作成し、提供する活動と5領域との関連性を明記した「支援プログラム」を作成して保護者に説明するとともに公表することが求められています(令和7年度からは義務、それまでは努力義務)。これはサービスの質を高め、偏りのない支援を保証するための重要な取り組みです。


放課後等デイサービスとは?
事業者・運営
運営主体は多様です。社会福祉法人、NPO法人に加え、2012年の制度開始以降、株式会社などの営利法人の参入が急速に増え、近年設立された事業所では多数を占めています。その他、医療法人や一般社団法人などが運営する場合もあります。運営主体が多様化したことで事業所数は大幅に増えましたが、一方でサービスの質のばらつきなども課題として指摘されるようになりました。
多機能型事業所とは、一つの事業所で放課後等デイサービスと他の障害福祉サービス(特に未就学児向けの「児童発達支援」が多い)などを組み合わせて提供している事業所のことです。利用者にとっては、未就学期から学齢期まで継続して同じ(または系列の)事業所で支援を受けられる可能性があり、環境の変化による負担が少ないというメリットがあります。
(補足:また、事業者にとっても、人員配置基準の緩和措置がある、経営が安定しやすいなどのメリットがあります。)
児童発達支援管理責任者(児発管)は、放課後等デイサービスなどの障害児支援事業所に配置が義務付けられている専門職です。主な役割は、お子さんや保護者との面談(アセスメント)、個別支援計画の作成・管理、支援スタッフへの助言・指導、関係機関(学校、相談支援事業所など)との連携など、質の高いサービス提供の要となる重要なポジションです。
はい、事業所ごとに運営方針、専門性、提供するプログラム(運動療育、学習支援、SSTなど)、スタッフの雰囲気などは異なります。事業所を選ぶ際は、以下の点などを確認すると良いでしょう。


放課後等デイサービスとは?
メリット・効果
子どもと家族の双方に多くのメリットがあります。
放課後等デイサービスは、保護者への支援も重要な役割と位置づけています。レスパイト以外には、以下のような支援が挙げられます。


放課後等デイサービスとは?
他のサービスとの比較
主な違いは以下の点です。
対象年齢が異なります。児童発達支援は主に0歳から6歳までの未就学児を対象としており、早期からの発達支援(療育)を提供します。放課後等デイサービスは6歳から18歳(必要なら20歳まで)の学齢児が対象です。どちらも療育を提供しますが、年齢や発達段階に応じて支援内容は異なります。
どちらも日中の活動を支援するサービスですが、主な違いは根拠法と目的です。


放課後等デイサービスとは?
現状の課題と今後の展望
特に2024年度に大きな制度改正がありました。サービスの質の向上と適正化を目指すもので、主な変更点は以下の通りです。
はい、国はサービスの質の向上と標準化のために、様々な取り組みを進めています。
これらの取り組みにより、質の底上げと適正なサービス提供が目指されています。
いくつかの課題が指摘されています。
これらの課題に対し、国は児童発達支援センターの機能強化や連携促進策なども含め、継続的に改善に取り組んでいます。
契約に関するご相談は無料です。こちらからご予約ください。
面談方法は、Zoomによるオンライン面談となります。
はじめての方でも簡単にご利用いただけますのでご安心ください。
まずは以下のボタンからお申し込みください。
ご記入いただいたメールアドレス宛に事前ヒアリングシートのURLをお送りいたします。
面談に先立って事前ヒアリングシートへのご記入をお願いいたします。
ご記入いただいた事前ヒアリングシートに基づいて、面談時にヒアリングを実施致します。
ヒアリング内容に基づいて、お見積りをいたします。
お見積り内容に合意いただけた場合は、ご契約の手続を進めさせていただきます。
その他のお問い合わせはこちらから
【全国対応】
運営基準で要求される
\就労支援会計・区分会計に対応!/

介護・障がい福祉に強い! コスパ抜群の定額制! 創業期・小規模を応援! 記帳代行で負担軽減! 全国対応! 税理士が直接対応! 融資に強い! MFクラウド専門!
