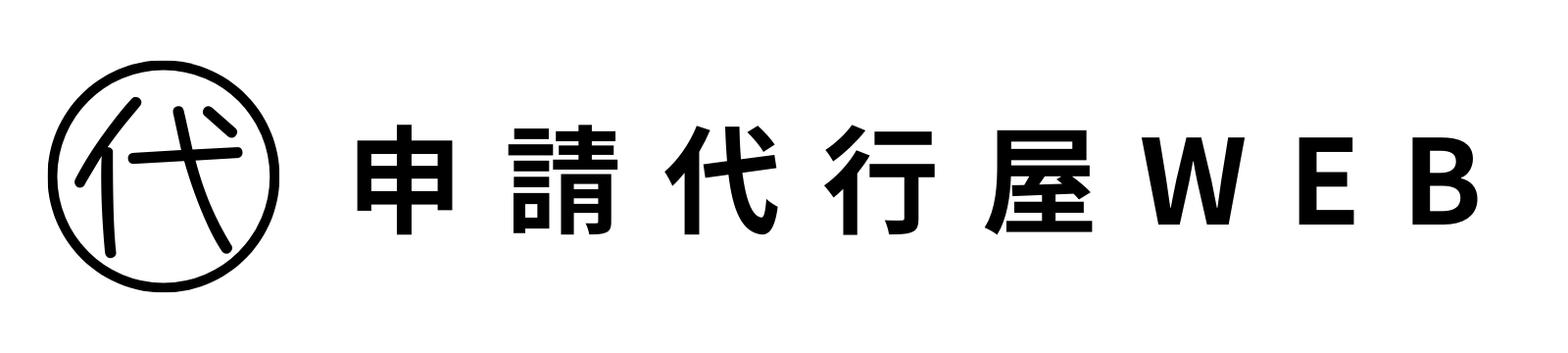日本で自動車を所有する際には、さまざまな手続きが伴います。その中でも特に重要でありながら、少し複雑に感じられるかもしれないのが「車庫証明」の取得です。正式には「自動車保管場所証明書」と呼ばれるこの書類は、新車や中古車の購入時だけでなく、引っ越しや譲渡の際にも必要となることがあります。
「手続きはどうすればいいの?」「どんな書類が必要?」「軽自動車の場合は?」「最近ルールが変わったって本当?」など、疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。特に2025年には保管場所標章(ステッカー)の廃止など、大きな制度変更もありました。
この記事では、そんな車庫証明について、基本的な知識から具体的な申請方法、軽自動車との違い、最新の法改正情報、注意すべき点まで、網羅的にわかりやすく解説していきます。自動車の購入や関連手続きをスムーズに進めるために、ぜひ最後までお読みください。
\専門家がお手頃価格で代行/
車庫証明代行 おすすめの行政書士事務所
🔵en行政書士事務所

車庫証明関係の申請書を作成します
ご依頼主様ファーストを目指しております!
サービスの特徴
車庫証明の申請書作成を代行!手続きをスムーズにサポート!
- 自動車の保管場所証明(車庫証明)に必要な申請書類一式の作成を行政書士が代行
- 警察署へご自身で書類を提出できる方に向けた、書類作成に特化したサービス
- 面倒な書類作成の手間を専門家が代行し、手続きをスムーズに進めるお手伝い
オンライン完結!チャットで依頼しPDFデータで納品!
- 依頼はチャットを通じて行い、必要情報(車検証のコピー、免許証のコピーなど)を提出
- 完成した申請書はPDFデータとしてチャットで納品
- ご自身で印刷して警察署へ提出するだけ
- 保管場所の地図や配置図はご自身で用意が必要
自動車業界経験のある行政書士が対応!24時間受付可能!
- 自動車業界での実務経験を持つ行政書士が、専門知識を活かして書類を作成
- 24時間365日いつでも相談・依頼が可能
- 保管場所が自己所有か賃貸かによって必要な書類(自認書または使用承諾証明書)が異なるが、適切に対応(使用承諾証明書の取得代行はオプション)
基本料金5,000円!分かりやすい価格設定!
- 基本的な申請書一式の作成代行を5,000円で提供
- 警察署へ支払う申請手数料(証紙代 約2,700円〜2,800円)は別途必要
- 賃貸駐車場の場合に必要な「使用承諾証明書」の取得代行もオプション(+15,000円)で依頼可能
\ 今すぐチェック!! /
🔵行政書士 山田涼太事務所



行政書士が車庫証明申請を代行します
証紙代込み♪基本対応警察署以外も、お気軽にご相談ください♪
サービスの特徴
全国の車庫証明、まずはご相談ください!
- 千葉・東京の基本対応エリアはもちろん、その他の全国の警察署も見積り対応
- 平日に休みが取れない、そんな全国のあなたに代わって専門家が手続き
証紙代込み!安心のコミコミ料金!
- 基本対応エリアは、警察署に支払う証紙代も含まれた分かりやすい価格設定
- 全国の警察署についても、事前の見積りで料金がわかるから安心
申請から受領・返送まで、まるっとおまかせ!
- 面倒な車庫証明の申請から受領、返送までを行政書士が一括でサポート
- 申請書や配置図・所在図の作成も、オプションで依頼可能
行政書士事務所だから、安心!
- 行政書士の山田涼太事務所が、責任をもって手続き
- 申請・受取代行:13,000円~
\ 今すぐチェック!! /
🔵サージ行政書士事務所



車庫証明の書類を作成します
全国対応 車庫証明用の書類作成サービスです
サービスの特徴
書類作成に特化!全国対応の車庫証明サポート!
- 「警察署には行けるけど、書類作成は面倒」という方向けのサービス
- 普通車・軽自動車の申請書と、所在図・配置図の作成を代行
- 全国どこからでも依頼可能
情報提供から3営業日以内に作成!
- 必要な情報を提供すれば、3営業日以内に書類をPDFで納品
- 依頼者はPDFを印刷し、自分で用意した書類と合わせて警察署に提出
- 自認書や使用承諾書のひな形は、無料で提供
専門家への依頼がこの価格で!
- 行政書士による本格的な書類作成サポートが、驚きの価格で実現
- 車庫証明申請書類作成:4,000円~
\ 今すぐチェック!! /
車庫証明って何?まずは基本を理解しよう
自動車を所有する際、耳にする「車庫証明」。一体どのようなもので、なぜ必要なのでしょうか?ここでは、車庫証明の基本的な知識を押さえていきましょう。
正式名称は「自動車保管場所証明書」 – その意味とは?
「車庫証明」は通称で、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。これは、あなたが使う自動車の保管場所が、法律(車庫法)で定められた要件を満たしていることを、警察署長が証明する公的な書類です。新車や中古車を買ってナンバーを取得する時(新規登録)や、引っ越し(変更登録)、名義変更(移転登録)などの際に、運輸支局等へ提出する必要があります。
単に「駐車場がある」というだけでなく、「法律で認められた保管場所を確保している」ことを証明する、重要な意味を持つ書類なのです。
なぜ必要?車庫証明制度の目的
車庫証明が必要な一番の理由は、道路交通の安全と円滑化のためです。自動車の持ち主にきちんと保管場所を確保させ、道路を駐車場代わりに使わせないようにすることで、無秩序な駐車による交通渋滞や事故を防ぐことを目的としています。特に日本では限られたスペースに多くの車があるため、この制度は重要な役割を果たしています。
根拠となる法律「車庫法」とは?
車庫証明のルールは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、通称「車庫法」に基づいています。1962年に制定されたこの法律は、自動車が増えることによる駐車問題を解決するために作られました。
主なポイントは以下の通りです。
- 保管場所の確保義務(第3条)
- 道路を保管場所として使用することの禁止(第11条第1項)
- 自動車登録時の車庫証明書提出義務(第4条)
- 長時間駐車の禁止(例:昼間12時間以上、夜間8時間以上、第11条第2項)
- 違反した場合の罰則(第17条、第18条)
車庫証明が必要になるのはどんな時?申請手続きガイド
次に、具体的にどのような場合に車庫証明の申請が必要で、どうやって手続きを進めればよいのかを見ていきましょう。
こんな時に申請!車庫証明が必要なケース
車庫証明の申請が必要になるのは、主に次の3つのタイミングです。
- 新車・中古車を購入し、新たにナンバーを取得する時(新規登録)
- 引っ越し等で住所(使用の本拠の位置)が変わり、管轄の警察署が変わる時(変更登録)
- 車の所有者が変わり、かつ住所(使用の本拠の位置)も変わる時(移転登録)
特に引っ越しなどで住所(使用の本拠の位置)や保管場所が変わった場合は、関連法規(車庫法第7条、道路運送車両法第12条など)に基づき、変更があった日から15日以内に手続きを行う必要があると一般的に解されています。この期限は忘れずに守りましょう。
車庫証明がいらない地域もある?適用除外地域について
実は、日本全国どこでも車庫証明が必要なわけではありません。人口が少ない町村部や島など、「適用除外地域」に指定されている場所では、手続きが不要な場合があります。
ただし、どの地域が適用除外かは、普通自動車と軽自動車で異なることがあります。例えば、東京都の檜原村は普通車も軽自動車も不要ですが、福生市は普通車は必要でも軽自動車は不要、といった具合です。
ご自身の地域が対象かどうかは、必ず最新の情報を管轄の警察署や都道府県警察のウェブサイトで確認してください。
申請に必要な書類リスト【完全版】
車庫証明の申請には、以下の書類を準備し、保管場所(駐車場)のある地域を管轄する警察署に提出します。
- 自動車保管場所証明申請書
- 警察署の窓口やウェブサイトで入手できます。車両情報や申請者情報を記入します。2025年4月以降、ステッカーに関する欄は記入不要です。
- 保管場所の所在図・配置図
- 所在図
自宅など(使用の本拠の位置)と駐車場の位置関係、目印、直線距離を記した地図。Google マップ等の地図のコピーでも可。 - 配置図
駐車スペースの寸法(縦・横)、出入口や接する道路の幅を記した図。
- 所在図
- 保管場所使用権原疎明書面
(保管場所を使う権利を証明する書類)
次のどちらか一方。- 自認書
駐車場が自己所有(自分の土地・建物)の場合。 - 保管場所使用承諾証明書
駐車場を借りている場合(月極、マンション駐車場、親族所有地など)。大家さんや管理会社、土地所有者に署名または記名してもらう必要があります。2020年末より押印は原則不要となっていますが、書類自体は権限を持つ方によって正しく発行される必要があります。
- 自認書
- 使用の本拠の位置を確認できる書類
(場合により)- 住民票の写しや公共料金の領収書など。
申請から交付までの流れをステップ解説
申請手続きは、基本的に以下の流れで進みます。
- 書類作成
- 上記の書類を不備なく正確に作成します。記入ミスや漏れがあると、再提出になることも。
- 警察署へ提出
- 書類一式を保管場所を管轄する警察署の車庫証明窓口へ提出します。受付は平日日中のみの場合が多いです。
- 手数料納付
- 申請手数料(都道府県により異なりますが、例として2,000円台前半など)を収入証紙などで納めます。
- 重要
2025年4月1日以降、保管場所標章(ステッカー)の交付手数料(従来500円~550円程度)は不要になりました。正確な手数料は申請先の都道府県警察にご確認ください。
- 審査
- 警察署で書類審査と、必要に応じて現地確認が行われます。
- 証明書受領
- 申請から通常3日~7日ほどで証明書が交付されます。再度警察署へ行き、申請時の控えなどを持参して受け取ります。
車庫として認められるための条件とは?
申請する駐車場(保管場所)は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 距離
- 自宅など(使用の本拠の位置)から駐車場まで直線距離で2km以内。
- アクセス
- 道路から問題なく出入りでき、車全体を収容できる。
- サイズ
- 車全体が収まる十分な広さがある。
- 場所
- 道路以外の場所(車庫、駐車場、空き地など)である。
- 権利
- その場所を使用する正当な権利(所有権、賃借権など)を持っている。
特に「直線2km以内」は重要な条件です。
軽自動車の場合はどうなる?「保管場所届出」を解説
軽自動車については、普通車とは手続きが少し異なります。「証明」ではなく「届出」という形になります。
「証明」と「届出」の違いを知っておこう
普通車の「車庫証明」と軽自動車の「保管場所届出」の主な違いは以下の通りです。
- タイミング
- 証明(普通車)
ナンバー取得(登録)の前に申請・取得が必要。 - 届出(軽自動車)
ナンバー取得(登録)の後に警察署へ届け出る。
- 証明(普通車)
- 性質
- 証明(普通車)
警察が確認して「証明書」を発行する申請手続き。 - 届出(軽自動車)
保管場所の情報を警察に通知する手続き。基本的に受理される。
- 証明(普通車)
- 交付物
- 証明(普通車)
「自動車保管場所証明書」が交付される。 - 届出(軽自動車)
2025年4月以降、原則として交付物はない(希望すれば受理印を押した控えをもらえる程度)。証明書は発行されない。
- 証明(普通車)
手続きは簡略化されていますが、保管場所を確保する義務や、その場所が満たすべき条件は普通車と全く同じです。
軽自動車の保管場所届出の手順
軽自動車の保管場所届出は、以下の手順で行います。
- タイミング
- 届出が必要な地域で、軽自動車を新たに保有したり、保管場所を変更したりした場合、ナンバー取得後(または変更後)速やかに(一般的に15日以内)届け出ます。
- 届出先
- 保管場所の所在地を管轄する警察署。
- 必要書類
普通車の証明申請とほぼ同じです。- 自動車保管場所届出書
- 所在図・配置図
- 使用権原疎明書面(自認書または使用承諾証明書)
- 手数料
- 2025年4月の標章廃止に伴い、届出手続き自体は無料の場合が多いです。
- 完了
- 書類が受理されれば手続き完了です。
軽自動車の届出が必要な地域・不要な地域
軽自動車の保管場所届出が必要な地域(届出義務地域)は、普通自動車の車庫証明が必要な地域よりも限定されています。主に都市部とその周辺が対象で、多くの地方や町村では不要です。
(例)届出が必要な地域
- 東京23区、大阪市、名古屋市、福岡市などの大都市
- 多くの政令指定都市、県庁所在地
(例)届出が不要な地域
- 東京都福生市、羽村市など
- 全国の多くの町村
繰り返しになりますが、ご自身の地域が対象かどうかは、必ず警察のウェブサイト等で確認してください。
【2025年最新情報】車庫証明制度の大きな変更点
2025年から、車庫証明に関するルールが大きく変わりました。
さよなら車庫証明シール!保管場所標章(ステッカー)の廃止
2025年4月1日から、車のリアガラスなどに貼っていた保管場所標章(車庫証明シール・ステッカー)が廃止されました。
- なぜ廃止?
- 警察のシステムが進化し、ナンバープレートから保管場所情報をすぐに照会できるようになったため、物理的なシールの必要性が薄れたこと、そして利用者の負担(手数料・貼付の手間)を減らすためです。
- どう変わる?
- 申請・届出時にシールが交付されなくなりました。
- 車にシールを貼る義務がなくなりました(貼ってあるものは剥がしてもOK)。
- シール交付手数料(従来500円~550円程度)が不要になりました。
- 注意点!
- シールは廃止されましたが、車庫証明の取得や保管場所の届出の義務はそのままです。手続き自体が不要になったわけではありません。
オンライン申請が可能に?OSS(ワンストップサービス)とは
自動車に関する手続きをまとめてオンラインで行える「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」が普及しつつあります。これを使えば、車庫証明の申請もオンラインでできる場合があります。
- どんなもの?
- パソコン、マイナンバーカード(電子証明書付き)、ICカードリーダー(またはマイナポータルアプリ対応スマホ)などを使って、OSSポータルサイトから申請し、手数料も電子納付できるシステムです。警察署に行く手間が省けます。
- 進化と現状
- OSSの対象手続きは順次拡大されており、システムの改善も進んでいます。例えば、警察署で紙の車庫証明を取得した後、運輸支局での登録手続きをOSSで行うといった組み合わせも可能になっています。
- 注意点
- 対応地域が限定的
まだ全国全ての警察署で利用できるわけではありません。利用可能か事前に確認が必要です。 - 対象は主に普通車
軽自動車向けの「軽自動車OSS(K-OSS)」は、新車の新規検査手続きなどが中心で、保管場所届出への対応はまだ限定的です。 - 準備が必要
マイナンバーカードや機材の準備、パソコン操作に慣れが必要です。
- 対応地域が限定的
OSSは便利ですが、まだ誰もが簡単に利用できる状況ではなく、従来の書面申請も引き続き利用されています。
注意!車庫証明の有効期間と違反行為
最後に、車庫証明に関する注意点や、やってはいけないことについて確認しましょう。
車庫証明書の有効期間はいつまで?
警察署で交付された車庫証明書は、運輸支局での車両登録手続きに使える期間が決まっています。一般的に発行日(証明の日)から概ね1ヶ月以内とされています。
この期間を過ぎると無効になってしまうため、車庫証明を取得したら速やかに車両登録手続きを進めましょう。ただし、実務上は運輸支局の内部通達などに基づき「40日程度」まで認められる場合もあるようですが、これは確実ではなく、最終的な判断は提出先の運輸支局によります。そのため、1ヶ月以内を目安に手続きを進めるのが最も安全です。
紛失・期限切れの場合はどうする?
- 期限切れ
- 有効期間(概ね1ヶ月、実務上40日程度の許容も考慮されるが確実ではない)を過ぎた証明書は使えません。もう一度、最初から申請し直す必要があります(手数料も再度かかります)。
- 紛失(有効期間内)
- まだ有効期間内であれば、警察署によっては簡単な手続きで再発行してもらえる場合があります。ただし、有効期間が切れてから紛失に気づいた場合は、新規申請と同じ扱いになります。
証明書はなくさず、期限にも注意しましょう。
絶対NG!「車庫飛ばし」などの違反行為
以下の行為は車庫法で禁止されており、罰則の対象となります。
- 車庫飛ばし
虚偽の内容で車庫証明を取得すること。例えば、- 実際は使わない遠くの駐車場で申請する。
- 引っ越したのに手続きをしない(結果的に実態と異なる登録状態になる)。
- 道路の車庫代わり使用
- 道路(公道や一般交通の用に供するその他の場所)を駐車場として日常的に使うこと。
- 道路での長時間駐車
- 同じ場所に長時間(昼間12時間以上、夜間8時間以上)駐車し続けること。
「車庫飛ばし」は、単なるルール違反ではなく、悪質な場合は刑事罰に問われる可能性もある重大な違反です。
違反するとどうなる?罰金や罰則について
車庫法に違反した場合の主な罰則は以下の通りです。
- 虚偽の保管場所証明申請(車庫飛ばし)
- 最大20万円以下の罰金
- 保管場所の不届け・虚偽届出
最大10万円以下の罰金。- ※2025年の標章廃止に伴い、特に軽自動車の届出義務の確実な履行のため、法人等に対する両罰規定が強化されるなど、罰則の一部が見直されています。
- 道路の車庫代わり使用
- 最大3ヶ月以下の懲役 または 20万円以下の罰金 + 違反点数3点
- 道路での長時間駐車
- 最大20万円以下の罰金 + 違反点数2点
軽い気持ちでの違反が、思わぬペナルティにつながる可能性があります。
まとめ:車庫証明を正しく理解して手続きしよう
これまでのポイントをおさらい
- 車庫証明は、適正な保管場所の確保を証明する公的な書類。
- 車の購入、引っ越し、名義変更(+住所変更)などの際に必要。
- 保管場所は自宅等から直線2km以内などの要件あり。
- 軽自動車は登録後に「届出」が必要(適用地域のみ)。
- 2025年からステッカーは廃止されたが、証明・届出の義務は継続。
- オンライン申請(OSS)も可能だが、制約あり、システムは進化中。
- 証明書の有効期間は約1ヶ月(実務上40日程度の許容幅あり)。
- 車庫飛ばしや道路の不正使用は法律違反で罰則あり(軽自動車の不届け罰則も一部強化)。
制度変更への対応とアドバイス
- 自分の地域が対象か確認する(特に軽自動車、届出要否)。
- 手続きは計画的に(申請日数と有効期間を考慮)。
- 書類は正確に作成する(押印不要など最新ルールも確認)。
- ステッカー廃止後も義務は守る。
- 法律違反は絶対にしない(罰則強化も意識)。
- 困ったら行政書士に相談するのも手。
なぜ法律を守ることが大切なのか
ステッカー廃止やOSSの進化など、手続きは変化していますが、車庫法の「すべての車に、適法な保管場所を」という根本的な考え方は変わりません。車を持つ責任の一つとして、ルールを守って適切な保管場所を確保することが、安全で快適な交通社会の維持につながります。車庫証明・届出制度を正しく理解し、定められた手続きを誠実に履行しましょう。
- 【安心代行】三重県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】京都府の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】兵庫県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】北海道の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】千葉県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】和歌山県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】埼玉県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】大阪府の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】奈良県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】宮城県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】岐阜県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】岡山県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】広島県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】徳島県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】愛媛県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】愛知県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】新潟県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】東京都の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】栃木県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】滋賀県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】熊本県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】神奈川県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】福岡県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】福島県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】群馬県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】茨城県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】車庫証明とは?申請手続き・必要書類・注意点まで徹底解説
- 【安心代行】長野県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】静岡県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】香川県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)
- 【安心代行】高知県の車庫証明を徹底解説!(2025年最新版)