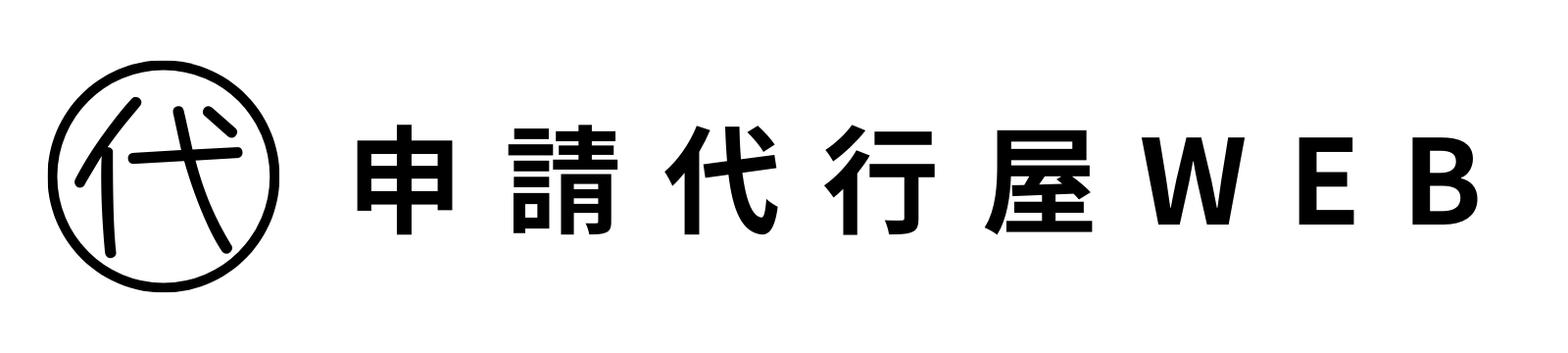「民泊」とは、一般的に住宅の全部または一部を活用し、旅行者などに有料で宿泊サービスを提供する事業形態です。特に東京都では、国内外からの観光客増加に伴い、宿泊施設の選択肢として重要性が高まっています。
2018年の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行は、無許可営業や地域トラブルに対応し、健全な普及を図る転換点となりました。この法律により、一定ルールの下で住宅を活用した宿泊サービス提供が可能となり、市場の透明性と安全性が向上しました。
しかし、東京都で民泊を始めるには、民泊新法に加え、旅館業法に基づく簡易宿所営業、特定地域(大田区など)で適用される国家戦略特別区域法に基づく特区民泊という複数の法制度が存在します。さらに、都や各区が定める条例(上乗せ条例)が状況を複雑にし、特に民泊新法の営業日数や区域に追加制限を課すことがあります。
成功のためには、これらの法制度と地域ごとの独自規制を理解し、適切な事業形態を選択し、手続きを着実に実行することが不可欠です。この記事では、東京都での民泊事業開始を検討する方へ、関連法規、事業モデル比較、申請手続き、施設・運営要件、費用、公的リソースまで、包括的かつ実践的な情報を提供します。
\専門家がお手頃価格で代行/
民泊開業 東京都でおすすめの行政書士事務所
🔵北海道石狩国際法務行政書士事務所

民泊・簡易宿所(シェアハウス)旅館開業申請承ります
経験豊富な行政書士が開業申請書類作成と申請を代行します‼
サービスの特徴
面倒な許認可申請は、専門家におまかせ!
- 経験豊富な行政書士が、書類の準備から許可までを完全サポート
- 民泊、簡易宿所、旅館事業など、各種申請に幅広く対応
全国での豊富な実績が信頼の証!
- 北海道から沖縄まで、全国各地での申請実績が多数
- 前年度は民泊から旅館まで、数多くの申請実績あり
レスポンスの良さで高評価!
- 利用者から「素晴らしい説明」「丁寧で迅速」と絶賛の声
分かりやすい料金体系で、納得の依頼!
- サービス基本料金に、許認可ごとの加算料金で構成
- 民泊事業、簡易宿所、旅館事業それぞれに明確な料金を設定
- 民泊申請:90,000円~
- 簡易宿泊所:170,000円~
\ 今すぐチェック!! /
🔵民泊専門の行政書士事務所



民泊申請・温泉申請┃12万円〜行政書士が対応します
一部サポート/全てお任せ/全国の民泊申請代行します
サービスの特徴
複雑な民泊申請は、専門家におまかせ!
- 民泊・旅館業に注力する行政書士が、申請を徹底サポート
- 年間30件以上の申請に対応する豊富な実績
- 複雑な法規制や地域ごとの条例も、きちんと調査
費用を抑えたい方に!選べるサポート体制!
- 「全てお任せ」から「一部サポート」まで、柔軟に対応
- 自分でできる作業は自分で行い、費用を抑えることが可能
- お客様の状況に合わせ、一番安価なプランを見積り作成
親切・丁寧な対応で高評価!
- 利用者から「とても親切で、安心してお任せできた」と絶賛の声
全国の書類作成と、一部地域の現場対応!
- 全国の民泊申請書類の調査・収集・作成に対応
- 関東近郊や大阪・京都では、保健所への相談や近隣説明なども代行可能
- 民泊申請:12万円~
\ 今すぐチェック!! /
🔵新谷行政書士事務所



民泊ついてお気軽に相談をお受けします
民泊・宿泊業界に詳しい行政書士にご相談ください
サービスの特徴
民泊・宿泊業界に詳しい行政書士が相談対応!
- 民泊(住宅宿泊事業法、旅館業法、特区民泊)の開業・運営に関する相談に行政書士が対応
- 業界に詳しい専門家が、これから民泊を始めたい方の不安や疑問を解消
- ぼんやりとしたイメージでも、気軽に相談可能
30分3,500円!ビデオチャットで全国対応!
- ビデオチャットで30分間、じっくり相談可能
- オンラインで全国どこからでも相談OK
- 相談料は30分3,500円の分かりやすい価格設定
ゲストハウス運営経験者が、実践的アドバイス!
- 講師自身も2019年にゲストハウスを開業した経験者(現在は行政書士・民泊代行)
- 運営経験者だからこそ分かる、実践的なノウハウや注意点をアドバイス
- 民泊開業までの流れ、Airbnbなどの活用法、許可取得のポイントなどをサポート
届出・申請の悩みも解決!スムーズな開業をサポート!
- 「どうやって申請すればいいか」「何から始めればいいか」といった具体的な手続きの悩みにも対応
- 専門家に任せることで、複雑な届出や申請の手間を削減し、ご自身の時間を有効活用
- 利用者からは「丁寧に教えてもらえた」「的確なアドバイス」と高評価
\ 今すぐチェック!! /
🔵デコレート行政書士事務所



48時間納品/行政書士が民泊新法の図面を作成します
民泊専門の行政書士による図面作成代行です。
サービスの特徴
70件以上の実績!民泊専門の行政書士が図面を作成!
- 民泊・旅館業の手続きで70件以上の実績を持つ、専門の行政書士が対応
- 民泊新法や旅館業許可申請に必要な、専門的な図面作成を代行
48時間納品!修正回数は無制限!
- お急ぎの方に最適!48時間以内に図面をスピード納品
- 納品後の軽微な修正や加筆は、いつでも何回でも無料で対応
図面作成に特化!PDF・JPGで納品!
- 依頼者は、壁芯が記載された物件資料などを提示するだけ
- 完成した図面は、PDFまたはJPG形式で納品
- 行政への提出は、利用者自身で行うサービス
- 民泊申請図面作成:4万円~
\ 今すぐチェック!! /
知っておきたい!民泊のルール(法律と条例)
東京都の民泊事業は、主に3つの国の法律と、それを補完する都・区の条例によって規律されます。事業形態と物件所在地に応じて、適用される法規を正確に把握する必要があります。
住宅宿泊事業法(民泊新法)
2018年6月15日施行。住宅を活用した小規模な民泊(ホームシェアリング型)が主な対象です。
- 概要
- 旅館業法の許可なく、住宅に有料で人を宿泊させる事業を「住宅宿泊事業」と定義。事業者は都道府県知事等(特別区は区長)へ「届出」が必要。許可や認定ではなく届出制のため、手続きのハードルは比較的低いとされます。
- 年間営業日数
- 年間180日以内という上限規制があります。実際に宿泊した延べ日数で計算されます。
- 対象となる「住宅」
- 法律上の「住宅」に限られます。「台所、浴室、便所、洗面設備」があり、かつ「現に人の生活の本拠」「入居者募集中の家屋」「随時居住用に供されている家屋」のいずれかの要件を満たす必要があります。投資目的の新築で居住実態がない物件は原則対象外です。
- 管理業者の必要性
- 家主不在型や居室数5を超える場合、原則として国土交通大臣登録の「住宅宿泊管理業者」に管理業務を委託しなければなりません。管理業者は宿泊者名簿管理、鍵の受け渡し、清掃、苦情対応などを代行します。
旅館業法に基づく簡易宿所営業
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業全般を規律する法律。民泊では「簡易宿所営業」が関連深いです。ゲストハウスや年間180日を超えて営業したい施設などが選択します。
- 概要
- 保健所を窓口とする自治体からの「許可」が必要。届出制より手続きや審査は厳格です。
- 年間営業日数
- 年間営業日数の上限はありません。年間を通じて営業可能です。
- 施設・安全基準
- ホテルや旅館に近い、比較的厳しい基準が求められます。客室延床面積(10人未満: 1人あたり3.3m²以上、10人以上: 全体で33m²以上)、換気、採光、入浴・洗面・便所設備などが必要です。
- 用途地域
- 原則としてホテル・旅館が建築可能な用途地域(第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域など)でしか営業できません。住居専用地域での営業は基本的に不可能です。
国家戦略特別区域法に基づく特区民泊
国家戦略特区において既存規制を緩和する法律。東京都内では大田区などが「特区民泊」制度を設けています(正式名称:国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)。外国人も日本人も宿泊可能です。
- 概要
- 特区を所管する自治体の長(例:大田区長)からの「認定」が必要。旅館業法の適用が除外されます。
- 年間営業日数と最低宿泊日数
- 年間営業日数の上限はありませんが、一回の滞在が最低2泊3日以上(大田区の場合)という要件があります。
- 施設要件
- 1居室あたり原則25m²以上の床面積が必要。台所、浴室、便所、洗面設備の設置、外国語での施設案内・緊急時情報提供なども要件です。
- 用途地域
- 住居専用地域でも認定を受ければ営業可能です(自治体による制限あり)。
- 契約形態
- 宿泊契約ではなく「賃貸借契約」及びこれに付随する契約に基づきます。
東京都及び特別区の条例(上乗せ条例)の重要性
国の法律に加え、特に民泊新法に基づく民泊に対しては、各特別区が制定する「上乗せ条例」が重要です。国の基準より厳しい制限(営業日数や区域)を設けることを認めています。
- 影響
- 多くの区で、住居専用地域等において民泊新法の営業を年間180日より短い期間(週末のみ等)に制限したり、全面的に禁止したりしています。これにより事業展開が困難になる地域もあります。一方、制限がほとんどない区も存在します。
- 確認の必要性
- 物件所在地の区が定める上乗せ条例を、事業計画の初期段階で必ず確認することが不可欠です。区のウェブサイトや担当窓口で確認します。
これらの法制度が重層的に存在するため、東京都での民泊事業は複雑な規制環境下にあります。2018年以降、無許可営業への罰則も強化され、コンプライアンス遵守の重要性が増しています。選択するモデルと立地に応じた規制を正確に理解し、遵守する体制構築が必要です。特に区の条例は、民泊新法モデルの採算性を左右する決定的な要因となり得ます。
どのやり方で始める?3つの民泊モデルを比較
住宅宿泊事業法(新法民泊)、国家戦略特別区域法(特区民泊)、旅館業法(簡易宿所営業)のいずれかに基づき、適切な手続き(届出、認定、許可)が必要です。モデルごとに営業日数、手続き難易度、施設要件、運営制約が大きく異なるため、事業目的、物件特性、立地、運営形態を総合的に勘案し、最適なモデルを選択することが成功の鍵です。
主要3モデルの比較概要
| 特徴項目 | 住宅宿泊事業法 (新法民泊) | 国家戦略特別区域法 (特区民泊:大田区例) | 旅館業法 (簡易宿所営業) |
|---|---|---|---|
| 根拠法 | 住宅宿泊事業法 | 国家戦略特別区域法 | 旅館業法 |
| 行政手続き | 都道府県知事等への 届出 | 自治体(区長等)からの 認定 | 保健所への 許可 申請 |
| 年間営業日数 | 180日以内 | 制限なし | 制限なし |
| 最低宿泊日数 | 制限なし (1泊2日以上) | 2泊3日以上 | 制限なし (1泊2日以上) |
| 住居専用地域での営業 | 可能 (ただし区条例による制限あり) | 可能 (ただし自治体による制限あり) | 原則不可 |
| 客室最低床面積 | 1人あたり 3.3m² 以上 | 1居室あたり原則 25m² 以上 | 宿泊者10人未満: 1人あたり 3.3m² 以上 / 10人以上: 全体で 33m² 以上 |
| 消防設備要件 | 原則必要(家主居住型は緩和措置あり) | 必要 | 必要 |
| 管理業者への委託義務 | 家主不在型 or 居室数5超の場合 必要 | 不要 | 不要 |
| 手続き難易度(一般論) | 低 | 中 | 高 |
| 主なメリット | 手続きが比較的容易、住居専用地域でも可能 | 年間営業日数制限なし、住居専用地域でも可能 | 年間営業日数制限なし、高い収益性の可能性 |
| 主なデメリット | 年間180日(又は区条例)の上限、家主不在時の管理委託 | 最低宿泊日数(2泊3日)の制約、実施可能エリア限定 | 手続きが煩雑、住居専用地域不可、初期投資大の可能性 |
戦略的なモデル選択のための考慮事項
どのモデルが最適かは、事業者の状況や目標によります。以下の点を考慮して選択します。
- 収益性と手続きのバランス
- 簡易宿所や特区民泊は営業日数制限がなく高収益の可能性がありますが、許可・認定の基準が厳しく手続きも複雑です。新法民泊は届出で容易に開始できますが、営業日数上限(区条例でさらに短縮も)が収益の制約です。
- 立地の制約(用途地域と区条例)
- 物件所在地がモデル選択を左右します。用途地域を確認し、簡易宿所が可能か(住居専用地域は原則不可)、特区民泊対象エリアか(大田区など)を判断。新法民泊は用途地域の制約は緩いですが、区条例で住居専用地域等の営業が大幅に制限されている場合があります。エリアの用途地域と区条例を照らし合わせ、実行可能なモデルを絞り込むことが第一歩です。
- 物件の特性
- 物件の規模や構造も影響します。特区民泊は1居室25m²以上、簡易宿所も定員に応じた面積基準があります。マンションは管理規約で民泊が禁止されていないか確認が不可欠です。
- 家主の関与度(住宅宿泊事業の場合)
- 新法民泊では、家主居住型か不在型かが重要です。家主不在型は管理業者への委託が義務付けられコストが増加します。一部の区では家主不在型に厳しい日数制限を課す場合があります。
各モデルに一長一短があり、絶対的に有利なモデルはありません。新法民泊は参入ハードルが下がりましたが、都心部や住宅地では区条例の制約が大きく、実質的な運営可能日数が限られるケースが多いため注意が必要です。立地と条例を最優先に確認し、自身の事業目標と照らし合わせて最適なモデルを見極めることが求められます。
始める前にチェック!物件とルールの事前準備
申請・届出前に重要な準備段階があります。怠ると手続きが滞ったり、事業開始が不可能になったりする可能性があります。
物件の評価と検証
事業の核となる物件が、民泊運営に適し、法的要件を満たせるかを事前に徹底調査します。
- 用途地域の確認
- 自治体のウェブサイトや窓口で公式な用途地域を確認。旅館業法(簡易宿所)が可能か、特区民泊の対象か、新法民泊なら条例による区域制限がないかを判断します。
- 建築基準法等との適合性
- 物件の構造や設備が、建築基準法、消防法、選択する民泊モデルの基準(必要設備、安全設備設置可能性)を満たせるか初期評価。古い建物は現行基準への適合に改修が必要な場合があります。
- マンション管理規約の確認
- 分譲マンションの場合、管理規約で民泊が禁止されていないか確認することが絶対条件です。規約に明記なくても、管理組合として禁止方針がないか確認し、証明書類(誓約書や議事録写し)の提出が求められる場合があります。管理組合の意向は事業可否を決定づける重要要素です。
- 賃貸借契約の確認(賃貸物件の場合)
- 賃借物件で運営する場合(転貸)、賃貸借契約で転貸が禁止されていないか確認し、必ず所有者(貸主)から民泊事業としての転貸について明確な承諾を得る必要があります。書面での承諾(転貸承諾書)が望ましいです。
- (重要)
上記、マンション管理規約の確認や賃貸物件所有者の転貸承諾は、他の準備(行政相談、図面作成等)に先立って確認すべき絶対的な前提条件(事業を進められるかどうかの判断材料)です。これらの確認を怠ると、後から事業が不可能と判明し、それまでの投資が無駄になるリスクがあります。最優先で確認すべき事項です。
関係行政機関への事前相談
申請・届出書類準備と並行して、またはその前に、管轄行政機関へ事前相談を行うことが強く推奨されます。個別の要件や注意点を確認でき、手続きを円滑に進められます。
- 保健所(生活衛生課など)
- 旅館業法(簡易宿所)申請を検討する場合、必須の相談先。新法民泊や特区民泊でも、区によっては事前相談を推奨・必須としている場合があります。施設の衛生基準や手続き詳細を確認。多くの場合、事前予約が必要です。
- 消防署
- すべてのモデルで消防法適合は不可欠であり、事前相談は極めて重要です。建物の構造・規模、運営形態に応じ、必要な消防用設備(自動火災報知設備、消火器、誘導灯など)の種類や設置場所、避難経路確保について具体的な指導を受けます。相談結果、「消防法令適合通知書」が交付される場合や、「事前相談記録書」の提出が求められる場合があります。
- 区役所の担当課
- 物件所在地の区役所民泊担当部署に相談し、区独自の条例(上乗せ条例)、申請・届出手続き、必要書類、近隣住民への説明方法など、ローカルルールについて正確な情報を得ることが重要です。
近隣住民への説明と同意形成
近隣住民との良好な関係は、円滑な運営のために不可欠です。法律や条例の手続きに加え、丁寧なコミュニケーションが求められます。
- 法的な通知義務
- 新法民泊および特区民泊では、事業開始前に近隣住民へ事業計画内容を周知することが義務付けられています。周知範囲(例:新宿区では届出住宅外壁から20m及び敷地から10mの範囲)や方法(戸別訪問、説明会、ポスティング等)、タイミング(例:新宿区では届出7日前まで、目黒区では15日前まで)は、区の条例やガイドラインで定められている場合があるため、必ず確認が必要です。「説明実施報告書」などの提出が求められます。
- 積極的なコミュニケーション
- 法定通知義務に加え、事前に挨拶回りを行うなど、良好な関係構築に努めることが望ましいです。事業内容や騒音・ゴミ出しルール、緊急連絡先などを丁寧に説明し、理解と協力を得ることで、トラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。
- 重要性
- 民泊は騒音やゴミ問題、不特定多数の出入りへの不安から、近隣トラブルが発生しやすい側面があります。法令遵守はもちろん、地域コミュニティへの配慮を欠かさない姿勢が、長期的な事業継続の鍵となります。
これらの事前準備は時間と労力を要しますが、事業開始後のリスクを低減し、円滑な運営を実現するための重要な投資です。特にマンション管理規約確認や消防署協議は計画の根本に関わるため、早期着手が推奨されます。
いよいよ申請!手続きの流れと必要書類
事前準備が整ったら、選択したモデルに応じて、管轄行政機関へ正式な申請または届出を行います。多数の書類が必要となり、正確かつ漏れのない準備が求められます。
必要書類チェックリスト
申請・届出に必要な書類は、モデルや状況(法人/個人、賃貸/自己所有、管理委託有無など)で異なりますが、一般的に要求される主な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 内容・目的 | 主な対象モデル | 備考・入手先例 |
|---|---|---|---|
| 届出書/申請書 | 事業の基本情報を記載するメイン書類 | 全モデル | 各自治体ウェブサイト、民泊制度ポータルサイト |
| 登記事項証明書(建物) | 物件の所有権等を証明 | 全モデル | 法務局 |
| 賃貸借契約書の写し及び転貸承諾書 | 賃借物件の場合、賃貸借関係と所有者の転貸承諾を証明 | 全モデル(賃貸の場合) | 物件所有者・管理会社 |
| 図面 | 間取り、面積、設備位置、安全措置、避難経路等を明示 | 全モデル | 事業者作成または建築士等に依頼 |
| 消防法令適合通知書 または 事前相談記録書 | 消防法規への適合状況を証明 | 全モデル | 管轄消防署 |
| 住民票の写し(個人)、定款・寄付行為及び登記事項証明書(法人) | 申請者・届出者の身分・法人格を証明 | 全モデル | 住所地の市区町村、法務局 |
| 身分証明書(破産手続きに関する証明) | 欠格事由に該当しないことを証明(個人の場合) | 全モデル(個人) | 本籍地の市区町村 |
| 欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 法令で定められた欠格事由に該当しないことを誓約 | 全モデル | 各自治体指定様式 |
| 周辺住民への説明実施報告書 | 近隣住民への事前説明を行ったことを報告 | 新法民泊、特区民泊 | 各自治体指定様式 |
| 管理規約の写し(マンションの場合) | マンションのルールを確認 | 全モデル(マンション) | 管理組合・管理会社 |
| 民泊禁止の意思がない旨の誓約書等(マンション) | 管理規約に定めがない場合、管理組合が民泊を禁止しないことを証明 | 全モデル(マンション) | 管理組合(自治体指定様式の場合あり) |
| 管理受託契約書の写し | 住宅宿泊管理業者への委託内容を証明 | 新法民泊(委託義務がある場合) | 契約した管理業者 |
| 廃棄物処理に関する確認書・契約書写し等 | 事業系ごみの適正処理体制を確認 | 自治体により要求(例:新宿区) | 廃棄物処理業者 |
| その他(各自治体指定書類) | 区条例に基づく誓約書、チェックリストなど | 各モデル(自治体による) | 各自治体ウェブサイト |
上記は代表例であり、詳細は必ず管轄自治体にご確認ください。外国籍の方は、身分証明書に代わる書類が必要な場合があります。図面の要件(縮尺、記載事項等)や、消防署、管理組合から入手する書類など時間のかかるものもあるため、余裕を持った準備が必要です。
事業モデル別 手続きフロー
- 住宅宿泊事業法(新法民泊)
- 事前準備(物件評価、消防・区役所相談)
- 近隣住民への周知(届出の一定期間前までに実施)
- 必要書類の準備・作成
- 届出書類の提出(原則「民泊制度運営システム」でオンライン申請)
- 届出受理、届出番号通知、標識受領
- 事業開始(標識掲示。年間180日及び区条例の範囲内で運営)
- 国家戦略特別区域法(特区民泊:大田区例)
- 事前準備(物件評価、保健所・消防署等へ事前相談)
- 近隣住民への説明・周知
- 認定申請書類の準備・作成
- 認定申請書の提出(例:大田区生活衛生課窓口)及び手数料納付(例:大田区新規¥20,500)
- 書類審査及び施設への立入検査(現地調査)
- 認定基準適合の場合、認定書の交付
- 事業開始(最低宿泊日数等の要件遵守)
- 旅館業法(簡易宿所営業)
- 事前準備(物件評価、保健所・消防署・(場合により)都市計画担当部署へ事前相談)
- 許可申請書類の準備・作成(建築士協力が必要な場合あり)
- 許可申請書の提出(管轄保健所窓口)
- 書類審査及び施設への立入検査(保健所、消防署)
- 許可基準適合の場合、許可証の交付
- 事業開始
標準的な所要期間と手数料
- 所要期間
- ケースバイケース。新法民泊は書類準備が順調なら1ヶ月程度で開始可能性もあるが、通常2〜3ヶ月。旅館業許可や特区民泊認定は書類審査・現地調査に時間を要し、数ヶ月以上を見込む必要あり。消防設備設置や改修が必要な場合は大幅に延びる可能性。
- 手数料
- 新法民泊届出自体は法定手数料なし(添付書類取得費は別途)。
- 特区民泊認定申請には手数料必要(例:大田区新規 ¥20,500)。
- 旅館業許可申請手数料は自治体により異なり、一般的に数万円程度。
- その他、証明書取得費、図面作成依頼の建築士費用、申請代行の行政書士報酬などが発生。
手続きの複雑さ、特に必要書類の多さと正確性の要求は大きな負担です。計画的な進行と、必要に応じた専門家(行政書士、建築士等)の活用が、円滑な事業開始には不可欠です。
どんな施設が必要?設備と安全のルール
民泊施設は、宿泊者の安全と快適性を確保するため、法律や条例で定められた様々な基準を満たす必要があります。特に消防関連要件は厳格で、初期投資にも大きく影響します。
基本的な設備と構造基準
- 必須設備
- 新法民泊および特区民泊では、「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」の設置が義務。旅館業法(簡易宿所)でも、適切な規模の入浴・洗面・便所設備が必要。
- 衛生基準
- 適切な換気、採光、照明、防湿、排水の設備が求められます。
- 構造
- 特区民泊では、居室と他部分の境界は壁造り、出入口・窓に鍵が必要など規定。新法民泊(家主居住型)の場合、区によっては宿泊者と家主の部屋を壁で区画し施錠管理を求める場合あり(例:新宿区)。
詳細な消防安全・避難要件
宿泊者の生命を守るため、消防法に基づく安全対策は極めて重要であり、全モデルで遵守が求められます。これは、しばしば最も費用のかかる要件の一つとなります。
- 重要性
- 消防法令適合は事業開始の絶対条件。不適合なら開始できません。
- 主な必要設備
建物の規模・構造、収容人数、運営形態で異なりますが、一般的に以下が求められます。- 消火器
- 自動火災報知設備(感知器設置場所等、細かく規定)
- 誘導灯・避難口表示
- 非常用照明器具
- 避難経路図(各室や共用部に掲示)
- モデルによる違い
- 旅館業法(簡易宿所)、特区民泊、新法民泊(特に家主不在型)では、ホテル等と同等の厳しい基準が適用される傾向。新法民泊(家主居住型)で小規模な場合は一部緩和可能性もありますが、最終判断は管轄消防署の指導に従う必要あり。自己判断せず必ず消防署に事前相談を。
- (重要)費用に関する注意
- 物件の状況によっては、自動火災報知設備や誘導灯などの設置・改修に数百万円単位の費用がかかることも珍しくなく、これが事業計画の大きな障壁となる場合があります。必ず早期に管轄消防署に相談し、専門業者による見積もりを取得することが極めて重要です。
- 適合証明
- 消防署との協議の結果、「消防法令適合通知書」の交付を受け、保健所や区役所に提出する必要あり。区によっては消防署の「事前相談記録書」提出で代える場合も。安全措置実施状況チェックリスト提出が求められ、建築士確認が必要な場合あり。
スペースとレイアウトに関する考慮事項
- 最低床面積
- 新法民泊: 宿泊者1人あたり 3.3m² 以上の居室面積。
- 旅館業法(簡易宿所): 10人未満は1人あたり 3.3m² 以上、10人以上は合計 33m² 以上の客室延床面積。
- 特区民泊(大田区例): 1居室あたり原則 25m² 以上の床面積。 これらの面積要件は収容可能人数、ひいては収益性に直接影響します。
- レイアウト
- 避難経路が明確に確保されている必要あり。新法民泊(家主居住型)の場合、宿泊者と家主スペースが明確に区画され、プライバシー確保が求められる場合あり。
- フロント(玄関帳場)
- 2018年の旅館業法施行令改正により、一定要件(ICT活用本人確認、緊急時駆けつけ体制等)を満たせば、簡易宿所でもフロント設置義務はなくなりました。新法民泊や特区民泊でも通常不要。ただし宿泊者名簿管理や本人確認は依然義務であり、代替措置(タブレット等)が必要。
施設要件、特に消防安全基準適合は、専門知識と相当な費用を要する場合があります。既存建物を活用する場合、大規模改修が必要なケースも。物件取得や賃貸契約前に、専門家(建築士、消防設備士等)による詳細調査と見積もりを行い、コンプライアンス達成の実現可能性とコストを正確に把握することが、事業リスク管理上、極めて重要です。
始めてからも大事!運営ルールと注意点
事業開始後も、法律や条例に基づき、様々な運営上の義務を継続的に果たす必要があります。これらの義務を確実に履行するには、日々の運営の中で継続的な管理体制と相応の時間・労力が必要となります。
宿泊者管理
- 宿泊者名簿の作成・保管
- 全事業者は、宿泊者全員の氏名、住所、職業、宿泊日を記載した名簿を作成し、通常3年間保管する義務があります。感染症発生時の追跡調査やテロ防止に不可欠です。
- 本人確認(IDチェック)
- チェックイン時に本人確認が必要。特に日本国内に住所がない外国人宿泊者にはパスポート提示を求め、国籍・旅券番号を名簿に記載し、パスポート写しを名簿と共に保管する義務があります。提示拒否の場合は理由確認し、必要なら警察連絡など適切な対応が求められます。
ハウスルールと情報提供
- ハウスルールの設定と周知
- 騒音、ゴミ分別・排出、喫煙ルール、パーティー禁止など明確なハウスルールを設定し、宿泊者に遵守を求めることが事業者の責任です。
- 多言語対応
- 外国人宿泊者に対し、施設の利用方法、交通案内、緊急時対応、ハウスルールについて、理解可能な言語(最低1つ以上の外国語)で情報提供を行うことが、特に新法民泊および特区民泊で法律上義務付けられています。東京都産業労働局等の多言語文例集活用が推奨されます。
- 廃棄物処理
- 宿泊者のゴミは事業系ごみとして、地域のルールに従い適切に分別し、許可を受けた廃棄物収集運搬業者に委託して処理する必要があります。自治体によっては契約書写しの提出を求められる場合があります。
安全確保、緊急時対応、報告義務
- 緊急連絡体制
- 事業者または管理業者の連絡先、警察、消防、救急の連絡先を施設内に明確に表示する必要があります。
- 非常時の備え
- 火災や地震などの災害に備え、避難経路・場所を宿泊者に周知し、非常用設備を常に正常に維持管理することが重要です。
- 苦情対応
- 宿泊者や近隣住民からの苦情・問い合わせに迅速かつ誠実に対応する体制を整備し、対応記録を保管することが求められます。家主不在型新法民泊では管理業者との連携が不可欠です。
- 定期報告
- 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに定期的に(通常2ヶ月ごと)宿泊日数、宿泊者数、国籍別内訳等を管轄自治体に報告する義務があります。原則として民泊制度運営システムでオンライン報告。宿泊実績がなくても報告が必要です。特区民泊や簡易宿所も自治体ごとに報告義務がある場合があるので確認が必要です。
管理業務の委託に関するルール
- 委託義務
- 新法民泊で、家主不在の場合や居室数5を超える場合は、国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。
- 管理業者の業務
- 宿泊者名簿管理、施設維持管理、鍵受け渡し、清掃指示・実施、宿泊者対応、苦情処理、周辺地域への配慮など広範な業務を代行します。
- 管理業者の選定
- 国土交通省登録業者である必要あり。リストは国交省ウェブサイト等で確認可。緊急時に迅速対応できる体制(例:新宿区では30分程度の駆けつけ目安)が求められる場合があるため、物件からの距離も選定要素。
- コスト
- 管理委託料は運営コストの大きな部分を占めるため、契約内容と費用を十分比較検討する必要があります。
これらの運営上の義務は、事業の信頼性と持続可能性を支える基盤です。特に宿泊者名簿の正確な管理、多言語対応、行政報告、苦情への迅速な対応は継続的な注意とリソースを必要とします。家主不在型新法民泊の管理委託義務はコスト増となる一方、専門業者による適切な運営管理が期待できますが、事業者自身の最終責任は免除されません。運営業務を適切に遂行する体制構築が不可欠です。
ここがポイント!「区のルール(上乗せ条例)」をチェック
東京都の民泊規制の最大の特徴であり注意点が、23区が独自に定める「上乗せ条例」です。これは主に住宅宿泊事業法に基づく民泊(新法民泊)を対象とし、国の基準に加えて、営業可能な日数や区域にさらなる制限を課すものです。事業の実現可能性と収益性を大きく左右するため、物件所在地の区の条例を正確に把握することが極めて重要です。
上乗せ条例の現状と確認の重要性
多くの区では、国の基準(年間180日)より厳しい営業日数制限(例:週末のみ営業可、特定の期間のみ営業可)や、特定の用途地域(特に住居専用地域)での営業制限または禁止などを設けています。また、家主が不在の場合により厳しい制限を課す区もあります。
区ごとの具体的な規制内容は頻繁に変更される可能性があります。インターネット上の古い情報や他の区の事例を鵜呑みにせず、必ず事業を検討している区の公式ウェブサイトを確認するか、区役所の担当部署に直接問い合わせて、最新かつ正確な条例・ガイドラインを入手してください。これが事業計画の前提となります。
東京23区 上乗せ条例 概要(参考情報)
注意:こちらは参考情報です。最新かつ正確な情報は必ず各区の公式ウェブサイトや担当窓口で確認してください。
| 区名 | 主な制限タイプ | 制限内容の概要(例) |
|---|---|---|
| 千代田区 | 区域・家主居住有無 | 文教地区等で制限。家主不在・管理者非駐在の場合、さらに厳しい日数制限の可能性あり。 |
| 中央区 | 日数(全域) | 区内全域で土曜正午~月曜正午のみ営業可。平日は不可。 |
| 港区 | 区域・家主不在型 | 家主不在型の場合、住居専用地域・文教地区で特定期間(学期中に相当)の営業不可。 |
| 新宿区 | 区域(住居専用地域) | 住居専用地域では、月曜正午~金曜正午は営業不可(週末・祝日のみ可)。 |
| 文京区 | 区域 | 住居専用地域、文教地区等で、月曜正午~金曜正午は営業不可(週末・祝日のみ可)。 |
| 台東区 | 家主居住有無 | 家主居住または管理者常駐の場合は制限なし(180日)。不在・非駐在は土日祝・年末年始のみ可。 |
| 墨田区 | 制限なし | 特段の上乗せ条例なし。 |
| 江東区 | 日数(全域) | 区内全域で土日祝のみ営業可。 |
| 品川区 | 区域 | 商業地域・近隣商業地域(文教地区除く)は制限なし。他は土日のみ可。 |
| 目黒区 | 日数(全域) | 区内全域で日曜正午~金曜正午は営業不可(週末のみ可)。近隣周知は15日前まで。 |
| 大田区 | 特区民泊中心 | 特区民泊制度が主。新法民泊にも区独自のガイドラインあり。 |
| 世田谷区 | 区域 | 住居専用地域・文教地区で制限あり。 |
| 渋谷区 | 区域・家主居住有無 | 住居専用地域・文教地区で特定期間営業不可。ただし家主居住等の例外あり。 |
| 中野区 | 区域 | 住居専用地域で制限あり。 |
| 杉並区 | 区域・家主居住有無 | 住居専用地域・文教地区で制限。家主不在の場合、さらに厳しい日数制限の可能性あり。 |
| 豊島区 | 家主居住有無 | 家主不在の場合、制限の可能性あり。 |
| 北区 | 制限なし | 特段の上乗せ条例なし。 |
| 荒川区 | 日数(全域)・管理者要件 | 区内全域で土日祝・年末年始のみ可。管理者常駐要件等あり。 |
| 板橋区 | 区域 | 住居専用地域で制限あり。 |
| 練馬区 | 区域 | 住居専用地域で月曜正午~金曜正午は営業不可。近隣周知は15日前まで。 |
| 足立区 | 区域 | 住居専用地域で制限あり。 |
| 葛飾区 | 制限なし | 特段の上乗せ条例なし。 |
| 江戸川区 | 制限なし(管理委託要件あり) | 上乗せ条例なし。ただし家主不在型は管理業者への委託必須。 |
主要区の事例(最新情報は必ず各区で確認してください)
以下はあくまで過去の事例や傾向を示す参考情報であり、現在の規制内容を保証するものではありません。
- 新宿区
- 過去には、住居専用地域において平日の営業を制限し、週末と祝日のみ可能とする規制がありました。住居専用地域以外では日数制限がない傾向でしたが、手続き面では近隣周知期間や消防署への相談記録提出、区独自の誓約書などが求められることがありました。
- 渋谷区
- 過去には、住居専用地域や文教地区で学校の長期休暇期間以外の営業を原則禁止する一方で、家主居住などの場合に年間180日まで可能とする例外規定を設けている時期がありました。区独自の誓約書等の様式が求められる傾向がありました。
- 大田区
- 国家戦略特区として「特区民泊」制度を推進しており、年間営業日数制限がない代わりに最低宿泊日数(2泊3日以上)や面積要件(1居室25m²以上)などが課されるのが特徴です。住宅宿泊事業法に基づく民泊も可能ですが、区独自のガイドラインが存在する場合があります。
これらの事例からもわかるように、区によって規制の内容は大きく異なります。新法民泊を検討する場合、上乗せ条例は事業の収益性や運営の自由度を大きく左右する決定的な要因です。したがって、物件選定の際には、希望するエリアの区の条例を最優先で調査し、その制限下で事業計画が成り立つかを慎重に評価する必要があります。「東京都」という一括りではなく、「〇〇区」という単位での極めて詳細な事前調査が不可欠です。
お金の話:必要な費用と税金は?
民泊事業の開始・運営には様々な費用が発生します。初期投資から運営コスト、納税義務まで、財務的側面を正確に把握し計画することが持続可能性に不可欠です。
初期投資費用(初期費用)
- 物件関連費用
- 購入(購入代金、仲介手数料、登記費用、不動産取得税等)または賃貸(敷金、礼金、保証金、前家賃、仲介手数料等)。
- 改修・リフォーム費用
- 設備基準(台所、浴室等)満たすための改修、内装工事等。
- 消防設備設置費用
- 自動火災報知設備、誘導灯、消火器等の購入・設置工事費。物件状態・規模・モデルで大きく変動し、最も大きな割合を占める可能性あり。
- 申請・許認可関連費用
- 申請手数料(特区民泊認定、旅館業許可)、専門家報酬(建築士、行政書士)、各種証明書取得費用。
- 家具・備品購入費用
- ベッド、寝具、家電、調理器具、Wi-Fi、鍵、標識設置費用等。
継続的な運営費用(運営費用)
- 物件関連費用
- 賃貸なら家賃・管理費等、購入ならローン返済。
- 水道光熱費
- 電気、ガス、水道料金。
- 通信費
- インターネット回線利用料。
- 消耗品費
- トイレットペーパー、シャンプー、洗剤等。
- サービス費用
- 清掃委託費、リネンサプライ費。
- 予約・集客費用
- 予約サイト(OTA)手数料(売上の一定割合)、広告宣伝費。
- 管理委託費
- 住宅宿泊管理業者への委託費用(月額または成果報酬)。
- 維持管理・修繕費
- 定期メンテナンス、故障時修理費用。
- 保険料
- 火災保険、賠償責任保険(民泊対応のもの)。
- 廃棄物処理費用
- 事業系ごみ収集運搬委託料。
関連する税金(税金)
- 所得税・法人税
- 個人は事業所得または不動産所得として所得税・住民税。法人は法人税等。
- 固定資産税・都市計画税
- 不動産所有の場合、毎年課税。
- 消費税
- 課税売上高が年間1,000万円超の場合、納税義務者。宿泊料収入は基本的に課税対象。
- 宿泊税(東京都)
- 1人1泊あたり宿泊料金(税抜)に応じ課税(1万円未満:非課税, 1万円以上1.5万円未満:100円, 1.5万円以上:200円)。事業者が徴収・納付義務。
- 事業税(個人)
- 所得が一定額超の場合、個人事業税が課される場合あり。
これらの費用・税金を正確に見積もり収支計画を立てることが重要です。特に新法民泊では、区条例による厳しい営業日数制限がある場合、限られた営業日数で初期投資(特に高額になりがちな消防設備費用)や運営コストを回収し、利益を確保する必要があります。条例の制限を考慮した慎重な収支計画と、採算性の見極めが不可欠です。初期投資、特に消防設備関連費用が想定以上にかかる可能性も考慮し、十分な資金計画を立てることが、安定した事業運営の前提となります。
困ったときは?相談窓口とサポート情報
東京都で民泊事業を開始・運営するにあたり、公的な情報源や相談窓口、専門家の支援を活用することで、より円滑かつ確実に手続きを進められます。
政府のポータルサイトとガイドライン
- 民泊制度ポータルサイト(国土交通省観光庁)
- 新法民泊に関する最も包括的な公式情報源。法律概要、Q&A、オンラインシステム(民泊制度運営システム)へのリンク、各自治体窓口情報など。コールセンターも設置。
- 厚生労働省ウェブサイト
- 旅館業法に関する情報。「民泊サービスを始める皆様へ ~簡易宿所営業の許可取得の手引き~」は簡易宿所を目指す事業者に有用。
- 東京都福祉保健局
- 都全体の民泊情報、各区担当窓口リンク、宿泊税情報などを提供している可能性あり。
- 消防庁・東京消防庁
- 消防法令情報、民泊施設防火安全対策リーフレットなどを提供。
地方自治体(東京都・各区)の窓口
- 各特別区のウェブサイト: 民泊事業に関するページが多く、区独自の条例、申請・届出様式、手続きの流れ、担当部署連絡先などを確認可。上乗せ条例確認に最も重要。必ず最新情報を確認してください。
- 保健所(生活衛生課など): 旅館業許可申請の窓口、衛生基準に関する相談先。
- 消防署: 物件所在地管轄消防署が、消防法令相談、検査、適合通知書発行の窓口。
どの機関に何を相談・申請すべきか正確に把握することが重要。不明な場合はまず区役所の民泊担当窓口に問い合わせるのが良いでしょう。
手引き、様式集、セミナー情報
- 自治体の手引き・ガイドライン
- 各区が詳細な手引きを作成・公開している場合あり(例:渋谷区「民泊のてびき」、新宿区「住宅宿泊事業ルールブック」等)。非常に役立ちます。必ず最新版を入手してください。
- 申請・届出様式
- 民泊制度ポータルサイトや各区ウェブサイトからダウンロードできることが一般的。
- セミナー・説明会
- 自治体や関連業界団体が開催する場合あり。自治体ウェブサイト等で告知される可能性。
専門家による支援
- 行政書士
- 申請・届出書類作成および提出代行の専門家。手続きに不安がある場合に強力なサポート。
- 建築士
- 施設適法性確認、改修設計、申請図面作成、安全措置チェックリスト作成・確認など建物に関する専門的支援。
- 不動産業者
- 民泊に適した物件探しをサポート。民泊関連法規や区条例に詳しい業者を選ぶことが重要。
- 民泊コンサルタント・運営代行会社
- 民泊特化コンサルティングや運営業務全般(集客、予約管理、清掃、ゲスト対応等)の代行サービス提供。
これらのリソースを効果的に活用し、情報の不足や誤解を防ぎ、法令を遵守したスムーズな事業開始と運営を目指せます。特に地域ごとの規制が複雑な東京都では、区の担当窓口や公式ウェブサイトを一次情報源とし、必要に応じて専門家の助言を求めることが賢明です。
まとめ:東京で民泊を成功させるには
東京都の民泊事業は、活発な観光需要を背景に魅力的な機会を提供する一方、国の複数法律と各区の「上乗せ条例」が複雑に絡み合う、極めて精緻な規制環境下での挑戦です。
成功は、この複雑性を乗り越えるための徹底した**事前調査(デューデリジェンス)**にかかっています。
- 立地の精査
- 物件所在地の用途地域と区が定める最新の上乗せ条例(営業日数・区域制限等)を最優先で確認すること。これが事業モデル選択肢と収益性を根本的に決定づけます。
- 法的適合性の検証
- 選択モデルの要件(施設基準、消防安全基準等)を物件が満たせるか、専門家(建築士、消防設備士等)協力で評価すること。特に消防適合はコスト・時間両面で大きな影響要因であり、高額な費用がかかる可能性を念頭に置く必要があります。
- 権利関係の明確化
- 最優先事項として、マンションは管理規約で民泊禁止でないか、賃貸物件は所有者から明確な転貸承諾を得ているか確認すること。事業の前提条件です。
これらに基づき、自身の目標(収益性、手間、リスク許容度)と物件制約に最も合致する戦略的な事業モデルを選択する必要があります。手続き容易な新法民泊も、区条例の厳しい日数制限下では収益確保困難な場合があり、その際は手間のかかる旅館業許可(簡易宿所)や対象地域限定の特区民泊が現実的選択肢となるかもしれません。条例による収益性への影響を慎重に見極めることが重要です。
事業開始後も、コンプライアンスの徹底と地域社会との良好な関係維持が持続可能性の鍵です。宿泊者名簿管理、外国人への情報提供、廃棄物適正処理、行政への定期報告といった運営上の義務を確実に履行し、騒音・マナー苦情が発生しないよう、宿泊者への注意喚起と近隣住民への配慮を継続することが求められます。これには継続的な時間と労力が必要です。
申請・届出プロセスは複雑さから、特に初事業者には大きな負担となり得ます。時間とコストを考慮し、行政書士や建築士といった専門家の活用を積極的に検討することが、スムーズな事業立ち上げとコンプライアンス確保に繋がります。
結論として、東京都の民泊市場は、適切な準備と法令遵守、地域への配慮をもって臨めば、依然として事業機会が存在します。しかし、その成功は、規制の迷宮を解き明かすための入念な調査と計画、そして継続的なコンプライアンス努力の上に成り立つものであることを、深く認識する必要があります。
参考資料
コラム:東京都行政書士会とは
官公署への許認可申請、会社設立や相続・遺言に関する書類作成、契約書の作成相談など、私たちの暮らしやビジネスにおける様々な場面で、法的な手続きや書類作成をサポートする専門家が「行政書士」です。日本の首都であり、膨大な行政手続きが存在する東京都内で活動する多くの行政書士が所属し、その資質の維持向上や業務の適正化を図るための法定団体が「東京都行政書士会」です。今回は、その役割や都民向けのサービスについてご紹介します。
行政書士の指導・監督と専門性の向上
東京都行政書士会は、会員である個々の行政書士が、常に最新の法令知識や実務能力を身につけ、高い倫理観を持って業務を遂行できるよう、継続的な研修の実施や業務に関する指導・監督を行っています。行政書士の専門性と信頼性を確保することで、都民や事業者が安心して業務を依頼できる環境を整備しています。また、行政書士制度の意義や役割を社会に広く伝えるための広報活動や、無料相談会などを通じた社会貢献活動にも力を入れています。
都民・事業者向けの相談窓口と情報提供
東京都行政書士会は、都民や事業者が行政手続きに関する困りごとを抱えた際に、適切な行政書士を見つけるための重要な窓口となります。会の公式ウェブサイトでは、お住まいの地域(都内各支部に所属する行政書士)や、相談したい業務分野(建設業許可、相続、国際業務など)から、登録されている会員行政書士を検索できるシステムが提供されていることが一般的です。さらに、都内各地で定期的に無料相談会などを開催し、様々な分野の相談に行政書士が直接応じる機会を設けている場合もあります。手続きでお困りの際は、まず東京都行政書士会の情報を確認してみることをお勧めします。
- 【格安代行】三重県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】京都府の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】佐賀県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】兵庫県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】北海道で民泊開業!始め方を徹底解説!
- 【格安代行】北海道の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】千葉県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】和歌山県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】埼玉県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】大分県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】大阪府で民泊開業!始め方を徹底解説!
- 【格安代行】大阪府の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】奈良県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】宮城県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】宮崎県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】富山県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】山口県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】山形県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】山梨県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】岐阜県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】岡山県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】岩手県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】島根県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】広島県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】徳島県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】愛媛県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】愛知県で民泊開業!始め方を徹底解説!
- 【格安代行】愛知県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】新潟県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】東京都で民泊開業!始め方を徹底解説!
- 【格安代行】東京都の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】栃木県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】民泊とは?メリット・デメリットから法律、今後の展望まで徹底解説
- 【格安代行】民泊の開業!始め方を徹底解説!
- 【格安代行】沖縄県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】滋賀県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】熊本県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】石川県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】神奈川県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】福井県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】福岡県で民泊開業!始め方を徹底解説!
- 【格安代行】福岡県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】福島県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】秋田県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】群馬県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】茨城県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】長崎県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】長野県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】青森県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】静岡県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】香川県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】高知県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】鳥取県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】鹿児島県の民泊開業でおすすめの行政書士4選