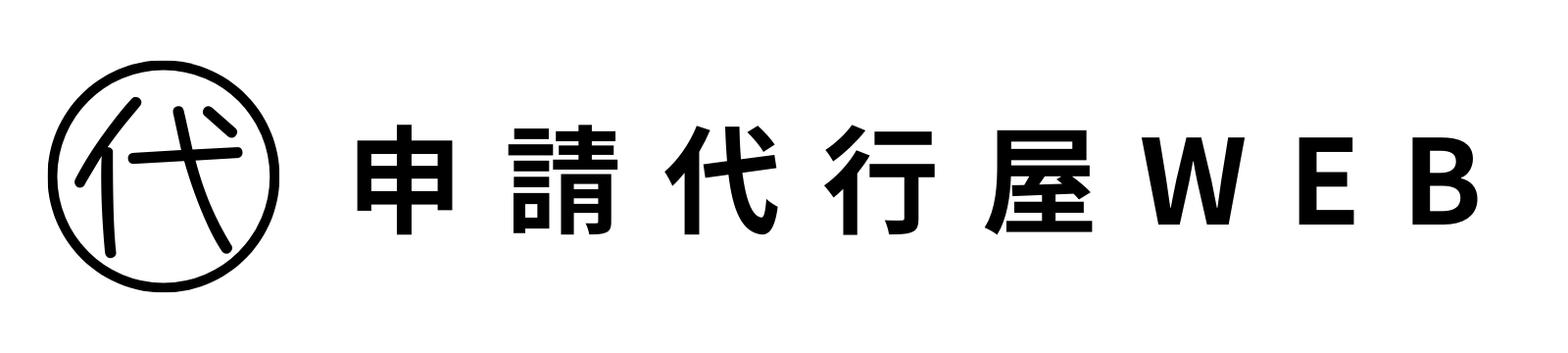なぜ特定技能制度が必要?背景と目的
日本は急速な少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少に直面し、多くの産業で深刻な人手不足が喫緊の課題となっています。国内人材の確保や生産性向上だけでは対応が困難な状況を受け、一定の専門性・技能を持つ即戦力となる外国人材を受け入れるため、2019年4月に新たな在留資格「特定技能」が創設されました。 これは、専門的・技術的分野以外での外国人労働者受け入れに慎重だった従来の政策からの転換点であり、経済的必要性から特定産業分野での就労を目的とする外国人受け入れを正面から認めるものとなりました。政府は「移民政策ではない」と強調しますが、後述する特定技能2号は長期定住の可能性も示唆しています。 法的根拠は2019年4月施行の改正「出入国管理及び難民認定法」(入管法)であり、「特定技能」という新たな在留資格が設けられました。これは入国許可である査証(ビザ)とは異なり、日本国内での活動内容や法的地位を定めるものです。 本稿では、この特定技能制度について、制度概要、対象分野、要件、手続き、支援体制、利用状況、課題、そして関連する最新動向まで、提供されたレポートに基づき詳細に解説します。
特定技能制度とは?2つの種類「1号」と「2号」を徹底比較
特定技能制度は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの区分から成り立っています。
特定技能1号:概要と特徴
- 対象:特定産業分野で、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人。
- 要件:原則、分野ごとの技能試験及び日本語能力試験(JFT-Basic A2レベル以上またはJLPT N4レベル以上)に合格が必要。ただし、技能実習2号を良好に修了した者は免除。
- 在留期間:通算上限5年。1年、6か月、4か月ごとの更新が必要。
- 家族帯同:原則不可。
- 支援:受け入れ機関または登録支援機関による義務的な支援が必要。
- 永住権:1号の在留期間は永住許可申請に必要な在留期間に算入されない。
特定技能2号:概要と特徴
- 対象:特定産業分野で、熟練した技能を要する業務に従事する外国人。
- 要件:分野ごとの、より高度な技能試験に合格が必要。多くの場合、監督者としての実務経験等も求められる。日本語試験は原則不要(分野や試験による)。
- 在留期間:更新上限なし。3年、1年、6か月ごとの更新で長期在留が可能。
- 家族帯同:要件(配偶者・子)を満たせば可能。
- 支援:義務的な支援は不要。
- 永住権:2号の在留期間は永住許可申請に必要な在留期間に算入される。
一目でわかる!特定技能1号と2号の違い
| 特徴 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 対象技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 在留期間上限 | 通算5年 | 更新により上限なし |
| 技能試験 | 必要(技能実習2号修了者は免除あり) | より高度な試験が必要 |
| 日本語試験 | 必要(JFT-Basic A2 / JLPT N4以上、技能実習2号修了者は免除あり) | 原則不要(分野・試験による) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能(配偶者・子) |
| 義務的支援 | 必要(受入機関または登録支援機関) | 不要 |
| 永住権への算入 | 不可 | 可能 |
| 対象分野(2024年) | 16分野 | 11分野(介護等除く) |
1号は中期的労働力、2号は高度人材の長期定着を意図していますが、2号に求められる「熟練した技能」のハードルは高く、実際の2号取得者数は極めて少ないのが現状です(2024年6月末時点で1号約25万人に対し、2号は153人)。技能実習2号修了者が試験免除で1号へ移行するルートが主流ですが、技能実習制度が抱える問題を特定技能制度に持ち込むリスクも指摘されています。
どんな仕事ができる?対象となる16の産業分野
対象分野一覧と最近の変更点
特定技能の対象となるのは、国内人材確保が困難な以下の16分野です(2024年時点)。分野ごとに従事できる業務内容は細かく定められています。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業(旧 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業(2024年追加)
- 鉄道(2024年追加)
- 林業(2024年追加)
- 木材産業(2024年追加)
これらの分野は、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省などが所管しています。 近年の主な変更点は以下の通りです。
- 介護:身体介護等に加え、2025年4月21日より、一定要件下で訪問系サービスへの従事が可能となった。
- 新規分野追加(2024年):自動車運送業(バス・タクシー・トラック)、鉄道(整備・運輸係員等)、林業、木材産業が1号対象に追加。当面は1号のみ。
- 製造業分野の統合・拡大:3分野が「工業製品製造業」に統合され、業務区分(紙器、コンクリート、印刷等)や対象事業所が拡大。特に『紡織製品製造』及び『縫製』の業務区分では、技能実習制度下での問題を踏まえ、①国際的な人権基準の遵守(第三者認証・監査機関の審査が必要)、②勤怠管理の電子化、③パートナーシップ構築宣言の実施、④特定技能外国人の給与の月給制、という4つの追加要件が課されている。
- 造船・舶用工業分野の再編・拡大:業務区分が再編され、作業範囲が拡大。
- 特定技能2号対象分野の拡大(2023年):従来の2分野から、介護を除く11分野へ拡大。介護分野は既に同様の在留資格「介護」が存在するため除外。
対象分野の継続的な見直し・拡大は、政府が特定技能制度を人手不足対策の主要ツールとして重視していることを示しています。
特定技能で働くには?外国人材と受け入れ企業の要件
外国人材に必要な条件(年齢・技能・日本語能力など)
特定技能外国人として認められるには、以下の基準を満たす必要があります。
- 年齢:18歳以上(試験受験は17歳以上可、国籍により異なる場合あり)。
- 技能水準:分野ごとの技能試験に合格。合格証明書は、多くの場合、発行日または受験日から10年間有効である。試験内容は分野により異なる。技能実習2号良好修了者は免除。2号はより高度な試験が必要。
- 日本語能力水準(1号):JFT-Basic A2レベル以上またはJLPT N4レベル以上に合格。基本的な日本語理解・日常会話レベル。介護分野は追加で介護日本語評価試験も必要。技能実習2号良好修了者は免除。2号は原則不要(分野・試験による)。
- 在留期間(1号):通算5年を超えていないこと。
- 契約・費用:保証金徴収や違約金契約がないこと。本人負担費用を理解していること。
- 健康状態:健康状態が良好であること。これを証明するため、指定された様式(参考様式第1-3号「健康診断個人票」及び別紙「受診者の申告書」)による健康診断結果の提出が必要であり、特定の検査項目(胸部X線検査等)に関する規定や診断書の有効期間(新規入国は申請前3か月以内、在留資格変更は申請前1年以内)がある。
- その他:出身国との二国間取決め(MOC)に基づく追加手続き等がある場合あり。『短期滞在』の在留資格で日本に滞在する者も、2020年4月1日以降、国内で実施される特定技能関連の試験を受験可能である。
受け入れ企業(特定技能所属機関)の条件と義務
外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)も基準を満たす必要があります。
適切な雇用契約の基準
- 業務内容:特定産業分野の技能を要する業務であること。
- 労働時間:通常の日本人労働者と同等であること。
- 報酬:日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上であること。
- 差別的取扱いの禁止:外国人であることを理由とする差別がないこと。
- 一時帰国休暇:希望した場合、有給休暇を取得させること。
- 雇用形態:原則直接雇用(農業・漁業は派遣も可)。
- 契約言語:本人が理解できる言語で作成・説明。
- 帰国費用:本人が負担できない場合、機関が負担。
- 健康診断:機会を提供。
受け入れ機関自体の適格性
- 法令遵守:労働・社会保険・租税関係法令を遵守。
- 違反歴:過去5年以内に重大な出入国・労働法令違反がないこと。
- 非自発的離職:過去1年以内に同種業務の労働者を非自発的に離職させていないこと。
- 行方不明者:過去1年以内に機関の責による行方不明者を発生させていないこと。
- 財政的健全性:著しく不安定(債務超過等)でないこと。
- 保証金等の禁止:保証金徴収や違約金契約がないこと。
- 分野別協議会への加入:多くの場合求められる。建設分野は事前に国土交通大臣の計画認定が必要。
- 支援体制(1号):外国人が理解できる言語での支援能力、支援責任者・担当者の選任。登録支援機関への全部委託も可。
- 適切な支援計画(1号):支援計画を作成し実施すること。
申請手続きの流れ:海外からと国内からのケース別解説
申請手続きは、外国人が海外にいるか、国内にいるかで異なります。
海外からの新規入国の場合(在留資格認定証明書(COE)交付申請)
- 試験合格:技能・日本語試験に合格。
- 雇用契約:日本の受入機関と契約。
- 支援計画策定(1号):受入機関が作成。
- COE申請:受入機関が地方出入国在留管理局に申請。
- 審査・交付:審査後、COE交付。
- COE送付:受入機関が本人へ送付。
- 査証(ビザ)申請:本人が自国の日本大使館等に申請。
- 査証発給:審査後、査証発給。
- 来日・入国審査:査証で来日し、入国審査を経て在留カード交付。
- 就労開始:住所登録等を済ませ就労開始。
国内からの在留資格変更の場合(在留資格変更許可申請)
- 試験合格(該当者):既に滞在中の者が試験に合格(技能実習2号修了者は免除あり)。
- 雇用契約:受入機関と契約。
- 支援計画策定(1号):受入機関が作成。
- 在留資格変更申請:本人が地方出入国在留管理局に申請。
- 審査・許可:審査後、変更許可。
- 在留カード受領:新しい在留カードを受領。
- 就労開始/継続:特定技能として就労開始または継続。
申請に必要な書類と審査期間の目安
申請には多岐にわたる書類が必要です。
- 主な申請者関連書類:申請書、写真、パスポート・在留カード写し、試験合格証明書写し、健康診断個人票、履歴書、納税証明書(国内申請時)等。
- 主な受入機関関連書類:機関概要書、登記事項証明書、役員住民票写し、決算文書写し、労働・社会保険料納付証明書写し、納税証明書、雇用契約書写し、雇用条件書写し、報酬比較説明書、支援計画書写し(1号)、支援委託契約書(委託時)、分野別誓約書・必要書類等。
申請は窓口、郵送、オンライン(要事前登録等)で行います。申請先は原則、受入機関本店所在地の管轄局です。
- 審査期間(目安):
- COE交付申請:1.5か月~3か月程度(平均62~78日との報告も)
- 在留資格変更許可申請:1.5か月~2か月程度(平均56~57日との報告も)
- 在留期間更新許可申請:2週間~1か月程度(平均38~42日との報告も)
- 査証(ビザ)発給(COE取得後):約1~2週間程度(国による)
これらは目安であり、状況により変動します。建設分野は事前の計画認定(1.5~2か月程度)が必要なため、さらに長くなります。書類が多く手続きが複雑なため、特に中小企業には負担が大きく、専門家(行政書士、登録支援機関)の活用が重要です。
特定技能1号への手厚いサポート:義務付けられた10項目の支援内容
特定技能1号外国人には、安定した就労・生活のため、受け入れ機関による包括的な支援が義務付けられています。
誰が支援する?受け入れ機関と登録支援機関の役割
支援の責任は受け入れ機関にありますが、支援業務の全部または一部を、国の登録を受けた「登録支援機関」に委託することが可能です。全部委託すれば、受け入れ機関は自ら支援体制を持つ必要がなくなります。 登録支援機関は専門的な支援を提供しますが、登録には基準(法令違反がないこと、多言語対応能力等)を満たす必要があり、登録期間は5年です。登録機関リストは公開されています。支援業務の再委託はできません。
具体的な支援内容:10項目を詳しく解説
受け入れ機関または登録支援機関は、以下の10項目の支援を、外国人が理解できる言語で実施しなければなりません。
- 事前ガイダンス:雇用契約後、申請前に労働条件等を対面またはオンラインで説明(目安3時間)。
- 出入国する際の送迎:入国時は空港等から住居等へ、帰国時は空港の保安検査場まで送迎・同行。交通費は機関負担。
- 住居確保・生活契約支援:連帯保証人になる、社宅提供、物件探し補助等で住居確保を支援。住居は一定基準(一人7.5㎡以上等)を満たす必要あり。銀行口座開設、携帯契約、ライフライン契約等を補助。社宅提供の場合、敷金等は本人負担不可。
- 生活オリエンテーション:日本のルール、マナー、公共機関利用、災害時対応、相談窓口等を説明(目安8時間以上)。
- 公的手続等への同行:必要に応じ、役所での住民登録、社会保障・税金手続き等に同行・補助。
- 日本語学習の機会提供:日本語教室や教材の情報提供、手続き補助等を行う。
- 相談・苦情への対応:仕事や生活の悩み・苦情に母国語等で対応し、助言・指導、関係機関案内を行う。記録保管義務あり。
- 日本人との交流促進:地域住民との交流の場(祭り等)の情報提供や参加補助を行う。
- 転職支援(人員整理等の場合):機関都合での解雇時に、次の受入先探しを支援(求人情報提供、推薦状作成等)、関連手続きの情報提供を行う。
- 定期的な面談・行政機関への通報:支援責任者等が本人及び上司と3か月に1回以上面談。法令違反等があれば労基署等に通報義務あり。
これらの義務的支援に加え、任意的な支援(資格取得支援等)も推奨されます。支援の実効性は提供側の質と熱意に左右され、登録支援機関が受け入れ機関の意向を優先し、外国人本位の支援が疎かになる懸念も指摘されています。
特定技能の利用状況:データで見る現状(国籍・分野・地域別)
在留者数の推移と国籍・分野・地域の偏り
特定技能在留者数は急速に増加しています(2024年6月末時点 速報値)。
- 特定技能1号:約251,647人
- 特定技能2号:153人 1号は一貫して増加していますが、2号は依然として極めて少ない状況です。
国籍別(1号) では、ベトナムが約半数を占め、次いでインドネシア、フィリピン、ミャンマー、中国と続きます。 産業分野別(1号) では、飲食料品製造業、工業製品製造業が上位を占め、次いで介護、建設、農業となっています。 都道府県別(1号) では、愛知県が最も多く、大阪府、埼玉県、千葉県、東京都など、製造業等が盛んな地域や大都市圏及び近郊への集中が見られます。この地域偏在は、技能実習制度とも類似しており、既存の労働力移動パターンを強化している可能性があり、地域インフラへの負荷増大も懸念されます。
政府目標との比較:受け入れは進んでいる?
政府は2024年度からの5年間で新たに82万人の受け入れを見込んでいます。これは当初目標から大幅な引き上げであり、制度への依存度を高める方針を示しています。現状、多くの分野で見込み数を下回っていますが、全体の増加ペースは速いです。
特定技能制度が抱える課題:人権・転職・コスト・支援の質
人権侵害や搾取のリスクは?
技能実習制度からの移行者が多いことから、同制度で問題視された人権侵害や搾取が特定技能制度にも波及するリスクがあります。
- 労働条件の問題:低賃金、長時間労働、劣悪な環境、ハラスメント、労災、パスポート取上げ等の報告があります。
- 悪質な仲介者(ブローカー・送出し機関):来日前に高額な手数料や保証金を支払わされ、多額の借金を負うケースが後を絶ちません。これが不当な扱いへの抗議や転職を困難にさせ、搾取構造を生んでいます。
- 転職(転籍)の制限:同一分野内に限られる等の制約が、労働者を弱い立場に置く要因となり得ます。
「転職しやすさ」と「地域偏在」のジレンマ
転職の自由度向上は権利保護の観点からは前進ですが、地方や労働条件が厳しい企業から、より魅力的な都市部へ人材が流出する懸念があります。統計が示す通り、大都市圏とその周辺に集中しており、地方の人手不足を深刻化させる可能性も指摘されています。権利保障と安定的な労働力確保(特に地方・中小企業)のバランスが大きな論点です。
受け入れ企業の負担:コストと管理の手間
受け入れ企業には様々な費用・管理負担が生じます。採用関連費、申請関連費、支援関連費、初期費用、健康診断費、協議会費、帰国旅費などの金銭的コストに加え、複雑な申請手続き、支援計画の実施・管理(1号)、定期・随時報告義務といった管理的負担、さらに教育・研修、職場環境整備、離職リスクなどの育成・定着に関わる負担があります。これらは特に中小企業にとって重く、制度活用の障壁となり得ます。
支援の質は大丈夫?登録支援機関の課題
義務的支援制度は、その運用において質の担保が課題です。登録支援機関の質にはばらつきがあり、十分な支援が提供されないケースや、受け入れ企業の意向が優先される懸念があります。国の監督・指導体制の十分性や、労働者自身が情報や権利を知り、問題時に安心して相談できる窓口へのアクセス整備も重要です。
技能実習からの移行:連携と課題
技能実習からの移行は主要ルートですが、技能実習の職種と特定技能の分野が一致しない、技能実習での評価が形骸化し必要な技能を習得していない可能性がある、技能実習下の問題(借金、不信感等)が継続・再発するリスク、といった課題があります。
制度はどう変わる?最新動向と「育成就労制度」の新設
最近の主な変更点まとめ(分野追加・拡大など)
- 特定技能2号対象分野拡大(2023年):介護を除く11分野へ拡大。
- 特定技能1号新規分野追加(2024年):自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野を追加。
- 既存分野の改定:製造業統合・拡大、飲食料品製造業・外食業・造船業での業務範囲拡大等。
- 運用面の更新:5年間の受け入れ見込み数を82万人に再設定、申請様式等の更新、移行予定者への特例措置等。
新設!「育成就労制度」とは?技能実習からの変更点
技能実習制度に代わり、2024年6月に関連法が公布され、2027年までに施行される予定の新制度です。
- 目的:「人材確保」と「人材育成」を明確化。未熟練人材を3年で特定技能1号レベルへ育成。
- 対象分野:特定技能制度と原則一致させ、スムーズな移行を図る。
- 育成期間:原則3年。
- 転籍(転職):一定条件下(就労1年以上、試験合格等)で本人都合の転籍を認める(技能実習では原則不可)。
- 入国時の要件:一定の日本語能力(JLPT N5相当等)が求められる見込み。
- 支援・監理体制:監理団体は「監理支援機関」へ移行し、要件厳格化、人権保護重視へ。
特定技能制度への影響は?今後の展望
育成就労制度の導入により、育成就労→特定技能1号→特定技能2号という明確なキャリアパスが構築され、技能レベルの整合性向上が期待されます。また、転籍容認等で技能実習の問題点改善や、特定技能への人材供給増加の可能性もあります。一方で、転籍運用や監理支援機関の質などの新たな課題への対応も必要となります。
特定技能制度、どう評価する?関係者の声
政府・有識者会議の検討状況と提言
政府は技能実習制度の問題を認識し見直しを進め、有識者会議は2023年11月に育成就労制度創設などを提言。これを受け関連法が成立しました。
経済界(企業側)の見方と要望
経済界は人手不足から受け入れ拡大を支持し、育成就労制度に期待。一方、育成投資回収や人材定着、地域バランスへの配慮、過度な転籍緩和への懸念も表明。企業自身が魅力的な労働条件、支援、人権保護、キャリアパスを提供し、「選ばれる国」となる必要性を強調しています。
労働組合(労働者側)の懸念と主張
労働組合は、権利保護と労働条件確保を最重要視。育成就労制度では転籍の自由など労働者の権利保障を求め、日本人と同等以上の公正な労働条件を主張。国内労働市場への影響も注視し、相談・救済メカニズムの整備を訴えています。
支援団体(NPOなど)からの現場の声
JITCOは日本語習得の難しさを指摘。NPO/NGOなどは人権擁護の観点から批判的で、技能実習廃止や育成就労への懸念(根本問題未解決等)を示し、転職の完全自由、家族帯同、永住権などを要求。「生活者」としての権利と尊厳、共生の重要性を訴えています。
まとめ:特定技能制度の現状と未来への提言
特定技能制度は人手不足対応の主要政策として急速に拡大しましたが、2号への移行は限定的で、技能実習からの移行に伴う人権侵害リスクや悪質ブローカー問題、地域偏在、企業負担、支援の質などの課題が残ります。育成就労制度への移行は重要な改革ですが、その実効性が問われます。 制度の成功は、育成就労制度の実効性、特定技能2号への移行促進、地域・企業間格差是正、社会全体の受容性向上にかかっています。
以下の点を提言します。
- 監督・執行体制の強化:受け入れ機関・支援機関への実効性ある監査・指導、罰則強化。多言語相談・救済メカニズム拡充。労基署の監督強化。
- 悪質仲介者の排除と採用プロセス透明化:MOCを通じた手数料徴収規制・排除働きかけ。政府間採用ルート構築や透明な民間紹介プロセス促進。費用情報の透明化。国内違法業者取締強化。
- 特定技能2号への移行促進:移行障壁(試験、要件、支援不足等)の分析と改善策。学習支援や企業へのインセンティブ検討。キャリアパス情報提供強化。
- 地域偏在緩和と地方支援:地方就労インセンティブ検討・導入。自治体・経済団体・支援機関連携による地域別計画策定や支援体制強化への財政的・技術的支援。
- 中小企業への支援強化:手続き簡素化、費用助成、専門家活用補助、多言語対応支援等拡充。優良企業へのインセンティブ。
- 育成就労制度の適正な導入・運用:施行に向けた詳細な運用基準策定と厳格運用。施行後の継続的評価と柔軟な見直し。
特定技能制度と育成就労制度が、単なる労働力対策ではなく、外国人材が尊厳を持って働き、生活し、キャリアを形成でき、日本社会全体の活力向上に貢献する、持続可能で共生を志向した制度となるよう、関係者一体となった努力が求められます。
- 【格安代行】三重県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】京都府の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】佐賀県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】兵庫県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】北海道の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】千葉県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】和歌山県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】埼玉県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】大分県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】大阪府の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】奈良県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】宮城県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】宮崎県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】富山県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】就労ビザとは?外国人雇用のための完全ガイド
- 【格安代行】山口県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】山形県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】山梨県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】岐阜県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】岡山県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】岩手県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】島根県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】広島県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】徳島県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】愛媛県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】愛知県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】新潟県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】東京都の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】栃木県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】沖縄県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】滋賀県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】熊本県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】石川県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】神奈川県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】福井県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】福岡県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】福島県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】秋田県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】群馬県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】茨城県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】長崎県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】長野県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】青森県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】静岡県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】香川県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】高知県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】鳥取県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】鹿児島県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 日本での就労を目指す方へ:ビザ申請から生活情報まで完全ガイド
- 特定技能制度とは?制度の概要から課題、将来展望まで徹底解説
- 育成就労制度とは?外国人材と共生する新たな日本のカタチ