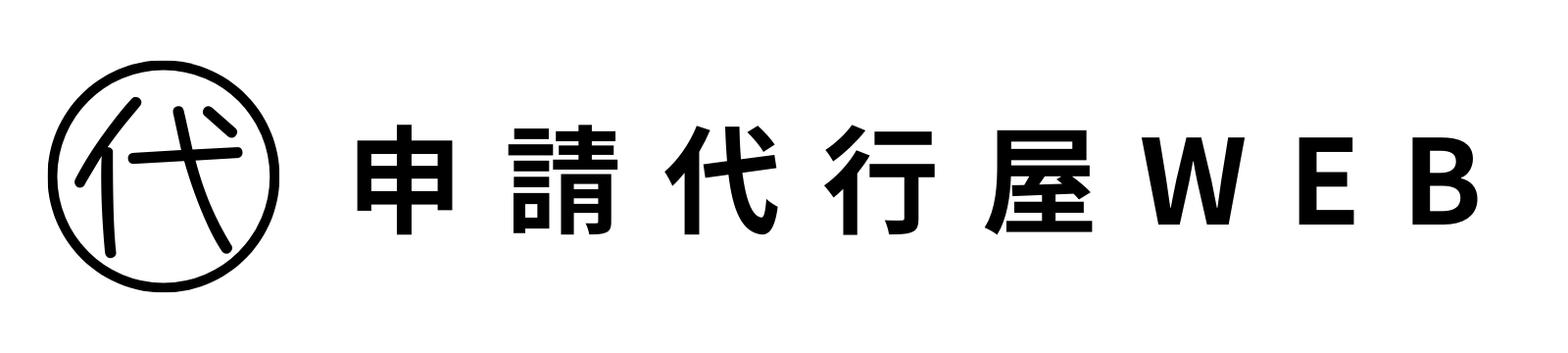愛知県内で道路に関連する工事、イベントの開催、看板や足場の設置などを計画している事業者や個人の皆様へ。道路を本来の交通目的以外で使用する場合、多くの場合、「道路使用許可」または「道路占用許可」、あるいはその両方の取得が必要となります。これらの許可は、道路の安全と円滑な交通を維持し、公共のインフラである道路を適切に管理するために不可欠な手続きです。
しかし、「道路使用許可と道路占用許可は何が違うの?」「どんな時にどちらの許可が必要?」「申請手続きはどうすればいい?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、愛知県における道路使用許可と道路占用許可について、運用実態に基づきながら、それぞれの目的、具体的な対象行為、申請手続きの流れ、必要書類、手数料、審査基準、管轄窓口などを網羅的に解説します。この記事を読むことで、愛知県内での道路利用に関する許可制度への理解を深め、スムーズな申請手続きを進めるための一助となれば幸いです。
\専門家がお手頃価格で代行/
道路使用許可/占用許可 愛知県でおすすめの行政書士事務所
🔵デコレート行政書士事務所

即日申請/道路使用の申請代行します
全国対応可能|市道、県道、国道、お任せください!
サービスの特徴
100件以上の実績!全国の道路許可申請に対応!
- 道路使用許可申請で100件以上の豊富な実績を持つ、行政書士事務所が対応
- 市道、県道、国道まで、全国どこでも相談可能
- 道路占用許可や24条申請にも対応
どの許可が必要か分からなくても安心!
- 足場設置や車両作業など、様々なシチュエーションに対応
- 作業内容を伝えるだけで、必要な許可を事務所が調査
- 希望通りの許可が難しい場合も、最も近い内容で提案
図面作成のみなら即日申請も可能!
- 図面作成のみの依頼は、即日でのスピード申請に対応
- 見積り後、購入から24時間以内に正式納品
- 納品後の軽微な修正や加筆は、回数無制限で無料対応
安心の料金体系で、高品質なサポートを!
- 道路許可:44,000円~
- 料金は事前の見積り相談で、納得の上で依頼可能
\ 今すぐチェック!! /
🔵行政書士Z法務事務所



道路占用許可・道路使用許可、申請代行します
大阪府近県対応!国道、施工承認もお任せください!
サービスの特徴
面倒な道路許可申請は、専門家におまかせ!
- 行政書士が申請書作成から作図、申請まで一括で代行
- 国道、施工承認、水路など、様々な許可申請に対応
幅広いエリア・状況に対応!
- 大阪府、京都府、兵庫県などの近畿エリアを幅広くカバー
- 記載のないエリアでも、相談次第で対応可能
- 足場設置や資材搬入など、あらゆる現場の状況に対応
どの許可が必要か分からなくても安心!
- 作業内容を伝えるだけで、必要な許可を無料で調査・提案
- 占用料なども事前に無料で調べてくれる
リピーター多数!迅速・丁寧な対応で高評価!
- 利用者から「迅速で確実」「丁寧でわかりやすい」と絶賛の声
安心の料金体系で、高品質なサポートを!
- 道路許可:45,000円~
- 料金は事前の見積り相談で、納得の上で依頼可能
- どの許可が必要か、占用料はいくらか、などの調査は無料で対応
\ 今すぐチェック!! /
🔵阿保行政書士事務所



道路使用許可申請代行致します
大阪、京都の道路使用許可はお任せください
サービスの特徴
大阪・京都の道路使用許可はおまかせ!
- 阿保行政書士事務所が、申請書作成から図面作成、申請代行まで対応
- 主な対応エリアは大阪府枚方市や京都府八幡市などで、エリア外も相談可能
図面作成も代行!手ぶらで相談OK!
- 依頼者は、工事や作業の内容が分かる資料を提示するだけ
- 位置図や交通安全対策図、工程表なども事務所で作成可能
基本料金+エリア別オプションの明確な料金体系!
- 道路使用許可の代行は、基本料金30,000円
- 京都府は+2,000円、大阪府は+2,000円~2,500円の追加オプション
- 報酬とは別に、申請手数料や交通費の実費が必要
安心の料金体系で、高品質なサポートを!
- 道路許可:30,000円~
- 料金は事前の見積り相談で、納得の上で依頼可能
\ 今すぐチェック!! /
🔵行政書士Wanvisa Office



道路使用許可申請書作成します
通信工事会社で申請担当歴10年の行政書士がサポートします
サービスの特徴
申請担当歴10年の行政書士がサポート!
- 通信工事会社で申請担当歴10年の、現場を知る行政書士が対応
- どのような申請や資料が必要か、専門家が調べて申請
工事からイベントまで!申請・受取をフルサポート!
- 道路工事、広告板の設置、露店、チラシ配りなど、様々な用途に対応
- 書類作成から警察への提出、許可書の受取、依頼者への送付まで全ておまかせ
大阪府が対象!まずは無料の見積り相談から!
- 対象地域は大阪府、その他の地域も相談可能
- 申請料は有料オプション(2,000円~)で対応、別途必要
安心の料金体系で、高品質なサポートを!
- 道路許可:25,000円~
- 料金は事前の見積り相談で、納得の上で依頼可能
\ 今すぐチェック!! /
道路使用許可とは?(道路交通法に基づく許可)
道路使用許可は、道路交通法第77条に関連し、所轄の警察署長等(高速道路の場合は高速道路交通警察隊長)が交付する許可です。その主な目的は、道路における「交通の安全と円滑を図る」ことにあります。
本来、道路は人や車が通行するためのものですが、一時的に交通以外の目的で道路を使用する必要が生じることがあります。そのような場合に、交通への支障を最小限に抑え、安全を確保するための条件を付けて許可を与えるのが道路使用許可制度です。
道路使用許可が必要となる主な行為
(道路交通法第77条第1項各号に関連する運用上の例)
- 1号許可関連:道路における工事や作業
- 道路工事(舗装、掘削、管路埋設など)
- 建築工事に伴う作業(資材搬入出、クレーン作業など)
- マンホール作業、架空線作業、高所作業車を用いた作業
- 測量、調査、街路樹の手入れ、清掃
- ロケーション撮影(映画、テレビ、CMなど)
- 移動採血車、レントゲン車等による作業
- 2号許可関連:工作物の設置
- 石碑、銅像、記念碑
- 広告板、看板、標識(私設)
- アーチ
- 工事用仮囲い、足場、落下物防護用施設(朝顔など)
- 街路灯、防犯カメラ(私設)
- 装飾(イルミネーション、旗、横断幕など)
- 舞台、やぐら
- 3号許可関連:場所を移動しない露店、屋台等
- 祭礼、イベント等における露店、屋台
- 路上での物品販売台の設置
- 4号許可関連:祭礼行事、イベント、集団行進等
- 祭礼(山車・神輿の巡行など)
- パレード、マラソン大会、歩行者天国
- デモ行進、集会
- 消防訓練、防災訓練
- 広告宣伝活動(チラシ配り等、場所を占有する場合)
愛知県特有の例としては、名古屋まつりや豊田おいでんまつりでの山車巡行(4号関連)、リニア中央新幹線関連工事や名古屋駅周辺再開発に伴う工事作業(1号・2号関連)などが挙げられます。
道路占用許可とは?(道路法に基づく許可)
道路占用許可は、道路法第32条に関連し、道路管理者(国、県、市町村など)が交付する許可です。こちらの主な目的は、「道路の構造を保全し、自由な通行を確保しつつ、道路空間の有効利用を図る」ことにあります。
道路の地上、地下、または上空に、電柱、看板、工事用足場、日よけ、地下埋設管といった工作物、物件、または施設(占用物件)を設け、「継続的に」道路を使用する場合に必要となります。
道路占用許可が必要となる主な占用物件
(道路法第32条、同法施行令第7条に関連する運用上の例)
- 電柱、電線、電話柱、公衆電話ボックス、郵便ポスト
- 水道管、下水道管、ガス管等の地下埋設管
- 鉄道、軌道
- 歩廊(アーケードなど)、雪よけ
- 突出看板、建植看板、広告塔
- 日よけ、雨よけ
- 工事用足場、仮囲い、敷鉄板(継続的な設置)
- 地下街、地下室、地下通路
- 露店、商品置場(継続的なもの)
- バス停留所標識、ベンチ(公共交通事業者等設置)
- パーキングメーター
愛知県の事例としては、商店街のアーケード設置や、各種インフラ(電気、ガス、水道)の地下埋設管などが考えられます。
道路使用許可と道路占用許可の主な違いと関係性
両許可の運用上の主な違いを表にまとめます。
| 項目 | 道路使用許可 (警察) | 道路占用許可 (道路管理者) |
|---|---|---|
| 関連法規 | 道路交通法関連 | 道路法関連 |
| 許可権者 | 所轄警察署長等 | 道路管理者(国、県、市町村等) |
| 主な目的 | 交通の安全と円滑の確保 | 道路の構造保全と機能維持、継続的な空間利用の管理 |
| 対象行為 | 一時的な行為(工事、作業、イベント等) | 継続的な物件設置・使用 |
| 継続性 | 一時的な利用が主 | 継続的な利用が前提 |
重要なポイント:両方の許可が必要なケース
工事用足場の設置や、道路上に看板を継続的に設置する場合のように、一つの行為が道路使用許可(作業や工作物設置)と道路占用許可(継続的な物件設置)の両方の要件に該当することが多くあります。この場合、原則として両方の許可を取得する必要があります。
このようなケースでは、申請手続きにおいて警察と道路管理者の連携・調整が不可欠となります。
愛知県における管轄行政機関
許可申請先は、道路の種類と所在地によって異なります。事前に必ず確認しましょう。
道路使用許可
- 一般道(国道、県道、市町村道):その道路の所在地を管轄する警察署の交通課
- 高速道路:高速道路交通警察隊
道路占用許可
- 国道(指定区間)
- 国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所 及びその管轄下の維持出張所
- 国道(指定区間外)
- 名古屋市内:名古屋市(主に各区土木事務所が窓口、緑政土木局道路管理課が全体調整)
- 名古屋市外:愛知県の管轄建設事務所
- 県道
- 名古屋市内:名古屋市(主に各区土木事務所が窓口、緑政土木局道路管理課が全体調整)
- 名古屋市外:愛知県の管轄建設事務所
- 市町村道
- 各市町村の道路管理担当部署(土木課、建設課など)
- 有料道路
- 各道路管理者(例:愛知道路コンセッション株式会社、愛知県道路公社)
愛知県における申請手続きの流れ
一般的な申請手続きの流れは以下の通りですが、詳細は必ず事前に管轄機関にご確認ください。
- 事前相談【最重要】
- 計画内容(目的、場所、期間、方法、設置物など)を固め、管轄の警察署と道路管理者の両方に相談します。
- 許可要件、必要書類、手数料/占用料、処理期間の見込み、注意点、特に両許可が必要な場合の調整方法などを確認します。
- 申請書類の準備・作成
- 後述する必要書類一式を準備します。
- 申請書様式は、各行政機関のウェブサイトからダウンロードするか、窓口で入手します。名古屋市では、一般用、工事施設用、突出看板用など、占用の種類に応じて様式が細分化されている場合があります。
- 位置図、平面図、構造図、交通規制図などの図面類は、指定に従い正確に作成します。
- 申請書の提出
- 道路使用許可
管轄警察署の交通課窓口へ。 - 道路占用許可
管轄道路管理者の窓口へ。 - 一括提出制度
両方の許可が必要な場合、事前相談の上、可能な場合は一方の窓口(警察署または道路管理者)に両方の申請書を一括提出できる場合があります。愛知県の建設事務所では、占用許可申請時に警察署への使用許可申請書も併せて提出する運用があります。ただし、一括提出は主に書類受付の利便性のためであり、書類不備等があれば結局もう一方の機関の窓口へ出向く必要がある場合もあります。
- 道路使用許可
- 審査
- 各許可権者が提出書類に基づき、審査基準に照らして審査を行います。
- 書類不備があれば補正指示があります。
- 必要に応じて現地調査や、警察と道路管理者間の協議が行われます。
- 手数料納付 / 占用料算定・納付
- 道路使用許可
許可証交付時に手数料(愛知県では原則2,500円、一部免除規定あり)を納付します。キャッシュレス決済または愛知県収入証紙で納付可能です。※令和6年6月以降、申請者により4号許可が有料となる可能性あり。 - 道路占用許可
申請自体に手数料は原則不要ですが、許可後に占用物件の種類、大きさ、場所、期間に応じた占用料の納付が必要です。道路管理者から送付される納入通知書に基づき納付します。
- 道路使用許可
- 許可証交付
- 審査の結果、基準を満たせば許可証が交付されます。
- 許可には期間、場所、方法、安全対策、原状回復などの条件が付されることが一般的です。
- 着手届・完了届の提出(占用・工事の場合)
- 道路占用許可や道路工事承認を受けた場合、工事着手前に「着手届」、完了後に「完了届」を道路管理者に提出する必要があります。完了後は検査が行われる場合があります。
愛知県での申請に必要な主な書類
必要書類は申請内容や管轄機関により異なるため、必ず事前相談で確認してください。様式は、愛知県警察、国土交通省(名古屋国道事務所)、愛知県(建設事務所)、名古屋市、その他市町村の各ウェブサイトからダウンロード可能です。各管轄機関の窓口で入手できます。
道路使用許可申請 (例)
- 道路使用許可申請書(2通)
- 位置図・見取図
- 平面図(使用範囲、作業帯、交通整理員の配置等)
- 交通規制図・う回路図(交通規制を行う場合)
- 安全対策図(保安設備の設置計画)
- 工程表
- 工作物の構造図・仕様書(2号許可関連の場合)
- 道路占用許可証(または申請書)の写し(占用許可も必要な場合)
- その他(イベント計画書、警備計画書など警察署長が必要と認める書類)
道路占用許可申請 (例)
- 道路占用許可申請書(協議書)(2通または3部、要確認)
- 位置図
- 公図の写し等
- 平面図(占用物件の位置、寸法、道路境界からの距離等)
- 横断図・縦断図
- 構造図・仕様書
- 占用求積図
- 道路復旧図面・復旧方法を示した図書(掘削する場合等)
- 保安設備図(安全対策図)
- 現況写真
- 理由書・工程表
- 道路使用許可申請書の写し(使用許可も必要な場合)
- その他(利害関係人の同意書、他法令の許可証写し等、道路管理者が必要と認める書類)
手数料、処理期間、審査基準、許可条件
手数料・占用料
- 道路使用許可手数料
- 愛知県では原則2,500円(キャッシュレス決済または県収入証紙)。
- 道路占用料
- 占用物件の種類、大きさ、場所、期間等に基づき算定されます。算定基準は国(道路法施行令)、愛知県(愛知県道路占用料条例)、各市町村(各市町村の道路占用料条例)がそれぞれ定めています。納入通知書により納付します。
標準的な審査・処理期間
これらはあくまで目安であり、申請内容、書類不備、関係機関との調整、混雑状況により変動します。余裕を持った申請を心がけましょう。
- 道路使用許可
- 愛知県警オンライン申請案内では「1週間(行政庁の休日を除く)ほど」とされていますが、実際にはこれ以上かかる場合もあります。書類補正や道路管理者との協議が必要な場合は更に日数を要します。
- 道路占用許可
- 国道(国交省)
原則として「3週間以内」。 - 県道等(愛知県)
標準「16日」(土日祝日・年末年始除く)。 - 名古屋市
通常「15日」程度(土日祝日、年末年始、補正期間、警察協議期間を含まず)。 - その他市町村:「2週間程度」から、内容や他の関係部署(例:水道課)との調整によりそれ以上かかる場合も。
- 国道(国交省)
審査基準
- 道路使用許可
(道路交通法第77条第2項に関連する運用)- 現に交通の妨害となるおそれがないか。
- 許可条件に従えば交通妨害のおそれがなくなるか。
- 交通妨害のおそれがあっても、公益上・社会慣習上やむを得ないか(祭礼など)。
- 具体的には、交通容量の確保、安全施設の機能阻害、迂回路の適切性などが審査されます。
- 道路占用許可
(道路法第33条第1項に関連する運用)- 占用許可対象物件であるか。
- 道路敷地外に余地がなく、やむを得ないか(必要不可欠性)。
- 占用期間、場所、構造等が法令基準(占用令基準)に適合するか。
- 具体的には、設置場所(交差点付近不可など)、構造の安全性、歩道有効幅員の確保、高さ制限、地下埋設管の深さなどが審査されます。
許可条件(例)
- 道路使用許可
- 許可期間・時間帯の遵守、交通誘導員の配置、保安資機材の設置、作業方法の指定、広報・周知、緊急連絡体制の確保など。
- 道路占用許可
- 占用料の納付、占用物件の維持管理責任(定期点検・報告義務含む)、期間満了・廃止時の原状回復義務、道路工事に伴う移設協力、変更時の届出義務など。
オンライン申請について
- 道路使用許可(愛知県警察)
- 警察庁「警察行政手続サイト」を通じて、過去に許可を受けた同一内容の再申請、記載事項変更届、再交付申請などが可能です。新規申請は原則窓口となります。手数料納付や許可証受領も窓口で行う必要があります。
- 道路占用許可(道路管理者)
- 国道(国交省)
専用の「道路占用システム」でのオンライン申請が可能です。 - 愛知県・市町村
統一的なオンライン申請システムは限定的です。一部市町村で着手届等がオンライン可能な場合もありますが、多くの場合、窓口申請が中心です。
- 国道(国交省)
申請書様式のダウンロードは各機関のウェブサイトで広く提供されています。
関連する他の許認可
大規模な工事などでは、道路使用・占用許可に加え、以下のような許認可が必要になる場合があります。 プロジェクト計画段階で、必要な許認可を漏れなく洗い出し、関係機関と調整することが重要です。
- 建築確認(建築基準法)
- 開発許可(都市計画法)
- 産業廃棄物処理計画書/報告書、建設リサイクル法届出
- 騒音・振動規制法に基づく特定建設作業実施届出
- 河川法、港湾法、文化財保護法に基づく許可・届出
- 屋外広告物許可
まとめ:愛知県でのスムーズな許可取得のために
愛知県内で道路使用許可・道路占用許可を申請する際は、以下の点を心掛けてください。
- 早期の許可要否と管轄特定:計画の早い段階で必要な許可と管轄機関を正確に把握する。
- 徹底した事前相談【最重要】:必ず関係する警察署・道路管理者の双方に事前相談を行い、最新・正確な情報を得る。
- 正確・完全な書類準備:不備がないよう、指定通りに書類・図面を作成する。
- 十分な期間の確保:標準処理期間は目安と考え、補正や協議の時間も考慮し、余裕をもって申請する。
- 許可条件の理解と遵守:交付された許可条件をよく理解し、遵守する計画を立てる。
- 情報の直接確認:特に処理期間、オンライン申請の可否、必要部数などは、必ず管轄機関に直接確認する。
- 関連許認可の確認:プロジェクト全体で必要な他の許認可も早期に確認する。
- 専門家活用の検討:複雑な案件では、行政書士などの専門家の活用も有効です。
道路は皆が利用する大切な公共インフラです。ルールを守り、適切な手続きを行うことで、安全かつ円滑な道路利用を実現しましょう。本記事が、愛知県における道路使用許可・道路占用許可申請の一助となれば幸いです。
愛知県内のサービス提供地域
愛知県の道路使用許可/道路占用許可サポートサービスは、愛知県内全域に対応しております。お客様のお住まいの地域を問わず、まずはお気軽にご相談ください。
愛知県
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村
上記に記載のない地域、またはサービスの詳細な対応エリアについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
参考資料
コラム:愛知県警とは
日本有数の人口を擁し、自動車産業をはじめとする「ものづくり産業」が集積する愛知県。その活発な社会経済活動と、約750万人の県民の安全・安心な暮らしを守るためには、多様化・複雑化する様々な事案に的確に対応できる強力な警察組織が不可欠です。「愛知県警察」、通称「愛知県警」は、多くの専門部署が有機的に連携することで、その責務を果たしています。
事件・事故に対応する専門部署の役割
愛知県警の組織内には、それぞれの分野における専門的な知識や捜査技術、経験を持つ部署が設置されています。例えば、殺人・強盗・誘拐といった凶悪犯罪から、日常的に発生する窃盗や詐欺事件まで、あらゆる犯罪の捜査と犯人検挙を担当する「刑事部」。ストーカーやDV(配偶者等からの暴力)、児童虐待、少年非行問題、そして近年増加するサイバー犯罪への対策などを担う「生活安全部」。交通指導取締りや交通事故捜査、運転免許に関する業務を行う「交通部」。テロ対策や災害発生時の警備、要人警護などを担当する「警備部」などが、それぞれの専門性を発揮しています。
組織的な連携と地域に根差した活動
これらの専門部署は、単独で活動するだけでなく、事案に応じて互いに情報を共有し、緊密に連携することで、複雑な事件や大規模な事故・災害にも組織全体として対応します。そして、こうした警察活動の基盤となり、県民に最も近い場所で活動しているのが、県内各地の警察署や交番・駐在所に勤務する「地域警察官」です。彼らは日々のパトロールや巡回連絡、遺失物・拾得物の取り扱い、各種相談などを通じて地域の実情を把握し、県民と警察を結ぶ重要な役割を果たしています。
コラム:名古屋国道事務所とは
愛知県内を走り、人々の生活や物流を支える重要な幹線道路網の一部である国道。その中でも国が直接管理する区間の整備や維持管理といった業務を担っているのが、国土交通省 中部地方整備局の出先機関である「名古屋国道事務所」です。今回は、私たちの暮らしと経済活動に不可欠な国道の安全と円滑な交通を守る、名古屋国道事務所の主な役割と業務内容についてご紹介します。
国道の整備・改築と維持管理、防災対策
名古屋国道事務所の中心的な業務は、管轄する愛知県内の国道(例えば国道1号、19号、23号、41号などの一部区間)について、計画的な整備・改築工事を実施すること、そして日々の適切な維持管理を行うことです。道路の拡幅やバイパス整備、老朽化した橋梁の補修・架け替え、路面の補修、道路標識の管理、除草や清掃などを通じて、安全で快適な道路環境を確保しています。また、大雨による冠水や土砂災害、地震など、自然災害から道路を守り、通行の安全を確保するための防災対策や、交通事故を未然に防ぐための交通安全対策も重要な任務です。
道路情報の提供と許認可事務
道路を安全・円滑に利用してもらうためには、適切な情報提供が欠かせません。名古屋国道事務所では、管内道路の工事に伴う交通規制の情報や、大雨・大雪・事故などによる通行止め情報を、公式ウェブサイトや道路情報提供システムなどを通じて、リアルタイムに発信しています。さらに、国道敷地内で工事を行う場合や、電柱・水道管・ガス管などを設置する場合、あるいは看板や日よけなどを設置する際に必要となる「道路占用許可」などの許認可に関する手続きの窓口ともなっており、国道の適正な利用と管理を図っています。
コラム:道路交通法とは
自動車やバイク、自転車の運転者、そして歩行者など、道路を利用するすべての人に関わる最も身近な法律の一つが「道路交通法」(略称:道交法)です。私たちが日々安全に道路を使い、円滑な交通社会を維持するための基本的なルールが定められています。今回は、私たちの暮らしに不可欠なこの法律の目的と、定められている主な内容について解説します。
道路交通法の目的:危険防止と安全・円滑な交通の確保
道路交通法の第一条には、その目的が明確に記されています。それは、「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害(交通公害など)の防止に資すること」です。この大きな目的を達成するために、歩行者はどのように道路を通行すべきか、自動車や自転車はどのように走り、どこに停めるべきか、運転者が守るべき義務は何か、そして信号機や道路標識の意味、交通事故が起きた場合の措置、違反した場合の罰則など、道路交通に関する非常に広範なルールが具体的に定められています。
すべての道路利用者が守るべきルールと法改正
信号の色に従って進んだり止まったりすること、指定された最高速度を守ること、横断歩道では歩行者を優先すること、シートベルトやヘルメットを正しく着用すること、そして飲酒運転や無免許運転が絶対に許されないことなどは、道路交通法で定められた基本的なルールのほんの一部です。この法律は、自動車技術の進歩(自動運転技術など)や、新たな乗り物(電動キックボードなど)の登場、社会問題化する交通事象(あおり運転など)に対応するため、時代の変化に合わせて頻繁に改正が行われています。すべての道路利用者が常に最新の交通ルールを正しく理解し、それを守ることが、安全で円滑な交通社会を実現するための基本となります。
コラム:道路法とは
私たちが日々利用している「道路」。その構造や管理、費用負担など、道路というインフラそのものに関する基本的なルールを定めているのが「道路法」です。信号機の意味や通行方法といった交通ルールを定める「道路交通法」とは目的も内容も異なります。今回は、私たちの社会基盤を支える道路法の役割について解説します。
道路の種類と管理者を定めるルール
道路法はまず、全国に張り巡らされた道路網を機能や重要性に応じて「高速自動車国道」「一般国道」「都道府県道」「市町村道」という4つの種類に分類しています。そして、それぞれの種類の道路について、誰がその道路を管理する責任者(道路管理者)となるかを定めています。例えば、高速自動車国道や指定された区間の一般国道は国(国土交通大臣)が、都道府県道は都道府県が、市町村道は市町村が、原則として道路管理者となります。道路の新設や改築、維持、修繕といった管理は、この道路管理者が責任を持って行うことになっています。
道路の構造基準と占用に関するルール
道路法は、道路の種類と管理者を定めるだけでなく、道路が安全で円滑な交通を確保できる構造を持つための技術的な基準についても規定しています(具体的な基準は政令等で定められます)。また、道路は誰もが通行できる公共の空間ですが、電気・ガス・水道などの管路の埋設、工事用足場の設置、看板や日よけの設置などで道路の一部を使用(占用)する場合には、道路管理者の許可が必要です。道路法では、この「道路占用」に関する許可の基準や手続き、占用料などについてもルールを定めており、道路の適正な利用と管理を図っています。
- 【格安代行】三重県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】京都府の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】佐賀県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】兵庫県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】北海道の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】千葉県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】和歌山県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】埼玉県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】大分県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】大阪府の道路使用許可/道路占用許可を徹底解説!【2万5千円~】
- 【格安代行】大阪府の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】奈良県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】宮城県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】宮崎県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】富山県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】山口県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】山形県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】山梨県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】岐阜県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】岡山県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】岩手県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】島根県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】広島県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】徳島県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】愛媛県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】愛知県の道路使用許可/道路占用許可を徹底解説!【2万5千円~】
- 【格安代行】愛知県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】新潟県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】東京都の道路使用許可/道路占用許可を徹底解説!【2万5千円~】
- 【格安代行】東京都の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】栃木県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】沖縄県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】滋賀県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】熊本県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】石川県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】神奈川県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】福井県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】福岡県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】福島県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】秋田県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】群馬県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】茨城県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】道路使用許可/道路占用許可とは?申請手続きと違いを徹底解説【2万5千円~】
- 【格安代行】長崎県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】長野県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】青森県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】静岡県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】香川県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】高知県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】鳥取県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】鹿児島県の道路使用許可でおすすめの行政書士