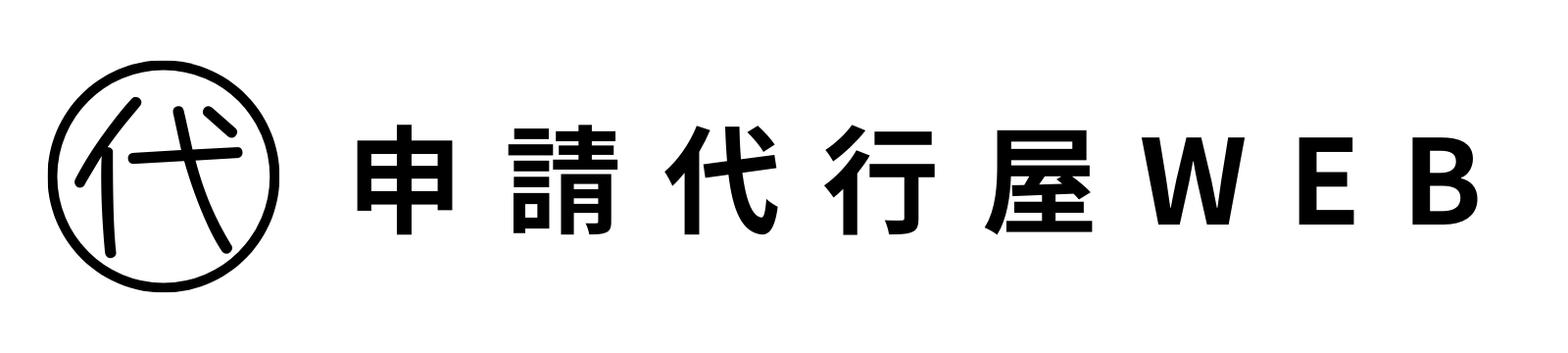建設業界で事業を営む上で、「建設業許可」は非常に重要な意味を持ちます。一定規模以上の建設工事を請け負うためには、この許可が法的に義務付けられており、無許可での営業は厳しい罰則の対象となります。建設業許可制度は、建設業者の資質向上、工事の適正な施工の確保、そして発注者の保護を目的として設けられています。信頼性のある事業者として活動し、事業を拡大していくためには、建設業許可の取得と適切な維持管理が不可欠です。
この記事では、建設業許可制度の基本から、具体的な取得要件、申請手続き、許可取得後の義務、さらには最近の法改正の動向まで、建設業許可に関する情報を網羅的に解説します。これから建設業許可の取得を目指す方、すでに許可をお持ちで更新や管理について確認したい方にとって、必読の内容となっています。
\専門家がお手頃価格で代行/
建設業許可 千葉県でおすすめの行政書士事務所
🔵難波行政書士事務所

申請実績150社以上!建設業許可申請書作ります
許可が下りなければ全額返金!最短2日で申請書作成します!
サービスの特徴
面倒な書類作成は、専門家におまかせ!
- 100社以上の申請実績を持つ行政書士が、通る建設業許可申請書を作成
- 万が一、許可が下りなければ全額返金という安心の保証付き
建設業許可のあらゆる手続きに対応!
- 新規申請はもちろん、更新、業種追加、変更届まで幅広く対応
- 全国どこからの依頼でもOK
あなたの手間は最小限!とにかく楽でスピーディ!
- 依頼後はチェックリストに回答するだけ 専門家がスピーディーに書類を作成
- 最短2日で申請書を作成する、そのスピードと正確さに自信あり
豊富な実績が信頼の証!
- これまで100社以上の許可申請をサポートしてきた圧倒的な経験値
- 利用者からは「とても丁寧な対応」という満足の声
専門家への依頼がこの価格で!
- 行政書士による知事新規申請の書類作成が、この価格で実現
- 新規知事免許:10万円~
- 許可要件の相談は無料で対応
\ 今すぐチェック!! /
🔵行政書士茶屋英博事務所



建設業許可・経審・決算変更の書類作成代行承ります
新規取得応援キャンペーン中「建設業の許可票」プレゼント実施中
サービスの特徴
建設業許可・経審の専門家が、徹底サポート!
- 建設業許可と経審を専門とする行政書士が、親身に寄り添って対応
- 自分で申請して拒否された方や、元請けに許可取得を求められた方も相談OK
- 事前の連絡で、土日や夜間の相談も可能
新規取得応援!「建設業の許可票」プレゼント!
- 新規で許可を取得した方には、「建設業の許可票」をプレゼント
- 万が一、不許可処分となった場合は、報酬を全額返金する安心の保証付き(※)
- (※依頼者側の虚偽申告などを除く)
取得後も安心!充実のアフターサービス!
- 5年ごとの更新手続きや、毎年の決算変更のアラートでお知らせ
- 度々おこる法令変更にも、コンサル付きで対応
まずは無料の要件診断・見積りから!
- 最初に許可が取れるかどうかの要件診断を行い、無料で見積りを提示
- 書類が揃えば、最短1日でのスピード申請も可能
- 申請手数料(新規9万円~)や証明書取得実費などは、報酬とは別途必要
専門家への依頼がこの価格で!
- 行政書士による知事新規申請の書類作成が、この価格で実現
- 新規免許:12万円~
- 許可要件の相談は無料で対応
\ 今すぐチェック!! /
🔵行政書士事務所みらい



建設業許可申請書の作成をサポートします
建設業の経営者様必見!行政書士が書類作成をサポートします。
サービスの特徴
全国対応!建設業の許可申請をサポート!
- 行政書士が、建設業許可申請書の作成をサポート
- 全国の建設業の経営者様に対応
書類を送るだけのシンプル手続き!
- 依頼者は、指定された書類の返送や、メール・電話での情報提供だけでOK
- 有料オプションで、早期完成も可能
まずは無料の見積り相談から!
- 依頼前には、まず見積り・カスタマイズの相談から
- 申請手数料90,000円は、報酬とは別途必要
- 契約時には、情報提供の協力などに関する誓約書の提出が必要
専門家への依頼がこの価格で!
- 行政書士による知事新規申請の書類作成が、この価格で実現
- 新規免許:9万円~
- 許可要件の相談は無料で対応
\ 今すぐチェック!! /
建設業許可とは?その基本を理解する
建設業許可制度の目的と法的根拠
建設業許可制度は、建設業法(1949年法律第百号)に基づいて設けられています。その主な目的は以下の通りです。
- 建設業を営む者の資質向上
- 経営能力や技術力に関する一定の基準を設けることで、質の高い建設業者を育成します。
- 建設工事の請負契約の適正化
- 不適切な契約や取引を防ぎ、公正な競争環境を整備します。
- 建設工事の適正な施工の確保
- 技術基準を満たした業者による施工を確保し、工事の品質と安全性を高めます。
- 発注者の保護
- 信頼できる業者に工事を発注できるよう、許可制度を通じて情報を提供します。
- 建設業の健全な発達と公共の福祉増進
- 業界全体のレベルアップを図り、社会インフラの整備に貢献します。
歴史的に見ると、建設投資の増加に伴い、技術力や経営基盤に問題のある業者による粗雑工事や事故が発生したこと、不公正な競争による倒産の増加、国際競争力の強化といった課題に対応するため、許可制度が導入・強化されてきました。
建設業許可が必要なケースとは?
建設業法における「建設業」とは、元請・下請の別や名義を問わず、建設工事の完成を請け負う営業を指します。法人・個人事業主を問わず、建設業を営む場合は、原則として国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。
許可を受けずに営業した場合(後述の軽微な工事を除く)、建設業法第47条に基づき、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに注意すべき点として、法人の代表者や従業員等が違反行為を行った場合、法人自身に対しても最大1億円以下の罰金が科される両罰規定(建設業法第53条)が存在します。これは極めて重い罰則であり、コンプライアンス遵守の観点からも許可取得は必須と言えます。
許可が不要な「軽微な建設工事」
例外として、以下の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
- 建築一式工事以外
- 工事1件の請負代金(消費税込み)が500万円未満の工事。
- 建築一式工事
次のいずれかに該当する工事。- 工事1件の請負代金(消費税込み)が1,500万円未満の工事。
- 請負代金の額にかかわらず、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事。
- 「木造」とは主要構造部が木造のもの。
- 「住宅」とは、専用住宅、共同住宅、店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)を指します。
【軽微な工事に関する注意点】
- 契約分割
正当な理由なく契約を分割しても、合計額で判断されます。許可逃れを目的とした分割は認められません。 - 材料提供
注文者が材料を提供する場合(材工分離)、その材料の市場価格と運送費を請負代金に 加算して判断する必要があります。契約金額だけではなく、実質的な工事規模で判断することが重要です。 - 消費税
上記金額は消費税込みの金額です。 - 未満
500万円「未満」、1,500万円「未満」であるため、ちょうど500万円、1,500万円の工事は軽微な工事には該当せず、許可が必要です。
その他の許可不要ケース
上記の軽微な工事以外にも、建設業法の「建設工事の完成を請け負う営業」に該当しないため、許可が不要な場合があります。
- 自社で使用する建物を自ら建設する工事(自社施工)。
- 不動産業者が販売目的の建売住宅を自社で建設する工事。
- 船舶や航空機など、土地に定着しない工作物の製造・修理。
- 建設工事に該当しない作業(樹木の剪定、除草、清掃、保守点検、測量、設計、資材運搬、地質調査、警備など)。
附帯工事について
許可を受けた建設業(主たる工事)に係る建設工事を請け負う場合、その工事に附帯する他の建設業種の工事(附帯工事)であれば、その附帯工事の業種の許可がなくても請け負うことができます。
【附帯工事の条件】
- 主たる工事を施工するために必要不可欠な工事であること。
- それ自体が独立した使用目的を持つものではないこと。
- 通常、附帯工事の請負金額が主たる工事の金額より少ないこと。
【具体例】
- 電気工事(主)に伴う内装仕上げ工事(壁紙復旧など)
- 外壁塗装工事(主)に伴う足場設置工事(とび・土工)
- 建具工事(主)に伴う左官工事(玄関土間の補修など)
この規定は実務上の利便性を考慮したものですが、あくまで主たる工事との関連性が前提です。独立した工事や主たる工事より規模が大きい工事を附帯工事として無許可で行うことはできません。判断が難しい場合は、行政庁や専門家への確認、または関連業種の許可追加取得を検討しましょう。
建設業許可の種類と区分を理解する
建設業許可は、事業者の営業形態や規模に応じて、いくつかの種類と区分に分けられます。自社に必要な許可の種類を正確に把握することが、申請の第一歩です。
大臣許可と知事許可:営業所の設置場所で決まる
この区分は、建設業を営む営業所の所在地のみで判断されます。
- 国土交通大臣許可(大臣許可)
- 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合に必要です。実際の申請手続きは、本店所在地を管轄する地方整備局長等が行います。
- 都道府県知事許可(知事許可)
- 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合に必要です。営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可権者となります。
【営業所の定義】
建設業法上の「営業所」とは、単なる連絡所や作業所ではなく、以下の要件を満たす実質的な活動拠点を指します。
- 本店または支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所であること。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
- 契約締結権限を持つ使用人(支配人など)が常勤していること。
- 電話、机、事務スペース等の物理的な施設を有していること。
- 営業所技術者等が常勤していること。
【よくある誤解】
- 「大臣許可なら全国で工事できるが、知事許可は許可県内のみ」
→ 誤り。どちらの許可でも、工事を行う地域に制限はありません。 - 「大臣許可の方が取得が難しい/信頼性が高い」
→ 誤り。許可の種類による優劣はありません。営業所の展開状況のみで決まります。
ただし、申請先が異なるため、申請手数料(大臣許可が高い)や審査期間(大臣許可が長い)などには差があります。
一般建設業と特定建設業:下請契約の規模で決まる
この区分は、元請負人として受注した工事を下請に出す際の、下請代金の規模によって決まります。下請負人の保護と大規模工事の適正な施工確保が目的です。
- 特定建設業許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事について、下請契約の請負代金合計額が以下の基準額以上となる下請契約を締結して施工する場合に必要となります。金額要件は法改正により見直されており、契約締結日に注意が必要です。- 【2025年2月1日以降に締結される契約】
- 建築工事業以外
5,000万円(消費税込み)以上 - 建築工事業
8,000万円(消費税込み)以上
- 建築工事業以外
- 【2025年1月31日までに締結された契約】
- 建築工事業以外
4,500万円(消費税込み)以上 - 建築工事業
7,000万円(消費税込み)以上
- 建築工事業以外
- 【2025年2月1日以降に締結される契約】
- 一般建設業許可
- 上記の特定建設業許可が必要となるケース以外の場合です。元請として大規模工事を受注しても、下請への発注総額が上記基準未満であれば、一般建設業許可で足ります。
特定建設業許可は、元請としての重い責任を担う能力を担保するため、後述する許可要件(特に財産的基礎、営業所技術者等の資格)が一般建設業よりも厳しくなっています。
【注意点】
- 一つの業種について、一般と特定の両方の許可を取得することはできません。特定を取得すると、その業種の一般許可は失効します。
- 最初は一般許可で事業を開始し、後に特定許可が必要になった場合は、「般・特新規」として申請します。
- 特定建設業の要否判断における下請代金には、元請が提供する資材費は含みません。消費税は含みます。
業種別許可制:29種類の工事区分
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に取得する必要があります。建設業法では、工事を以下の29種類に分類しています。
- 一式工事 (2種類)
- 土木一式工事、建築一式工事
- 専門工事 (27種類)
- 大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体
営業しようとする業種の許可をそれぞれ取得する必要があります。複数の業種を同時に申請したり、後から追加することも可能です。
【注意点】
- 大臣許可と知事許可を業種によって使い分けることはできません。全ての業種で同じ許可行政庁(大臣or知事)、同じ区分(一般or特定)となります。
- 「一式工事」の許可は、個別の専門工事の許可を包含しません。一式工事は、総合的な企画・指導・調整のもとに行われる大規模・複雑な工事を想定しています。例えば、建築一式許可を持っていても、その中で行う専門工事(例:大工工事)の請負金額が500万円以上になる場合は、原則として大工工事の許可も別途必要です。
自社の事業内容を正確に把握し、必要な業種の許可を漏れなく取得することが重要です。
許可の有効期間:5年間
建設業許可の有効期間は、許可があった日から 5年間 です。有効期間は、許可日から満5年を経過する日の前日をもって満了します。例えば、2025年4月1日に許可を受けた場合、有効期間は2030年3月31日までとなります。
【注意点】
- 有効期間の満了日が行政機関の休日に当たっても、期間は延長されません。
- 有効期間が満了すると許可は 自動的に失効 します。
- 引き続き営業するには、有効期間満了前に 更新手続き が必要です。更新を怠ると、軽微な工事以外は請け負えなくなり、事業継続に深刻な影響が出ます。
許可の有効期間管理は、建設業者にとって極めて重要な業務です。
建設業許可を取得するための6つの要件
建設業許可を取得するには、建設業法に定められた以下の6つの主要な要件をすべて満たす必要があります。これらの要件は、建設業者が適正な経営を行い、質の高い工事を確実に施工する能力があることを担保するために設けられています。
1. 経営業務の管理体制(経管の配置)
【内容】
建設業の経営に関して一定の経験を持つ人物(経営業務の管理責任者、通称「経管」)を、役員等の中に常勤で配置する必要があります。これは、建設業特有の複雑な経営(資金調達、資材購入、技術者配置、契約締結、施工管理など)を適切に行う能力を担保するためです。
【基準】
法人の場合は常勤役員の1人、個人事業主の場合は本人または支配人の1人が、以下のいずれかの経験を有することが必要です。
- 許可を受けたい建設業種に関して、5年以上の経営業務管理責任者としての経験。
- 許可を受けたい建設業種以外の建設業種に関して、6年以上の経営業務管理責任者としての経験。(※法改正により7年から短縮されました)
- 許可を受けたい建設業種に関して、経営業務管理責任者に準ずる地位での経験:
- 執行役員等として5年以上、経営業務を総合的に管理した経験。
- 経営業務を補佐した経験が6年以上。(※法改正により7年から短縮されました)
- 上記1~3と同等以上の能力があると国土交通大臣が認定した者。
「常勤」とは、本社等で休日を除き毎日所定時間勤務し、その職務に専従していることを指します。
【証明方法】
- 常勤性
- 健康保険証の写し、住民票など。
- 経営経験
- 法人役員経験
商業登記簿謄本、建設業許可通知書写し、工事請負契約書など。 - 個人事業主経験
確定申告書(第一表・第二表)、工事請負契約書など。 - 準ずる地位・補佐経験
組織図、業務分掌規程、取締役会議事録、人事発令書、工事請負契約書など、地位・業務内容・期間を証明する書類。
- 法人役員経験
- 申請様式
- 常勤役員等証明書(様式第7号)、常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙)など。
経営経験の証明、特に役員以外の地位での証明は、客観的な資料で実質的な関与を示す必要があり、許可申請の重要なポイントとなります。
2. 営業所技術者等の配置(旧:専任技術者)
【内容】
許可を受けたい建設業種ごとに、その業種に関する一定の資格または経験を持つ技術者を、営業所ごとに常勤で配置する必要があります。これは、各営業所で契約や施工に関する技術的な判断を適正に行うためです。
注: 2024年12月13日より、「専任技術者」から「営業所技術者等」(一般許可は「営業所技術者」、特定許可は「特定営業所技術者」)に呼称が変更されました。
【基準】
一般建設業と特定建設業で要件が異なります。
<営業所技術者(一般建設業)> 以下のいずれかに該当する者が必要です。
- 国家資格保有者
業種に対応した国家資格(施工管理技士、技術士、建築士、電気工事士など)を持つ者。 - 学歴+実務経験
指定学科(土木工学、建築学等)を卒業し、一定期間(大学・高専卒は3年以上、高校卒は5年以上)の実務経験を持つ者。 - 実務経験
業種に関して10年以上の実務経験を持つ者。 - 技術検定第一次検定合格+実務経験
(2023年7月緩和)1級一次合格者は大学卒相当(3年実務)、2級一次合格者は高校卒相当(5年実務)とみなされます(一部業種除く)。 - 複数業種の実務経験
国が定める複数業種で一定期間経験がある場合、年数短縮あり。 - 大臣認定
上記と同等以上の能力があると認められた者。
<特定営業所技術者(特定建設業)>
一般より厳しい要件です。以下のいずれかに該当する必要があります。
- 1級国家資格等保有者
業種に対応した1級の国家資格等(1級施工管理技士、1級建築士、技術士など)を持つ者。原則2級は不可。 - 指導監督的実務経験者
一般の営業所技術者要件を満たし、かつ元請として請負代金額が以下の基準を満たす工事で2年以上の指導監督的実務経験(現場代理人、主任技術者等)を持つ者。金額要件は契約締結日により異なります。- 【2025年2月1日以降に締結される契約に基づく経験】
5,000万円(税込)以上 - 【2025年1月31日までに締結された契約に基づく経験】
4,500万円(税込)以上
- 【2025年2月1日以降に締結される契約に基づく経験】
- 大臣認定
上記1、2と同等以上の能力があると認められた者。 - 指定建設業の特例
特に高度な技術が求められる7業種(土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)は、上記1(1級資格等)または3(大臣認定)の者でなければならず、指導監督的実務経験のみでは認められません。
営業所技術者等は、その営業所に常勤し、原則として専任(他の営業所との兼務不可)である必要があります。ただし、以下の現場兼務緩和措置があります。
【証明方法】
- 常勤性
健康保険証の写し、住民票など。 - 資格・学歴
合格証・免許証写し、卒業証明書など。 - 実務経験
実務経験証明書(様式第9号)、指導監督的実務経験証明書(様式第10号、特定の場合)。裏付けとして契約書、注文書、請求書写しなどが必要な場合あり。 - 申請様式
営業所技術者等証明書(様式第8号)、営業所技術者等一覧表(様式第1号別紙4)など。
実務経験の証明は、期間だけでなく内容の適合性や常勤性の確認も重要です。
【現場兼務の緩和(2024年12月13日施行)】
生産性向上と技術者不足対応のため、以下の要件等を満たす場合に、営業所技術者等が現場の主任技術者・監理技術者(専任配置が必要な工事)を兼務できるようになりました。
- 対象工事
所属営業所が契約した工事であること。 - 工事規模
請負代金額1億円未満(建築一式は2億円未満)。 - 兼務現場数
営業所での職務に加え、兼務できる現場は1現場のみ。 - 近接性・連絡体制
営業所と現場間が近接し(例: 移動時間往復2時間目安)、常時連絡が取れ、必要に応じ速やかに移動できること。また、現場に連絡員を配置すること。 - ICT環境
営業所からWeb会議システム等を用いて現場状況を遠隔で確認・指示でき、CCUS(建設キャリアアップシステム)連携等により作業員の状況をリアルタイムで把握できる環境が整備されていること。 - 下請次数
兼務対象工事の下請契約の次数が原則として3次以内であること。 - 体制把握・計画
CCUS等を活用した施工体制の遠隔把握、人員配置やICT活用に関する具体的な計画の作成・保存がなされていること。
この緩和措置を活用するには、ICT環境の整備やリスク管理体制の構築が不可欠であり、国土交通省のガイドライン等を遵守する必要があります。
3. 誠実性
【内容】
許可申請者(法人、個人事業主、役員等)及びその主要な使用人(支店長、営業所長等)が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが 明らかでない ことが求められます。建設業は信用が重視されるためです。
【対象者】
法人自身、役員等、政令使用人、個人事業主本人、政令使用人。
【基準】
- 「不正な行為」
契約締結・履行時の詐欺、脅迫、横領など。 - 「不誠実な行為」
工事内容、工期等に関する契約違反。 - 過去にこれらの行為があった場合や、他法令(建築士法等)で免許取消処分等を受け5年未経過の場合などは、誠実性に欠けると判断される可能性があります。
【証明方法】
- 誓約書(様式第6号)
- 調書(様式第12号、第13号)
- 役員等の身分証明書(本籍地発行)
- 商業登記簿謄本(法人の場合)
抽象的ですが、過去の法令遵守状況や契約履行状況が確認されます。
4. 財産的基礎又は金銭的信用
【内容】
請け負った工事を完成させるために必要な経済的な基盤や信用力があることが求められます。工事着手には準備資金が必要なためです。
【基準】
一般建設業と特定建設業で大きく異なります。
<一般建設業> 申請時に、以下のいずれかを満たすこと。
- 自己資本(純資産合計)が500万円以上。
- 500万円以上の資金調達能力(金融機関発行の預金残高証明書等で証明)。
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績(更新申請など)。
<特定建設業>申請時(直前の決算期)に、以下のすべてを満たすこと。
- 欠損の額が資本金の20%を超えない。
- 流動比率が75%以上((流動資産 ÷ 流動負債) × 100)。
- 資本金の額が2,000万円以上。
- 自己資本(純資産合計)が4,000万円以上。
【証明方法】
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)(様式第15号~第19号)。
- 預金残高証明書(一般で資金調達能力証明の場合、基準日から1ヶ月以内)。
- 納税証明書(提出を求められる場合あり)。
- 建設業許可通知書写し(一般で過去実績証明の場合)。
特定建設業の要件は非常に厳格で、元請としての財務体力が求められます。一般でも最低限の経営基盤が必要です。これらの要件は更新時にも維持する必要があります。
5. 欠格要件に該当しないこと
【内容】 建設業法第8条等に定められた、建設業を営む上で不適格とされる事由(欠格要件)に、申請者や役員等が 該当しない ことが必要です。一つでも該当すると、他の要件を満たしても許可は受けられません。
【対象者】
申請者本人(法人含む)、役員等、個人事業主、支配人、令3条使用人、法定代理人、実質的な支配力を持つ株主等も含まれる場合があります。
【主な欠格要件】
- 申請書類への虚偽記載・重要事実の記載漏れ。
- 成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ない者。
- 不正手段による許可取得等を理由に許可を取り消され、5年経過しない者。
- 上記取消処分を免れるため廃業届を出し、5年経過しない者(関係役員等含む)。
- 営業停止命令を受け、停止期間中の者。
- 営業禁止処分を受け、禁止期間中の者。
- 禁錮以上の刑に処せられ、執行終了等から5年経過しない者(執行猶予期間中も含む)。
- 建設業法、労働関係法令、暴力団対策法違反等で罰金刑を受け、執行終了等から5年経過しない者。
- 暴力団員等、または暴力団員等でなくなってから5年経過しない者。
- 心身の故障により適正な営業ができない者。
- 暴力団員等が事業活動を支配する者。
【証明方法】
- 誓約書(様式第6号)。
- 調書(様式第12号、第13号)。
- 登記されていないことの証明書(法務局発行)。
- 身分証明書(本籍地発行)。
- 商業登記簿謄本(法人の場合)。
欠格要件は範囲が広く、過去の法令違反歴も審査対象となるため、コンプライアンスが極めて重要です。
6. 社会保険への加入
【内容】
健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険に適切に加入していることが、許可要件として明確化されています。労働者の福祉確保と企業の法令遵守を示すためです。
【基準】
- 法人
常勤役員・従業員がいれば、原則としてすべてに加入義務あり。 - 個人事業主
常時雇用従業員5人以上で健康保険・厚生年金保険に加入義務あり。雇用保険は従業員1人以上で原則加入義務あり(適用除外あり)。
2020年10月の法改正で要件化され、重要性が増しています。
【証明方法】
- 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
事業所整理記号・番号等を記載。 - 確認資料
保険料納付書(領収印付)、納入証明書、社会保険料納入確認書などの提示・提出が求められる場合あり。
社会保険未加入は、許可取得・更新ができないだけでなく、公共工事の入札(経営事項審査)でも大きな不利益となります。適切な加入と納付が不可欠です。
(参考)営業所の設置
許可要件とは別に、建設業の営業を行うための物理的な拠点(営業所)が必要です。前述の「大臣許可と知事許可」で定義した通り、実質的な営業活動拠点としての形態(事務所スペース、設備、常勤者等)を備えている必要があります。賃貸借契約書や不動産登記簿謄本、営業所の写真などで確認されます。
建設業許可の申請手続き:ステップ・バイ・ステップ
建設業許可を取得するための手続きは、準備から申請、許可通知まで、いくつかのステップに分かれます。
申請の全体的な流れ
一般的な申請プロセスは以下の通りです。
- 許可の種類・区分・業種の決定
- 自社の事業内容、営業所、受注形態に合わせて、取得すべき許可(大臣/知事、一般/特定、業種)を正確に判断します。
- 要件充足の確認と証明資料の準備
- 上記6つの許可要件を満たしているか確認し、証明書類を収集・準備します。
- 申請書類の作成
- 国や都道府県指定の様式に従い、許可申請書と添付書類一式を作成します。誤りや矛盾がないよう注意が必要です。
- 申請手数料・登録免許税の準備
- 許可種類・区分に応じた費用を用意します。納付方法は申請先により異なります。
- 申請窓口への提出
- 作成した書類一式を管轄行政庁(地方整備局または都道府県担当部署)へ提出します。持参、郵送、電子申請(JCIP)が可能です。
- 審査
- 行政庁が提出書類に基づき審査します。不備があれば補正指示や追加資料提出が求められます。
- 営業所調査(実施される場合)
- 申請内容確認のため、営業所の実態調査が行われることがあります。
- 許可通知
- 審査で要件を満たすと判断されれば、許可通知書が交付されます。
建設業許可申請は複雑で時間を要するため、専門家への依頼も有効です。
主な申請書類一覧
必要書類は申請区分や許可種類によって異なりますが、主なものを以下に示します。必ず申請先の最新手引きを確認してください。
【主要様式】
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 役員等一覧表(別紙1)
- 営業所一覧表(別紙2(1) / (2))
- 収入印紙・証紙はり付け欄(別紙3)
- 営業所技術者等一覧表(別紙4)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の工事施工金額(様式第3号)
- 使用人数(様式第4号)
- 誓約書(様式第6号)
- 常勤役員等(経管)証明書(様式第7号)、略歴書(別紙)
- 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
- 営業所技術者等証明書(様式第8号)
- 実務経験証明書(様式第9号)
- 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)(特定の場合)
- 令第3条使用人一覧表(様式第11号)
- 許可申請者等の調書(様式第12号)
- 令第3条使用人の調書(様式第13号)
- 定款(法人)
- 株主(出資者)調書(様式第14号)(法人)
- 財務諸表(様式第15号~第19号)
- 営業の沿革(様式第20号)
- 所属建設業者団体(様式第20号の2)
- 主要取引金融機関名(様式第20号の3)
【主な添付・確認資料】
- 登記事項証明書
- 役員・本人・令3条使用人等の身分証明書
- 役員・本人・令3条使用人等の登記されていないことの証明書
- 役員・本人・令3条使用人等の住民票(不要な場合あり)
- 営業所技術者等の資格者証・免許証写し等
- 卒業証明書(学歴証明の場合)
- 経管・営業所技術者等の常勤性証明資料(健康保険証写し等)
- 財産的基礎証明資料(残高証明書等)
- 納税証明書
- 社会保険加入証明資料(保険料領収書等)
- 営業所の写真、案内図、賃貸借契約書写し等
申請様式は行政庁ウェブサイト等で入手可能です。無料作成支援ソフトもあります。書類間の整合性(財務諸表と工事経歴書等)もチェックされるため、正確な作成が重要です。
申請手数料・登録免許税
申請には法定費用が必要です。金額は許可種類と申請区分で異なります。
| 申請区分 | 許可行政庁 | 一般又は特定の一方のみ申請 | 更新・業種追加 | 納付種別・納付先等 (主な例) |
|---|---|---|---|---|
| 大臣許可 | 国土交通大臣 | 登録免許税 15万円 | 手数料 5万円 | 新規等: 管轄税務署へ納付 更新等: 収入印紙(申請書貼付) |
| 知事許可 | 都道府県知事 | 手数料 9万円 | 手数料 5万円 | 都道府県により異なる(収入証紙、現金、オンライン決済等) |
| 行政書士報酬 (目安) | – | 新規: 10~20万円程度 | 5~10万円程度 | 依頼する場合 |
| その他実費 (証明書代等) | – | 数千円~1万円程度 | 数千円~1万円程度 | 登記簿謄本、納税証明書等の取得費用 |
上記は主なケースの金額です。一般と特定を同時に申請する場合などは異なります。
これらの費用のうち、手数料については不許可や取下げの場合でも原則還付されません。ただし、大臣許可の新規申請等に係る登録免許税は、不許可や申請取下げの場合は納付義務が発生しないため、事実上還付される(または納付不要となる)運用が一般的です。
申請窓口と提出方法
【申請窓口】
- 大臣許可
- 主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局等へ直接提出します(2020年4月以降原則)。
- 知事許可
- 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県の担当部署(本庁または出先機関)です。
【提出部数】
- 大臣許可
正本1部+副本(営業所のある都道府県数と同数)の写し(例: 関東地方整備局)。 - 知事許可
都道府県の規定によります(例: 正副各1部)。
【提出方法】
- 持参
窓口へ直接提出。事前予約が必要な場合あり。 - 郵送
郵送も可能。受付日は到着日。控え返送希望時は返信用封筒同封。 - 電子申請 (JCIP)
「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」によるオンライン申請も可能。GビズID取得等が必要。添付書類はPDF化。手数料はPay-easy納付可(都道府県による)。
申請窓口、提出方法、部数は許可種類や都道府県で異なるため、最新情報の確認が必須です。
標準処理期間(審査期間の目安)
申請が受理されてから許可・不許可の処分がされるまでの標準的な期間の目安です。書類不備の補正期間は含みません。実際の期間は変動します。
- 大臣許可
- 地方整備局へ直接申請の場合、おおむね90日程度。
- 知事許可
- 都道府県により異なるが、一般的に30日程度が多い。ただし、変動あり(例: 東京都約2週間、福岡県約2ヶ月)。
【全体の期間】
申請準備期間(通常1~1.5ヶ月程度)+審査期間を合わせると、許可取得までには、知事許可で最短1.5ヶ月~通常2.5ヶ月程度、大臣許可で最短3ヶ月~通常4ヶ月程度を見込む必要があります。特定の期日までに許可が必要な場合は、十分な余裕をもって準備を開始することが極めて重要です。書類不備は許可取得を遅らせる最大の要因です。
許可取得後の手続きと義務:許可の維持管理
建設業許可は取得して終わりではありません。許可を有効に維持し、適法に事業を続けるためには、様々な手続きと義務を履行する必要があります。
1. 許可の更新
【必要性】
許可の有効期間は5年間です。満了後も営業を続ける場合は、期間満了前に更新申請が必要です。更新を怠ると許可は失効します。
【申請時期】
有効期間満了日の30日前までに申請が必要です。行政庁によっては早期申請を推奨しています。余裕を持った申請が重要です。
【申請中の効力】
適正な更新申請が期間満了前に行われていれば、審査中に満了日を迎えても、処分が下りるまでは従前の許可が有効とみなされます。
【手続き】
基本的に新規申請と同様、申請時点での許可要件をすべて満たしていることを証明する書類が必要です。更新手数料は、大臣・知事、一般・特定に関わらず、1業種区分につき5万円です。
【重要ポイント】
更新申請の前提条件として、後述する毎年の「決算変更届」や変更事項発生時の「変更届」が、過去5年分すべて適正に提出されていることが求められます。これらの届出を怠ると更新申請が受理されないため、日頃からの適切な手続きが不可欠です。
2. 変更届の提出
許可内容に変更が生じた場合、定められた期間内に変更届を提出する義務があります。行政庁が最新情報を把握し、許可要件維持を確認するためです。
【提出期限】
変更内容により、変更日から14日以内または30日以内となります。
- 変更後14日以内(人的要件の根幹に関わる変更等):
- 経営業務の管理責任者の変更。
- 営業所技術者等の変更。
- 令第3条使用人(支店長等)の変更。
- 欠格要件への該当。
- 変更後30日以内(上記以外の主な変更):
- 商号または名称の変更。
- 営業所の名称、所在地の変更。
- 営業所の新設、廃止。
- 営業所の業種追加、一部廃止。
- 資本金の額の変更。
- 法人の役員の変更。
- 個人の支配人の変更。
- 廃業
- 建設業の全部または一部を廃止した場合、廃止日から30日以内に廃業届(様式第22号の4)を提出する必要があります。
【提出先・方法】
管轄の行政庁へ、所定の様式及び添付書類を用いて提出します。持参、郵送、または電子申請(JCIP)が可能です。
【届出懈怠のリスク】
これらの変更届(廃業届含む)の提出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(建設業法第50条)。また、届出の種類によっては10万円以下の過料に処せられる場合もあります(建設業法第55条。例: 廃業届の未提出)。さらに、罰則だけでなく、更新申請が受理されない、経営事項審査で減点される、行政処分(指示・営業停止)の対象となるなど、事業運営に支障をきたす重大なリスクがあります。変更が生じた場合は、速やかに手続きを行いましょう。
3. 決算変更届(事業年度終了報告)
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、その事業年度の工事経歴書、財務諸表などを添付した「決算変更届」(正式名称: 事業年度終了報告書)を提出する義務があります。
【目的】
行政庁が、許可業者の毎年の経営状況や施工実績を把握し、許可要件(特に財産的基礎など)が継続して満たされているかを確認するためです。
【提出書類】 (主なもの)
- 事業年度終了変更届出書(様式第22号の2)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 財務諸表(様式第15号~第19号)
- 納税証明書(都道府県により必要)
【重要性】
この決算変更届の提出は、建設業法で定められた義務であり、その履行は極めて重要です。提出を怠ると、許可の更新申請が受理されません。また、公共工事の入札に必要な経営事項審査も受けられません。さらに、提出を怠ったり、虚偽の記載をして提出したりした場合は、100万円以下の罰金(建設業法第52条)または6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(建設業法第50条、虚偽の場合)の対象となる可能性があります。事業継続のためには、毎年度必ず期限内に提出する必要があります。
4. 標識の掲示義務
建設業許可業者は、その店舗(本店、支店、営業所)及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、許可を受けた業者であること等を示す標識(金看板など)を掲示しなければなりません(建設業法第40条)。
【標識記載事項】 (例)
- 商号または名称
- 代表者の氏名
- 許可を受けた建設業(一般・特定、業種)
- 許可番号、許可年月日
- (現場の場合)主任技術者または監理技術者の氏名 など
標識のサイズや材質、記載内容には規定があります。掲示を怠ると10万円以下の過料の対象となります(建設業法第55条)。
5. 帳簿の備付け・保存義務
建設業許可業者は、その営業に関する事項(請負契約の内容、発注者名、工事場所、請負代金、工期、支払状況、下請契約に関する事項など)を記載した帳簿を、営業所ごとに 備え付けなければなりません(建設業法第40条の3)。
さらに、その帳簿及び営業に関する図書(契約書、契約の申込書、請負代金領収書、工事の施工に関する図面、仕様書、記録、発注者との打合せ記録、施工体系図など)を、以下の期間保存する義務があります。
【保存期間】
- 帳簿:5年間
- 営業に関する図書
- 発注者から直接請け負った新築住宅に係るもの:10年間
- 上記以外のもの:5年間
これらの義務を怠ると、10万円以下の過料に処せられる可能性があります(建設業法第55条)。帳簿や図書は、経営状況の把握、トラブル発生時の証拠、税務調査への対応などのためにも重要ですので、適切に作成・保存しましょう。
建設業法違反と罰則
建設業法に違反した場合、厳しい罰則や行政処分が科される可能性があります。コンプライアンスを軽視すると、事業継続そのものが困難になりかねません。
【主な違反行為と罰則・処分例】
- 無許可営業
軽微な工事を除き、許可なく建設業を営んだ場合
→ 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人には最大1億円以下の罰金)。 - 名義貸し
自己の名義をもって他人に建設業を営ませること
→ 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人には最大1億円以下の罰金)。 - 虚偽申請
許可申請や変更届等で重要な事項について虚偽の記載をした場合
→ 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(法人には同額以下の罰金)。 - 変更届・決算変更届の未提出・虚偽提出
→ 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(虚偽の場合)、100万円以下の罰金(決算変更届未提出等)、10万円以下の過料(変更届・廃業届未提出等)。 - 主任技術者・監理技術者の不設置
必要な技術者を配置しなかった場合
→ 100万円以下の罰金(法人には同額以下の罰金)。 - 一括下請負(丸投げ)の禁止違反
発注者から直接請け負った建設工事を、実質的に関与することなく一括して他人に請け負わせること(一部例外あり)
→ 主に監督処分(指示、営業停止)の対象。悪質な場合は罰則の可能性あり。 - 標識の未掲示
→ 10万円以下の過料。 - 帳簿の不備・不保存
→ 10万円以下の過料。
【監督処分】
上記の罰則とは別に、国土交通大臣または都道府県知事は、建設業法違反や不適切な行為を行った建設業者に対し、以下のような監督処分を行うことができます。
- 指示処分
業務改善等を指示する。 - 営業停止処分
違反が悪質な場合、一定期間(最長1年間)の営業停止を命じる。 - 許可取消処分
特に重大な違反や欠格要件該当の場合、許可を取り消す。
許可取消処分を受けると、原則として5年間は新たに許可を取得できません。日頃から建設業法を遵守し、適正な事業運営を心がけることが極めて重要です。
まとめ:建設業許可を正しく理解し、事業の礎を築く
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者にとって、単なる手続きではなく、事業の信頼性と継続性を支える根幹となる制度です。許可取得には、経営体制、技術力、財産的基礎、誠実性など、多岐にわたる要件を満たす必要があり、そのプロセスは複雑です。
また、許可取得後も、更新手続き、変更届、決算変更届の提出、帳簿の保存など、継続的な管理が求められます。これらの義務を怠ると、罰則や許可失効のリスクがあり、事業に深刻な影響を及ぼしかねません。
建設業法は、社会情勢の変化や業界の課題に対応するため、改正が重ねられています。特に近年では、社会保険加入の義務化、技術者配置要件の緩和(ICT活用との連携)など、重要な変更が行われています。常に最新の情報を把握し、法令を遵守することが不可欠です。
建設業許可の取得や維持管理に不安がある場合、あるいは手続きが複雑で手が回らない場合は、行政書士などの専門家に相談することも有効な手段です。専門家のサポートを得ることで、スムーズかつ確実に手続きを進め、コンプライアンスを確保し、安心して事業に専念することができます。
建設業許可制度を正しく理解し、適切に対応していくことが、建設事業者としての信頼を高め、持続的な成長を実現するための重要な鍵となるでしょう。
- 【格安代行】三重県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】京都府の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】佐賀県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】兵庫県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】北海道の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】千葉県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】千葉県の建設業許可申請を徹底解説!【9万円~】
- 【格安代行】和歌山県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】埼玉県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】埼玉県の建設業許可申請を徹底解説!【9万円~】
- 【格安代行】大分県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】大阪府の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】大阪府の建設業許可申請を徹底解説!【9万円~】
- 【格安代行】奈良県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】宮城県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】宮崎県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】富山県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】山口県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】山形県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】山梨県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】岐阜県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】岡山県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】岩手県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】島根県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】広島県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】建設業許可とは?取得要件から申請手続き、更新まで徹底解説【9万円~】
- 【格安代行】徳島県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】愛媛県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】愛知県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】愛知県の建設業許可申請を徹底解説!【9万円~】
- 【格安代行】新潟県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】東京都の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】栃木県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】沖縄県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】滋賀県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】熊本県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】石川県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】神奈川県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】神奈川県の建設業許可申請を徹底解説!【9万円~】
- 【格安代行】福井県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】福岡県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】福岡県の建設業許可申請を徹底解説!【9万円~】
- 【格安代行】福島県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】秋田県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】群馬県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】茨城県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】長崎県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】長野県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】青森県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】静岡県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】香川県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】高知県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】鳥取県の建設業許可でおすすめの行政書士3選
- 【格安代行】鹿児島県の建設業許可でおすすめの行政書士3選