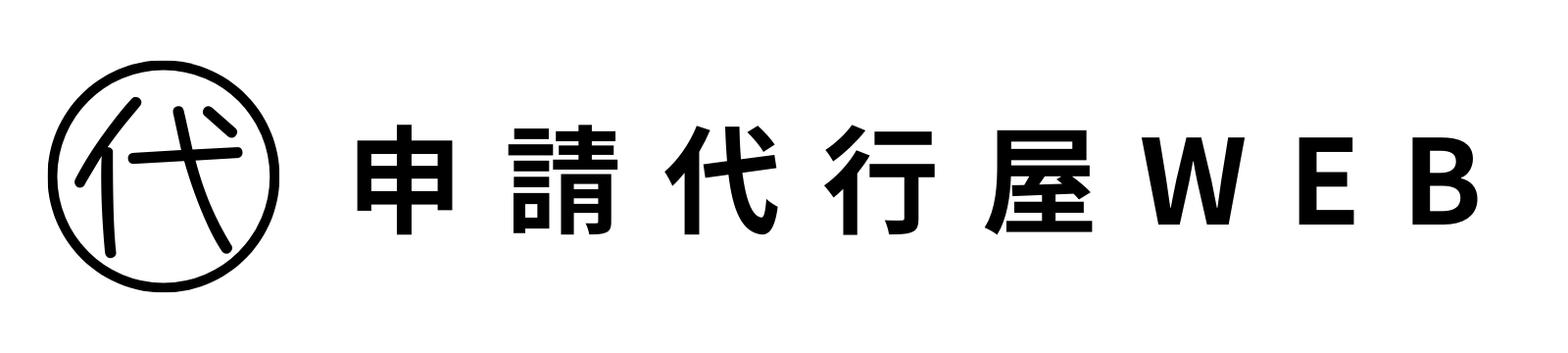日本の人口構造は、少子高齢化の進行により大きな転換期を迎えています。総人口は2020年の約1億2615万人から、2070年には約8700万人まで減少すると予測されており、特に労働力人口の減少は深刻です。多くの産業分野で人手不足が顕著となり、外国人労働者への期待が高まっています。実際、日本で働く外国人労働者数は増加を続け、2024年10月末時点で230万人を超えました。
このような状況を受け、日本政府も外国人材の受け入れと定着を促進するための政策を進めています。「特定技能」制度の創設・拡充や、技能実習制度を見直し「育成就労」制度を導入するなど、外国人材が日本の経済社会を支える上で不可欠な存在であることを示しています。
しかし、「外国人材を雇用したいけれど、手続きが複雑そう」「どの種類のビザ(在留資格)が必要なのかわからない」といった悩みを持つ企業担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、日本の就労ビザ制度(就労可能な在留資格制度)について、その基礎知識から主要な種類、具体的な手続き、雇用上の注意点、そして最新の動向まで、外国人雇用を成功させるための情報を網羅的に解説します。
就労ビザ おすすめの行政書士事務所
経験豊富な
行政書士(許認可のプロ)に
就労ビザの相談・書類作成を依頼
\詳しくはこちら/
経験豊富な
行政書士(許認可のプロ)に
就労ビザの相談・書類作成を依頼
\詳しくはこちら/
就労ビザと在留資格:まず知っておきたい基本
外国人雇用を考える上で、まず「ビザ(査証)」と「在留資格」の違いを理解することが重要です。
ビザ(査証)とは?
「ビザ(査証)」は、外国にある日本大使館や領事館が、その外国人のパスポート(旅券)が有効であり、日本への入国が適当であると推薦するものです。あくまで入国推薦であり、日本での活動内容を保証するものではありません。
在留資格とは?
「在留資格」は、日本に入国・在留する外国人が、日本で行うことができる活動内容や身分・地位を類型化したものです。これは日本の出入国在留管理庁(入管庁)によって許可され、日本での活動範囲や期間を定めます。
一般的に「就労ビザ」と呼ばれるものは、この「在留資格」のうち、日本国内で収入を伴う活動(就労)を行うことが認められているものを指します。
就労が認められる在留資格の種類
日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)では、様々な種類の在留資格が定められています。就労が可能な在留資格は多岐にわたりますが、大きく以下の2つに分類できます。
- 活動内容に制限のない在留資格
(身分・地位に基づくもの)- 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など。これらの在留資格を持つ人は、原則として職種や業種に制限なく就労できます。
- 定められた範囲内での就労が認められる在留資格
(活動に基づくもの)- 本記事で主に解説するもので、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」「経営・管理」などがあります。これらの在留資格は、許可された特定の業務内容や分野でのみ就労が可能です。
次からは、主要な就労関連の在留資格について詳しく見ていきましょう。
【種類別】主要な就労関連の在留資格を徹底解説
ここでは、企業が外国人を雇用する際に関わることが多い、代表的な就労関連の在留資格について解説します。
高度専門職(HSP: Highly Skilled Professional)
概要
日本の学術研究や経済発展に貢献し得る、高度な能力を持つ外国人材(高度人材)を積極的に受け入れるための在留資格です。活動内容は「研究活動」「専門技術活動」「経営管理活動」の3つに分類されます。
特徴:高度人材ポイント制
最大の特徴は「高度人材ポイント制」です。申請者の学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格、日本語能力などをポイント化し、合計が70点以上であることが認定の要件となります。
種類と優遇措置
- 高度専門職1号
- 在留期間は原則5年。複合的な活動が許容されたり、永住許可要件が緩和されたり(通常10年のところ、70点以上で3年、80点以上で1年)、配偶者のフルタイム就労が許可されたり、一定条件下で親や家事使用人の帯同が許可されたりするなど、多くの優遇措置があります。
- 高度専門職2号
- 「1号」で3年以上活動し要件を満たすと移行可能。在留期間が無期限となり、活動範囲もさらに広がります。
企業側の留意点
年収がポイントに大きく影響するため、採用時に年収交渉を受ける可能性があります。また、更新時にもポイント維持が必要です。グローバルな人材獲得競争の中で、魅力的な報酬やキャリアパスの提示が重要になります。
技術・人文知識・国際業務(技・人・国)
概要
最も多くの外国人専門職人材が取得している代表的な就労資格です。以下の3つのカテゴリーのいずれかに該当する業務に従事する場合に許可されます。
- 技術
- 理学、工学、IT等の自然科学分野の専門知識・技術を要する業務(例:エンジニア、プログラマー、設計者)。
- 人文知識
- 法律、経済、社会学等の人文科学分野の専門知識を要する業務(例:企画、営業、マーケティング、経理、人事、コンサルタント)。
- 国際業務
- 外国文化に根差した思考・感受性を必要とする業務(例:翻訳、通訳、語学指導、海外取引、デザイナー、商品開発)。
重要な要件:学歴・職歴と業務の関連性
従事する業務内容と、申請者の学歴(大学卒業または日本の専門学校卒「専門士」)または実務経験との間に密接な関連性があることが極めて重要です。例えば、大学で機械工学を専攻した人が機械設計を行う、経済学部卒がマーケティング業務を行う、といったケースです。国際業務については、原則として3年以上の実務経験が必要ですが、大学を卒業した方が翻訳、通訳、または語学の指導に係る業務に従事する場合は、この実務経験要件は不要です。
注意点
単純労働(工場での組立、清掃など)はこの在留資格の対象外です。学歴・職歴と業務の関連性が不明確な場合や、職務内容に単純作業が多く含まれると判断されると不許可になる可能性が高いため、職務記述書の作成や候補者の経歴確認は慎重に行う必要があります。
在留期間
5年、3年、1年、または3か月のいずれか。
企業内転勤
概要
外国にある日本の企業の本店、支店、子会社、関連会社などの職員が、日本の関連事業所に期間を定めて転勤し、業務に従事するための在留資格です。
活動内容
許可される活動は「技術・人文知識・国際業務」の範囲内に限られます(専門的・技術的業務)。
主な要件
- 転勤直前に、外国の関連会社等で継続して1年以上、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していること。
- 日本での報酬が、日本人が同等の業務に従事する場合と同等額以上であること。
- 転勤元と転勤先の機関に一定の資本関係があること。
特徴
「技術・人文知識・国際業務」と異なり、大学卒業等の学歴は必須要件ではありません。転勤という状況と直近の職務経験が重視されます。
在留期間
5年、3年、1年、または3か月。
経営・管理
概要
日本で事業の経営を開始したり、既存事業に投資して経営に参加したり、事業の管理に従事する外国人のための在留資格です(例:代表取締役、取締役、部長、支店長など)。
主な要件
- 事業規模
- 資本金(出資金)が500万円以上、または日本に居住する常勤職員を2名以上雇用。
- 事業所の確保
- 日本国内に独立した事務所(事業所)が確保されていること(バーチャルオフィス等は原則不可)。
- 事業計画
- 新規事業の場合、具体性と実現可能性のある事業計画書が必要。
- 経営・管理経験
- 管理職として従事する場合は、通常3年以上の経営または管理経験が必要。
注意点
主たる活動が経営・管理業務である必要があり、現場作業や単純労働がメインであってはなりません。更新時には、事業の継続性(黒字経営等)や税金・社会保険料の適正な納付状況が厳しく審査されます。
在留期間
5年、3年、1年、6か月、4か月、または3か月。
補足:4か月の在留期間は、特に新規事業立ち上げの準備段階(法人設立、事務所契約等)や、東京都などが実施する特定の外国人創業支援プログラムを利用する場合などに付与されることがあります。
技能
概要
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。
対象分野例
外国料理の調理師(最も多い)、外国特有の建築技術者、宝石加工職人、動物調教師、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエなど、法務省令で定められた特定の分野に限られます。
重要な要件:実務経験
各分野で定められた実務経験が必須です(例:外国料理調理師は原則10年以上、タイ料理は5年以上)。学歴よりも長年の経験による熟練技能が重視されます。
注意点
省令で列挙された職種に限定されており、類似していてもリストにない職種は対象外です。
在留期間
5年、3年、1年、または3か月。
特定技能 (SSW: Specified Skilled Worker)
概要
国内人材の確保が困難な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために2019年に創設された在留資格です。
種類
- 特定技能1号
- 対象
特定16分野(下記参照)で相当程度の知識・経験を要する技能を持つ外国人。 - 対象分野
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業。 - 要件
原則、分野別技能試験と日本語能力試験(N4程度等)に合格。技能実習2号を良好に修了した場合は免除あり。 - 在留期間
通算上限5年。 - 家族帯同
原則不可。 - 支援
受入れ機関(雇用主)または登録支援機関による支援計画の策定・実施が義務。
- 対象
- 特定技能2号
- 対象
「建設」「造船・舶用工業」および、特定技能1号の分野から「介護」「ビルクリーニング」「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」を除く9分野(工業製品製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)の合計11分野で熟練した技能を持つ外国人。 - 要件
より高度な技能試験に合格。 - 在留期間
上限なし(更新可能)。長期就労が可能。 - 家族帯同
可(配偶者・子)。
- 対象
特徴
特定分野の人手不足解消が目的で、当初から労働者としての受け入れを前提としています。1号から2号へのステップアップや、将来的な永住への道も開かれています。
介護
概要
日本の国家資格である「介護福祉士」の資格を有する外国人が、日本の介護施設等との契約に基づき、介護業務または介護の指導に従事する場合の在留資格です。
重要な要件
介護福祉士の資格を保有していること。これは、日本の養成施設卒業または実務経験+国家試験合格により取得できます。
特徴
- 在留期間
5年、3年、1年、または3か月で、更新に制限はなく長期滞在が可能。 - 家族帯同
可(配偶者・子)。
特定技能「介護」と比較して資格要件は高いものの、在留期間の上限がなく家族帯同も可能なため、介護専門職としてのキャリアを目指す外国人にとっては目標となる在留資格です。
【分野別】特にニーズの高い「介護分野」の外国人材
日本の介護分野は深刻な人手不足に直面しており、外国人介護人材の受け入れは重要な対策となっています。
受け入れルート
現在、主な受け入れルートは以下の4つです。
- EPA(経済連携協定)
- インドネシア、フィリピン、ベトナムからの介護福祉士候補者。就労・研修しながら国家試験合格を目指す(滞在期間4年)。
- 在留資格「介護」
- 日本の介護福祉士資格を持つ専門職。長期就労・家族帯同可。
- 特定技能1号「介護」
- 技能・日本語試験合格者。在留期間は通算5年。期間中に介護福祉士資格を取得すれば「介護」へ変更可能。
- 技能実習/育成就労
- 技能実習は廃止され、特定技能1号レベルの人材育成を目的とする「育成就労」へ移行。原則3年間で基礎を習得し、特定技能1号を目指す。
これらのルートは、要件、在留期間、家族帯同の可否、キャリアパスなどが異なります。
受け入れの現状と課題
特定技能「介護」を中心に受け入れは増加しており、特にアジア諸国の若年層が多くを占めています。しかし、定着には課題もあります。
- コミュニケーションの壁
- 日常会話、業務指示、記録作成、利用者・家族との対話など。
- 文化・価値観の違い
- 仕事の進め方、時間管理、人間関係など。
- 労働環境・待遇
- 長時間労働、賃金、キャリアパスの不明確さなど。
- 差別・ハラスメント
- 利用者や同僚からの差別的な言動など。
- 孤独感・相談相手の不在
企業の取り組みと支援制度
定着促進のため、企業には以下の取り組みが求められます。
- 体系的な日本語教育(専門用語含む)
- 異文化理解研修(日本人職員含む)
- 明確なコミュニケーション(やさしい日本語、多言語ツール活用)
- キャリアパス提示と資格取得支援(特に介護福祉士)
- 相談体制の整備(メンター、母国語対応)
- ハラスメント対策
国や自治体、関連団体による日本語学習支援、試験対策、相談窓口、受け入れ施設への巡回訪問などのサポート制度も活用できます。特定技能1号では、登録支援機関に支援業務を委託することも可能です。
外国人雇用の具体的な手続き:採用から雇用後まで
外国人材を雇用する際の手続きは、採用する人が海外にいるか、日本にいるかで異なります。
ステップ1:採用前 – 在留資格と就労可否の確認(最重要!)
内定を出す前に、必ず候補者の在留資格を確認し、予定している業務に従事できるかを確認します。
- 日本在住者の場合
在留カードを確認し、「在留資格の種類」「在留期間」「就労制限の有無」をチェックします。- 「永住者」「日本人の配偶者等」などは原則就労制限なし。
- 「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などは許可された範囲内のみ。
- 「留学」「家族滞在」は原則就労不可だが、「資格外活動許可」があれば週28時間以内のアルバイト可(在留カード裏面を確認)。
- 就労資格証明書
- 日本在住者を採用する際、任意で「就労資格証明書」の交付を入管庁に申請できます。これにより、採用可否の判断が確実になり、更新手続きもスムーズになるメリットがあります。
ステップ2:採用決定後 – 労働条件の明示と雇用契約
採用内定後、労働基準法に基づき、労働条件(契約期間、場所、業務内容、時間、休日、賃金、退職等)を明記した「労働条件通知書」を交付します。外国人にも理解できるよう、平易な日本語や母国語訳を付記することが望ましいです。同様の内容で雇用契約書を締結します。
ステップ3:在留資格の手続き(入管庁への申請)
ケース1:海外から新規雇用する場合 → 在留資格認定証明書(CoE)交付申請
- 目的
- 日本入国前に、予定活動が在留資格要件に適合することを日本の入管庁が審査・証明するもの。
- 申請者
- 本人、受入れ機関(企業)職員、行政書士など。多くは企業が代理申請。
- 申請先
- 企業所在地等を管轄する地方入管庁(オンライン申請可)。
- 時期
- 雇用契約締結後、速やかに。審査には通常1~3か月。
- 有効期間
- 発行日から3か月。この期間内に入国が必要。
- 必要書類
- 申請書、写真、企業書類(登記簿、決算書等)、雇用契約書、本人の学歴・職歴証明書など(資格や企業規模により異なる)。
- 電子CoE
- メールでの受取りも可能。
ケース2:日本在住者を採用(資格変更が必要な場合)→ 在留資格変更許可申請
- 対象
- 「留学」から就労資格へ変更する場合など、現在の活動内容と異なる活動を行う場合。
- 申請時期
- 変更事由発生後、現在の在留期間満了前に速やかに。審査には通常1~2か月。
- 申請者・申請先
- CoE申請と同様(オンライン申請可)。
- 必要書類
- 申請書、写真、パスポート・在留カード提示、新しい在留資格の要件を満たす書類一式(CoE申請書類に類似)。
- 注意点
- 許可されるまでは新しい活動を開始できません。「短期滞在」からの変更は原則不可。
ケース3:雇用を継続する場合 → 在留期間更新許可申請
- 対象
- 既に雇用している外国人の在留期間が満了に近づき、同じ資格で雇用を継続する場合。
- 申請時期
- 在留期間満了日の約3か月前から申請可能。審査には通常2週間~1か月程度(余裕をもって申請を)。
- 申請者・申請先
- 変更申請と同様(オンライン申請可)。
- 必要書類
- 申請書、写真、パスポート・在留カード提示、在職証明書、住民税の課税・納税証明書(直近年度分)など。
- 審査ポイント
- 引き続き在留資格要件を満たしているか、素行は良好か、納税・社会保険料納付義務を適正に履行しているか(滞納は不許可の大きな要因)。
オンライン申請の活用
近年、CoE交付、変更、更新などの申請は「在留申請オンラインシステム」を通じてオンラインで行うことが可能です。窓口に行く手間が省け、24時間申請可能、処理期間短縮の傾向があるなどのメリットがあります。(利用にはマイナンバーカードや事前の利用者登録などが必要)。
ステップ4:雇用開始後の雇用主の義務
- ハローワークへの届出(外国人雇用状況の届出)
- 雇用保険加入者
資格取得届・喪失届提出時に在留資格等を追記。 - 雇用保険非加入者
「外国人雇用状況届出書」を雇入れ・離職の翌月末日までに提出。
- 雇用保険加入者
- 入管庁への届出
- 中長期在留者の受入れに関する届出
受入れ開始・終了から14日以内。 - 所属(契約)機関に関する届出(本人義務だが企業も注意喚起を)
契約終了・締結から14日以内。 - 活動機関に関する届出(本人義務)
機関の名称・所在地変更等から14日以内。
- 中長期在留者の受入れに関する届出
- 労働関連法規の遵守
- 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などが日本人同様に適用されます。国籍による差別は禁止。
- 社会保険への加入
- 加入要件を満たす場合は、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険に加入させる義務があります。
これらの義務を怠ると罰則や、従業員の在留資格審査で不利になる可能性があります。
外国人雇用の注意点:在留資格申請の不許可理由とコンプライアンス
外国人雇用を成功させるには、手続きの正確性に加え、様々な課題やリスクへの対応が不可欠です。
在留資格申請の不許可理由
CoE交付、変更、更新が不許可となる主な理由には以下のようなものがあります。
CoE交付・変更申請の不許可理由
- 申請者側の問題
- 学歴・職歴要件と業務内容の不一致(特に技・人・国)
- 業務内容が単純労働等と判断される
- 過去の在留状況不良(留学時の出席率、資格外活動超過、オーバーステイ歴、犯罪歴など)
- 申請内容の矛盾・虚偽
- 上陸拒否事由への該当
- 受入れ機関(企業)側の問題
- 経営状況の不安定(赤字継続、債務超過など)
- 事業実態の不明確さ、業務量の不足
- 雇用条件(報酬が日本人と比較して低いなど)
- 過去の法令違反、税金・社会保険料の滞納
- 「経営・管理」での事業所未確保、資本金不足など
- 身分系資格特有の問題
- 配偶者ビザ
結婚の信憑性への疑義、日本人配偶者の扶養能力不足 - 家族滞在ビザ
扶養者の収入不足
- 配偶者ビザ
更新申請の不許可理由
- 公的義務の不履行
- 住民税等の税金滞納・遅延、社会保険料の未納・滞納(最重要!)
- 活動内容の変化・不適合
- 転職等により、現在の業務が許可された活動範囲から逸脱
- 経済的基盤の喪失・不安定化
- 失職、低収入、経営悪化など
- 在留状況不良
- 許可された活動をしていない、届出義務違反、法令違反など
不許可への対応
まずは入管庁で理由を確認し、改善可能であれば書類修正・追加の上で再申請できる場合があります。専門家への相談も有効です。
外国人雇用における課題
- 企業側
- 適切な人材のマッチング難、コミュニケーションの壁、異文化マネジメント、人材育成・評価の難しさ、管理負担(在留資格、コンプライアンス)。
- 外国人労働者側
- 言語の壁、文化適応の難しさ・孤独感、不適切な労働条件のリスク、差別・ハラスメントのリスク、相談相手の不在。
公正な労働慣行と搾取防止
外国人労働者も日本の労働法規で保護され、国籍による差別は禁止されています。企業は以下を徹底する必要があります。
- 法令遵守(労働時間、賃金、休日、安全衛生)
- 明確な契約(理解できる言語での説明)
- 安全で健全な職場環境(ハラスメント・差別防止)
- 相談・苦情処理体制の整備
今後の動向と企業が取るべき戦略:将来展望
外国人労働者政策は変化し続けています。今後の主要な動向と、企業が取るべき戦略を解説します。
2024年以降の主な法改正・制度変更
技能実習制度から育成就労制度へ
従来の技能実習制度は廃止され、新たに「育成就労」制度が創設されます(関連法は2024年6月21日公布)。
- 施行時期
- 公布日から3年以内に施行される予定であり、具体的な施行日は未定ですが、2027年頃になる見込みです。
- 目的転換
- 「国際貢献」から「人材育成と人材確保」へ。
- 特定技能との連携強化
- 原則3年間で特定技能1号レベルの人材に育成し、スムーズな移行を目指す。
- 転籍(転職)の緩和
- 一定要件下(同一分野、1年以上の就労等)で本人都合の転籍が可能に。人権侵害等の場合は期間によらず可能。
- 入国時日本語要件
- N5相当以上が必要に。
この変更は、労働者の権利保護やキャリアパス構築に繋がる一方、企業にとっては人材流出リスクへの対応も必要になります。
特定技能制度の拡充と運用変更
- 対象分野拡大
- 2024年に特定技能1号に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加され全16分野に。特定技能2号の対象も上記で解説した通り11分野へ拡大されました。
- 介護分野での訪問系サービス解禁
- 2025年4月頃から、一定条件下で特定技能・育成就労外国人の訪問介護従事が可能になりました。
- 運用面の変更(2025年4月1日~)
- 定期届出の頻度変更
従来の四半期ごとから年1回の届出に変更されます(2025年4月1日適用開始)。なお、この新制度に基づく最初の年次報告(対象期間:2025年4月1日~2026年3月31日)の提出期間は、2026年4月1日から5月31日までとなります。 - 定期面談のオンライン実施
本人の同意があればオンラインでの実施が可能になります(初回や問題発生時などを除く)。
- 定期届出の頻度変更
デジタル化の進展
在留資格申請のオンライン化やCoEの電子化は今後も拡大・推進される見込みです。
将来の労働市場と人口動態
今後数十年にわたり日本の人口減少・高齢化は続き、労働力不足はさらに深刻化すると予測されています。外国人労働者は、もはや一時的な補完ではなく、日本の経済社会にとって長期的に不可欠な構成要素となります。
企業への戦略的提言
変化に対応し、外国人材を効果的に活用するために、以下の戦略が推奨されます。
- 新制度への適応
- 育成就労制度や特定技能の変更点を理解し、育成計画、日本語教育、転籍可能性を考慮したマネジメント体制を構築する。
- 定着支援の強化
「育成し、定着してもらう」視点が不可欠。- オンボーディングと研修(業務、日本語、文化)の整備。
- キャリアパスの明確化と支援(特定技能2号や専門資格への移行支援)。
- インクルーシブな職場環境(言語対応、異文化理解、相談窓口、公正な評価、福利厚生)。
- コンプライアンスの徹底
入管法、労働法、税法、社会保険関連法の遵守。- 在留資格管理の徹底(種類、期間、活動内容把握、適切な手続き)。
- 各種届出義務の履行(ハローワーク、入管庁)。
- 労働条件の適正化(法令遵守、差別禁止)。
- 納税・社会保険の適正履行支援(従業員の在留資格維持に直結)。
- デジタルツールの活用
- オンライン申請の活用、社内コミュニケーションや業務管理へのICT導入。
- 外部リソースの活用
- 必要に応じ、人材紹介エージェント、登録支援機関、弁護士、行政書士などの専門家を活用する。
まとめ:外国人雇用の未来に向けて
日本の労働市場において外国人材の重要性は増す一方であり、政府も育成就労制度や特定技能制度の改革を通じて、計画的・持続的な受け入れ体制を整備しようとしています。
企業にとっては、法制度の変化を的確に捉え、コンプライアンスを確保しつつ、外国人材が安心して長期的に活躍できるインクルーシブな環境とキャリア支援を提供することが、これからの持続的な成長に不可欠です。外国人雇用は、もはや単なる人事戦略ではなく、企業の未来を左右する経営課題と言えるでしょう。本記事が、貴社の外国人材活用の一助となれば幸いです。
- 【格安代行】三重県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】京都府の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】佐賀県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】兵庫県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】北海道の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】千葉県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】和歌山県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】埼玉県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】大分県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】大阪府の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】奈良県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】宮城県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】宮崎県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】富山県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】就労ビザとは?外国人雇用のための完全ガイド
- 【格安代行】山口県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】山形県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】山梨県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】岐阜県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】岡山県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】岩手県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】島根県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】広島県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】徳島県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】愛媛県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】愛知県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】新潟県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】東京都の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】栃木県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】沖縄県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】滋賀県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】熊本県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】石川県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】神奈川県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】福井県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】福岡県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】福島県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】秋田県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】群馬県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】茨城県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】長崎県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】長野県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】青森県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】静岡県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】香川県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】高知県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】鳥取県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】鹿児島県の就労ビザ申請でおすすめの行政書士4選
- 日本での就労を目指す方へ:ビザ申請から生活情報まで完全ガイド
- 特定技能制度とは?制度の概要から課題、将来展望まで徹底解説
- 育成就労制度とは?外国人材と共生する新たな日本のカタチ