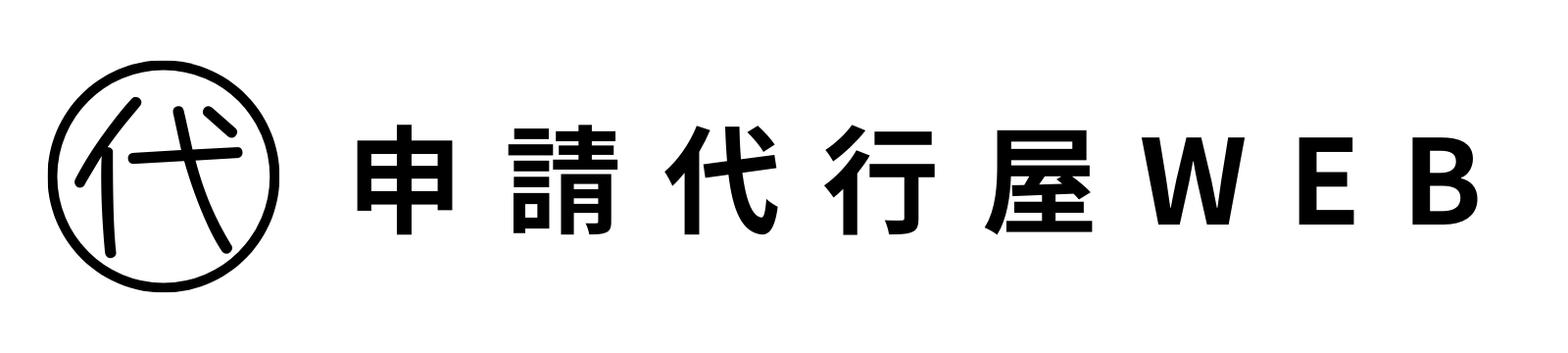大阪府内で道路工事、イベント開催、看板設置など、公道に影響を及ぼす活動を行う際には、「道路使用許可」または「道路占用許可」の取得が必要となる場合があります。これらの許可は、道路の安全かつ円滑な交通を確保し、公共の福祉を守るために不可欠な手続きです。しかし、両者の違いや申請方法が複雑で、どちらの許可が必要なのか、どのように手続きを進めればよいのか分からないという方も少なくありません。
この記事では、大阪府における「道路使用許可」と「道路占用許可」について、その違い、必要となるケース、申請手続きの流れ、注意点などを詳しく解説します。大阪府内で道路に関連する活動を計画されている事業者様や個人の方は、ぜひご一読いただき、適切な手続きを進めるための参考にしてください。
\専門家がお手頃価格で代行/
道路使用許可/占用許可 大阪府でおすすめの行政書士事務所
🔵デコレート行政書士事務所

即日申請/道路使用の申請代行します
全国対応可能|市道、県道、国道、お任せください!
サービスの特徴
100件以上の実績!全国の道路許可申請に対応!
- 道路使用許可申請で100件以上の豊富な実績を持つ、行政書士事務所が対応
- 市道、県道、国道まで、全国どこでも相談可能
- 道路占用許可や24条申請にも対応
どの許可が必要か分からなくても安心!
- 足場設置や車両作業など、様々なシチュエーションに対応
- 作業内容を伝えるだけで、必要な許可を事務所が調査
- 希望通りの許可が難しい場合も、最も近い内容で提案
図面作成のみなら即日申請も可能!
- 図面作成のみの依頼は、即日でのスピード申請に対応
- 見積り後、購入から24時間以内に正式納品
- 納品後の軽微な修正や加筆は、回数無制限で無料対応
安心の料金体系で、高品質なサポートを!
- 道路許可:44,000円~
- 料金は事前の見積り相談で、納得の上で依頼可能
\ 今すぐチェック!! /
🔵行政書士Z法務事務所



道路占用許可・道路使用許可、申請代行します
大阪府近県対応!国道、施工承認もお任せください!
サービスの特徴
面倒な道路許可申請は、専門家におまかせ!
- 行政書士が申請書作成から作図、申請まで一括で代行
- 国道、施工承認、水路など、様々な許可申請に対応
幅広いエリア・状況に対応!
- 大阪府、京都府、兵庫県などの近畿エリアを幅広くカバー
- 記載のないエリアでも、相談次第で対応可能
- 足場設置や資材搬入など、あらゆる現場の状況に対応
どの許可が必要か分からなくても安心!
- 作業内容を伝えるだけで、必要な許可を無料で調査・提案
- 占用料なども事前に無料で調べてくれる
リピーター多数!迅速・丁寧な対応で高評価!
- 利用者から「迅速で確実」「丁寧でわかりやすい」と絶賛の声
安心の料金体系で、高品質なサポートを!
- 道路許可:45,000円~
- 料金は事前の見積り相談で、納得の上で依頼可能
- どの許可が必要か、占用料はいくらか、などの調査は無料で対応
\ 今すぐチェック!! /
🔵阿保行政書士事務所



道路使用許可申請代行致します
大阪、京都の道路使用許可はお任せください
サービスの特徴
大阪・京都の道路使用許可はおまかせ!
- 阿保行政書士事務所が、申請書作成から図面作成、申請代行まで対応
- 主な対応エリアは大阪府枚方市や京都府八幡市などで、エリア外も相談可能
図面作成も代行!手ぶらで相談OK!
- 依頼者は、工事や作業の内容が分かる資料を提示するだけ
- 位置図や交通安全対策図、工程表なども事務所で作成可能
基本料金+エリア別オプションの明確な料金体系!
- 道路使用許可の代行は、基本料金30,000円
- 京都府は+2,000円、大阪府は+2,000円~2,500円の追加オプション
- 報酬とは別に、申請手数料や交通費の実費が必要
安心の料金体系で、高品質なサポートを!
- 道路許可:30,000円~
- 料金は事前の見積り相談で、納得の上で依頼可能
\ 今すぐチェック!! /
🔵行政書士Wanvisa Office



道路使用許可申請書作成します
通信工事会社で申請担当歴10年の行政書士がサポートします
サービスの特徴
申請担当歴10年の行政書士がサポート!
- 通信工事会社で申請担当歴10年の、現場を知る行政書士が対応
- どのような申請や資料が必要か、専門家が調べて申請
工事からイベントまで!申請・受取をフルサポート!
- 道路工事、広告板の設置、露店、チラシ配りなど、様々な用途に対応
- 書類作成から警察への提出、許可書の受取、依頼者への送付まで全ておまかせ
大阪府が対象!まずは無料の見積り相談から!
- 対象地域は大阪府、その他の地域も相談可能
- 申請料は有料オプション(2,000円~)で対応、別途必要
安心の料金体系で、高品質なサポートを!
- 道路許可:25,000円~
- 料金は事前の見積り相談で、納得の上で依頼可能
\ 今すぐチェック!! /
道路使用許可とは?: 一時的な道路の使用に関する許可
道路使用許可は、道路交通法第77条に基づき、本来の目的である「人や車両の通行」以外の目的で一時的に道路を使用する場合に必要な許可です 。主に、道路交通の安全と円滑を図ることを目的としており、行為地を管轄する警察署長が許可を出します 。
道路使用許可が必要となる主なケース(例)
- 道路工事や作業
- 道路工事(舗装、上下水道、ガス管、電気・通信ケーブル敷設など)
- 高所作業車を用いた作業(外壁清掃、看板設置・撤去、樹木剪定など)
- 建設用クレーン車等を用いた資材搬入・搬出作業
- マンホール内での作業
- 路上での測量作業
- 工作物の設置
- 工事用の足場、仮囲い、やぐらなど(交通に影響を与えるもの)
- 露店、屋台、商品置場など(ただし、場所や状況によっては占用許可も必要になる場合がある点に注意 )
- イベント等で使用する仮設ステージ、テントなど
- 広告板、のぼり旗、横断幕など(一時的なもの)
- 催し物やロケーション撮影
- お祭り、パレード、マラソン大会、地域イベントなど
- 消防訓練、避難訓練など
- 映画、テレビ、CMなどのロケーション撮影
- 街頭でのアンケート調査、募金活動、ビラ配りなど(交通の妨げになる場合)
これらの行為は、一時的に車両や歩行者の通行を妨げたり、交通の危険を生じさせたりする可能性があるため、事前に警察署の許可を得て、交通整理や安全対策を講じる必要があります 。許可を受ける際には、通行者や車両の安全を確保するための措置(誘導員の配置、保安資材の設置など)が求められます 。
- 根拠法規:道路交通法 第77条
- 許可権者:行為地を管轄する警察署長
- 目的:道路交通の安全と円滑の確保
道路占用許可とは?:継続的な道路の占用に関する許可
道路占用許可は、道路法第32条に基づき、道路上に一定の工作物、物件、または施設を設け、継続的に道路を使用(占用)する場合に必要な許可です 。道路の構造保全や交通への支障防止を目的としており、その道路を管理する「道路管理者」が許可を出します 。
- 国道
- 原則として国土交通省が管理者ですが、大阪府内では国が直接管理する「指定区間」と、管理が大阪府や政令指定都市(大阪市、堺市)に移管されている「指定区間外」が存在します 。どちらに該当するかで申請先が全く異なります。
- 府道
- 原則として大阪府(各土木事務所)が管理者ですが、政令指定都市内の区間は市が管理している場合があります 。
- 市町村道
- 各市町村が管理者です 。
道路管理者の特定に関する注意点
道路管理者は、道路の種類によって原則的に異なりますが、実際の管轄は複雑な場合があり、必ず事前の確認が必要です 。 特に国道の指定区間内外の区別や、行政境界付近の道路については、管轄がどちらなのか判断が難しいケースがあります。計画地の道路管理者が不明な場合は、必ず事前に市役所、大阪府の土木事務所、国土交通省の出張所などに問い合わせて、正確な申請先を確認してください 。
道路占用許可が必要となる主なケース(例)
- 地上に設置するもの
- 電柱、電話柱、街灯、信号機
- バス停留所の上屋、標識
- 看板(突き出し看板、袖看板など)、アーチ
- 路上に設置する変圧器(トランスボックス)
- 工事用の足場、仮囲い(占用期間が長期にわたる場合や、道路敷地に深く関わる場合)
- 露店、商品置場(常設的なもの)
- ベンチ、花壇など(公共的な目的で設置されるものも含む)
- 自動販売機(道路敷地内にはみ出す場合)
- 地下に埋設するもの
- 上水道管、下水道管、ガス管
- 電気ケーブル、通信ケーブル
- 地下通路、地下駐車場への接続路
- 道路の上空に設置するもの
- 建物の出窓、日よけ、雨よけ(道路境界線を越えて設置される場合)
- 上空通路
- 電線、通信線
これらの物件は、道路という公共空間の一部を継続的に独占して使用することになるため、道路管理者の許可が必要となります 。占用許可を受ける際には、占用する物件の構造、設置場所、占用期間などが審査され、占用期間や面積に応じて「占用料」の納付が必要になるのが一般的です 。なお、道路管理者によっては(例: 大阪市 )、占用許可の申請自体に別途「申請手数料」が必要となる場合もあります 。
- 根拠法規:道路法 第32条
- 許可権者:道路管理者(国、大阪府、大阪市、堺市、その他市町村など)
- 目的:道路の構造保全、交通への支障防止、公正な使用の確保
道路使用許可と道路占用許可の主な違い:一目でわかる比較
混同しやすい「道路使用許可」と「道路占用許可」ですが、目的、根拠法規、許可権者、対象となる行為、期間、費用などに明確な違いがあります。
| 項目 | 道路使用許可 | 道路占用許可 |
|---|---|---|
| 目的 | 道路交通の安全と円滑の確保 | 道路の構造保全、交通支障防止、公正な使用確保 |
| 根拠法規 | 道路交通法 | 道路法 |
| 許可権者 | 管轄の警察署長 | 道路管理者(国、大阪府、市町村等) |
| 対象行為 | 一時的な道路の使用(工事、作業、催し物など) | 継続的な道路の占用(工作物・物件・施設の設置など) |
| 期間 | 原則として一時的 | 比較的長期・継続的 |
| 費用 | 申請手数料 | 占用料 + 場合により申請手数料 |
| 申請先 | 行為地を管轄する警察署 | 行為地を管轄する道路管理者の事務所(土木事務所など) |
ポイント
- 「使用」 は交通への影響が主眼であり、一時的な行為が対象。警察が管轄 。
- 「占用」 は道路という空間を継続的に使うことが主眼。道路管理者が管轄 。
どのような場合に許可が必要か?:大阪府での具体例
大阪府内で具体的にどのような場合に各許可が必要になるか、さらに詳しく見ていきましょう。(これらは典型例であり、個別の判断は必ず関係機関にご確認ください)
道路使用許可が必要な例(大阪府内)
- 大阪市内の商店街で地域のお祭りを開催し、一部道路を通行止めにする 。
- 堺市内の府道沿いで、ビルの窓拭きのために高所作業車を一時的に停車させ作業する 。
- 東大阪市の市道で、水道管の修繕工事のため、道路を一部掘削し、交通誘導員を配置する 。
- 吹田市内の国道で、テレビドラマの撮影のため、数時間、一部車線規制を行う 。
- 枚方市内の道路で、マラソン大会を実施する 。
道路占用許可が必要な例(大阪府内)
- 大阪市内の御堂筋(国道※要管理者確認)沿いのビルに、道路上空へ突き出す形で看板を設置する 。
- 豊中市内の府道に、新たにバス停留所の上屋を設置する 。
- 八尾市内の市道に、店舗の日よけが道路境界線を越えて設置される 。
- 岸和田市内の道路地下に、新たに通信ケーブルを埋設する 。
- 高槻市内の歩道上に、電力会社の変圧器(地上設置型)を設置する 。
注意
上記は一般的な例です。占用許可と使用許可の両方が必要になるケースも多いため(後述)、必ず個別の計画に基づき、関係機関に確認してください。
申請手続きの流れ:スムーズな許可取得のために【重要:事前確認必須】
許可を取得するための一般的な手続きの流れを解説します。ただし、具体的な必要書類、申請書の様式・部数、手数料の有無・金額、オンライン申請の可否、処理期間、警察との連携方法は、申請する警察署や道路管理者(国、府、市町村)によって大きく異なります 。以下の流れはあくまで目安とし、必ず事前に各申請先に詳細を確認してください。
道路使用許可の申請手続き(警察署)
- 事前相談(強く推奨)
- 計画段階で、行為地を管轄する警察署の交通課(交通規制係など)に相談します 。
- 許可の要否、必要書類、安全対策、手数料などを確認します 。
- 申請書類の準備
- 道路使用許可申請書(通常2通)
- 添付書類(例):位置図、現況図・平面図、工程表、安全対策計画図など 。※警察署により異なる場合あり。
- 申請書類の提出
- 管轄の警察署の窓口に提出します 。
- 大阪府の手数料条例に基づく申請手数料が必要です(通常、許可証交付時等に納付) 。
- 審査
- 警察署で、交通への影響、安全対策などを審査します。(標準処理期間は原則7日間(行政庁の休日を除く)とされていますが、確認が必要です) 。
- 許可証の交付
- 審査の結果、問題がなければ道路使用許可証が交付されます 。
- 許可には条件が付されることがあります(例: 作業時間の制限、誘導員の増強など)。許可条件を必ず遵守してください 。
道路占用許可の申請手続き(道路管理者)
- 事前相談(極めて重要・強く推奨)
- 計画の初期段階で、必ず占用する道路を管理する道路管理者の事務所(例: 大阪府の土木事務所、市の道路管理担当課、国交省の事務所など)に相談してください 。
- 占用許可は技術的な審査(構造の安全性、他の占用物との関係等)や権利関係の調整を含むことが多く、手続きが複雑です 。事前相談は、単なる推奨ではなく、円滑な手続きのためには実務上不可欠に近いステップです 。占用が可能か、技術基準、必要書類、占用料、申請手数料の有無、手続きの流れ、所要期間などを詳細に確認します 。
- 申請書類の準備
- 道路占用許可申請書
- 添付書類(例):位置図、実測平面図・断面図、構造図、工事実施方法、復旧方法、同意書など 。※道路管理者ごとに様式や必要書類が異なります。例えば、堺市では掘削の有無で添付書類の部数が異なる場合があります 。
- 申請書類の提出
- 管轄の道路管理者の事務所に提出します 。大阪府などオンライン申請が可能な場合もあります 。
- 審査
- 道路管理者で、道路法に基づく基準(占用がやむを得ないか、構造は安全か、交通に支障はないか等)に適合するか審査します 。審査期間は内容により大きく異なり、数週間から数ヶ月かかる場合もあります 。警察協議が必要な場合はさらに時間がかかることがあります 。
- 許可(または不許可)の決定・通知
- 審査の結果、許可基準に適合すると判断されれば、許可書が交付されます。不許可の場合は、その理由が通知されます 。
- 許可には条件が付されることがあります(例: 維持管理義務、占用期間、原状回復義務など) 。
- 占用料・申請手数料の納付
- 許可後、定められた占用料を納付します 。前述の通り、道路管理者によっては(例:大阪市 )、別途申請手数料の納付が必要な場合があります 。
許可取得の重要性と罰則:無許可は厳禁!
道路使用許可や道路占用許可を必要な場合に取得せずに道路を使用・占用することは、法律違反となります。
- 道路使用許可(道路交通法)
- 無許可で道路使用行為を行った場合、罰金等の刑事罰が科される可能性があります(例: 道路交通法第119条等) 。また、警察署長から行為の中止や工作物の除去を命じられることもあります 。
- 道路占用許可(道路法)
- 無許可で道路を占用した場合、監督処分として占用物件の除去等を命じられたり(道路法第71条) 、罰金等の刑事罰が科されたりする可能性があります(例: 道路法第102条等) 。
これらの罰則だけでなく、無許可での工事やイベントは、事故の原因となったり、周辺住民や他の道路利用者に多大な迷惑をかけたりする可能性があります。社会的な信用を失うことにもなりかねません 。必ず事前に適切な許可を取得してください。
道路使用許可と道路占用許可の両方が必要な場合:注意すべき連携プロセス
一つの行為が、「一時的な道路の使用」と「継続的な道路の占用」の両方の性質を持つ場合、道路使用許可(警察署)と道路占用許可(道路管理者)の両方の許可が必要になります 。
両方の許可が必要となる典型的な例
- 道路工事
道路を掘削して上下水道管を埋設する場合 。- 管の埋設自体は「占用」→ 道路管理者の「道路占用許可」
- 工事に伴う交通規制、重機設置は「使用」→ 警察署長の「道路使用許可」
- 沿道の建物工事に伴う足場の設置
- 足場の道路敷地への設置は「占用」→ 道路管理者の「道路占用許可」
- 設置・解体作業、資材搬出入は「使用」→ 警察署長の「道路使用許可」
- イベントでの露店設置
- 露店の継続的な設置が「占用」とみなされる場合 → 道路管理者の「道路占用許可」
- イベント開催や設営・撤去作業が交通に影響する場合 → 警察署長の「道路使用許可」
両方の許可が必要な場合の注意点
- 申請の順序と相互依存性
- 一般的には、まず道路管理者に「道路占用許可」を申請し、その許可(または許可見込み)を得てから、警察署に「道路使用許可」を申請する流れが多いです 。警察署が使用許可申請時に占用許可書の写しなどを求めることがあるためです 。しかし、単なる順番の問題ではなく、両機関の審査プロセスは相互に連携・依存しています 。例えば、道路管理者が占用許可を出す前に、その占用計画に伴う交通管理について警察に協議し、問題がないか確認するプロセス(警察協議)が多くの自治体で設けられています 。逆に警察も、使用許可を出す際に占用が適法に行われる見込みがあるかを確認します。このため、両方の申請は「連携審査」として進められると理解し、一方の手続きが他方に影響を与えることを念頭に置く必要があります 。
- 時間的余裕
- 両方の申請と、機関間の調整・照会が必要となるため、極めて十分な準備期間と申請から許可までの期間を見込むことが重要です 。審査期間は占用許可の方が長くかかる傾向があります 。
- 両機関への事前確認
- 計画段階で、管轄の警察署と道路管理者の双方に、両方の許可が必要か、具体的な手続きの流れ(特に警察協議の有無やタイミング)、必要書類、所要期間などを必ず確認してください 。
スムーズな申請のためのヒント:事前の準備と確認が鍵
許可申請を円滑に進めるためには、以下の点を心がけましょう。
- 早期の相談(最重要)
- 計画の初期段階で、必ず管轄の警察署と道路管理者の両方に相談しましょう 。要件、手続き、必要書類、費用、期間等を正確に把握できます。特に占用許可は複雑なため、早期相談が不可欠です 。
- 正確な書類作成
- 申請書や添付図面は、各機関の指示に従い、正確かつ分かりやすく作成しましょう 。不備は遅延の原因となります。
- 十分な時間的余裕
- 審査、特に占用許可や両許可が必要な場合は時間がかかります 。数ヶ月単位の余裕をもって計画・申請しましょう。
- 安全対策の具体化
- 特に道路使用許可では、どのように交通の安全を確保するかが重要です 。誘導員の配置計画、保安資材の設置場所などを具体的に図示しましょう 。
- 関係機関との調整
- 必要に応じて、他の関係機関(例: 電力会社、ガス会社、水道局など)との調整も事前に行っておきましょう 。
- 専門家への相談
- 手続きが複雑で難しいと感じる場合は、行政書士などの専門家に相談・依頼することも有効な手段です 。申請書類の作成や提出代行を依頼できます。
まとめ
大阪府内で道路を使用・占用する際には、「道路使用許可」と「道路占用許可」の適切な手続きが必要です。一時的な交通への影響が主なら警察署へ「道路使用許可」を、継続的に道路空間を占用する場合は道路管理者へ「道路占用許可」を申請します。内容によっては両方の許可が必要となり、その手続きは相互に連携しています 。
これらの許可は、道路の安全と円滑な交通を守り、公共の利益を確保するために不可欠です。無許可での行為は罰則の対象となるだけでなく、事故やトラブルの原因にもなりかねません 。
大阪府内で道路に関する活動を計画する際は、本記事を参考にしつつも、必ず行為地を管轄する警察署および道路管理者(国、府、市町村)の双方に直接連絡を取り、最新かつ正確な情報を確認してください 。特に道路管理者の特定や、自治体ごとの手続きの違い 、両許可が必要な場合の連携プロセス には注意が必要です。十分な準備期間を設け、早期の相談と確認を行うことが、スムーズな許可取得の鍵となります。
参考資料
大阪府内のサービス提供地域
大阪府の道路使用許可/道路占用許可サポートサービスは、大阪府内全域に対応しております。お客様のお住まいの地域を問わず、まずはお気軽にご相談ください。
大阪府
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村
上記に記載のない地域、またはサービスの詳細な対応エリアについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
コラム:大阪府警とは
西日本の経済・文化の中心地であり、昼夜を問わず多くの人々が行き交う活気あふれる大都市圏・大阪府。その複雑で多様な都市の治安を守り、約880万人の府民の安全・安心な暮らしを確保するという重責を担っているのが、「大阪府警察」、通称「大阪府警」です。警視庁に次ぐ日本で二番目の規模を誇る警察組織として、日々様々な治安課題に取り組んでいます。
規模を活かした組織力と専門的な対応
大阪府警は、その大きな組織力を背景に、刑事、生活安全、交通、警備、地域警察など、各分野において高度な専門性を持つ多数の部署と人員を擁しています。これにより、都市部特有の複雑な事件や、大規模な繁華街におけるトラブル、巧妙化・国際化する組織犯罪、そして日々深刻化するサイバー犯罪など、高度な専門知識や捜査技術が求められる多様な事案にも的確に対応できる体制を整えています。
大規模イベント警備と府民生活の安全確保
大阪府内では、国際会議や大規模なスポーツイベント、伝統的な祭り、多くの観客が集まるコンサートなどが年間を通じて数多く開催されます。これらのイベントが安全かつ円滑に実施されるよう、事前の計画策定から当日の雑踏警備、交通整理、テロ警戒などを行うことも、大阪府警の重要な任務の一つです。こうした大規模警備と並行して、府民の日常生活を守るための地道なパトロール活動や、特殊詐欺・侵入盗などの身近な犯罪の抑止・検挙活動にも力を注いでいます。
コラム:大阪国道事務所とは
大阪府内の経済活動や多くの人々の移動を支える基幹的な道路網である国道。その中でも国が管理する区間について、日々の維持管理から計画的な整備・改築まで、幅広い業務を担当しているのが国土交通省 近畿地方整備局の出先機関である「大阪国道事務所」です。今回は、大都市・大阪の交通インフラを支える大阪国道事務所の主な役割と業務内容についてご紹介します。
国道の整備・改築と安全な道路環境の維持
大阪国道事務所の中心的な業務は、管轄する大阪府内の国道(例えば国道1号、2号、25号、26号、163号、170号などの一部区間)を、安全で快適、そして円滑に利用できるよう整備・管理することです。具体的には、交通渋滞の緩和や安全性の向上のための道路改良工事やバイパス整備、老朽化した橋梁の補修・架け替え、路面の維持修繕、道路標識や照明といった交通安全施設の設置・管理などを計画的に行っています。また、大雨や地震といった自然災害から道路を守るための防災対策も重要な任務です。
道路情報の提供と許認可・占用事務
安全な道路利用のためには、正確で迅速な情報提供が不可欠です。大阪国道事務所では、管内の道路工事に伴う交通規制(車線規制や通行止めなど)の情報や、災害発生時の道路状況などを、公式ウェブサイトや道路情報板、SNSなどを通じてリアルタイムに発信しています。さらに、国道敷地内で工事を行う、あるいは看板や日よけ、電柱などを設置する場合に必要となる「道路占用許可」の申請受付や審査、一定の大きさを超える特殊車両が通行する際の「特殊車両通行許可」に関する事務なども担当しており、国道の適正な利用と管理を推進しています。
コラム:道路交通法とは
道路は、歩いて渡る人、自転車で走る人、自動車やバイクを運転する人など、様々な立場の利用者が共有する公共の空間です。すべての人が安全に、そして円滑に道路を利用できるように、共通のルールを定めているのが「道路交通法」(略称:道交法)です。今回は、この法律がそれぞれの道路利用者にどのように関わっているのか、その基本的な考え方について見ていきましょう。
それぞれの立場に応じた通行方法と義務
道路交通法は、まず「歩行者」「自転車を含む軽車両」「自動車・原動機付自転車」といった区分で、それぞれの基本的な通行方法や守るべき義務を定めています。例えば、歩行者は原則として歩道や路側帯を通行すること、横断歩道を利用することなどが定められています。自転車利用者には、車道が原則で左側通行、ヘルメット着用の努力義務(※法改正により)、二人乗りの禁止(一部例外あり)などが定められています。そして自動車運転者には、速度制限の遵守、適切な車間距離の保持、横断歩道での歩行者優先、飲酒運転・無免許運転の絶対禁止などが厳しく義務付けられています。
相互理解と譲り合いで築く交通安全
この法律に定められたルールを知ることは、自分が違反しないようにするためだけでなく、他の道路利用者がどのようなルールに基づいて行動する(あるいは、すべき)かを理解するためにも非常に重要です。例えば、自動車の運転者が自転車の通行ルールを知っていれば、交差点での左折時などに自転車の動きをより注意深く予測できます。逆に自転車利用者が自動車の死角などを理解していれば、より安全な行動をとることができます。道路交通法は、単に違反を取り締まるためのものではなく、立場の違う者同士が互いを尊重し、譲り合うことで、皆で安全な交通社会を築いていくための基本的な約束事なのです。
コラム:道路法とは
高速道路から身近な生活道路まで、全国に張り巡らされた「道路」は、私たちの社会生活や経済活動を支える上で最も基本的なインフラの一つです。この大切な道路網を国民共有の財産として計画的に整備し、将来にわたって適切に維持管理していくための基本的なルールを定めているのが「道路法」です。今回は、交通ルールを定める道路交通法とは異なる、道路法そのものの役割について解説します。
道路網の体系的な整備と管理体制
道路法は、道路をその機能や重要性に応じて「高速自動車国道」「一般国道」「都道府県道」「市町村道」の4種類に分類し、それぞれの路線を指定・認定する手続きや、道路管理者(国、都道府県、市町村)を明確に定めています。これにより、国の基幹となる道路から地域住民の生活に密着した道路まで、全国的な視点での体系的な道路ネットワークの整備と、それぞれの道路に対する責任ある管理体制の構築を図っています。道路の新設や改築、維持・修繕などは、この法律に基づいて計画・実行されます。
公共の利益と私権との調整、適正な利用
新しい道路を造ったり、既存の道路を拡幅したりすることは、多くの人々の利便性を高め、地域経済の活性化にもつながる「公共の福祉」に貢献します。一方で、そのためには個人の土地が必要になるなど、私的な権利との調整が必要となる場面も生じます。道路法は、こうした公共の利益と私権との調整に関する手続きや、道路が安全な構造を持つための技術基準、さらには道路敷地の一部を工事やイベントなどで一時的に使用(占用)する場合の許可制度などを定めることで、道路が公共インフラとして最大限の効用を発揮し、かつ適正に管理・利用されることを目指しています。
- 【格安代行】三重県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】京都府の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】佐賀県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】兵庫県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】北海道の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】千葉県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】和歌山県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】埼玉県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】大分県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】大阪府の道路使用許可/道路占用許可を徹底解説!【2万5千円~】
- 【格安代行】大阪府の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】奈良県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】宮城県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】宮崎県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】富山県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】山口県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】山形県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】山梨県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】岐阜県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】岡山県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】岩手県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】島根県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】広島県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】徳島県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】愛媛県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】愛知県の道路使用許可/道路占用許可を徹底解説!【2万5千円~】
- 【格安代行】愛知県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】新潟県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】東京都の道路使用許可/道路占用許可を徹底解説!【2万5千円~】
- 【格安代行】東京都の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】栃木県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】沖縄県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】滋賀県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】熊本県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】石川県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】神奈川県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】福井県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】福岡県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】福島県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】秋田県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】群馬県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】茨城県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】道路使用許可/道路占用許可とは?申請手続きと違いを徹底解説【2万5千円~】
- 【格安代行】長崎県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】長野県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】青森県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】静岡県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】香川県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】高知県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】鳥取県の道路使用許可でおすすめの行政書士
- 【格安代行】鹿児島県の道路使用許可でおすすめの行政書士