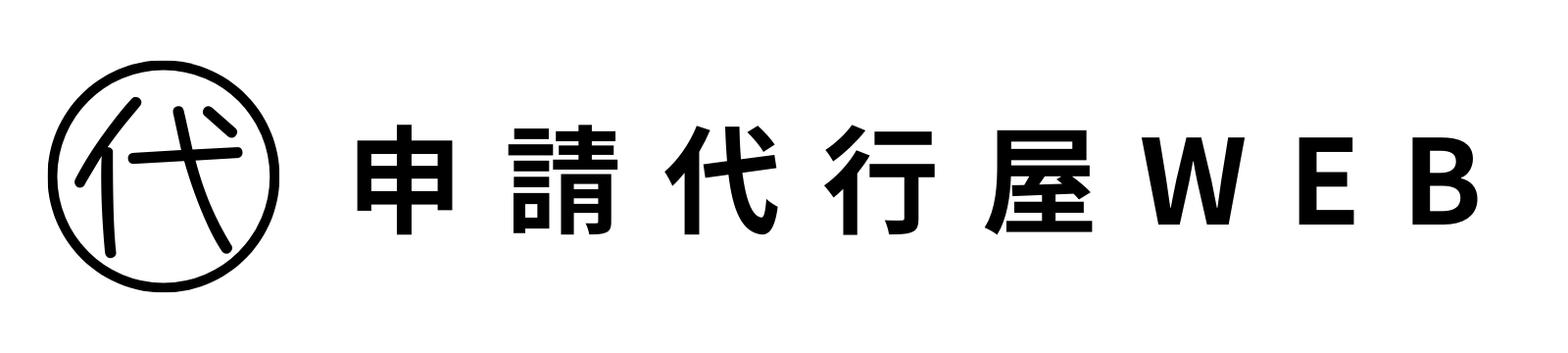近年、訪日外国人観光客の増加や2025年の大阪・関西万博開催への期待を背景に、大阪府内での「民泊」への関心が高まっています。民泊は、空き家や住宅を活用できる新たな宿泊ビジネスの選択肢として注目されていますが、実際に始めるには国の法律だけでなく、大阪府や物件所在地の市町村が定める条例・規則を正確に理解し、遵守する必要があります。
特に大阪市のような大都市では、地域の実情に合わせた独自の規制が設けられているため注意が必要です。
この記事では、大阪府で民泊事業を始めたいと考えている方に向けて、主に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」と「国家戦略特別区域法(特区民泊)」という2つの制度を中心に、事業形態の比較、必要な準備や手続き、満たすべき基準、運営上の注意点、費用、そして大阪府・市町村独自のルールまで、開業に必要な情報を網羅的に解説します。
\専門家がお手頃価格で代行/
民泊開業 大阪府でおすすめの行政書士事務所
🔵北海道石狩国際法務行政書士事務所

民泊・簡易宿所(シェアハウス)旅館開業申請承ります
経験豊富な行政書士が開業申請書類作成と申請を代行します‼
サービスの特徴
面倒な許認可申請は、専門家におまかせ!
- 経験豊富な行政書士が、書類の準備から許可までを完全サポート
- 民泊、簡易宿所、旅館事業など、各種申請に幅広く対応
全国での豊富な実績が信頼の証!
- 北海道から沖縄まで、全国各地での申請実績が多数
- 前年度は民泊から旅館まで、数多くの申請実績あり
レスポンスの良さで高評価!
- 利用者から「素晴らしい説明」「丁寧で迅速」と絶賛の声
分かりやすい料金体系で、納得の依頼!
- サービス基本料金に、許認可ごとの加算料金で構成
- 民泊事業、簡易宿所、旅館事業それぞれに明確な料金を設定
- 民泊申請:90,000円~
- 簡易宿泊所:170,000円~
\ 今すぐチェック!! /
🔵民泊専門の行政書士事務所



民泊申請・温泉申請┃12万円〜行政書士が対応します
一部サポート/全てお任せ/全国の民泊申請代行します
サービスの特徴
複雑な民泊申請は、専門家におまかせ!
- 民泊・旅館業に注力する行政書士が、申請を徹底サポート
- 年間30件以上の申請に対応する豊富な実績
- 複雑な法規制や地域ごとの条例も、きちんと調査
費用を抑えたい方に!選べるサポート体制!
- 「全てお任せ」から「一部サポート」まで、柔軟に対応
- 自分でできる作業は自分で行い、費用を抑えることが可能
- お客様の状況に合わせ、一番安価なプランを見積り作成
親切・丁寧な対応で高評価!
- 利用者から「とても親切で、安心してお任せできた」と絶賛の声
全国の書類作成と、一部地域の現場対応!
- 全国の民泊申請書類の調査・収集・作成に対応
- 関東近郊や大阪・京都では、保健所への相談や近隣説明なども代行可能
- 民泊申請:12万円~
\ 今すぐチェック!! /
🔵新谷行政書士事務所



民泊ついてお気軽に相談をお受けします
民泊・宿泊業界に詳しい行政書士にご相談ください
サービスの特徴
民泊・宿泊業界に詳しい行政書士が相談対応!
- 民泊(住宅宿泊事業法、旅館業法、特区民泊)の開業・運営に関する相談に行政書士が対応
- 業界に詳しい専門家が、これから民泊を始めたい方の不安や疑問を解消
- ぼんやりとしたイメージでも、気軽に相談可能
30分3,500円!ビデオチャットで全国対応!
- ビデオチャットで30分間、じっくり相談可能
- オンラインで全国どこからでも相談OK
- 相談料は30分3,500円の分かりやすい価格設定
ゲストハウス運営経験者が、実践的アドバイス!
- 講師自身も2019年にゲストハウスを開業した経験者(現在は行政書士・民泊代行)
- 運営経験者だからこそ分かる、実践的なノウハウや注意点をアドバイス
- 民泊開業までの流れ、Airbnbなどの活用法、許可取得のポイントなどをサポート
届出・申請の悩みも解決!スムーズな開業をサポート!
- 「どうやって申請すればいいか」「何から始めればいいか」といった具体的な手続きの悩みにも対応
- 専門家に任せることで、複雑な届出や申請の手間を削減し、ご自身の時間を有効活用
- 利用者からは「丁寧に教えてもらえた」「的確なアドバイス」と高評価
\ 今すぐチェック!! /
🔵デコレート行政書士事務所



48時間納品/行政書士が民泊新法の図面を作成します
民泊専門の行政書士による図面作成代行です。
サービスの特徴
70件以上の実績!民泊専門の行政書士が図面を作成!
- 民泊・旅館業の手続きで70件以上の実績を持つ、専門の行政書士が対応
- 民泊新法や旅館業許可申請に必要な、専門的な図面作成を代行
48時間納品!修正回数は無制限!
- お急ぎの方に最適!48時間以内に図面をスピード納品
- 納品後の軽微な修正や加筆は、いつでも何回でも無料で対応
図面作成に特化!PDF・JPGで納品!
- 依頼者は、壁芯が記載された物件資料などを提示するだけ
- 完成した図面は、PDFまたはJPG形式で納品
- 行政への提出は、利用者自身で行うサービス
- 民泊申請図面作成:4万円~
\ 今すぐチェック!! /
根拠法規:大阪の民泊を支えるルール
大阪府で民泊を始めるには、主に以下の法律や条例が関わってきます。
住宅宿泊事業法(民泊新法)
2018年に施行された、比較的新しい民泊のルールです。
- 定義
- 旅館業の許可を持たない人が、宿泊料を得て住宅に人を泊める事業で、年間の営業日数が180日を超えないもの。
- 「住宅」の条件
- 「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」があり、かつ「現在、人が住んでいる家」「入居者募集中の家」「持ち主などが随時使う家」のいずれかに該当する必要があります。
- 主な関係者
- 事業を行う「住宅宿泊事業者」、家主が不在の場合に管理を代行する「住宅宿泊管理業者」、宿泊予約を仲介する「住宅宿泊仲介業者」がいます。
- 主な義務
- 施設の衛生管理、宿泊者への騒音防止等の説明、近隣からの苦情対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示などが定められています。
- 監督
- 都道府県知事等(大阪市などの保健所設置市では市長)が届出受理や指導を行います。
国家戦略特別区域法(特区民泊)
特定の地域(国家戦略特区)で、地域の活性化などを目的に、旅館業法の規制を緩和する制度です。大阪府や大阪市の一部地域で認められています。
- 旅館業法の適用除外
- 条例で定められた要件を満たし、自治体から「特定認定」を受ければ、旅館業法の適用を受けずに宿泊事業を行えます。
- 実施可能エリア
- 国が指定した特区内で、かつ自治体が条例で認めた地域に限られます。
- 主な要件
- 原則2泊3日以上の宿泊、居室面積25㎡以上、外国語での案内提供などが基本的な条件となります。
大阪府及び市町村の条例・規則
国の法律に加え、大阪府や各市町村(特に大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、枚方市、豊中市など)が独自の条例や規則を定めています。これにより、国や府の基準より厳しいルール(例:営業できる区域の制限、住民への説明義務など)が課される場合があります。事業を行う場所の市町村のルールを必ず確認することが非常に重要です。
事業形態の比較:あなたに合うのはどのタイプ?
大阪府で可能な主な民泊の形態には、それぞれメリット・デメリットがあります。
住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊
- 家主居住型
- 事業者自身が住んでいる家で、宿泊者を受け入れるタイプ。管理業者への委託は不要です。
- 家主不在型
- 事業者が住んでいない家で、宿泊者を受け入れるタイプ。運営業務(標識掲示除く)のほぼ全てを登録された住宅宿泊管理業者に委託することが法律で義務付けられています。
- 年間営業日数
- いずれも年間180日以内。
- 最低宿泊日数
- 制限なし(1泊から可能)。
- 実施可能地域
- 工業専用地域を除き、原則として用途地域による制限は緩やか(住居専用地域でも可能)。ただし、大阪市のように学校周辺での営業が制限されるなど、自治体独自のルールがあります。
- メリット
- 特区民泊より始められるエリアが広い。1泊からの短期需要に対応できる。家主居住型は比較的始めやすい。
- デメリット
- 年間180日の営業日数制限が収益の大きな制約になる。家主不在型は管理委託コストがかかる。
特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)
- 年間営業日数
- 制限なし(365日可能)。
- 最低宿泊日数
- 原則2泊3日以上(1泊は不可)。
- 実施可能地域
- 国家戦略特区内で、自治体が条例で定めた限定的な地域のみ。大阪市では主にホテル・旅館が建てられる地域に限られます。住居専用地域では原則不可。
- 施設要件
- 居室面積が原則25㎡以上など、民泊新法より厳しい基準があります。
- その他
- 外国語での案内提供が必須。手続きは「届出」ではなく「認定」が必要です。管理業者の委託義務はありません。
- メリット
- 年間営業日数に制限がなく、高い収益性が期待できる。
- デメリット
- 実施できるエリアが限定的。2泊3日以上の滞在が必要。施設要件(特に面積)が厳しい。
旅館業法に基づく許可(参考)
ホテル、旅館、簡易宿所などがこれにあたります。「許可」が必要で、一般に民泊制度より施設基準(フロント設置など)や用途地域の要件が厳しいですが、営業日数や最低宿泊日数の制限はありません。
どの形態を選ぶかは、物件の場所や広さ、ターゲット客層、かけられる費用、許容できる規制の厳しさなどを総合的に考えて決める必要があります。
フェーズ1:事前準備・確認事項
申請・届出の前に、必ず以下の点を確認・相談しましょう。
物件の適格性評価
- 用途地域
- 物件がある場所の都市計画上の用途指定を確認。特に特区民泊は実施可能エリアが限られます。市町村の都市計画担当部署に確認しましょう。
- 建築基準法適合性
- 建物が建築基準法に合っているか。検査済証の有無や、特に耐震性・防火性が重要です。不明な点は建築士に相談を。
- 賃貸借契約(賃貸物件の場合)
- 契約書で「民泊不可」となっていないか確認。記載がなくても、必ず大家さん(所有者)から書面で民泊使用の承諾を得る必要があります。転貸(又貸し)の場合は、元の所有者と直接の貸主双方の承諾が必要です。
- マンション管理規約(分譲マンション等の場合)
- 管理規約で「民泊禁止」なら不可。禁止されていなくても、管理組合から民泊実施を禁止しない旨の証明書(承諾書や議事録写し等)をもらう必要があります。他の住民の理解を得るのが難しい場合もあります。
事前相談の重要性
申請・届出前に、以下の関係機関への事前相談が実務上必須です。物件の図面など、具体的な資料を持っていくとスムーズです。
- 保健所
- 許認可の中心的な窓口。物件の適格性、手続き、必要書類、地域独自のルールについて相談します。物件所在地を管轄する保健所に連絡しましょう。
- 消防署
- 最重要の相談先です。民泊は一般住宅より厳しい消防法基準が適用されることが多いです。必要な消防設備(火災報知器、誘導灯、消火器など)について、工事や購入前に必ず確認し、「消防法令適合通知書」の交付を受ける必要があります。
- 環境局等(廃棄物担当)
- 民泊のごみは「事業系ごみ」扱いとなり、家庭ごみとは別の処理(許可業者との契約等)が必要です。事前にごみ処理計画について相談し、手続きを確認します(特に大阪市など)。
- 建築士・行政書士等
- 専門的な判断や複雑な手続きの代行が必要な場合に相談します。
これらの事前確認・相談を怠ると、後で計画変更や追加費用が発生したり、最悪の場合、法令違反となるリスクがあります。
フェーズ2:申請・届出手続き
事前準備が整ったら、いよいよ申請・届出です。
必要書類の準備
非常に多くの書類が必要です。事業形態や物件状況によって異なりますので、必ず事前に管轄の保健所に確認してください。主なものを挙げます。
- 共通
- 申請書/届出書、住民票(個人)/登記簿謄本・定款(法人)、物件の権利書(登記簿謄本や賃貸借契約書+承諾書)、マンションの場合は管理規約+組合の証明書、物件の図面(各階平面図、設備位置、面積、安全措置、避難経路などを明記)、消防法令適合通知書(写し)。
- 住宅宿泊事業(家主不在型)
- 管理業者との管理受託契約書の写し。
- 特区民泊
- 宿泊者と結ぶ賃貸借契約等の約款。
- その他
- 周辺住民への事前説明に関する書類、廃棄物処理方法に関する書類、苦情対応体制を示す書類、宿泊者名簿の様式、欠格事由に該当しない旨の誓約書など。
書類不備があると受理されません。細心の注意を払って準備しましょう。
提出・審査プロセス
- 提出方法
- 民泊新法は国の「民泊制度運営システム」でオンライン提出が原則。特区民泊は自治体の指示に従います。
- 提出先
- 物件所在地を管轄する保健所の担当部署。
- 審査
- 保健所が書類を審査します。
- 現地調査
- 書類審査後、通常、保健所職員による現地調査が行われます(特区民泊は必須)。施設が申請内容通りか、基準を満たしているかを確認します。
- 結果
- 住宅宿泊事業:受理されると届出番号が付与されます。
- 特区民泊:認定されると特定認定書が交付されます。
- 標識の受領・掲示
- 届出受理・認定後、交付される公的な標識を、施設の外部から見やすい場所に掲示する義務があります。
審査には数週間〜数ヶ月かかることもあります。余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
フェーズ3:施設整備 – 基準の遵守
民泊として営業するには、以下の設備・安全基準を満たす必要があります。
基本的な設備要件
- 必須
- 「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」。
- 特区民泊(大阪市)の追加要件例
- 台所と洗面は別、飲用適の水供給、電子レンジ・コンロ、掃除機、ごみ箱など、より詳細な規定があります。
居室の面積と構造
- 住宅宿泊事業法
- 法律上の最低面積規定はなし。ただし、宿泊者1人あたり3.3㎡以上の確保が必要(定員10人未満の場合)。
- 特区民泊(大阪市)
- 一居室あたり25㎡以上(壁芯計算)が厳格に求められます。各部屋が基準を満たす必要があり、例外はありません。
安全確保・消防設備(最重要項目)
人命に関わるため、消防法の遵守は絶対です。必ず事前に消防署に相談・確認してください。
- 主な設備
- 消火器、自動火災報知設備、非常用照明器具、誘導灯、避難経路表示、避難経路図の掲示。
- 防炎物品
- カーテン、じゅうたん等は防炎性能のあるもの(防炎ラベル付き)を使用。
- 避難経路の確保
- 廊下や階段等に物を置かず、常に確保・明示。
- 消防法令適合通知書
- 消防署の検査を経て交付される、適合証明書。申請・届出に必須です。
消防設備の設置・改修には高額な費用がかかる場合があります。事業計画の大きな要素となります。
換気・採光・衛生
- 適切な換気設備(窓または機械換気)。
- 適度な採光と照明設備。
- 常に清潔を保ち、害虫駆除措置。宿泊者入れ替え時の清掃・消毒、シーツ交換は必須。
- 安全な飲用水の供給(水道水以外は水質検査が必要な場合あり)。
家具・備品
寝具、テーブル、椅子、収納、調理器具、食器、清掃用具など、生活に必要なものを備え付けます。
外国語対応・標識
- 外国語対応(特区民泊必須)
- 施設案内や緊急時情報を、少なくとも1言語以上の外国語で提供。
- 標識掲示
- 交付された公的標識を、外部から見やすい場所に掲示。
- その他推奨表示
- 避難経路図、ハウスルール、ごみ分別案内など。
フェーズ4:運営上の義務とルール
開業後も、様々なルールを守り続ける必要があります。
宿泊者管理
- 宿泊者名簿の作成・備付け・保管
- 宿泊者の氏名、住所、職業、宿泊日を記載。外国人(国内住所なし)の場合は国籍・旅券番号も必須で、パスポートの提示を求め、写しを名簿と共に保存します。
- 本人確認
- 確実に行います(特に外国人)。
- 契約者以外の滞在禁止
- 原則禁止であり、宿泊者に周知が必要です。
騒音防止・廃棄物処理
- 騒音防止
- 宿泊者に騒音防止(特に夜間)を注意喚起。近隣から苦情があれば迅速・適切に対応。
- 廃棄物処理
- 民泊のごみは事業系ごみです。家庭ごみ集積所には出せません。自治体の許可を持つ産業廃棄物処理業者と契約し、収集を依頼します。宿泊者には分別・保管・排出ルールを明確に指示します。
近隣住民への配慮と苦情対応
- 事前の説明
- 事業開始前に周辺住民へ説明を行うことが推奨され、義務付けられている場合もあります(特に大阪市特区民泊の説明会)。
- 苦情対応体制
- 近隣からの苦情・問合せに対応する窓口(連絡先)を設置し、周知。迅速・誠実に対応。
- 日常的な配慮
- 共用部分の使い方、駐車・駐輪マナー、喫煙場所などもルールを周知し、配慮します。
緊急時の対応
- 体制整備
- 24時間対応可能な連絡体制。家主不在型や特区民泊では、事業者が迅速に現場に駆けつけられる体制(例:おおむね10分程度)が求められます。
- 情報提供
- 緊急連絡先、避難場所・経路等を宿泊者に分かりやすく提供(特区民泊は外国語も)。
- 対応マニュアル
- 作成し、いつでも参照できるようにしておくことが望ましいです。
衛生・安全管理の維持
- 定期的な清掃、消毒、換気。
- 消防用設備等の定期点検・メンテナンス。
これらの義務を怠ると、近隣トラブルや行政指導、最悪の場合は事業停止につながる可能性があります。
費用と資金調達
民泊事業のコストを正確に見積もりましょう。
初期費用(開業費用)
- 許認可手数料
- 特区民泊認定申請料(大阪府は新規21,200円など)。民泊新法届出は基本無料(書類取得費は別途)。
- 物件関連費用
- 購入費または賃貸初期費用(敷金礼金等)。
- 改修・リフォーム費用
- 法令基準適合、消防設備設置(高額になる可能性あり)、内装美装化など。
- 設備・備品購入費用
- 家具、家電、寝具、食器、アメニティなど。
- 専門家への報酬
- 行政書士、建築士、税理士などへの依頼費用。
- その他
- 鍵交換、ネット回線、初期広告費など。
運営費用(ランニングコスト)
- 賃料・管理費(賃貸の場合)
- 水道光熱費、通信費
- 清掃費、リネンサプライ費
- 消耗品費
- 廃棄物処理費(業者契約料)
- 保険料(火災保険、賠償責任保険への加入推奨)
- 管理委託手数料(該当する場合)
- 予約サイト手数料
- 修繕・維持管理費
- 広告宣伝費
税金
- 所得税または法人税
- 消費税(売上による)
- 固定資産税・都市計画税(所有物件の場合)
- 個人事業税(該当する場合)
- 宿泊税(大阪府)
- 現在は1人1泊あたりの宿泊料金(食事代等を除く)が7,000円以上の場合に100円~300円が課税されます。事業者は宿泊者から徴収し、府に納付する義務があります。ただし、2025年9月1日宿泊分からは、課税対象となる最低宿泊料金が5,000円以上に引き下げられ、各料金区分の税率も引き上げられる予定です。 将来の事業計画を立てる際には、この変更点も考慮に入れる必要があります。
補助金・融資制度
民泊特化のものは限定的ですが、中小企業支援の一環として、設備投資(省エネ、バリアフリー、防災等)への補助金や低利融資が利用できる可能性があります。大阪府や市町村の商工担当部署、日本政策金融公庫などに確認しましょう。
収支計画は、180日制限(民泊新法の場合)なども考慮し、慎重に立てることが重要です。
地域独自の規制:大阪府・大阪市及びその他主要市町村
大阪府内、特に大阪市など保健所を設置する市では、国や府の基準に加えて独自の規制(上乗せ条例)があるため、最大限の注意が必要です。
大阪市における主な独自規制例
- 特区民泊の実施区域
- ホテル・旅館建築可能地域に限定。
- 特区民泊の最低居室面積
- 25㎡以上(例外なし)。
- 特区民泊の住民説明
- 説明会の開催が義務(ポスティングのみは不可)。
- 住宅宿泊事業の学校周辺営業制限
- 小学校等の周囲100m以内では、家主不在型は月曜正午〜金曜正午の営業不可。
- 住宅宿泊事業の接道要件
- 住居専用地域では幅員4m以上の道路に接すること。
- 住宅宿泊事業の届出時の消防法令適合通知書
- 提出が必須。
その他の市町村の動向
保健所設置市以外の市町村でも、特区民泊の実施状況(全域実施、一部実施、実施しない)は異なります。また、騒音・ごみ等に関して市町村レベルのガイドライン等が存在する可能性もあります。必ず事業地の市町村に最新情報を確認してください。
相談窓口及び情報源
不明な点は、以下の窓口や情報源を活用しましょう。
公的相談窓口
- 大阪府 健康医療部 生活衛生室 環境衛生課(府管轄地域)
- 大阪市 健康局 環境衛生監視課(大阪市内)
- その他の保健所設置市の担当部署(堺市、東大阪市、高槻市、枚方市、豊中市)
- 各市町村の担当部署(上記以外の市町村)
- 所轄消防署(消防法関連)
- 各自治体の環境担当部署(廃棄物関連)
- 国の民泊制度コールセンター(制度全般の問合せ)
専門家によるサポート
- 行政書士
- 申請・届出手続き代行
- 建築士
- 建築基準法適合確認、改修設計
- 弁護士
- 法的トラブル相談
- 税理士
- 税務相談
- 不動産コンサルタント・民泊運営代行会社
- 事業計画、運営実務相談
信頼できる情報源(ウェブサイト等)
- 国土交通省 観光庁 民泊制度ポータルサイト「minpaku」
- 大阪府庁ウェブサイト(健康医療部 生活衛生室 環境衛生課など)
- 大阪市役所ウェブサイト(健康局など)
- その他市町村ウェブサイト
- 消防庁ウェブサイト、各消防本部ウェブサイト
まとめ
大阪府での民泊事業は、大きな可能性がある一方で、国の法律、府・市町村の条例・規則が複雑に絡み合い、厳しい基準や地域への配慮が求められます。成功のためには、
- 事業形態(民泊新法か特区民泊か)を慎重に選択する。
- 物件の適格性を確認し、保健所・消防署等への事前相談を必ず行う。
- 必要な書類を漏れなく準備し、手続きを進める。
- 施設基準(特に消防設備)を確実に満たす。
- 運営上の義務(名簿管理、騒音・ごみ対策、近隣対応、緊急時対応等)を継続的に遵守する。
- 費用を正確に見積もり、採算性を評価する(将来の宿泊税変更も考慮)。
- 大阪市など、地域独自の規制を必ず確認・遵守する。
ことが不可欠です。最新情報を常に確認し、必要に応じて専門家の力も借りながら、計画的に事業を進めていきましょう。
参考資料
大阪府内のサービス提供地域
大阪府の民泊開業サポートサービスは、大阪府内全域に対応しております。お客様のお住まいの地域を問わず、まずはお気軽にご相談ください。
大阪府
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村
上記に記載のない地域、またはサービスの詳細な対応エリアについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
コラム:大阪府行政書士会とは
建設業許可や飲食店営業許可、会社設立、相続・遺言に関する手続き、外国人の在留資格申請など、私たちの暮らしやビジネスには多種多様な行政手続きや書類作成が伴います。これらの専門家として活躍するのが「行政書士」です。活発な経済活動が展開される大阪府内で活動する行政書士が所属し、その資質向上と府民からの信頼確保を図るための法定団体が「大阪府行政書士会」です。今回は、その役割や府民向けのサービスについてご紹介します。
行政書士の資質向上と制度発展への貢献
大阪府行政書士会は、会員である行政書士が常に質の高いサービスを提供できるよう、最新の法令知識や実務に関する研修会などを企画・実施しています。また、行政書士としての倫理観を高め、業務が適正に行われるよう、会員への指導や監督も行っています。これらを通じて行政書士全体の専門性と信頼性を維持・向上させるとともに、行政書士制度の意義や役割を社会に広く知らせるための広報活動や、無料相談会などを通じた社会貢献にも積極的に取り組んでいます。
府民・事業者のための相談窓口機能
「どの行政書士に相談すればいいかわからない」「相続手続きについて専門家のアドバイスが欲しい」といった場合、大阪府行政書士会は府民や事業者にとって頼りになる相談窓口となります。会の公式ウェブサイトなどでは、お住まいの地域(大阪府内には複数の支部があります)や、依頼したい業務内容(許認可、法人関連、民事法務など)から、登録されている会員行政書士を探すことができる検索システムが提供されていることが一般的です。また、府内各地で定期的に無料相談会を開催し、様々な分野の相談に所属する行政書士が直接応じる機会を設けている場合もありますので、情報を確認してみると良いでしょう。
- 【格安代行】三重県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】京都府の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】佐賀県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】兵庫県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】北海道で民泊開業!始め方を徹底解説!
- 【格安代行】北海道の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】千葉県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】和歌山県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】埼玉県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】大分県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】大阪府で民泊開業!始め方を徹底解説!
- 【格安代行】大阪府の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】奈良県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】宮城県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】宮崎県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】富山県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】山口県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】山形県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】山梨県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】岐阜県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】岡山県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】岩手県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】島根県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】広島県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】徳島県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】愛媛県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】愛知県で民泊開業!始め方を徹底解説!
- 【格安代行】愛知県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】新潟県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】東京都で民泊開業!始め方を徹底解説!
- 【格安代行】東京都の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】栃木県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】民泊とは?メリット・デメリットから法律、今後の展望まで徹底解説
- 【格安代行】民泊の開業!始め方を徹底解説!
- 【格安代行】沖縄県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】滋賀県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】熊本県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】石川県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】神奈川県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】福井県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】福岡県で民泊開業!始め方を徹底解説!
- 【格安代行】福岡県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】福島県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】秋田県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】群馬県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】茨城県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】長崎県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】長野県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】青森県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】静岡県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】香川県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】高知県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】鳥取県の民泊開業でおすすめの行政書士4選
- 【格安代行】鹿児島県の民泊開業でおすすめの行政書士4選