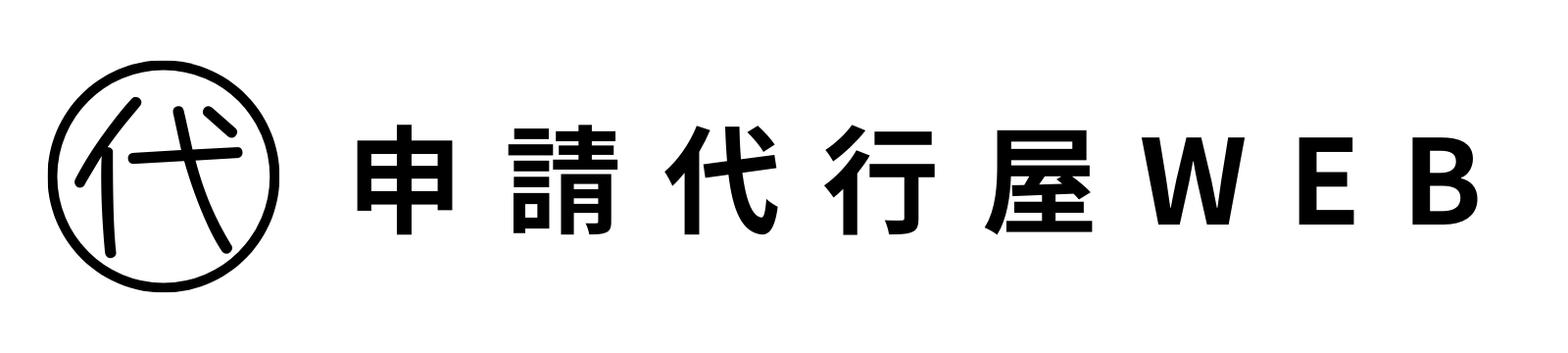中古品の売買やレンタル、リサイクルショップの経営などを事業として行う際に、避けて通れないのが「古物商許可」の取得です。フリマアプリの普及などで個人間の取引が活発になっていますが、利益目的で中古品を継続的に取り扱う場合は、この許可が必要不可欠となります。
「自分は対象になるのか?」「手続きが難しそう」「どんな義務があるの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、古物商許可の基本的な概要から、許可が必要となる具体的なケース、申請手続きの詳細、許可取得後の重要な義務、そして違反した場合の罰則に至るまで、網羅的に解説します。これから古物営業を始めようと考えている方、既に事業を行っているが改めて制度を確認したい方は、ぜひ参考にしてください。
\専門家がお手頃価格で代行/
4,000円~!古物商許可 おすすめの行政書士事務所
🔵古物商専門の行政書士事務所

古物商┃専門の行政書士が申請書を作成します
個人4000円法人6000円┃日本全国・賃貸物件・外国籍の方
サービスの特徴
古物商専門の行政書士が、あらゆるケースに対応!
- 古物商許可を専門とする行政書士が、申請書を作成
- 法人、全国、賃貸、外国籍、違法状態の方まで全て対応可能
- メルカリでの販売や中古車店、せどりなど、様々なビジネスに対応
個人4000円・法人6000円!分かりやすい料金体系!
- 個人は4,000円、法人は6,000円という、明確で手ごろな価格
- 役員や事業所の追加も、1,000円からのオプションで対応
申請書だけじゃない!充実の購入者特典!
- 取引記録に使える「古物台帳」を無料で提供
- 申請の流れや注意点、質問想定集も入った「準備完全マニュアル」付き
- 許可取得後の住所変更などの相談も無料で対応
マニュアル完備で安心!信頼の高評価!
- マニュアル付きで、警察署への提出も安心
- 豊富な販売実績と、高評価で信頼できる
- 利用者からは「丁寧にご対応くださり、安心できた」との声
専門家への依頼がこの価格で!
- 行政書士による本格的な書類作成サポートが、驚きの価格で実現
- 個人:4,000円~
- 法人:6,000円~
- 書類作成・申請代行:35,000円~
\ 今すぐチェック!! /
🔵栗原行政書士事務所



行政書士が古物商許可証の申請書類を作成します
古物営業を始められる方、迅速かつ誠心誠意サポート致します
サービスの特徴
自身も許可取得済み!経験豊富な行政書士がサポート!
- 自らも古物商許可証を取得した行政書士が、その経験を基に的確にアドバイス
- 法律を遵守し、申請に関わる全てのプロセスをサポート
警察との事前打合せも!安心の徹底サポートフロー!
- 事業内容のヒアリングから、申請要件の確認まで徹底
- 必要に応じて、警察署と事前に打ち合わせを行い、スムーズな申請を実現
- 完成した書類はPDFで送付、依頼者は内容確認後に警察署へ提出するだけ
まずは無料の見積り相談から!
- 法人申請や、役員・営業所の追加も、明確なオプション料金で対応
- 警察への申請手数料19,000円は、別途必要
迅速・丁寧な対応で、信頼の高評価!
- 豊富な販売実績と、多数のレビューで高評価
- 利用者からは「親切、丁寧、迅速!」「とてもスムーズ」と絶賛の声
- 初回の返答時間は1時間以内で、スピーディーなやり取りが可能
専門家への依頼がこの価格で!
- 行政書士による本格的な書類作成サポートが、驚きの価格で実現
- 個人:5,000円~
- 法人:7,000円~
\ 今すぐチェック!! /
🔵おおば法務事務所



古物商許可の申請書類を作成します
法人様・日本全国・賃貸物件・外国籍の方全て対応可能です!
サービスの特徴
面倒な書類作成は、専門家におまかせ!
- 国家資格を持つ行政書士が、古物商許可の完璧な申請書類を作成
- 複雑な案件でも安心 警察との事前打ち合わせまで代行してくれる
あらゆるケースに対応する、その対応力が魅力!
- 法人・個人はもちろん、日本全国、外国籍の方の申請まで幅広く対応
- 「賃貸で大家さんの承諾が得られない…」そんなお悩みも、許可取得のノウハウでしっかりサポート
あなたの手間は最小限!とにかく楽でスピーディ!
- 完成した書類に署名・捺印し、警察署に提出するだけで申請が完了
- 必要な情報が揃えば、最短2日(予定)で申請書類一式が手元に届くスピード感
豊富な実績と、驚異の高評価が信頼の証!
- 数多くの販売実績を誇り、レビューでは利用者から最高の評価を獲得
- 圧倒的多数の利用者から満点の評価を得ており、「迅速で助かった」「丁寧で安心できた」など、満足の声が寄せられている
取得後も嬉しいサポート体制!
- 取引記録に使える「古物台帳」を無料でプレゼント
- 許可取得後も、住所変更などの相談がなんと無料でできる万全のアフターフォロー付き
専門家への依頼がこの価格で!
- 行政書士による本格的な書類作成サポートが、驚きの価格で実現
- 個人:4,000円~
- 法人:6,500円~
\ 今すぐチェック!! /
古物商許可って何? 基本的な知識と目的を理解しよう
古物商許可の基本的な定義
古物商許可とは、個人または法人が、利益を得る目的で「古物」を売買、交換、または委託を受けて売買・交換する営業(古物営業)を行う際に、都道府県公安委員会から取得しなければならない許可のことです。申請は、事業の中心となる営業所の所在地を管轄する警察署が窓口となります。
この制度は「古物営業法」という法律に基づいています。リサイクルショップや中古書店といった実店舗はもちろん、インターネットを利用した中古品の売買も、事業として行うのであればこの許可が必要です。
「営業」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続して行うことを指します。したがって、一度きりの取引であっても、利益を得る目的があれば「営業」とみなされ、許可が必要になる可能性があります。
許可制度はなぜあるの? 盗品流通防止という大切な役割
古物営業法および古物商許可制度の最も重要な目的は、盗品などの不正な物品が市場に流通することを防ぎ、万が一流通した場合に迅速に発見・回復を図ることにあります。
中古品市場は、残念ながら窃盗犯が盗んだ品物を換金する場として利用されるリスクがあります。そこで、古物を取り扱う事業者を許可制とし、取引相手の身元確認や取引記録の保存といった義務を課すことで、盗品の流通を抑制し、捜査機関が不正品を追跡しやすくする仕組みを設けているのです。
特に、盗品が市場に入り込む主な経路である「買い取り」や「仕入れ」の段階に規制の重点が置かれています。この制度目的を理解することは、後述する様々な義務の根拠を知り、コンプライアンス意識を高める上で非常に重要です。
古物営業にはどんな種類がある?
古物営業法では、古物に関する営業を以下の3つに分類しています。
- 古物商
- 古物を売買、交換、または委託を受けて売買・交換する営業。最も一般的な形態で、リサイクルショップ、中古車販売店、古本屋などが該当します。この記事で主に解説するのはこの「古物商」です。
- 古物市場主
- 古物商間で古物の売買・交換を行うための市場(古物市場)を経営する営業。
- 古物競りあっせん業
- インターネットオークションのように、競りの方法で古物売買をあっせんする営業(例:ネットオークションサイト運営者)。こちらは許可ではなく「届出」が必要です。
自身の事業内容がどの種類に該当するかを正しく理解し、適切な手続き(許可申請または届出)を行う必要があります。
古物商許可は必要? あなたのビジネスが対象かチェック!
こんな活動には許可が必要です
具体的にどのような活動に古物商許可が必要なのでしょうか。営利目的で反復継続して以下の行為を行う場合、許可が必要です。
- 古物を買い取って販売する
- 古物を買い取って修理・加工して販売する
- 買い取った古物から部品等を販売する(例:中古車のパーツ販売)
- 他人の古物を預かり販売し手数料を得る(委託販売)
- 古物を他の物品と交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買い取った古物を海外へ輸出して販売する
- 上記のいずれかをインターネット上で行う
- 古物を下取りする
新品販売時に中古品を下取りする行為は、古物の「買い受け」にあたるため、原則として許可が必要です。- 【例外:許可が不要な下取り】
ただし、「下取り」という名目であっても、実質的に顧客サービスとしての一律の値引きとみなされる場合は、例外的に許可が不要です。これは、以下の両方の要件を満たす場合に限られます。- 形式的要件
会計処理上、新品の販売価格からの「値引き」として扱われている。 - 実質的要件
顧客サービスの一環として行われ、下取りする古物の市場価格(状態や型番など)を個別に査定せず、誰に対しても同じ金額を値引く。 - 具体例
「古いテレビの種類や状態に関わらず、新しいテレビを購入すれば一律〇〇円値引き」といったケースがこれに該当します。
- 形式的要件
- 【注意:許可が必要な下取り】
逆に、下取りする古物の市場価値(状態、型番、人気度など)に応じて値引き額(下取り価格)を変える場合は、実質的な「買取り」行為と判断され、原則通り古物商許可が必要になります。
- 【例外:許可が不要な下取り】
たとえ1回の取引でも、営利目的であれば許可が必要になる場合があります。特に委託販売は、商品を直接仕入れなくても許可対象となる点に注意が必要です。
こんな場合は許可が不要(例外と注意点)
一方で、以下のような場合は原則として古物商許可は不要です。
- 自分の不用品を売る
もともと自分で使う目的で購入した物(転売目的で仕入れた物を除く)を売る場合。フリマアプリでの売却もこれに含まれます。- 【注意点】
ただし、「不用品」の売却であっても、客観的に見て実質的に「事業」とみなされる場合は許可が必要になります。「事業」と判断されるかどうかは、個別のケースによりますが、一般的に以下の要素などを総合的に見て判断されます。- 営利(転売)目的での仕入れの有無
転売して利益を得る目的で商品を仕入れているか。 - 取扱商品の種類や数量
特定の種類の商品を大量に、または同じ商品を何度も繰り返し出品しているか。 - 取引の反復継続性
長期間にわたり、頻繁に取引を行っているか。 - 得ている利益の規模
社会通念上、お小遣い稼ぎの範囲を超え、事業として成立する規模の利益を継続的に上げているか。
- 営利(転売)目的での仕入れの有無
- 特に、フリマアプリなどを利用したいわゆる「せどり」や「転売ヤー」と呼ばれる行為は、これらの要素から客観的に「事業」と判断され、古物商許可が必要となる可能性が高いと言えます。ご自身の活動がどちらに該当するか判断に迷う場合は、無許可営業のリスクを避けるためにも、警察署や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
- 【注意点】
- 無償で譲り受けた物を売る
- 無料で入手した物を販売する場合。
- 処分費用を受け取って引き取った物を売る
- 相手から処分費用をもらって回収した物を販売する場合(別途、廃棄物処理業の許可が必要な場合あり)。
- 自分が売った相手から直接買い戻す
- 一度販売した商品を、その販売相手本人から買い戻す場合。
- 自分で海外で購入し輸入した物を売る
- 自身で海外から買い付けて輸入した物を国内で販売する場合(他者が輸入した物を国内で仕入れて売る場合は許可が必要)。
- 新品のみを販売する
- メーカーや卸から仕入れた新品のみを販売する場合。
- 消費される物、実体のない物などを販売する
- 化粧品、酒類、食品、医薬品、電子チケットなど。
「古物」って何? 法律上の定義と意外なポイント
古物営業法における「古物」とは、以下のいずれかに該当する物品を指します。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの(例:新品として購入後、未使用のまま保管していた物)
- これらの物品に幾分の手入れ(修理等)をしたもの
重要なのは、物の新しさ・古さではなく、「一度でも消費者の手に渡ったか、または使用目的で取引されたか」という点です。
したがって、小売店で買った「新品・未使用」の品物も、それを転売目的で仕入れて販売する場合は、法律上「古物」として扱われ、古物商許可が必要になります。この点は一般的な感覚と異なる場合があるため、注意が必要です。
古物の13品目区分
古物営業法では、取り扱う古物を以下の13品目に分類しています。許可申請時には、主に取り扱う品目を選択する必要があります。
- 美術品類:絵画、骨董品、日本刀など
- 衣類:和服、洋服、布団など
- 時計・宝飾品類:時計、宝石、貴金属など
- 自動車:本体、部品、カーナビなど
- 自動二輪車及び原動機付自転車:バイク本体、部品など
- 自転車類:本体、部品など
- 写真機類:カメラ、レンズ、望遠鏡など
- 事務機器類:パソコン、コピー機、電話機など
- 機械工具類:工作機械、医療機器、家電、工具など
- 道具類:家具、楽器、CD/DVD/ゲームソフト、おもちゃ、雑貨など(他の12品目に該当しないもの)
- 皮革・ゴム製品類:カバン、靴、毛皮など
- 書籍
- 金券類:商品券、乗車券、切手、チケットなど
申請時には、これらの品目から主に取り扱うものを1つ選びますが、複数の品目を取り扱うことも可能です。ただし、むやみに多くの品目を選択すると、警察からの問い合わせが増える可能性もあるため、事業計画に基づき、必要かつ十分な品目を選択することが重要です。
古物商許可の申請方法:手続きの流れを分かりやすく解説
申請手続きの流れ
古物商許可の申請は、一般的に以下の流れで進めます。
- 事前準備・確認
- 許可が必要か確認
- 申請スケジュール検討
- 個人/法人どちらで申請するか決定
- 欠格事由に該当しないか確認(申請者、役員、管理者)
- 取り扱う古物品目を決定
- 営業所の場所を確保し、使用権限を確認
- 営業所の管理者を決定
- 申請先の警察署(主たる営業所の管轄)を確認
- 【重要】警察署への事前相談
必要書類や、後述する「ローカルルール」について確認する。
- 申請書類の収集・作成
- 住民票、身分証明書、略歴書、誓約書、法人書類などを収集
- 許可申請書を作成
- 書類の整理
- 収集・作成した書類一式を不備なくまとめる
- 警察署への申請
- 事前に担当窓口(生活安全課 保安係等)に連絡し、訪問日時を予約推奨
- 予約日時に警察署へ出向き、書類一式を提出
- 申請手数料(19,000円)を納付
- 警察による審査
- 標準処理期間:約40営業日(約2ヶ月)
- 審査期間中は古物営業を開始できない
- 許可・不許可の連絡
- 警察署から電話等で結果連絡
- 許可証の受領
- 許可が下りたら、再度警察署へ出向き、許可証を受け取る
申請前の最重要ポイント:警察署への事前相談と「ローカルルール」
古物商許可申請において、非常に重要なステップが、申請前に「主たる営業所の所在地を管轄する警察署」に事前相談することです。
なぜなら、古物商許可申請に必要な書類の解釈や要件、特に「営業所の使用承諾書」の要否や書式、提出範囲などについて、全国一律の明確な基準が存在するわけではなく、都道府県警察や個々の警察署によって運用が異なる、いわゆる「ローカルルール」が存在する可能性が高いからです。
インターネットや書籍の情報だけを鵜呑みにして準備を進めると、いざ申請に行った際に、申請先の警察署が求める要件を満たせず、書類の不備や追加書類の要求で何度も足を運ぶことになり、時間と労力を大幅に浪費しかねません。
したがって、申請準備を本格的に始める前に、必ず、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の担当窓口(生活安全課 保安係など)に直接問い合わせるか、事前に予約して訪問し、ご自身の状況(個人/法人、営業所の形態、取り扱い品目など)を説明した上で、具体的にどのような書類が必要か、記載内容の注意点などを確認することが、スムーズな許可取得への不可欠なプロセスとなります。行政書士に依頼する場合でも、この事前確認は通常行われます。
どこに申請すればいい?
申請は、主たる営業所(本店など、古物営業の中心となる拠点)の所在地を管轄する警察署の生活安全課 保安係(または防犯係)で行います。複数の営業所があっても、最初の許可申請は主たる営業所の管轄警察署1ヶ所です。
申請に必要な書類一覧(個人・法人別)
主な必要書類は以下の通りです。個人申請と法人申請で異なります。(ただし、運用が異なる場合があるため、詳細は必ず申請先の警察署にご確認ください)
【個人・法人共通で必要な主な書類(申請者・役員全員・管理者ごと)】
- 許可申請書:各都道府県警察の様式を使用
- 略歴書:過去5年間の職歴等を記載
- 住民票の写し:「本籍(国籍)記載」「マイナンバー記載なし」のもの
- 誓約書:欠格事由に該当しない旨を誓約
- 身分証明書(日本国籍者のみ):本籍地の市区町村が発行するもの(運転免許証ではない)
【法人申請の場合に追加で必要な主な書類】
- 定款のコピー:事業目的に古物営業に関する記載が必要。原本証明が必要な場合あり。
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書):法務局発行。事業目的に古物営業に関する記載が必要。
【状況に応じて必要な主な書類】
- URLの使用権限を疎明する資料:インターネット取引を行う場合
- 営業所の賃貸借契約書のコピー:警察署により求められる場合(原則不要となりましたが、賃貸物件の場合に警察署により求められる可能性があります)
- 使用承諾書:警察署により求められる場合(原則不要となりましたが、賃貸物件で用途が住居専用の場合や、他人所有物件の場合に警察署により求められる可能性があります)
- 営業所の見取り図、周辺地図:警察署により求められる場合
- 駐車場の賃貸借契約書のコピー等:自動車を取り扱う場合
(補足)
- 住民票、身分証明書、登記事項証明書は、通常発行後3ヶ月以内のものが必要です。
- 各種様式は、申請先の都道府県警察のウェブサイト等から入手できますが、必ず最新のものを確認してください。
- 法人申請の場合、定款・登記簿の「事業目的」に古物営業を行う旨の記載がなければ、事前に目的変更登記が必要です。
要注意!「身分証明書」の取得方法
必要書類の中でも特に注意が必要なのが「身分証明書」です。これは運転免許証やパスポートのことではなく、本籍地の市区町村役場(戸籍担当課)でのみ発行される、破産宣告等を受けていないことを証明する書類です。
本籍地が遠方の場合は、郵送での請求も可能ですが、日数がかかります。申請準備の早い段階で取得に着手しましょう。自身の本籍地が不明な場合は、「本籍記載」の住民票を取得すれば確認できます。
申請にかかる費用と期間は?
- 申請手数料
- 新規申請には 19,000円 が必要です。申請時に警察署で納付します。不許可や取り下げの場合でも返金されません。
- 処理期間(審査期間)
- 申請書類が受理されてから許可・不許可の決定まで、標準的には 約40営業日(実質約2ヶ月) を要します。書類不備等があればさらに時間がかかります。
書類の取得費用や、行政書士への依頼費用(依頼する場合)も別途かかります。申請準備期間も考慮すると、営業開始予定日の最低でも2ヶ月半~3ヶ月前には準備を始めることをお勧めします。
許可を得るための必須条件:営業所と管理者のポイント
営業所の設置場所と条件
古物営業を行うための物理的な拠点として、「営業所」を最低1ヶ所定めて届け出る必要があります。インターネット取引のみの場合でも、事務作業を行う場所(例:自宅)などを営業所として届け出る必要があります。
- 要件
- 独立性があり、営業活動に適した実体のある場所であること。バーチャルオフィスや私設私書箱は不可。単なる倉庫や駐車場は営業所とみなされません。
- 賃貸物件・住居の使用
- 賃貸マンション等を営業所にすることは可能ですが、契約で事業利用が禁止されている場合(例:「居住専用」)、警察署によっては物件所有者等からの「使用承諾書」の提出を求められる可能性があります。
営業所の要件は、警察の監督が及ぶ範囲で適正な営業が行われることを担保するためのものです。使用承諾書の取得が必要な場合は、物件所有者等の協力が必要なため、早期の確認と交渉が重要です。
営業所の「管理者」とは? 役割と選任の注意点
各営業所には、業務を適正に実施するための責任者として「管理者」を1名選任しなければなりません。
- 役割
- 営業所における古物取引の管理・監督、従業員指導、法令遵守、警察との連携など、営業所の運営全般に責任を負います。
- 主な要件
- 常勤性
その営業所に常勤し、実質的に管理・監督できること。遠方居住などで日常的な通勤・業務遂行が困難な場合は認められません(通勤時間が片道2時間以上だと疑義が生じやすい)。 - 欠格事由非該当
管理者自身が後述の欠格事由に該当しないこと。 - 適格性・能力
業務を適正に実施する能力。特別な資格は通常不要ですが、取り扱う古物によっては知識・経験が求められる場合もあります。
- 常勤性
- 兼任不可の原則
- 原則として、一人の管理者が複数の営業所を兼任することはできません。
- 申請者本人も管理者になれる
- 個人事業主や法人の代表者・役員が管理者を兼任することは可能です。
管理者の「常勤性」要件は、特に多店舗展開や遠隔地での営業所設置において、人材確保の面で重要なポイントとなります。
要注意!許可が取れない「欠格事由」とは?
古物営業法には、許可を受けられない、または取り消される理由となる「欠格事由」が定められています。個人申請の場合は申請者本人、法人申請の場合は役員全員(監査役含む)、そして各営業所の管理者に適用されます。一人でも該当すると許可は取得できません。
主な欠格事由
- 破産者で復権を得ていない者
- 一定の刑(禁錮以上、または窃盗・背任・横領・盗品譲受け等の罪や古物営業法違反で罰金刑以上)に処せられ、執行終了等から5年を経過しない者(執行猶予期間中も含む)
- 暴力団関係者(元構成員も含む)
- 住居の定まらない者
- 古物営業許可を取り消されて5年を経過しない者
- 心身の故障により適正に業務を実施できない者
- 未成年者(一定の例外あり)
- 管理者を適正に選任できない者
- 法人役員に上記いずれかの該当者がいる場合
これらの欠格事由は、古物営業に関わる者の信頼性を担保するためのものです。特に法人申請では役員全員が対象となるため、申請前の確認が極めて重要です。「5年」という比較的長い不適格期間が設けられている点も注意が必要です。
許可を取ったら終わりじゃない! 古物商に課される義務
古物商許可を取得した後も、適正な営業を続けるために様々な義務が課せられます。これらは主に盗品等の流通防止・発見を目的としており、遵守を怠ると罰則や行政処分の対象となります。
古物商の重要ルール「防犯三大義務」とは?
特に重要な義務として、以下の3つが「防犯三大義務」と呼ばれています。
- 取引相手の確認義務(本人確認義務)
- 対象
- 確認事項
相手の住所、氏名、職業、年齢。 - 確認方法(対面)
運転免許証等の身分証明書の提示を受ける、相手に署名してもらう等の方法があります。 - 確認方法(非対面:ネット、電話等)
相手と直接対面しない取引では、なりすまし等のリスクが高いため、より厳格な本人確認方法が法律で定められています。単に身分証明書のコピーや画像をメール等で送ってもらうだけでは、原則として認められません。法律で認められている代表的な方法には、以下のようなものがあります(いずれか一つ、または複数を組み合わせる必要があります)。- eKYC(オンライン本人確認)の利用
申込み時に、本人の容貌(顔写真)の画像と、写真付き身分証明書の画像またはICチップ情報の送信を受ける方法。 - 本人限定受取郵便等の利用
確認書類などを本人限定受取郵便等で送付し、相手が確実に受け取ったことを確認する方法(例:配達完了の通知を受ける、相手から受付票等を返送してもらう、など)。 - 電子署名と電子証明書の利用
相手から電子署名が行われた申込み情報と、その電子署名が本人のものであることを示す電子証明書の送信を受ける方法。 - その他の組み合わせ
住民票の写し等の送付を受け、記載された住所へ転送不要郵便等を送付して到達を確認する方法や、身分証コピー送付+転送不要郵便送付+本人名義口座への代金振込、といった複数の手段を組み合わせる方法などもあります。 - 義務の免除
取引対価が1万円未満の場合は原則免除。ただし、バイク(部品含む)、ゲームソフト、CD/DVD等、書籍は盗難品が多く出回る傾向があるため、1万円未満でも確認が必要です。 - (注意点)
フリマアプリ等で個人から古物を仕入れる(買い取る)際、匿名性の高いプラットフォーム上で、上記のような法律が要求する厳格な非対面での本人確認を行うことは、出品者の協力が得にくい、または仕組み上困難な場合が多く、コンプライアンス上のリスクが高いと言えます。そのため、多くの古物商は、これらのプラットフォームを主に販売チャネルとして利用し、仕入れは本人確認が確実に行われる古物市場(古物商専用オークション)などを利用する傾向があります。
- eKYC(オンライン本人確認)の利用
- 不正品の申告義務
- 古物の買い受け等の際に、その品物が盗品等の不正品である疑いがあるときは、直ちに警察官に申告しなければなりません。
- 「確信」は不要で、「疑い」の段階で申告義務が生じます。少しでも怪しいと感じたら、取引を中止し、通報することが求められます。
- 取引価額に関わらず(1万円未満でも)申告義務があります。
- 申告先は、営業所の所在地を管轄する警察署です。
- 帳簿等への記録・保存義務
- 古物の売買、交換等を行った場合、その取引に関する事項を帳簿(古物台帳)または電磁的方法(パソコン等)で記録し、保存しなければなりません。
- 記録事項
取引年月日、品目・数量、特徴、相手の住所・氏名・職業・年齢、確認方法。 - 記録対象
買い受け、交換、委託販売の場合。売却の場合も、美術品類、時計・宝飾品類、自動車、バイク等は価額に関わらず記録が必要。 - 義務の免除
買い受けの場合、対価1万円未満は原則免除(バイク、ゲームソフト等は除く)。 - 保存期間
最終記載日から3年間、営業所に備え付け保存。 - 電磁的記録
パソコン等で記録・保存する場合、改ざん防止措置を講じ、必要時に印刷できる状態で保存する必要があります。データ管理(バックアップ等)が重要です。
お店には「標識(プレート)」の掲示を忘れずに
許可を受けた古物商は、営業所及び仮設店舗(露店等)ごとに、公衆の見やすい場所に、定められた様式の標識(古物商プレート)を掲示しなければなりません。
- 様式
- 紺色地に白文字、縦8cm×横16cm、公安委員会名、許可番号、主たる品目、氏名・名称を記載。
- 目的
- 正規の許可業者であることを外部に示すため。
- 違反
- 10万円以下の罰金。
ネット販売・買取を行う場合のルール
- URLの届出
- 自社サイトやオンラインモール上のストアページ等で古物営業を行う場合、そのURLを警察に届け出る必要があります(使用権限証明資料も必要)。
- ウェブサイト上の表示義務
- 届け出たサイト上には、許可公安委員会名、許可証番号、許可を受けた者の氏名または名称を表示しなければなりません。
- 特定商取引法
- ネット販売は「通信販売」にあたり、古物営業法に加えて、特定商取引法に基づく表示(事業者氏名・住所・電話番号等)も必要です。
- 非対面での本人確認
- ネットでの買い受けには、前述の厳格な本人確認が必要です。
出張買取やイベント出店(行商)のルール
- 行商とは
- 許可を受けた営業所以外の場所(例:顧客宅への出張買取、催事場での露店営業、古物市場での取引)で古物営業を行うこと。
- 行商の届出
- 行商を行うには、許可申請時に「行商をする」を選択しておく必要があります(後からの変更も可能ですが、届出と許可証の書換が必要になるため、最初から「する」で申請することが推奨されます)。
- 買い受け場所の制限
一般顧客から古物を買い受けられる場所は、原則として「自身の営業所」または「取引相手の住所・居所」に限定されます。デパート催事場、イベント会場、路上などでの一般顧客からの買い受けは原則禁止です。- 例外:仮設店舗
事前に日時・場所を警察に届け出た「仮設店舗」では買い受けが可能です(届出は営業日の3日前まで)。
- 例外:仮設店舗
- 販売場所の制限
- 販売には、買い受けほどの厳しい場所制限はありません。
- 行商時の義務
- 本人が行商する際は古物商許可証を携帯。
- 従業員に行商させる場合は行商従業者証を携帯。
- 相手から求められたら提示。
- 仮設店舗では標識を掲示。
- 違反
- 罰則(10万円以下の罰金等)あり。
警察への協力も古物商の義務
- 品触れ(ひんぶれ)への対応
- 警察から盗難品手配書(品触書)が送付されたら、到達日を記載し6ヶ月間保存。該当品を所持・受領したら直ちに警察へ届出。
- 差止め(さしとめ)への対応
- 警察官から盗品等の疑いがある古物の保管を命じられた(差し止められた)場合、その指示に従い保管(最長30日間)。売却等は不可。
許可内容の変更・違反した場合の罰則・許可取消し
住所変更やURL追加など、変更があった場合の手続き
許可取得後に申請内容に変更が生じた場合は、定められた期間内に警察署へ変更届出を行う必要があります。怠ると罰則(10万円以下の罰金)の対象です。
- 事後届出(変更後14日以内、登記が必要な場合は20日以内)
- 対象
氏名・名称、住所、法人役員、管理者、主たる品目、URLなど - 管理者の交替時は、新管理者の書類(略歴書、住民票等)が必要。
- 手数料
届出自体は無料。許可証の記載事項変更を伴う場合は書換申請(手数料1,500円)が必要。
- 対象
- 事前届出(変更の3日前まで)
- 対象
営業所の名称・所在地の変更、新たな営業所の設置。 - 手数料
無料。
- 対象
- 注意点
- 変更内容によっては事前・事後の両方の届出が必要な場合(例:営業所新設)があります。
- 提出先
- 原則、主たる営業所の管轄警察署。
法律違反には厳しい罰則も
違反内容に応じて、刑事罰(懲役・罰金)や行政処分(営業停止・許可取消し)が科されます。
- 3年以下の懲役または100万円以下の罰金(最も重い)
- 無許可営業
- 不正手段による許可取得
- 名義貸し
- 営業停止命令違反
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 営業場所制限違反など
- 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 本人確認義務違反、帳簿記録義務違反など
- 10万円以下の罰金
- 変更届出義務違反、許可証不携帯、標識未掲示など
どんな場合に許可が取り消される?
公安委員会は、以下のような場合に許可を取り消すことがあります。
- 不正手段で許可を受けたことが判明した場合
- 許可後に欠格事由に該当した場合
- 許可後6ヶ月以上営業を開始しない、または6ヶ月以上営業を休止し再開の見込みがない場合
- 営業所や古物商の所在が不明になった場合
- 法令違反や公安委員会の処分に違反した場合
許可が取り消されると、その日から5年間は新たに許可を取得できません。
絶対にダメ! 無許可営業のリスクと罰則
許可を受けずに古物営業を行う「無許可営業」は、最も重い罰則(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となる重大な違反です。逮捕される可能性もあります。
「知らなかった」「後で取るつもりだった」という言い訳は通用しません。処罰されると、刑罰に加えて5年間は許可が取得できなくなります。
もし既に無許可で営業してしまっている場合は、直ちに営業を停止し、専門家(行政書士等)に相談の上、速やかに許可申請を行うべきです。状況を正直に説明し、改善意思を示すことが重要です。
知っておきたいその他の情報とQ&A
古物商許可に関するQ&A
- 個人許可と法人許可の違いは?
- 個人事業主は個人名義、法人は法人名義で許可を取得します。それぞれ独立しており、個人許可で法人として営業したり、その逆を行うことはできません(無許可営業や名義貸しにあたります)。個人事業主が法人成りした場合は、新たに法人として許可を取得し直す必要があります。
- 複数の営業所を持つ場合や、他の都道府県で営業するには?
- 以前は営業所を設置する都道府県ごとに許可が必要でしたが、法改正により運用が変わりました。最初に主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会から許可を受けていれば、他の都道府県に営業所を新たに設置する場合、その都道府県で改めて許可を取得する必要はなく、当該他の都道府県の公安委員会への「届出」で足りるようになりました。ただし、届け出た各営業所に、常勤可能で欠格事由のない適格な管理者をそれぞれ選任・配置する必要がある点は変わりません。
- 自動車を取り扱う場合の注意点は?
- 車両を保管するための場所(駐車場等)を確保していることの証明(賃貸借契約書のコピーなど)の提出が、申請時に求められます。
- レンタル事業に許可は必要?
- 中古品を仕入れて(買い取って)レンタルする場合は、古物商許可が必要です。メーカーなどから新品を仕入れてレンタルする場合は不要です。
- 下取りに許可は必要?
- 新品販売時の下取りも原則として古物の「買い受け」にあたるため許可が必要ですが、「サービスとしての一律値引き」とみなされる特定の条件下では不要となる例外があります。詳しくは本記事の「許可が必要なケース・不要なケース」の項をご確認ください。
- 輸入品の販売に許可は必要?
- ご自身で海外に直接出向いて買い付け、輸入した物を国内で販売する場合は、古物商許可は不要です。しかし、他の輸入業者が輸入した物などを国内で仕入れて販売する場合は、国内での仕入れ行為が発生するため許可が必要になります。
手続きが不安なら行政書士への依頼も検討
行政書士は、官公署への書類作成・手続き代行の専門家です。古物商許可申請も主要業務の一つです。
- メリット
- 複雑な書類の収集・作成、警察署との事前調整や折衝、申請書類の提出代行などを任せることができます。これにより、申請にかかる時間と手間を大幅に削減し、書類不備による遅延や不許可のリスクを低減できます。特に、警察署ごとのローカルルールへの対応や、法人設立と同時申請、欠格事由に関する懸念がある場合など、専門的な知識が求められる場面で頼りになります。
- 依頼の判断
- 申請手続きは個人でも可能ですが、特に法人として申請する場合、複数の営業所を持つ計画がある場合、事業開始までの時間的制約がある場合、または手続きに不安がある場合などは、行政書士への依頼を検討する価値が高いと言えます。費用はかかりますが、結果的に確実かつ迅速な許可取得につながり、スムーズな事業開始を後押ししてくれる可能性があります。
まとめ:安全・適法な古物営業のために知っておくべきこと
古物商許可を取得し、適法に事業を運営するための要点を再確認しましょう。
- 許可対象となるか正確に判断する
- 「古物」の定義、「業として」の基準を正しく理解し、特に「不用品の売却」と「事業」の境界線や、「下取り」の例外規定について注意する。
- 必ず事前に許可を取得する
- 古物営業を開始する前に許可を得ること。無許可営業は絶対に行わない。
- 防犯三大義務を徹底する
- 取引相手の本人確認(特に非対面取引の方法を遵守)、不正品の疑いがある場合の警察への即時申告、取引記録の正確な記帳と3年間の保存を確実に行う。
- 営業所・管理者の要件を満たす
- 実体のある営業所を確保し、常勤可能で欠格事由のない管理者を各営業所に配置する。賃貸物件等では使用権限を確認する。
- 各種ルール(行商、ネット取引、変更届出等)を遵守する
- 許可取得後も、行商時のルール、インターネット取引での表示義務、許可内容の変更が生じた際の届出などを忘れずに行う。
- 計画的に準備し、必ず事前に警察に相談する
- 十分な準備期間(最低2.5~3ヶ月)を確保し、書類収集や手続きを進める。特に、ローカルルールが存在する可能性があるため、申請前には必ず主たる営業所を管轄する警察署に相談し、具体的な要件を確認する。不明点は自己判断せず、警察署または専門家(行政書士)に相談する。
古物商許可制度は、盗品流通防止という社会的な要請に応えるための重要な規制です。一見すると手続きや義務が煩雑に感じられるかもしれませんが、その目的を理解し、ルールを正しく守り、誠実に対応することで、法令を遵守した安心・安全な事業運営が可能となります。
- 【格安代行】三重県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】三重県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】京都府の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】京都府の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】佐賀県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】佐賀県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】兵庫県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】兵庫県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】北海道の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】北海道の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】千葉県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】千葉県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】古物商許可とは?取り方から義務、罰則まで徹底解説【4000円~】
- 【格安代行】和歌山県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】和歌山県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】埼玉県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】埼玉県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】大分県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】大分県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】大阪府の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】大阪府の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】奈良県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】奈良県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】宮城県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】宮城県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】宮崎県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】宮崎県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】富山県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】山口県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】山形県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】山梨県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】岐阜県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】岐阜県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】岡山県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】岡山県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】岩手県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】岩手県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】島根県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】広島県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】広島県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】徳島県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】愛媛県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】愛知県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】愛知県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】新潟県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】新潟県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】東京都の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】東京都の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】栃木県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】栃木県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】沖縄県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】沖縄県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】滋賀県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】滋賀県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】熊本県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】熊本県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】石川県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】神奈川県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】神奈川県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】福井県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】福岡県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】福岡県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】福島県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】秋田県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】秋田県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】群馬県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】群馬県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】茨城県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】茨城県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】長崎県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】長野県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】長野県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】青森県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】青森県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】静岡県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】静岡県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】
- 【格安代行】香川県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】高知県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】鳥取県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】鹿児島県の古物商許可でおすすめの行政書士6選
- 【格安代行】鹿児島県の古物商許可を徹底解説!【4000円~】