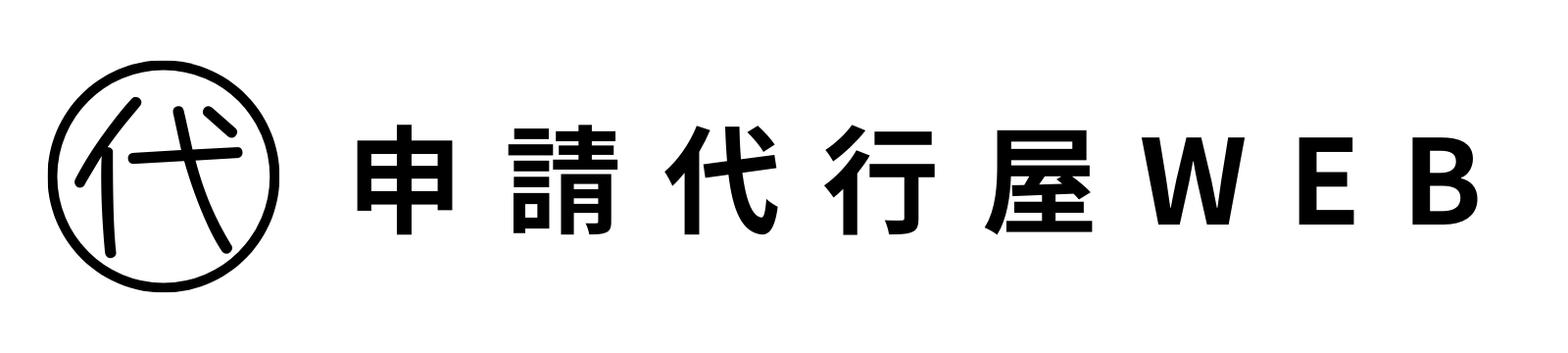福岡県で建設業を営む上で、建設業許可の取得は避けて通れない重要な手続きです。一定規模以上の工事を請け負う際には、建設業法に基づき許可が必要となります。しかし、許可制度は複雑で、要件や手続きについて正確な情報を把握するのは容易ではありません。 この記事では、福岡県内で建設業許可の取得や維持を目指す事業者様に向けて、許可の種類、取得要件、申請手続きの流れ、許可後の維持管理、そして最近の法改正の動向まで、福岡県の「建設業許可申請等の手引き」や関連情報をもとに、分かりやすく解説します。これから許可を取得される方、更新を控えている方、制度について理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。