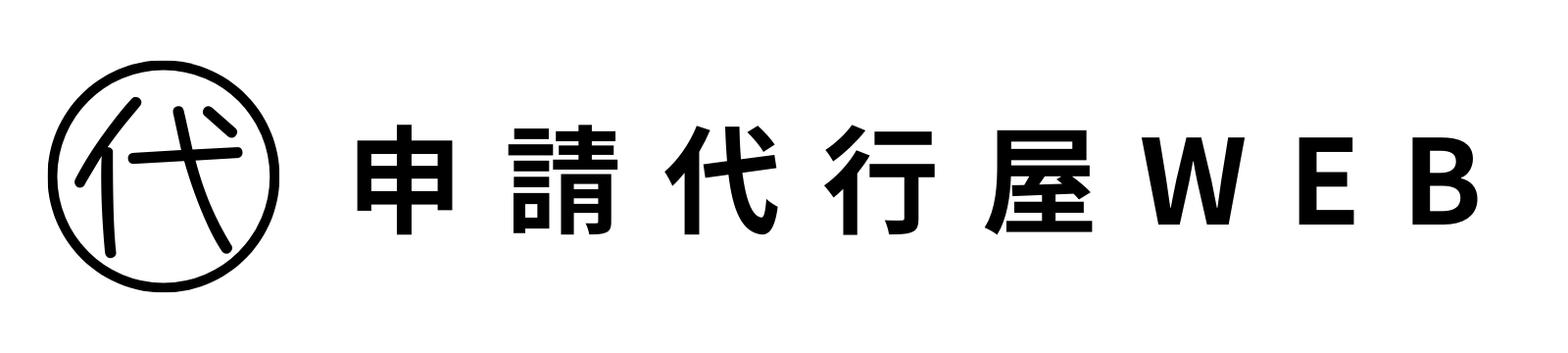神奈川県内で建設業を営む多くの事業者にとって、「建設業許可」は事業継続に不可欠なものです。建設業法では、軽微な建設工事を除き、建設工事の完成を請け負う営業を行う場合、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要と定められています。本記事では、神奈川県で建設業許可の取得を目指す事業者様向けに、神奈川県の「建設業許可申請の手引き」や関連情報をもとに、許可の種類、要件、申請手続き、更新、相談窓口まで、網羅的に解説します。法令遵守はもちろん、事業の信頼性向上にも繋がる建設業許可について、理解を深めていきましょう。