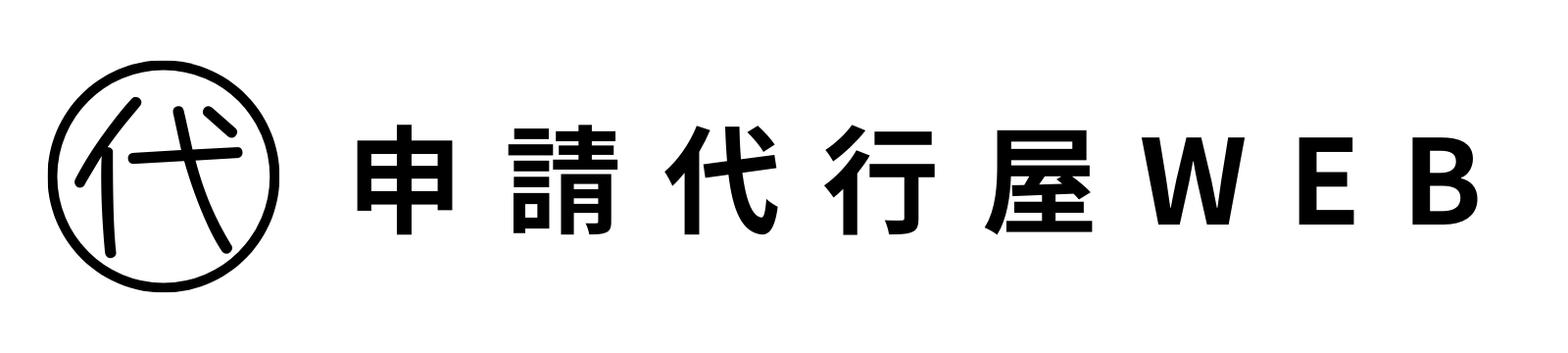東京都内で道路を使った工事、イベント、設備の設置などを行う場合、「道路使用許可」や「道路占用許可」といった手続きが必要になることがあります。これらの許可は、私たちの安全な交通と快適な生活を守るために非常に重要な役割を担っています。しかし、手続きが複雑で、「どちらの許可が必要なの?」「どこに申請すればいいの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、東京都における道路使用許可と道路占用許可について、その違いから申請手続き、注意点まで、網羅的に解説します。東京都内で道路の利用・占用を計画されている事業者様や個人の方は、ぜひ参考にしてください。